川名部 新 院長の独自取材記事
おばな内科クリニック
(川崎市中原区/武蔵新城駅)
最終更新日:2025/05/14
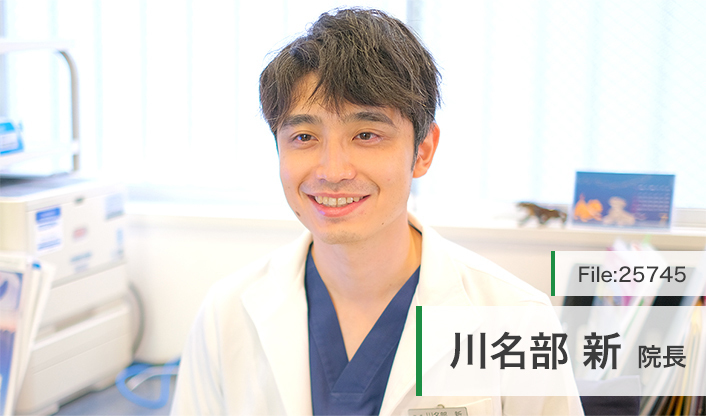
武蔵新城駅から徒歩1分の「おばな内科クリニック」は、糖尿病、内分泌代謝を得意とする内科クリニックだ。院長の川名部新先生は、日本糖尿病学会糖尿病専門医と日本内分泌学会内分泌代謝科専門医の資格を持ち、総合病院で経験を積んできた。勤務医時代から、将来的には患者を長く診られるクリニックで医療に従事することを目標に掲げてきた。患者とは治療と関係のない世間話をする機会も多いそうだが、それも患者を知る手立てになるという。そんな川名部院長に力を入れている診療や患者への想いについて詳しく聞いた。
(取材日2024年3月1日)
糖尿病・内分泌に強みを持つ内科クリニック
どういった患者さんがいらっしゃいますか?

この辺りの地域は、ファミリー層の30代くらいの方が多い印象です。来院される方は成人の方がほとんどで、小花前院長が当院を開院してから約20年以上もの長きにわたり、ずっと通院されている高齢の方々も少なくありません。90歳以上の患者さんもいらっしゃいますよ。また、専門にしている糖尿病の治療などでかかる方も、中年層の方も多くご来院くださいますね。そういう意味では地域に密着した、そして老若男女問わず、幅広い年齢層から街のかかりつけ医として、親しみをもって受け入れてもらえていることをとてもうれしく思います。
検査や治療法にも先端の技術を取り入れていると聞きました。
新たに糖尿病の血糖値を測定できるヘモグロビンA1c測定装置を導入しました。ヘモグロビンA1cというのは、過去約2ヵ月の血糖の平均値を表すのですが、これまでは院外で測定していたため、リアルタイムの値を患者さんと共有できませんでした。今回、測定装置を院内に設置したことで、10分程度で結果が判明し次回までの目標などを設定しやすくなりました。その他、尿検査もすぐに結果がわかるようにしたり、AIの画像診断アシストが搭載されたエックス線装置を導入したりと大幅にハード面を変更しています。高血圧の治療では、高血圧症治療補助プログラムというものを活用し始めました。これはスマートフォンに専用のアプリケーションを入れ、そこから出される提案に従って生活習慣を見直していくという治療の補助ツールで、患者さんの記録を医師も確認できます。費用も保険適用されるので、今後は積極的に患者さんに進めていきたいと思っています。
医師とスタッフの距離がとても近いという印象を受けました。

医師は現院長の私と看護師3人と受付はパートを含めて4人。看護師、受付はともに当院のベテランスタッフなので、患者さんのことをとても詳しく知っています。知り尽くしているというほどです。患者さんの様子をつぶさに観察し、いつもと歩き方が違うとか、いつもより元気がないといった情報を逐一私に報告してくれます。最近は検査装置を大幅に入れ替えたり、新たな治療法を導入したりとクリニックの変化が大きいのですが、積極的に勉強会に参加してくれて、今では私よりも装置の取り扱いに慣れているほどです。クリニックは医師とスタッフが一体となって患者さんをサポートする所ですので、今後もスタッフの力を借りながら患者さん一人ひとりを大切にする診療を心がけていきたいと思います。
患者の声に耳を傾けることが治療の第一歩
子どもの頃に、すてきな内科の医師との出会いがあったとか。

私は小学生の頃に小児喘息があったので、頻繁に地元の内科クリニックに通院していました。小学校へ行っても、息苦しいのは自分だけ、誰も自分の苦しさを理解してくれない、そうした自暴自棄な気持ちになることもありましたね。でもそのクリニックの内科の医師は、自分の話にじっくりと耳を傾けてくれるだけでなく、自分の苦しさに共感してくれました。「苦しいよね」、「つらいよね」といった言葉を投げかけてもらえるだけで、心が安らぎました。当時の私にとって、その先生はオアシスのような存在であり、かつ憧れの対象。大人になったら、この先生のように人の役に立つ職業に就き、人の気持ちに寄り添える存在になりたいと思いました。
糖尿病への関心が深まったきっかけはありますか。
2013年に聖マリアンナ医科大学医学部を卒業した後のことです。糖尿病を患うタクシー運転手が、大学病院に来院されました。その方の食事は不規則で、空いた時間に菓子パンを食べるという生活スタイル。管理栄養士による栄養相談では、1日3食を励行するようにといった教科書的なアドバイスをもらうだけ。仕事のスタイルを変えることができないので、自分でも実践できるアドバイスを求めているにもかかわらず、それを期待できずに患者さんは行き詰まってしまっていました。この方とお話しする中で、医療従事者は患者さんそれぞれの事情や状況を考慮した上で、その人に適した情報を抽出し、提供する必要があるということに気づかされました。その後、私は工夫を重ねながらその方の生活習慣や性格などに関する指導を行い、その方に合った健康のめざし方を見出せました。この経験がきっかけで、糖尿病の奥深さやその研究へのやりがいを見出したのです。
その経験から今でも続けられている工夫や診療でのこだわりはありますか。
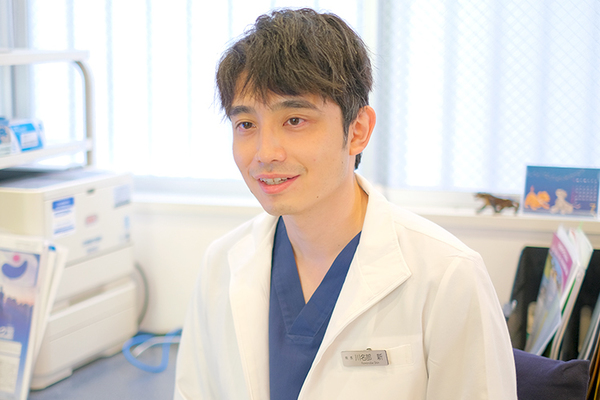
患者さんの声をじっくりと聞き、入手できた情報から治療方法を組み立てることにこだわっています。生活習慣病の代表的な疾患の1つである糖尿病を専門にしていることもあり、患者さんの人となりから始まり、どのような生活をしているのか、職業は何なのかなど、患者さんに関わるさまざまな情報を知ることが治療の第一歩です。患者さんの中には、医師を前にすると緊張して、思うようにコミュニケーションできない方もおられますので、私だけではなく長年地元の患者さんたちと信頼関係を築かれてきた看護師の力を借りながら、情報を収集しています。看護師から、こんなことを言っていましたよと教えてもらった場合には、看護師から聞いた情報を加味して、治療方法を変更します。私にとっての理想の医師像は、患者さんを長く診られる環境で医療提供を行うこと。理想像に少しずつ近づいていることを実感しています。
患者の将来を守る、これが診療のコンセプト
地域にとって、どのような存在になりたいですか。

この地域には糖尿病を専門とする医師が多くないので、私の得意分野を中心に据えた診療を行いたいと思っています。私のもう1つの専門は内分泌ですので、内分泌に関する診療を強化する予定です。特に甲状腺疾患は、倦怠感や多汗、動悸など、症状があいまいで他の病気との判別が難しく、患者さん自身が受診するまで時間がかかることもあります。女性の場合は不妊や流産につながるケースもあり、早めに治療を行うことが大切です。内分泌の専門医師も周辺でも少ないので、広く認知していただければと思います。また近隣にある他科クリニックの先生方と密に連携を取り交流を深めながら、地域全体でオールマイティーに患者さんの診療を行えるベースをつくりたいですね。
今後の展望について教えてください。
当院において、専門である糖尿病の診療を伸ばすこと、そしてもう1つの専門分野である内分泌の専門性を高めていきたいと思っています。内分泌の病気は、発見しにくいという特性があるので、それを発見するための検査は積極的に行う予定です。例えば、高血圧の患者さんに高血圧の治療だけを行っていても状況が芳しくない場合、裏には内分泌関連の病気が隠れていることがあります。それを放置すると、5年後10年後に心臓病を発症したり、脳出血や不整脈のリスクが高まることにつながりかねません。「患者さんの将来を守る」という意味で、検査を実施し、しっかりと診断を行うことが重要だと感じています。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。

病気にならないために、体重を増やさないように日々気をつけることが大切です。体重が増えると、11個程度の病気になるといわれているのをご存知ですか。糖尿病、高血圧症、脂質異常症、コレステロール異常症、腰痛、変形性腰椎症、膝痛や女性の生理不順など。体重管理は自宅で可能なので、体重測定を習慣化し、常に自分の体をモニタリングすることは、すごく大事だと思います。他には、定期検診を受診してもらいたいですね。基本的には、血液検査や尿検査を行うことで、情報把握につながります。当院のような内科では、症状が発症してから来院される方が多い傾向にありますが、それだと症状が進行していることがあるので、不安なことがあれば、早めに気軽にご相談いただきたいですね。






