内藤 祐次 院長の独自取材記事
柴田内科
(横浜市港北区/大倉山駅)
最終更新日:2025/08/13

大倉山駅から徒歩6分の住宅街にある「柴田内科」は、2025年5月に内藤祐次院長が継承し、新たなスタートを切った。17年間心臓血管外科の医師として研鑽を積んだ後、「手術以外にも、医師としてもっと幅広くできることがある」との思いから内科へ転向。内藤院長は、循環器や糖尿病、甲状腺疾患といった専門性を生かしながら、地域のプライマリケアも大切にする。「話を聞いている時間のほうが多いかもしれませんね」と笑う姿からは、診療の際に患者一人ひとりの背景を重視する温かな人柄が伝わってくる。学生時代を過ごした思い出深い大倉山で、どのような医療を展開していくのか。継承への思いや診療にかける信念について聞いた。
(取材日2025年7月18日)
心臓血管外科から内科の医師へ、新たな挑戦
心臓血管外科を17年間続けた後、内科へ転向されたきっかけは?

医学部卒業後すぐに心臓血管外科の世界に飛び込み、小児から成人まで多様な循環器疾患の手術に携わってきました。海外留学も経験し、心臓血管外科の医師として研鑽を積んでいたんです。ただ、長年外科をやっていく中で、手術でしか治療できない部分だけでなく、医師としてもっと幅広くできることがあるのではないかと考えるようになりました。特に術後の患者さんの慢性期管理や、手術に至る前の予防医療にも興味を持つようになったんです。アメリカ留学中に内科の勉強もしたことで、より一層その思いが強くなりました。そこで千葉西総合病院では循環器内科、湘南藤沢徳洲会病院では糖尿病内科や内分泌内科を学び直し、日本循環器学会循環器専門医、日本糖尿病学会糖尿病専門医、日本内分泌学会内分泌代謝科専門医といった資格も取得しました。外科時代の経験を生かしながら、より幅広い視点で患者さんを診られるようになりたいと思ったのが転向の理由です。
なぜ「柴田内科」を継承されたのですか?
開業するなら継承がいいと考えていたところ、ご縁があってこちらのクリニックと出会いました。実は私、横浜市立大学の学生時代を大倉山で過ごしていたんです。この土地には非常に愛着があり、クリニック前の通りも昔からなじみのある場所でした。柴田先生が30年にわたって地域医療を支えてこられた歴史あるクリニックを、この思い出深い土地で引き継げることを大変光栄に思っています。タイミングも良く、自分の専門性を生かしながら地域医療に貢献できる理想的な環境だと感じたんです。前院長の患者さんも多く通われていますが、皆さんを大切に診させていただきながら、循環器や糖尿病、甲状腺といった私の専門分野も加えて、より幅広い医療を提供していきたいと考えています。
継承から3ヵ月がたちましたが、率直な感想は?

正直なところ、想像以上にプライマリケアの需要が多いことに驚きました。風邪や胃腸炎など急性疾患の患者さんが多く来院されます。私は糖尿病や循環器疾患といった専門的な診療を中心にと考えていましたが、地域に根差した開業医というのはこういうものなのだと実感しています。年齢層も幅広く、高齢の方から若い方、時には小児科が閉まっている時にお子さんも来られます。専門外の相談を受けることもあり、対応が不十分だったかなと反省することもありますが、これも地域医療の大切な役割だと理解しました。理想としてはプライマリケア3割、専門分野7割くらいの比率をめざしていますが、まずは来てくださる患者さん一人ひとりをしっかり診ることが大切。開業医の役割の幅広さと責任の重さを日々感じながら、地域のニーズに応えられるよう努力しています。
患者の人生に寄り添う診療スタイル
特に力を入れている診療内容について教えてください。

糖尿病診療では血糖値だけでなく全身管理を重視しています。糖尿病の方は悪性腫瘍を合併したり、知らないうちに心機能が低下していることもあるんです。多くの症例を診てきた経験から、明らかな症状が出る前に発見できるよう心がけています。そのため血糖測定機器を導入し、来月からは超音波検査も始める予定です。甲状腺疾患も意外と多く、若い方から高齢の方まで幅広くいらっしゃいます。なんとなく調子が悪いという方の中に、甲状腺機能の異常が隠れていることもあります。健康診断では見つからないホルモン異常を、内分泌代謝科専門医としての視点で診断することも大切な役割だと考えています。循環器疾患については、糖尿病患者さんの心機能評価なども含めて総合的に診ています。
外科時代の経験は現在の診療にどう生きていますか?
外科の医師として手術をする際は、患者さんの年齢や仕事、将来の寿命まで考慮して術式を選択していました。小児の場合は成長を見据えて段階的な手術計画を立てることもあります。この「患者さんごとの背景を考えながら治療方針を決める」という視点は、糖尿病治療の選択と非常に似ているんです。例えば同じ血糖値でも、仕事が忙しい方と時間に余裕がある方では治療法が変わります。その人の生活スタイルや価値観に合わせた治療を提案することが大切です。また、外科の場合は手術で達成感を得られますが、内科でも甲状腺のバセドウ病など、しっかり診断して治療すれば改善が期待できる疾患があります。そういった瞬間は、外科も内科も共通のやりがいですね。患者さん一人ひとりの人生を見据えた治療という考え方は、外科医時代に培った財産だと思っています。
診療で最も大切にしていることは何ですか?

「話を聞く時間のほうが多いかもしれませんね」というのが私のスタイルです。患者さんが納得して満足してもらえることが一番大事だと考えているので、疑問や不安がありそうな時はじっくり聞くようにしています。時間との闘いになることもありますが、やはり話を聞いてもらって満足するという方は多いんです。また、共感することも大切にしています。いろんな価値観の方がいらっしゃいますから、医師の価値観で判断せず、その方の立場に立って考えるよう心がけています。最近はAIの活用も進んでいますが、患者さんの感情や生活背景まで考慮することは人間にしかできません。実際に話してみないとわからないことがたくさんあります。患者さんのバックグラウンドを理解し、その人にとってベストな治療を一緒に見つけていく。これがAIに負けない、人間にしかできない医療だと信じています。
地域とともに歩む、これからの医療
地域医療においてどのような役割を果たしていきたいですか?

地域に根差した医療というのは、患者さんだけでなくスタッフも含めた全体で社会に貢献することだと考えています。スタッフをしっかり育成し、皆が満足して働けるクリニックにすることも大切な役割です。診療面では、総合診療としてどんな症状でも最初に相談してもらえる存在でありながら、循環器や糖尿病、甲状腺といった専門領域では標準的な医療をしっかり提供できる。この二つのバランスが重要だと思っています。また、ブログやホームページでの情報発信にも力を入れています。医療DXの波に乗りながらも、アナログやリアルでしか感じられない部分も大切にしたい。技術の進歩と感情に訴える部分のバランスを考えながら、皆さまの人生に寄り添える医療を展開していきたいですね。
今後の展望について教えてください。
まずめざしているのは「患者さんの人生を見据えた質の高い糖尿病ケア」です。長期的な視点で、その方の人生に寄り添った治療を提供していきたい。循環器に関しては、私がこれまで診てきた先天性心疾患の患者さんが成人になり、最終的に心不全になることもあります。そういった方々を支えられるような、循環器としても実力を備えたクリニックをめざしています。将来的には在宅医療にも取り組みたいと考えています。以前、心不全専門の在宅クリニックで手伝いをしていた経験があり、在宅医療の面白さや大切さを実感しました。患者さんの人生を最後まで支えられるような診療体制を整えていければと思っています。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。
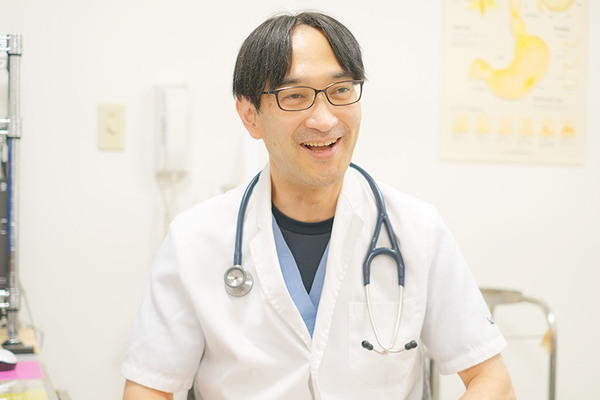
最初はわからないことも多いかもしれませんが、時間をかけて、その人にとってのベストを見つけ提供したいと思っています。どんな病気でも来ていただいて構いません。私のできる範囲でしっかり対応し、必要があれば適切な医療機関をご紹介しますので、何かお体のことでお困りのことがありましたら、気軽にご相談ください。プライマリケアから専門的な治療まで、幅広く対応させていただきます。この大倉山の地で、30年の歴史を持つクリニックを引き継いだ責任を感じながら、地域の皆さんと一緒に歩んでいければと思います。






