加藤 洋一 院長の独自取材記事
新横浜かとうクリニック
(横浜市港北区/新横浜駅)
最終更新日:2025/10/03

新横浜駅から徒歩5分のビル8階にある「新横浜かとうクリニック」。ドアを開けると、ホテルのロビーのようなラグジュアリーな空間が広がっている。しかし、加藤洋一院長とスタッフたちが温かく迎えてくれるので緊張する心配はない。国立がん研究センター研究所などで先進的な医療に携わってきた加藤院長のもとには、日本全国のみならず海外からの患者も訪れる。一方、かかりつけクリニックとして頼りにしている近隣住民も多く、風邪や腰痛など一般的な症状の診療にも力を入れている。未来を見据えた先進的な医療と、地道な地域貢献。どちらも等しく常に全力を注ぐ加藤院長に、診療にかける思いなどを詳しく聞いた。
(取材日2025年9月22日)
先進的な医療の可能性を追求しつつ保険診療にも注力
まず、医師を志したきっかけやご経歴を教えていただけますか。

子どもの頃、亡くなる間際の祖母に「大人になったらお医者さんになって、私と同じ病気の人を治してね」と言われたのが医師を志したきっかけです。大学卒業後は消化器外科で手術の研鑽を積むとともに、国立がん研究センター研究所で先進的な医療の研究に従事しました。恩師の「自分がメスを入れた患者は最後まで面倒を見ろ」という教えを大切にしていましたが、どうしても退院後までは追いきれません。もっとしっかりフォローアップしたいという思いから開業を決意しました。また、長く診ていた患者さんが横浜在住で「先生がそばにいてくれたら安心」とこの場所を用意してくれたのですが、全国からの患者さんも多いので、新幹線が止まる新横浜駅からすぐという立地はたいへん理想的でした。
開業当初から、新しい医療の提供に積極的だったと伺いました。
当時、大学病院と同じような先進的な医療に意欲的なクリニックはまだ珍しかったと思います。クリニックでそうした医療を始めるにはコストもかかり、リスクを取る覚悟も必要でした。クリニックのロゴマークを女神の船首像にしたのは、未知への航海を照らしてほしかったからです。しかし同時に、それだけでなく地域に根差したクリニックにしたいという思いもありました。子ども時代を過ごし、親戚もたくさん住んでいる横浜は故郷のようなもので、地域に貢献したかったからです。開業2年目には横浜市医師会の高齢者支援ネットワークの立ち上げにも携わりました。以来、当院では在宅医療にも積極的に取り組んでいます。
現在はどのような患者さんが多いですか。

9割が風邪や腹痛などの患者さんで、高血圧、高脂血症、糖尿病、慢性胃炎などの訴えが多いですね。内科症状だけではなく腰痛などにも対応できるのでご相談ください。腰痛は強めの内服薬を処方されることもありますが、当院ではエコーガイド下で生理食塩水と局所麻酔薬を注入する治療なども行っています。月に1回、日本呼吸器学会呼吸器専門医の診察日も設けているので、「検診で肺の影を指摘された」「血痰が出た」といったご相談も多いですね。また、がんに関しては全国各地はもとより海外からの患者さんも少なくありません。これまでの知見を駆使して、一人ひとりに応じた対応を心がけています。必要に応じて、提携している横浜市内の病院での手術・抗がん剤・放射線治療などの標準治療をご紹介することも可能です。
誠実に患者と向き合い、一人ひとりに寄り添う
検査やワクチン接種にも力を入れていると伺いました。

上部内視鏡検査、超音波検査、血液検査などを、予約不要で受けていただけるように整備しました。患者さんは腹痛、発熱など何かしらの困った症状があって来ています。だからこそ、すぐに検査を実施してなるべく多くの情報を集め、その日のうちに治療を開始したいと考えています。例えば喘息のセカンドオピニオンで来た方でも、検査をしてみたら別の病気が見つかることもあり得るでしょう。また、ワクチン接種に関しては、子宮頸がん、帯状疱疹、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザの他、B型肝炎、麻疹・風疹などにも対応しています。
広々とした点滴室が3部屋、それに培養室などがあって珍しいですね。
当院には遠方から家族連れで来る方も多いので、完全個室の点滴室はベッドの隣にソファーを置いて皆さんでゆったり過ごせるようにしています。治療後、新幹線や飛行機の時間までそのままお待ちいただいても構いません。また、培養室ではLAK(活性化リンパ球)と樹状細胞に関する研究もしています。そんなところもクリニックの特長かもしれませんね。
医師の立場から最近気になることはありますか。

開業当初は進行がん、末期がんの方がほとんどでしたが、最近はがんの予防に関心が高い方が増えていますね。「兄弟が40代で膵臓がんが見つかって半年で亡くなり、自分もいつそうなるか心配」といった相談もあります。当院ではがん予防のためのアプローチを行う際も、患者さん一人ひとりに合わせて、根拠を持って対応できるように心がけています。
患者さんと接する際に何を大切にしていますか。
患者さんが主体的に治療に取り組めるようにすることです。まずは不安を解消できるようにデータを用いながら理論的にご説明します。そして、うそはつかず、すべてをお伝えし、きちんとご本人が治療や病気について理解できるようにお話しするところから始めたいと思っています。それはどんな病気でも同じです。コレステロール値が高い方などは、薬を使ってその数値が低下したとき、自己判断で「治った」と勘違いされがちです。薬も処方はしますが、下がった値を維持できるようにまずは食事や運動習慣を「こうしなさい」ではなく「こうしてみましょう」と寄り添いながら改善していきたいと思っています。
総合的な予防医療で人生を最後まで楽しめるように
今後の展望についてお聞かせください。

大学病院の先生から「なぜ、町のクリニックでこんな取り組みができるのか」と聞かれることがあります。それは、常に「10年先を想像し5年後にやっと普及しているような医療を先んじて提供する」をポリシーとしてきたからかもしれません。今後とも未来を見据えた医療を追求し続けたいと思います。また、どんなに小さなことでも患者さんの要望にできる限り応えていきたいです。「こんなことは相談できない」などと遠慮せずに、何でも教えてください。実際、ざっくばらんにお話しくださる患者さんが多いのも当院の自慢です。長いお付き合いの患者さんと食事や旅行に行くこともありますが、プライベートでは「先生」ではなく「加藤さん」と呼んでくださるのも、とてもうれしく思っています。
お忙しい毎日ですが、健康管理で気をつけていることなどはありますか。
やはり、運動の習慣は大切にしています。横浜のマラソン大会も第1回から第5回までは参加しました。他にはゴルフもしています。ゴルフは失敗をしても焦らずにリカバリーする訓練になるところが面白いですね。筋肉量が多いほど免疫力も高まりやすいといわれていますが、確かにそうかもしれません。以前新型コロナウイルス感染症が流行した際、発熱症状を積極的に受け入れているクリニックは限られていたので、たくさんの患者さんを診ましたが、幸い感染することはありませんでした。
最後に読者へのメッセージをお願いします。
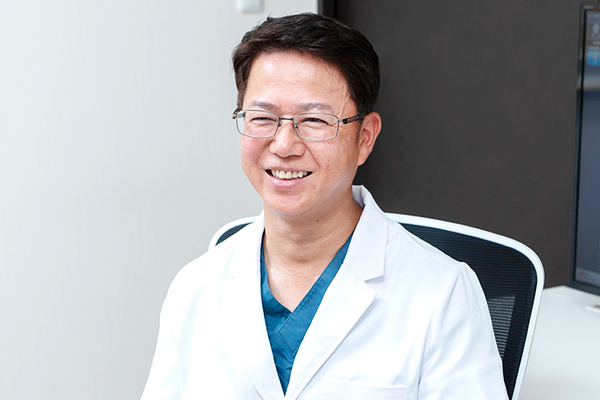
日本人のがん検診の受診率は海外と比較して低い状況です。「内視鏡検査はつらそう」「CTの被ばくが心配」など、いろいろなお考えもあるでしょう。ですが、検査を受けることはその後の人生をより良いものにするのに役立つはずです。病気で苦しむ方をたくさん診てきたからこそ、病気にならない体づくりの大切さも痛感しています。高齢社会の中で、人生を最後まで楽しむためのサポートをしていきたいと思っています。そのために、パーソナルトレーニング、リハビリテーション、食事なども楽しめるような場所をつくり、予防医療にますます力を入れていく予定です。幅広く対応していきますので、気になることがあればお気軽にご相談ください。






