清水 恵一郎 理事長の独自取材記事
阿部医院
(目黒区/都立大学駅)
最終更新日:2024/08/08
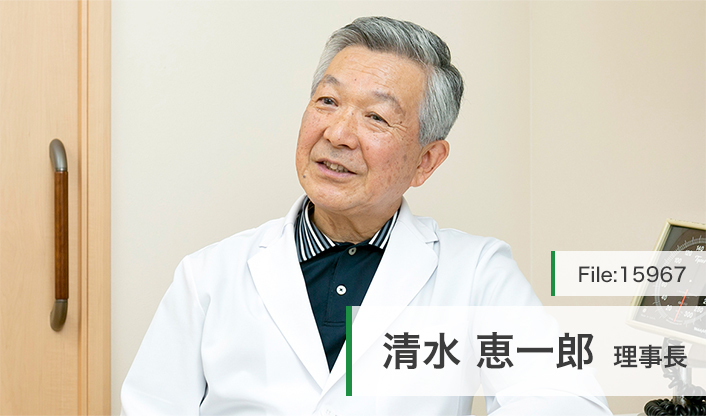
東急東横線都立大学駅や東急目黒線大岡山駅から徒歩10分ほどの住宅街にある「医療法人社団清令会 阿部医院」は、長年地域住民のさまざまな相談を受けてきた医院。理事長の清水恵一郎先生は「地域にお住まいのお子さんから高齢の方まで、健康で幸せに暮らせるようお手伝いをしたい」と話す。2016年のリニューアルでバリアフリー化や情報化などを進め、患者が気軽に安心して受診できる環境を整備。在宅医療にも力を入れるなど、地域にこれから必要な医療を提供する清水先生に話を聞いた。
(取材日2018年9月21日/更新日2024年7月31日)
義父から受け継いだ地域密着の医院を次の世代へ
こちらの医院は長く診療されているのですか?

私が妻の父から当院を受け継いで30年以上、義父の代も含めると60年以上になります。院名は当初からのもので、院長が私に代わったときも、長く地域に親しまれてきた名前は変えられないとの思いで、そのまま使わせていただいています。当院は目黒区西部の住宅街にあり、地域のかかりつけ医として、症状に関わらず総合的な診療を行っています。急に熱を出したとか、おなかが痛くなったといった小さなお子さんから、長く当院を利用されている高齢の方まで、患者さんの年齢も症状も幅広いですね。私は勤務医時代には内科、特に消化器内科が専門でしたが、義父が皮膚科が得意だったこともあって、当院を継いでから改めて皮膚科の勉強を始め、湿疹や乾癬、虫刺され、在宅療養で寝たきりの患者さんの床ずれなども専門的に診るようになりました。
そんなに続いているのに、院内はとても新しいですね。
2016年に自宅と医院を兼ねた建物を建て替えて、院内もそれまでとはまったく異なる造りにしたからでしょう。院内をバリアフリーにしたほか、待合室も診療室も以前より広々としたスペースにして、患者さんが待ち時間をゆったりと過ごせるよう、診療も楽な気持ちで受けていただけるようにと考えました。また、電子カルテを導入して患者さんの現状を医師やスタッフでより共有しやすいように改善しました。
診療の際に心がけている点などを教えてください。

患者さん一人ひとり、そして地域全体のかかりつけ医であるよう心がけています。私は内科領域の診療を通じて地域医療を推進する日本臨床内科医会にて、私も関わって作成した同会の「かかりつけ医宣言」は、私の思いと重なっています。それは幅広い医学的視野・知識で地域の皆さんに適切な医療を提供することを前提に、「病気の予防や早期発見、体力維持のための生活指導などによって健康寿命の延伸のお手伝いをすること」、「高齢の患者さんを地域の中で最期まで支える体制を整えること」、「常に患者さんに寄り添い、地域で安心して暮らしていただくこと」、というものです。当院は駅から少し離れていますが、これは周辺の方は駅前まで行かなくても近くで受診できるという意味。今後は義父の代から続く地域密着の医院を次世代につなげたいと思っています。
在宅医療は万一のとき駆けつけられる範囲と人数で
在宅医療にも力を入れていると聞きました。

当院に通院されていた患者さんが高齢などで通うのが難しくなったケースが中心ですが、最近では病院からの紹介も増えました。ただ当院で引き受けるのは私が自転車で回れる範囲で、訪問先も10件ほど。これは万一のときにすぐ駆けつけられるようにしたいからです。さらにクラウドサービスとスマートフォンで在宅の患者さんの体調を常時チェックし、24時間対応の訪問看護ステーション、休日・夜間も処方可能な調剤薬局、容体の急変時に入院ができる病院など、多職種・多施設と連携して、在宅の患者さんを24時間ケアしていきます。こうした枠組みではリアルタイムな情報共有と適切な対応が鍵で、特に患者さんのご家族やヘルパーさんから状況報告を受けるケアマネジャーとの連絡は欠かせません。たとえ診療中の連絡でも、そのとき診ていた患者さんに詫びながら、ケアマネジャーさんからの相談に応じることはよくあります。
先生が在宅医療で気をつけていることを教えてください。
まずお引き受けする患者さんの情報を集めることで、ケアマネジャーさんやこれまでの主治医から内容を聞き取り、在宅介護のキーパーソンは誰かなども確認します。患者さんの生活状況も大事で、マンションか戸建てか、部屋の間取りがどうかによって、医療や介護で必要な支援も変わります。食事は1日2食という方に「1日3回、食後に服用」の薬を出しても混乱されますから、生活に合わせて飲む回数を減らした処方などの工夫も必要です。さらに私は訪問時には五感を重視し、部屋のにおいが違えば口腔ケアや排泄の問題を考えますし、長期間入浴していないと肌にも異常が見られます。そのようなケースはケアマネジャーさんと連絡を取り、衛生面に留意してホームヘルパーさんを増やすなど対応を図っています。そして転倒や誤嚥(ごえん)などのリスクは常に考慮しつつ、その人が楽しく暮らしていただくことを大切にしています。
認知症の方も多く診ておられるのでしょうか?
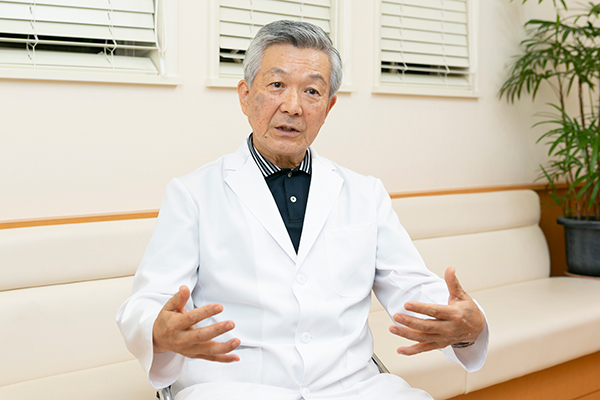
私は認知症サポート医として認知症の患者さんも診ています。高齢になれば多くの方が認知症になるのは仕方ないこと。それをご本人や周囲の方が受け入れる環境と心の準備が重要なんです。無理にやらせる必要はないのですが、できれば相性のいいホームヘルパーさんと一緒に定期的に外出するなど、社会性のある暮らしを送っていただきたいですね。デイサービスでは認知症の方同士、話がかみ合わなくても楽しく過ごされたりしていますね。また診療の際は相手の話を傾聴し、私はゆっくりと話し、こちらがその方を認めていることが伝わるようにと思っています。院内のバリアフリーはもちろん、心のバリアフリーも大切にしています。
心の通う多職種連携で、目黒区の孤独死ゼロを目標に
理学部、薬学の大学院を経て医学部と、ご経歴が多彩ですね。

結果としてそうなりましたね(笑)。もともと生き物が好きで大学もその方面を考えていたところ、高校の先生から「生物科より化学科のほうが就職の見込みがある」と助言され、東京理科大学の理学部化学科に入学しました。授業は興味深かったものの、入部した生物部では野外の生物調査にもよく出かけました。その流れで、卒業研究は生物部の顧問だった先生のもとで微生物を研究。さらに研究を深めたくて、大学院修士課程は微生物が研究できる薬学系を選び、博士課程で理学系に戻って博士号を取得し、その後に獨協医科大学医学部に入学したという流れです。実は私は博士課程の時に結婚していて、妻の父が当院の前院長なんです。私が博士課程修了前、「博士号も取れて仕事の見込みもあり、ようやく生活も安定しそうです」と報告に伺ったところ、「できれば医学部に入って、医院を継いでくれないか」と話があったのです。
大学院博士課程修了後に医学部に進まれたのですか。
ええ、入学時にすでに2人の子どもがいたので、薬剤師になって働いていた妻には非常に苦労をかけ、双方の実家にも世話になりました。医学部卒業後は大学病院などでの初期研修後、がん治療も手がける消化器内科を専門にしました。しばらくして体調を崩した義父を週1回、2回と手伝う機会が増え、1987年には病院を退職して当院を引き継いだのです。これまで化学、生物学、薬学、分子生物学、医学などを学んできましたが、すべてが今に生きていて無駄は何一つありませんでしたね。また現役入学の同級生とは10歳違いで気後れした面もありましたが、この年齢になるとその程度の差は気になりません。多方面で活躍する同級生とも力を合わせて、地域医療に取り組んでいます。
これからの目標を教えてください。
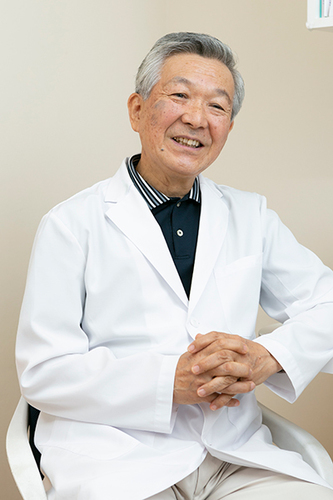
私というより地域の目標として「目黒区での孤独死ゼロ」を掲げています。お年寄りがご自宅で亡くなっても周囲が気づかないような事態をなくすには、医療や福祉・介護の従事者や地域のキーパーソンの「顔の見える連携」を一歩に進め、常にコミュニケーションを取り、積極的に協業するような「心の通う連携」が重要です。今後はリアルタイムに情報交換を行い、お年寄りのご家庭の状況をフォローするような地域づくりを目黒区医師会や行政とも協力して進めたいと考えています。また個人的には私がこれまでに得た経験を論文などで発表し、今後、地域医療を担う若い世代にも役立ててもらえたらと思っています。






