鎌田 絵里子 院長の独自取材記事
上野毛眼科
(世田谷区/上野毛駅)
最終更新日:2025/07/22

上野毛駅から徒歩2分、閑静な住宅街にある「上野毛眼科」は、2025年に開業20周年を迎えた眼科医院。れんが壁の外観が落ち着いた印象で、大きなハート形の葉をつけた観葉植物ウンベラータやアンティークデスクが置かれた院内はアットホームな雰囲気だ。「このウンベラータは開業当初から飾ってあるんですよ」とにこやかに話してくれたのは、鎌田絵里子院長。2018年に父である前院長の逝去に伴い医院を継承し、ドライアイ、アレルギー性結膜炎、眼精疲労などの日常的な目のトラブルのほか、緑内障や白内障、加齢黄斑変性症といった疾患や網膜疾患のレーザー治療など眼科疾患全般を幅広く診療している。「患者さんが安心して来院でき、温かい気持ちで帰っていただける医院でありたいと思っています」と語る鎌田院長に話を聞いた。
(取材日2025年6月3日)
父母が開いた医院が20周年。これからも地域のために
こちらの医院の成り立ちを教えてください。

当院は、眼科の医師である父と母が2005年に開業した医院です。長年、父と母2人で診療をしていましたが、2018年に父が亡くなり、私が医院を継承しました。母は今も当院での診療を続けています。私は東京慈恵会医科大学を卒業して、同大学附属柏病院や東急病院、康心会汐見台病院のほか、往診専門の医院などで診療してきました。父が亡くなる前から、少しずつ当院での診療に携わっておりましたが、父と一緒に仕事をした期間は、私にとって本当に貴重な期間だったと思っています。
どんな医院をめざしていますか?
開業当初より父はずっと、「患者さんが安心できて、温かい気持ちになって帰ってもらえる診療所をめざしたい」と言っていました。その思いはスタッフにも共有していますし、私も引き継いでいます。2025年は開業から20周年の節目の年になりますので、その思いが変わらないことをあらためてスタッフたちと再確認しました。患者さんに安心して帰ってもらうために、知識と技術、設備をアップデートしていくのはもちろんのこと、患者さんが何を求めてここに来ているのかをしっかりお聞きすることも大事にしています。皆さん不安を抱えていらっしゃっていると思いますので、できる限りわかりやすい言葉でお伝えして、不安を取り除けるような情報の提供も心がけています。
どのような患者さんがいらっしゃっていますか?

近隣にお住まいの方がほとんどで、小さなお子さんからご年配の方まで幅広く来院されています。地域の小・中学校で学校医もしていますので、その学校の子たちも来ますし、土曜日は働き世代など比較的若い方も多いですね。ニーズもさまざまで、ドライアイ、アレルギー性結膜炎、眼精疲労などの日常的な目のトラブルから、緑内障、白内障、加齢黄斑変性症、糖尿病網膜症の患者さんもおられます。当院では、主要な8種類のアレルゲンを20分で同時に確認できる血液検査を導入しています。また、網膜疾患のレーザー治療も行っております。そのほか、手術が必要な症例は東急病院や東京医療センター、東京慈恵会医科大学付属病院、昭和医科大学病院などの連携病院や、患者さんが希望される病院にご紹介し、術後は当院でフォローしています。地域のクリニックとして、必要に応じて高度医療機関に速やかにつなげることも大事な使命だと考えています。
全世代の眼科疾患に幅広く対応
特に力を入れている診療は何でしょうか?

特に緑内障とドライアイに力を入れています。緑内障は視野が徐々に欠け視力が低下していく病気ですが、自覚症状がほとんどなく、健診やほかの症状で受診した際に偶然見つかることがほとんどです。当院にはOCTという網膜の断層画像を撮影する機器もあり、この機器で視神経繊維層の厚さを測ることで、通常の視野検査では発見できない早期の緑内障の発見に努めています。また、世田谷区の特定健康診査・長寿健康診査では眼圧・眼底検査を受けることができ、当院でも対応しています。内科の先生からの紹介が必要ですが、ぜひ区の健診を活用して緑内障の早期発見・早期治療につなげていただきたいですね。ドライアイは点眼薬でコントロールが難しい場合には涙点プラグ挿入術をご提案しています。これは涙の排出口である涙点にプラグを挿入して涙の排出を抑える治療法で、目の表面に涙を保つことができれば症状の改善が期待できます。
そのほか、眼科の医師として気になる症状はありますか?
ここ数年で眼精疲労を訴える方が増えた印象があります。自宅でのテレワークに伴い、パソコンを使って作業する時間が増えたことが影響しているのかもしれません。眼精疲労の原因は目の病気や全身の病気、環境因子などさまざまです。点眼加療も行いますが、原因を精査し、対策を講じることが大切です。若い患者さんには度数の強すぎる眼鏡やコンタクトレンズを使っている方も多いのですが、度数が不適切なことで眼精疲労を引き起こしていることもあり、視力検査を行って適切な度数のレンズにするようお勧めしています。またパソコン周りの環境をお聞きして、モニターの位置は40㎝以上離し、視線が水平よりやや下になるようにする、部屋の照明を適切な明るさに調整する、意識的にまばたきを多くするといったアドバイスもしています。
お子さんの診療に関してはいかがでしょうか。

データ的にも体感としても、お子さんの近視が増加していると思います。タブレット学習なども増え仕方がない面もありますが、強度の近視は将来、緑内障など含めさまざまな病気になるリスクが高まることがわかっています。学校の眼科検査で視力低下が指摘されたり、物を見るとき目を細めたりしている場合は、早めに眼科を受診していただきたいと思います。当院では目の緊張を緩和させる機器でトレーニングを行っています。この機器をのぞいて立体風景を見ることで目の緊張の緩和が図れ、5分の使用で遠くの景色を長時間見つめるのと同等の緊張緩和が期待できるとされています。また、タブレット型端末やスマートフォンは30cm以上離して見る、適度に目を休める時間つくる、外遊びの時間を確保するなど、生活習慣の改善も大切です。
自覚のない緑内障。40歳以上は定期検診で早期発見を
同じ眼科の道に進まれて、ご両親は何かおっしゃっていましたか?

父からは、子どもの頃には「勉強しなさい」と言われたことはなかったのですが、医師になってからは「とにかく勉強しなさい」と言われるようになりました。特に眼科を専門に選んだ後は「幅広くなんでも診療できるように、専門以外の分野も積極的に勉強しなさい」と口うるさく言われましたね。勉強会などでは、あえて自分の専門外や不得意な分野の講演も積極的に聞きにいくようアドバイスしてくれて、今も勉強会へ行くたびに思い出します。私が今、勉強を続け、知識をアップデートしているのは、医師になってからの「勉強しなさい」という父の言葉が根底にあるのかもしれません。
休日はどのように過ごしていますか?
趣味はいろいろあるのですが、中でも読書が好きで、家の中で家族と一緒の空間で本を読むことが一番のリフレッシュになっています。さまざまな分野の本を読むのですが、とにかく知識を得ることが楽しくて。その趣味が高じて、資格取得も趣味のようになっています。宅地建物取引士やファイナンシャルプランナー、証券外務員の資格も取りました。写真集や図鑑を見るのも好きで、美術検定や世界遺産検定も挑戦しましたし、科学にも興味があって、今度は元素検定も受けようかなと考えています。植物を育てるのにもはまっていて、実は、待合室のニッチに置いてある鉢植えは毎日違うんですよ。育てている鉢植えの中から調子のいいものを1つ持ってきて毎日取り替えているんです。
最後に、地域の方や読者に向けてメッセージをお願いします。
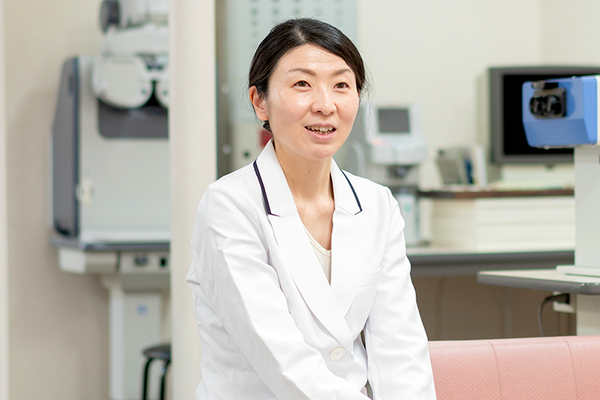
緑内障は40歳以上の20人に1人が発症するといわれ、進行すると失明する可能性が高い病気です。しかし、早期に介入して治療することで、症状の進行の抑制は期待できます。目に何か違和感があれば、気軽にご相談いただきたいのですが、緑内障は自覚症状がありませんので、定期検診を受けることが大事です。早期発見のためにも、40歳になったら定期検診を忘れないでいただきたいです。日本眼科学会認定眼科専門医として、地域の方々に信頼され、質の高い的確な医療を提供できるよう、日々努力してまいります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。






