難波 龍人 院長の独自取材記事
駒沢なんば眼科
(世田谷区/駒沢大学駅)
最終更新日:2025/10/10
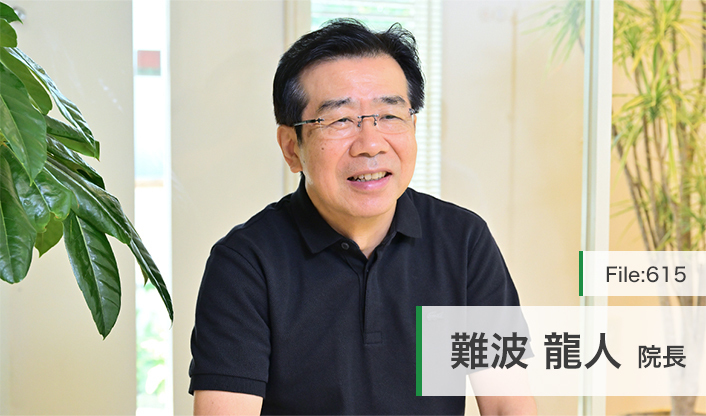
駒沢大学駅から4分ほど歩いた、閑静な住宅街にある「駒沢なんば眼科」。地域に根差した「目のかかりつけ医」として親しまれている院長の難波龍人先生。日本眼科学会眼科専門医の資格を持ち、大学病院で緑内障の診療に携わる一方で、神経眼科や小児の斜視・弱視といった専門性の高い分野にも研鑽を積んできた。結膜炎やドライアイ、ものもらい、白内障や緑内障の検査・治療など、眼科診療全般に注力。子どもの近視や若年層に増加傾向の急性内斜視についても、生活面のアドバイスも含めて丁寧に伝える他、糖尿病性網膜症や加齢黄斑変性症などの早期発見にも努める。同院の診療や患者への思い、診察を待つ間のクリニックとしての工夫について、難波院長に聞いた。
(取材日2025年7月23日)
さまざまな目の病気に対応する「目のかかりつけ医」
ご経歴と開業の経緯について教えてください。

子どもの頃から物作りが好きで、工学部への進学を考えたこともありましたが、眼科医である父の背中を見て育ったこともあり、自然と医学の道を志すようになりました。大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)を卒業後、同大学医学部眼科学教室に入局し、緑内障を専門とされる教授のもとで知識を深める他、北里大学では神経眼科を学び、斜視や弱視についても研鑽を積みました。そして両大学の医学部講師を経て、1999年に有楽町駅前にて開業。充実した診療を行っていましたが、場所柄、患者層はビジネスマンが中心に。私の理想とする開業医はお子さんからお年寄りまで幅広く診療する地域に根づいたホームドクターとしての診療をめざしていたため、2006年に家族層の多い現在の場所に移転しました。
こちらの診療にはどのような特色がありますか。
当院は、幅広い眼科疾患に対応する地域密着型の「目のかかりつけ医」です。結膜炎やドライアイ、白内障や緑内障など、加齢に伴う病気といった一般的な眼科疾患すべてに対応する他、小児の斜視や弱視、スマートフォンによる急性内斜視や近視の進行といった現代特有の視力トラブルにも力を注いでいます。特に、光干渉断層計(OCT)や視野検査を活用した緑内障や加齢黄斑変性の早期発見に注力し、糖尿病網膜症など内科疾患に関連する眼疾患は、近隣の医療機関とも連携して治療しています。医療機関は病気を治療する場であると同時に、日々新たな患者さんとの出会いの場。初診で訪れた患者さんが医師やスタッフと初めて顔を合わせ、話を交わすことで互いの理解を深め、良好な関係を築くことが治療にも良い影響をもたらすと考えています。病気がきっかけであっても、一人ひとりとの出会いを大切にし、心のつながりを重視した診療をめざしています。
緑内障の検査・診療について教えてください。

当院では、緑内障の早期発見・診断・治療に力を入れています。緑内障は視神経が障害され徐々に視野が狭くなる病気で、加齢によるもの、別の病気の合併症など、その原因はさまざま。多くのケースで自覚症状が乏しいため、早期の発見と継続的な管理が極めて重要です。当院では光干渉断層計による網膜の検査をはじめ、視野検査や眼圧測定など複数の検査を組み合わせ、初期段階での異常も見逃さないよう丁寧に診察を行っています。視野検査は、まず苦痛を感じるものではありませんので、気軽に受けていただきたいですね。特に、日本人に多いとされる正常眼圧緑内障にも対応し、眼圧だけに頼らない診断体制を整えているのが当院の特徴です。緑内障は発症すると治療は困難で、欠けた視野が元に戻ることはありません。点眼薬による治療を中心に、場合によってはレーザー治療や手術などで、進行の抑制と視機能の維持を図ります。
目の健康を守り抜くため、早期発見・治療を
早期発見・治療の重要性について教えてください。

やはり、目の病気は自覚症状が現れにくく、気づかないうちに進行してしまうことが多いという点で、早期発見が何よりも重要です。特に緑内障は、視野が徐々に欠けていく病気で、放置すれば失明のリスクもあるため、光干渉断層計や視野検査器などを活用した定期的なチェックが欠かせません。また、糖尿病性網膜症のように内科的な疾患と関連して起こる目の合併症もあり、眼科と他の診療科が連携して診ることが必要です。白内障も加齢とともに進行する代表的な病気ですが、早期に発見し、適切な時期に治療することで生活の質の改善につなげられます。当院では幅広い年代の患者さんに対し、こうした疾患の早期発見と予防に努めています。
目の病気の予防には、定期的な通院が有用なんですね。
たとえ検査や診察で異常が見られなかった場合でも、定期的な通院と継続的な生活習慣の見直しで、目の疾患を予防することが重要です。緑内障であれば40歳を超えたら一度は検査をし、目の状態によって定期的な検査が必要になることもあります。また糖尿病と診断されたら、合併症である糖尿病性網膜症を進行させないために、内科などで受検した各種検査結果をご持参いただき、眼科もぜひ受診していただきたいですね。視力が下がった、黒点・糸くず・蚊のようなものが浮いて見えるようになったなどの大きな違和感から、目がゴロゴロするといった日常にもありがちな目のお悩みまで、どんな症状でも何だかおかしいなと思ったら受診を検討してください。
目の健康について、お子さんのいる家庭や若年層に伝えたいことはありますか。

世界的に子どもの近視増加が問題となっています。近視は遺伝だけでなく、外遊びの減少、スマートフォンなど近くを見る時間の増加といった環境要因も、大きく影響しているといわれていますね。スマートフォンの過剰使用や眼鏡の過矯正も問題視されています。また10~20代で急増している急性内斜視は、生後6ヵ月以上で突然発症する、目の向きが内側に寄る症状。人間は近くを見る時に眼球を内側に寄せてピントを合わせていますが、この状態が長く続くと眼球が元に戻りにくくなり、遠くを見た時に物が二重に見えるようになります。当院では乳幼児の屈折異常や斜視を恐怖心なく検査できるようレフラクトメータを導入し早期発見に努め、必要に応じて点眼薬も使いながら、生活習慣の見直しを促し、目の状態を改善していきたいです。
電話での呼び出しなど、待ち時間への工夫が好評
待ち時間の負担軽減について工夫していることはありますか。

実は当院では、あえて予約制を導入していないんです。その理由は、診療には緊急性のあるケースや予想外の病気が見つかることもあり、予定どおりに診療を進めることが難しい場合もあるからです。そういった時に、前の患者さんの診療が長引いて予約時間が来ても診察や検査ができなかったり、予約優先を徹底して緊急度の高い症状で来院された患者さんが後回しになったりなど、予約制にすることが、かえって不満や不安を与えてしまうこともあります。現在は、混雑時には一時外出をご案内し、順番が近づいたらお電話でお呼びする方法を取っています。こうした対応を通じて、極力待ち時間の軽減に努めています。
鉄道がお好きで、院内でも模型を走らせていると伺いました。
私は鉄道ファンで、箱根、江の島、熊本、京都の嵯峨野など全国の路線を訪れ、風景を写真に収めたり水彩で描いたりしています。当院の受付の上部ではスイスの登山鉄道の模型を走らせており、数分に一度ホーンを鳴らして出発する場面を心待ちにしているお子さんも多いんですよ(笑)。鉄道Tシャツを着用してきたり、診察時に鉄道の話をしてくださったりする患者さんもいて、交流のきっかけにもなっています。人とのつながりが広がるのも、この趣味の魅力だと感じています。
地域の方へのメッセージをお願いします。
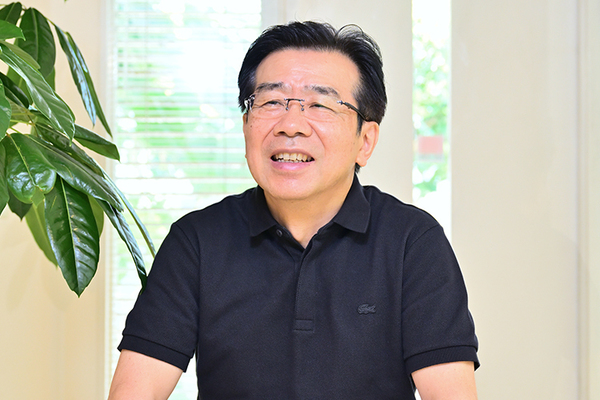
目に違和感や異変を感じたら、迷わず早めに病院を受診することが大切です。問題なければ安心して帰れますし、もし問題があれば詳しい検査や治療に進めます。忙しい日常の中で「大したことないかも」と思いがちですが、放置すると症状が悪化し、取り返しのつかないことにもなりかねません。特に、目が見えなくなることは生活に大きな影響を与えるため、早めの対処が重要です。痛みがある場合はすぐに来院される方が多いですが、痛みがなくても異変を感じたらためらわずに受診してください。「かかりつけ医」として、目だけでなく全身のことも含めて相談に応じ、必要があればより詳細な検査ができる医療機関へ紹介する体制を整えております。早期発見と治療が何よりも大切ですので、気になることがあれば気軽にご相談ください。






