- TOP >
- ドクターズ・ファイル特集一覧 >
- 新型コロナウイルスについて正しく知ろう
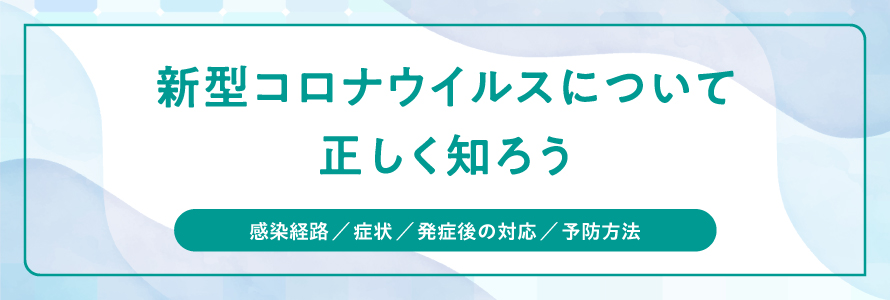
(公開日2020年3月26日/更新日2023年6月30日)
2019年末から世界中で大流行した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、私たちの生活はさまざまな制約を受けました。日本では2023年5月8日から感染症法上の位置づけが、これまでの「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症」に変更されました。しかし、新型コロナウイルスがなくなったわけではありませんから、感染予防や感染したときの対応はしっかりと考えておく必要があります。東京都病院協会常任理事を務める竹川勝治医師監修のもと、「Withコロナ」時代の基礎知識をまとめました。
そもそも、コロナウイルスとは
実はコロナウイルスは私たちの身近に存在するポピュラーなウイルスです。日常的にかかる風邪の10~15%(冬の流行期は30%程度)はコロナウイルスが原因とされ、感染しても多くの場合は軽症で済みます。しかし、コロナウイルスにはさまざまなタイプがあり、中には「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や「中東呼吸器症候群(MERS)」など、致死率、重症化率の高い病気を引き起こすものもあります。
新型コロナウイルス感染症とは
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、専門的にいえば「SARS-CoV-2」というコロナウイルスの一種に感染することで発症する感染症です。2023年5月9日までに日本では3380万件の感染が確認されています。多くは軽症か無症状ですが、人によっては重症化し、死亡することもありますので注意が必要です。潜伏期間は、現在流行しているオミクロン株では多くの人が2~3日程度で、長くとも7日以内がほとんどとの報告もあります。また新型コロナウイルスは変異するスピードが速く、感染力や毒性も変化しますので、常に新しい情報を得ることを心がけてください。
感染経路は?
新型コロナウイルスの感染経路は主に3つです。
飛沫感染
感染者が発するくしゃみ、咳などによる飛沫(唾液など)に含まれるウイルスが口や鼻、目から入り込むことによって感染することを飛沫感染といいます。特に屋内などで一定の時間、お互いの距離が十分に取れない環境に置かれたときは注意が必要です。近距離で多くの人と会話をする状況では、咳やくしゃみなどをしなくても、感染を拡大させるリスクがあります。
エアロゾル感染
飛沫よりも小さな液体粒子や乾燥した粒子をエアロゾルと呼びます。飛沫は放出されてから数秒から数分で落下しますが、エアロゾルは空気中を数分から数時間にわたって浮遊します。ウイルスを含んだエアロゾルを吸い込むことで起きる感染がエアロゾル感染です。そのため密閉された換気の悪い空間などでは、感染者から少し離れた場所でも感染するリスクがあります。
接触感染
感染者が咳やくしゃみをしたときに手で押さえるとウイルスが付着しますが、その手で物に触れるとさらに拡散されます。このように、接触によって感染することを接触感染といいます。電車やバスのつり革、ドアノブ、エスカレーターの手すり、スイッチなど、多くの人が触れるものを通じて感染することが多いとされています。
主な症状は?
初期症状

新型コロナウイルス感染症の主な初期症状は、発熱、頭痛、体のだるさ、咳、喉の痛みなどで、風邪やインフルエンザの症状に似ています。ウイルスの株(タイプ)にもよりますが、味覚や嗅覚の異常を伴うこともあります。重症化すると息切れや呼吸困難、胸痛などさまざまな症状が出現します。 オミクロン株に関してはワクチン接種の普及により感染してもほとんど無症状の人もいるため、注意が必要です。また、ワクチンを接種できなかった人の場合症状が強く出るケースがありますので、これもご自身で、意識したほうがよいでしょう。
重症化のリスク
新型コロナウイルス感染症は、重症化すると呼吸困難などの呼吸器症状を引き起こす他、さまざまな重篤な病気を発症させたり、悪化させたりすることがあります。特に高齢者や心血管疾患、糖尿病、慢性呼吸器疾患、がんなどの基礎疾患のある人は重篤な病気につながりやすいため、感染予防を徹底しましょう。
発症したら
新型コロナウイルス感染症の位置づけが「5類感染症」に変更されたことにより、医療体制が変わりました。これまでは限られた医療機関だけが診療していましたが、今後は幅広い医療機関が診療するようになります。 お勧めの方法は普段からかかりつけのクリニックを決めておき、初期症状が出た段階で受診することです。医療機関では院内感染を防ぐために受診のルールを決めていることが多いので、あらかじめ風邪のような症状が出たときはどうしたらいいか確かめておくか、受診する前に電話して聞きましょう。かかりつけ医がいない場合は、自治体のホームページや相談電話を利用して、対応できる医療機関を探してください。感染拡大している時期は医療機関も混雑することが予想されます。新型コロナウイルスの検査キットを自宅に常備しておき、検査結果と症状に応じて受診するのも一つの方法です。
発症後の対応は
5類感染症に移行したことにより、法律に基づく政府からの入院措置・勧告や外出自粛(自宅待機)要請は行われなくなります。ただ、発症後の翌日から起算して5日間は外出を控えることが推奨されています。また、5日を経過した後も発熱、痰、喉の痛みなどがあれば症状が治まって24時間程度は外出を控えることが推奨されます。学校の出席停止期間も同じです。新型コロナウイルスは変異が激しく、今後も状況が変わることが考えられます。迷ったらかかりつけ医に相談してみましょう。流行しているウイルスの性質や地域の状況などを踏まえてアドバイスしてもらえますよ。
検査
2023年5月20日現在、国が新型コロナウイルス感染症の診断に用いる検査として承認し、健康保険が適用されるのはPCR検査と抗原検査です。研究用として抗体検査キットも市販されていますが、体外診断用医薬品としては認められていません。
PCR検査
PCR検査は鼻咽頭ぬぐい液か唾液を採取した検体の中に、新型コロナウイルスを特徴づける遺伝子配列があるかどうかを調べる検査です。少ない量のウイルスも検出できますので症状が軽くても正確に診断できる可能性が高い検査です。ただ、ウイルスの検出に数時間を要し、さらに検体を検査機関に搬送する時間もかかります。
抗原検査
抗原検査は検体の中に新型コロナウイルスを特徴づけるタンパク質があるかどうかを調べる検査です。抗原定性検査と抗原定量検査がありますが、抗原定性検査は鼻咽頭ぬぐい液を用います。検体を採取した場所で約30分後には結果がわかりますので、クリニックなどでよく利用されています。抗原定量検査は鼻咽頭ぬぐい液と唾液のどちらでも検査可能で、抗原定性検査より少ない量のウイルスを検出できる精度の高い検査ですが、検体を検査機関に搬送して実施しますので、そのぶん時間がかかります。
ワクチン
新型コロナウイルス感染症に対して、感染予防および重症化予防の効果が認められているのはワクチン接種です。ワクチンとは病原体を構成する物質などをもとに作った薬です。ワクチンは病原体を直接攻撃するのではなく、体の中にその病原体に対する免疫を作ることで病原体を減らします。人口の一定割合以上の人が免疫を持つと、感染症の流行も抑えられます。2023年5月現在、日本で接種されている3種類の新型コロナウイルス感染症ワクチンは、ウイルスの増殖に関係するスパイクタンパク質という部分をもとに作られたもので、ワクチンを注射することで体内にウイルスを攻撃する免疫ができます。
ワクチンの効果と副反応
日本で接種されている新型コロナワクチンは臨床試験でいずれも十分な感染予防効果・重症化予防効果を示したワクチンです。ただワクチンの効果は100%ではなく、ウイルスが変異すると感染予防や重症化予防の効果が下がることもあります。また、副反応もあります。主なものは接種部位の痛みや疲労、頭痛などで大多数は数日以内に回復しています。しかし、まれにアナフィラキシーなど重篤な副反応が出ることもあります。接種を受けるかどうかは、年齢や基礎疾患、流行しているウイルスなどを踏まえて総合的に判断する必要があります。
(参考:厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/)
予防
新型コロナウイルスの感染予防の基本は、「①手洗い、②咳エチケット、③3密を避ける」の3つで、インフルエンザ対策と同様です。
手洗い

石けんやアルコール消毒液などによる手洗いが重要です。ドアノブや電車のつり革などさまざまなものに触れることにより、自分の手にウイルスが付着している可能性があるため、外出先から帰宅した際や調理の前後、食事前などにはこまめに手を洗いましょう。手洗いの際は、手のひらだけでなく、指先や爪の間、指の間、手首も忘れずに洗うことが大切です。
(参考:首相官邸ホームページ 「手洗い」)
咳エチケット
咳エチケットとは、病気を他の人にうつさないため、咳・くしゃみをする際にマスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻を押さえることです。マスク着用時は、しっかりと鼻と口を覆うことが大切。マスクが入手できない場合は、ティッシュやハンカチで鼻と口を覆うか、袖で口・鼻を覆うだけでも、飛沫の飛散を防ぐことができます。普段の生活では原則的にマスクをする必要はなくなりましたが、病気の人や高齢者が集まる病院やクリニック、薬局、介護施設などに行く際や、混雑した公共交通機関乗車時にはマスク着用を心がけましょう。
(参考:首相官邸ホームページ 「咳エチケット」)
密を避ける
密接・密集・密閉を「3密」と呼ぶようになりました。密閉された換気の悪い部屋などに多数の人が集まり、近い距離で会話したり歌ったりするような場所は感染リスクが非常に高くなります。感染拡大時にはできるだけ3つの密が重ならないように注意しましょう。「密」が高まるときは、部屋の換気、マスク着用、大声での会話を避けるといった対応を心がけることで、感染リスクを下げることができます。
(参考:首相官邸ホームページ 「3つの密を避けましょう」)
家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合
同居されているご家族は、家庭内感染を防ぐため、以下の8点にご注意ください。
- 感染が疑われる人(以下、患者)とは部屋を分け、患者はできるだけ部屋から出ない
- 患者の世話はできるだけ限られた人が行い、妊娠中の人や持病のある人は避ける
- マスクを装着し、外す際はゴムやひもをつまんで表面に触れないようにする
- 手洗い、アルコール消毒を徹底する
- 定期的に部屋の換気をし、共有スペースや他の部屋の空気も入れ替える
- ドアノブやベッド柵など、手で触れる共有部分を薄めた塩素系漂白剤で消毒する
- 体液で汚れた衣服やリネンは手袋とマスクをつけて家庭用洗剤で洗い、完全に乾かす
- 鼻をかんだティッシュなどのゴミはすぐにビニール袋に入れ、密閉して捨てる
※参考:2020年3月9日時点 厚生労働省『新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)』
まとめ
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、これまであったさまざまな行動制限が緩和されました。しかし、今後もいつ流行拡大が来ても不思議ではありません。ぜひ、読者の皆さんにお勧めしたいのが、普段から健康の相談に乗ってくれるかかりつけ医を持つことです。あなたやご家族が「コロナかもしれない」と不安になったとき、持病や地域の感染状況なども踏まえてきめ細かく対応してくれるはずです。重症化したときには専門的な治療が受けられる病院へ紹介し、子どもの幼稚園や学校はいつまで休めばいいのか、ワクチン接種は受けたほうがいいのかといった相談にも応じてくれるでしょう。常備していた検査キットで陰性であっても、症状が重ければ別の病気である可能性がありますから受診してください。気軽に受診できるのがかかりつけ医です。
また、5類感染症に移行したことで、お住まいの地域の検査・医療体制も変更されています。自治体のホームページなどで受診方法やその都度の感染状況をチェックするようにしましょう。
厚生労働省からの最新情報、参考URL
監修医師

東京都病院協会常任理事
竹川 勝治先生
1987年北里大学医学部卒業。同大学病院勤務を経て、1933年に協和病院へ。創設者である父の後を継ぎ1996年より愛育会理事長。専門は泌尿器科。北里大学医学部非常勤講師、東京都病院協会常任理事、江東区医師会監事、東京都老人保健施設協会理事・東京都国民健康保険団体連合会監査委員・医療関連サービス振興会運営委員を兼務。




