山口 幸一 院長の独自取材記事
内科・山口アーバンクリニック
(鹿児島市/騎射場駅)
最終更新日:2025/09/01

「山口アーバンクリニック」は騎射場駅より徒歩3分にある。消化器内科と肝臓を専門とする院長の山口幸一先生は、患者とのコミュニケーションを重視し、一人ひとりの悩みや不安に寄り添いながら、丁寧な対応に努める。症状だけでなく、生活習慣や背景を考慮した総合的な視点での診療を心がけている。診療後もオンライン勉強会に参加し、常に知識・技術のアップデートを継続しているという。「なんでも診る」という精神でできる範囲で対応し、必要に応じて各専門家と連携。朗らかな笑顔が印象的な山口院長に、同院の取り組みや診療時のモットーについて詳しく語ってもらった。
(取材日2025年8月4日)
健康長寿を守るために、かかりつけ医として全身を診る
医師を志したきっかけを教えてください。

もともと、人と関わる機会が多い仕事が良いなと思っていました。患者さんと一緒に悩んだり、考えたり、寄り添いながら歩んでいける仕事に魅力を感じ、医師という選択肢が浮かびました。そう考えるようになったのは大学に入る前くらいで、高校生の頃は、実は工学系の仕事にも興味があったんです。ですが、地元の鹿児島に残ることを考えたときに、「医療の道が良いかもしれない」と思うようになりました。
消化器系の内科から研鑽を積まれたと伺いました。
はい。最初は消化器系の内科に入局しました。当時は、消化器や肝臓の病気を抱える患者さんが非常に多かったんです。特に肝硬変や肝臓がんには本当に苦労しました。それが今では肝炎ウイルスの駆除がめざせるようになり、ウイルス性の肝臓疾患の患者さんは減ってきたと思います。一方で、脂肪肝を含めたメタボリックな疾患が非常に増えています。また、今は高齢の方が増えてきて、高齢者の医療が大きなテーマになっています。自分自身も年齢を重ねていく中で体が思うように動かないことや、体調の変化を実感するようになって、より一層、高齢者の悩みや気持ちがわかるようになってきたんです。ですから最近は、一緒にどう向き合っていくかという視点で医療を考えるようになってきました。
診療の際に大切にされているモットーは何ですか?
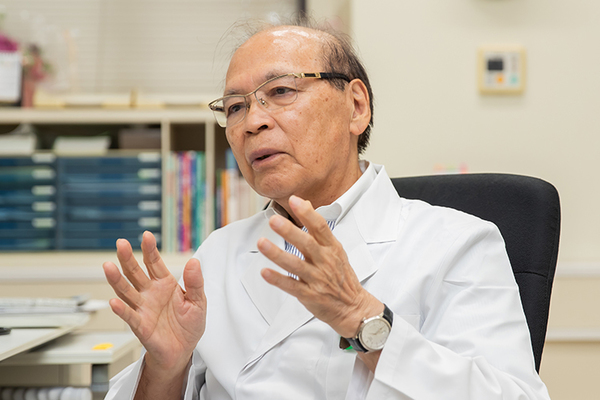
私は大型病院のように専門的な医療を提供するのではなく、かかりつけ医として地域の皆さんと向き合いながら、医療を提供する立場です。大切にしているモットーが2つあり、1つ目は、健康長寿を守るにはどうしたら良いかを考えています。病気を未然に防ぎ、健康な状態で長く暮らしてもらうために何ができるかということで、例えば、がんなどの悪性腫瘍ができていないかを早く見つけることが大事だと思っています。もちろん全部を見つけられるわけではないですが、できる限りの範囲で悪性腫瘍を拾い上げることができたらという思いで診療しています。もう1つは、血管をいかにフレッシュな状態に保てるかということです。血管は全身を巡るインフラのようなものですから、ここが詰まったり破綻したりすると、脳梗塞や心筋梗塞、腎機能の低下、足の血流障害など、さまざまな病気の引き金になります。だからこそ、糖尿病や高血圧など、全身の管理が重要になります。
些細なことでも相談できる、地域のかかりつけ医
患者さんとのコミュニケーションで意識されていることはありますか?

一番大切にしているのは患者さんは家族の一員であり、友人でもあるという考え方です。ですから、どんなに些細なことでも気軽に相談していただきたいと思っています。また、単に「血糖値が高い」「血圧が高い」と数値だけを伝えるのではなく、「なぜ糖が高いと良くないのか」「なぜ血圧を下げる必要があるのか」といった背景も含めて丁寧に説明し、患者さんご自身に納得して治療に取り組んでいただけるように意識しています。
どのような雰囲気で患者さんと接していらっしゃいますか?
患者さんが気軽に話ができるような雰囲気づくりを心がけています。場合によっては、冗談も交えながらお話しすることもあります。他院で受けた検査結果を持って来られて、「先生、これどう思う?」と聞かれることもあるんです。私は冗談で「そこで検査したんだから、そっちで聞いてよ」って笑いながらも、しっかりと細かく説明するようにしています。消化器の患者さんには、肝臓や胆のう、膵臓や膀胱などエコーでおなかを全体だけでなく、膀胱や前立腺まで診ることができます。急性胃腸炎などでは小腸や大腸の状態も見ながら、「今はこういう腸の動きだね」「こういう食事にすると良いよ」と、その場でリアルタイムの画像を確認していただきながらお話しすることを心がけています。
患者さんには具体的にどういったアドバイスをされているのでしょうか?

高齢者の方には身体機能の衰えであるフレイルを防ぐために、強い運動が難しい方でも、例えば座って足踏みをする、貧乏ゆすりでもいいから足を動かすといった、日常でできるアクションを提案します。年齢を重ねてもなるべく動かしてほしいですし、腎機能が極端に悪くない限り、たんぱく質も少し多めに取っていただくようにお話しします。私は10年ほどマラソンをやっていたこともあり、呼吸の仕方についてもアドバイスできるので、例えば喘息の患者さんには、腕の動かし方や胸の張り方、呼吸のリズムなどもご説明します。最近では、若い方でも自律神経のバランスを崩して、消化器系に不調を訴えるケースが増えています。例えば、過敏性腸症候群のようにおなかの不調を訴える方が少なくありません。そのようなケースでは、自律神経のケアの仕方などを表にしてお渡しするなど、できるだけ実践的なアドバイスを心がけています。
エコー検査を駆使した「見える診療」で安心を
最近感じる患者さんの変化はありますか?

やはり高齢の患者さんが増えてきました。高齢になると、血圧だけ、糖尿だけ、というふうに一つの病気だけを見ていれば良いというわけではなくなってきます。だからこそ、より総合的な視点で診て、お話をすることがますます大切になっていると感じます。自分自身も年を取ってきましたが、それが悪いことだとは思っていません。むしろ、自分が年を重ねることで「ああ、こういう不自由さがあるんだな」「なるほど、こういうことがつらいんだな」と、高齢者の悩みや困難が身をもって理解できるようになってきました。これは大きなことだと思っています。ちょっと言い過ぎかもしれませんが、今が医師として一番楽しく、充実している時期なのではないかと感じています。
今後の展望を教えてください。
私の今後の展望としては、患者さんの健康寿命をいかに延ばせる診療ができるかに尽きると考えています。ただ長生きするだけでなく、不自由なく、自立した生活を送れるようにサポートすることが重要です。血管系の病気で突然倒れてしまったり、フレイルの状態になったりすると、日々の生活の質は大きく低下してしまいます。だからこそ、一人ひとりの患者さんを診る際には、そうしたリスクを含めた視点を常に持つようにしています。
最後に、読者の方へのメッセージをお願いします。

少しでも体に異変を感じたら、どんな些細なことでも遠慮なく相談してほしいと思っています。血液検査でちょっと気になる数値が出た、なんとなく調子が悪い、あるいは「こんなこと聞いても良いのかな?」と思うようなことでも、私のわかる範囲でしっかりお話しします。例えば、眠れないなら薬を出しますで終わるのではなくて、薬をどう飲めば良いのか、どんな姿勢で寝たら薬がきちんと吸収されるか、細かいことも含めてお伝えします。実際、薬は小腸で吸収されるので、適した体の向きがあるとされます。診療の際はエコーを駆使して、首からおなか、見える臓器、血管系について可能な限りチェックするようにしています。気になることがあれば、まずは気軽にご相談ください。






