東 泰志 理事長、愛甲 孝 先生の独自取材記事
とそ総合クリニック
(鹿児島市/純心学園前駅)
最終更新日:2025/10/20
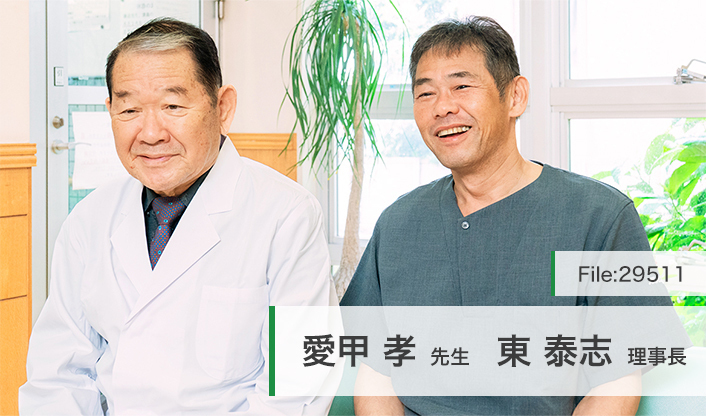
鹿児島市唐湊で50年以上地域医療を支えてきた「東内科」が、2025年7月より「とそ総合クリニック」へと名称を改め、総合的な医療を提供していく決意を新たにした。身近な存在でありながら19床の病床を備え、専門的な治療も行える有床診療所として、幅広いニーズに対応する同クリニック。院長の東泰志先生は、消化器外科医として、大学病院で多くのがん治療に携わってきた。加えて、がん治療の専門家である愛甲孝先生が新たに顧問として同クリニックに参画するようになったことも大きな強みとなっている。診断・治療レベルの向上が期待されるとともに、地域の大型病院や関連医師との連携もよりスムーズになるだろう。今回は、東院長と愛甲先生にクリニックの取り組みや診療への想いを聞いた。
(取材日2025年6月2日/情報更新日2025年7月1日)
外科の経験を生かし幅広く診られるクリニックをめざす
どのような患者さんが多いでしょうか?

【東院長】患者さんの年齢層は本当に幅広いです。当院は前院長の父から継承しましたが、もともと父が内科と小児科を診療していました。その流れで小学生から上は90歳を超える方までいらっしゃいます。中でも一番多いのは、やはり50代・60代・70代の方々ですね。最初は父の代から通ってくださっていた患者さんが多かったのですが、私が外科出身ということもあって、徐々に幅広い症状を抱える新しい患者さんが増えてきました。特に多いのは、高血圧などの生活習慣病の方です。ですが、消化器系を専門にしているので、「胃カメラをお願いします」という患者さんや健診での胃・大腸内視鏡検査の希望で来られる方もいらっしゃいます。
新たに愛甲先生が顧問に就任されたと伺いました。
【東院長】はい。愛甲先生に当院の顧問として加わっていただけることとなり、今後は外来診療やセカンドオピニオンの相談などで本格的に関わっていただく予定です。愛甲先生とのご縁は30年以上で、私が鹿児島大学の第一外科に入局した際、最初にご指導いただいた方でした。手術はもちろん診療の姿勢に至るまで、すべての基礎を教えていただきました。特に胃がんにおいては前線で活躍され、鹿児島大学名誉教授、ドイツ・ケルン大学の名誉教授といった肩書をお持ちで、「愛甲先生を知らない医師はいない」ともいわれるほどです。実は、プライベートでも深いご縁がありまして、私たち夫婦の仲人もしていただきました。
【愛甲先生】現代の医療は非常に複雑化しており、セカンドオピニオンの重要性もますます高まっています。第三者としての視点から、少しでも地域の皆さまのお役に立てることがあればと引き受けた次第です。
愛甲先生を迎えたことで、どんなことが可能になるのでしょうか?

【東院長】これまでは一人で診療してきましたが、今後はセカンドオピニオンや高度な外科的見解が必要なケースにも、愛甲先生と連携しながらより精密で迅速な判断が実現できるようになります。また、愛甲先生は鹿児島県内の医師たちとの幅広いネットワークをお持ちです。そのネットワークを生かし、地域の大型病院との連携体制もこれまで以上に強固になります。万が一の際のスムーズな紹介にも対応できるようになります。
「ここに来て良かった」と思ってもらえる医療を
クリニック名を変更された背景を教えてください。

【東院長】愛甲先生の教えは「最初から最期まで」。初期診断から手術、抗がん剤治療、看取りまで、一人の医師がすべてに責任を持つというものでした。特に地方では、他科の診療や内視鏡検査なども自分でこなす力が必要で、それを私は愛甲先生の背中を見て学びました。そんな愛甲先生が私に「あなたはもう十分にすべてできるようになっている。だから“総合”の名前をつけていい」とおっしゃったんです。その言葉に背中を押され、地域に根差し、幅広い診療を提供するという想いを込めて、「とそ総合クリニック」に名称を変更しました。
【愛甲先生】東先生はがんの診療を含め、プライマリケアから専門治療まで、非常に丁寧に対応されています。そんな東先生にふさわしいと思い、提案しました。
患者さんとのコミュニケーションで心がけていることを教えてください。
【東院長】一番大切にしているのは、患者さんを自分の一番身近な存在に置き換えて診療することです。例えば、50代・60代の女性であれば、自分の妻だったらどうするか。ご高齢の女性であれば、母だったらどんな治療を選ぶか。自分の大切な人を診る気持ちで、毎回患者さんと向き合うようにしています。私がめざしているのは、患者さんに「ここに来て良かった」と言っていただけるような医療です。心が少しでも軽くなるような、寄り添う医療が大切だと考えています。
患者さんのご家族とのコミュニケーションで意識されていることはありますか?

【東院長】特に大切にしているのは、信頼関係を築くことです。患者さんのご家族に「ここなら大丈夫」と感じていただくことが何よりも重要だと思っています。医療には限界があり、時には「これ以上の治療は厳しい」といった話を、お伝えしなければならないこともあります。その時も、やはり私たち医療者との間に確かな信頼関係がなければ難しくなります。私自身もスタッフも、医療には限界があることをよく理解した上で、それでもできる限りのことを尽くしたいと常に思っています。
【愛甲先生】大学病院のような大きな病院とは違い、地域に根差して開業し、一つのコミュニティーの中で医療を続けていくにあたっては、やはり患者さんご本人だけでなく、そのご家庭全体との信頼関係がなくては成り立ちません。そういう意味では、東先生は、専門性を存分に生かした医療を、この地域で家庭に寄り添いながら提供していけると、私は確信しています。
「総合的ながん治療の拠点」をめざして
今後力を入れていきたい診療はありますか?

【東院長】今後特に力を入れていきたい分野の一つが肛門疾患の診療です。この地域では専門の医師が少なく、手術が必要か薬で様子を見るべきかなど、的確な判断が重要だと思っています。また、がん治療においても体制を強化していきます。新たに、がんの薬物療法に精通した看護師と薬剤師が常駐することになり、抗がん剤治療に対してよりこまやかなフォローが可能となりました。副作用への対応や服薬管理だけでなく、メンタル面や経済的事情にも配慮した支援ができる体制を整えています。これにより、患者さんが安心して相談できる環境がさらに充実します。さらに、患者さんやご家族の負担軽減を目的としたレスパイト入院も積極的に取り入れています。これは、在宅療養中の一時的な休息を支援するもので、患者さんの生活の質を保つための重要な取り組みです。
今後の展望についてお聞かせください。
【東院長】がん治療は、現在、手術・抗がん剤・放射線・免疫療法など、さまざまな医療が組み合わされ、進歩を続けています。しかし、それでも限界があるのが現実です。私自身がこれから力を入れていきたいのは、統合医療的なアプローチです。具体的には、東洋医学的な観点を今の診療に取り入れていくことです。また、私が大きく影響を受けた愛甲先生は、多くの医療情報・研究をまとめ上げ、適切な医療方針を提示する医学のコーディネーターとしての能力に長けた方です。私もそうした姿勢を見習いながら、これからはがんのコーディネーター、病気のコーディネーターとしての立場を担っていきたいというビジョンがあります。西洋医学、東洋医学などを統合した医療を、この地で展開し、患者さんごとに適したオーダーメイドの治療を手がけたいと考えています。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。

【東院長】開業以来大切にしているのは、皆さんが「何か困ったことがあれば、いつでも気軽に相談できる場所」でありたい、ということです。自分の診療できる範囲のものはなんでも診療していきます。例えば、どのクリニックを受診すればいいのかなど、わからないことがあればご相談に乗りますし、症状に合わせたクリニックをご紹介することもできます。愛甲先生のコネクションでさまざまな大型病院を紹介することも可能です。お話を伺い、お悩みの原因は何にあるのかを一緒に考えていければと思います。
【愛甲先生】東先生は患者さんの視点に立って医療を進められる先生です。ぜひ、安心して、お気軽にご相談にいらしてください。






