山見 信夫 院長の独自取材記事
山見小児科
(日南市/日南駅)
最終更新日:2025/06/18

宮崎県南部の日南市にあり、市役所に隣接した場所で診療を行っている「山見小児科」。始まりは山見信夫院長の父が1960年に飫肥(おび)で開業。その後、現在の場所に移転したという65年の歴史を持つ小児科医院だ。2020年に同院を継承した山見院長は、日本小児科学会小児科専門医だが、小児科のほかにも内科、プライマリケア、スポーツ医学、潜水医学など、多岐にわたる分野に精通しているベテランドクター。診療の傍ら、海上保安庁などの潜水に関するアドバイザーも務め、現在は潜水医学に関する著書の英語版を制作中という一面も併せ持つ。「子どもの病気を治すだけでなく、ご家族に安心してもらえるように努めています」とやわらかな物腰で語る山見院長に、これまでの道のりやクリニックの診療内容について話を聞いた。
(取材日2025年3月28日)
最も弱い存在である子どもの助けになりたい
こちらの医院は先生のお父さまが開業されたと伺いました。

父が開業した時、僕はまだ生まれていませんでしたが、父は九州大学から宮崎県立日南病院に派遣され、小児科の初代医長に就任したと聞いています。その時に「日南の人たちが温かく、本当に良くしてくれたので、ここで開業したいと思った」ということを子どもの頃から幾度となく聞いていました。当初は飫肥地区で6畳2間を借りて開業したそうですが、そこが手狭になったため、僕が1~2歳の頃に現在の場所に移転しました。当時この辺りは一面田んぼでしたが、だんだん住宅が増え、毎日たくさんの患者さんが来院されていたのを覚えています。
先生が医師をめざしたきっかけと小児科を選んだ理由を教えてください。
もともと海と魚釣りが大好きで、瀬渡し船の船長に憧れていました。医師をめざしたのは、高校の時、「瀬渡し船をやるのは医師免許を取ってからで良いんじゃない? 医学部には今しか行けないんだから」と言われたのがきっかけでした。大学進学後も夏休みには漁師さんの家で1ヵ月住み込みで仕事をしたり、週末はダイビングショップでアルバイトをし、21歳でダイビングのインストラクターになりました。その延長で警視庁の潜水のインストラクターをしていたこともありますし、現在も海上保安庁やテレビ局の潜水に関するアドバイザーをしています。小児科を選んだのは、子どもの頃から身近な存在だったことと、病気の人を助けるのに全精力を注ぐなら最も弱い存在である子どもに注ぎたいという気持ちからです。
大学病院時代の経験で印象に残っていることはありますか?

大学を卒業して宮崎大学医学部附属病院(旧・宮崎医科大学医学部附属病院)に入局した当時は、大学に何日も寝泊まりすることも珍しくありませんでした。宮崎市や都城市の夜間急病センターの当直では、仮眠する間もないほど忙しいときもありましたが、自分の限界を感じることが楽しかったり、初めて診る病気をたくさん経験できたりして、楽しかった思い出ばかりが残っています。大学病院で小児科専門医の資格を取得してからは、内科や高齢医学について学びながら、潜水医学の研究もしたくて東京科学大学に移りました。当初は2年のつもりでしたが、楽しすぎて20年いてしまいました(笑)。こちらに帰ってきた理由は、大学では難しかったフィールドでの実験と小児科の診療を両立させることができるからです。自分のやりたいことを実現するためには、やはり生まれ育った地元・日南が最高の環境と思うようになったからです。
少しでも安心して帰ってもらえるような診療を
診察の際に心がけていることを教えてください。

特に意識していることはありませんが、皆さん不安な気持ちで来られているはずなので、少しでも安心して帰っていただけるようにと願いながら、絶対に治ってほしいという気持ちで診療しています。当院での治療が難しい場合は、専門の先生を紹介するなどして、患者さんとそのご家族が希望を持ち安心して過ごせるようなサポートができるよう心がけています。
特にこだわって診ている疾病はありますか?
一つの疾患にこだわらないのがこだわりかもしれません。小児科医が診る病気は皮膚や眼、耳、ちょっとした外科的な処置など全科にまたがりますから子どもに関するすべての病気を学びたいと思い、日本小児科学会小児科専門医のほかに、大学病院では総合診療の指導も専門的に行ってきました。また、大人の病気は子どもの発達段階から始まっていることが多いので、臨床内科についても専門的に学びました。加えて、子どもの病気は手術までできるようになりたいと思い、虫垂炎や鼠径ヘルニアなどを執刀していたこともあります。また、人は気圧の影響を受けて病気が発生することがありますから、高い気圧によって生じる病気を扱う高気圧医学と低い気圧によって生じる病気を扱う宇宙航空医学の分野にも携わり、ドクターヘリに乗務していたこともあります。部活動で体調を悪くされるお子さんも多いのでスポーツ障害も専門的に診てきました。
総合的に子どもたちを診ているんですね。

はい。今、それらの分野で身につけた知識を基盤に幅広く診療しています。外来ではお子さんを連れていらしたご家族を一緒に診ることも少なくありません。中高校生に成長されてからも通ってくださる方がいらして子どもも大人も包括的に診療したいと思っている僕にとってはとてもうれしいことです。生まれたときからの体質を知っていますからこまやかな診療ができると思っています。
先生の人生に影響を与えた人はいらっしゃいますか?
お世話になった方はたくさんいますが、一人だけ挙げるとしたら、小さい頃、魚釣りによく連れて行ってくれた近所の電気屋さんですね。ダイビングを始め潜水医学を研究する原点となったのが、子どもの頃の魚釣りがあったからです。道具の作り方から釣りのアルゴリズムまで、その方が細かく教えてくれました。子どもだからと軽く扱わず、優しく真剣に教えてくれたことが、その方を偉いなと思うようになった理由です。そういう経験から、僕も相手が子どもでも大人と同様、きちんと向き合い、丁寧に対応するよう心がけています。その方は最近亡くなりましたが、最期まで主治医を務めさせていただきました。
小さな相談にも対応できる医療を提供していきたい
休日の過ごし方や夢中になっていることを教えてください。

ダイビングや魚釣りに行けるのは年に1回か2回しかないので残念です。休日は研究にあてるか、本の原稿を書いています。28歳頃から数年前までダイビングの雑誌に連載を頼まれていました。多い時は月に5誌書いていた時もあります。2021年には『ドクター山見のダイビング医学』という著書を出版しました。現在は海外の出版社からその本の英語版を作りたいという依頼があり、英訳を終えて図版を入れたり校正したりしているところです。毎日編集者と英語でやりとりして、今はそれが忙しいですね。
健康のために実践していることはありますか?
僕自身としては特にありません。父はいつも「食べすぎない」「甘い物は控えめ」「20代半ばの体重を保つ」「毎日歩く」と言っていて、父自身、99歳になる今も元気に実践しています。私が「普通は実践するの難しいよね」と言うと「我慢すればいいだけよ」と言いきります。そう言われて考えたんですが、父に限らず戦時中の栄養失調を経験した人にとっては、どれも「ただ我慢すればいいこと」なのかもしれないですね。それが長生きの秘訣かどうかはわかりませんが、そういう姿勢が健康を維持する基盤になっているのかな、とも考えます。父は85歳まで一人で、僕が戻ってからは90歳まで一緒に診療していましたから、僕も85歳まで仕事ができればいいなとは思っています。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。
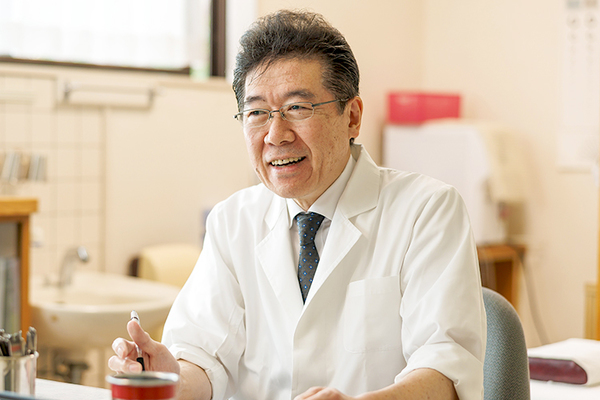
当院を選んで来院してくださるのですから患者さんには遠慮なく相談してほしいですね。僕がすべてを解決できるわけではないとしても、回復の糸口を見出せるかもしれませんから。僕が解決できないことは、専門の先生や医療機関を紹介するなどして、少しでも良い方向に進められるように努めます。優秀な知り合いの先生もたくさんいますので、紹介状代わりに症状や治療の経過を書いたメモを渡し、それを持って訪ねるように言うこともあります。そういった細かいことだけど安心につながる医療を提供していきたいです。子どもたちのため、そしてご家族のために一生懸命診察しますので、どうぞよろしくお願いいたします。






