田所 宏章 副院長の独自取材記事
田所耳鼻咽喉科
(新居浜市/新居浜駅)
最終更新日:2025/07/16

新居浜市徳常町の「田所耳鼻咽喉科」は、バス停留所の若水から徒歩約3分の場所にある、地域に根差したアットホームなクリニックだ。約60年前に、田所宏章(たどころ・ひろあき)副院長の祖父が開業し、3代にわたって診療を続けてきた。現在は、川崎医科大学附属病院で多くの手術や専門的な治療に携わってきた田所副院長が、院長である父・田所広文先生とともに診療を行っている。子どもから高齢者まで耳鼻咽喉科・アレルギー科の幅広い症状に対応し、「誰でも気軽に相談してもらえる存在」をめざす同院。今回は、4月より当院で勤務を開始された田所副院長に、これまでの歩みや今後のクリニックのあり方についてお話を伺った。
(取材日2025年5月29日)
大学病院での豊富な経験を生かし、地元の医療に貢献
最初に、医師としてのご経歴を教えてください。

2011年に岡山にある川崎医科大学を卒業し、付属病院で2年間の初期研修を受けました。その後は耳鼻咽喉科に進み、そのまま川崎医科大学附属病院に勤務。さらに、2018年には大学院へ進み、2025年3月まで在籍していました。大学病院では、鼻や喉の手術、好酸球性副鼻腔炎の治療の他、声が出しにくい・かすれるといった音声障害、いびきに関するお悩みにも向き合ってきました。さらに、食べ物や飲み物をうまく飲み込めない嚥下障害、また小児の扁桃肥大など、多岐にわたる症例を経験しました。特に、手術や専門的な処置を必要とするケースが多く、大学病院ならではの環境でさまざまな知見を深められたことは、自分にとって非常に貴重な経験だったと感じています。
医師を志したきっかけは?
このクリニックは、私の祖父が約60年前に開業したんです。つまり、父が2代目、私が3代目になります。いわゆる「家業」として医療が常に身近にある家庭で育ちました。クリニックと住まいが同じ場所だったので、学校から帰ってくると父や祖父が患者さんと向き合っている、というのが当たり前の光景でした。そんな環境の中で育ったので、「医師になろう」と意識して決めたというよりは、ごく自然にこの道を選んだという感覚が強いですね。
地元・新居浜に戻って来られたのはなぜですか。

もともといつかは地元に戻る前提で父とも話していたのですが、いくつかのタイミングが重なり、2025年4月に戻ってきました。まず、父が今年で70歳になること。そして自分自身も大学院を修了し、40歳という節目を迎えること。自分と家族の今後を考えたときに、「今が最も良いタイミングではないか」と判断したんです。子どもが2人いるのですが、上の子が幼稚園に入園する年齢だったので、生活環境を変える時期としてもちょうど良かったというのもあります。実際に戻って来てからは、昔からずっと通ってくださっている患者さんとお話しできたり、地域医療ならではのやりがいを日々感じています。
近隣の病院とも連携し、幅広い患者のニーズに対応
この地域の特性と患者層、主訴について教えてください。

当院には新居浜市内全域から幅広い世代の患者さんが来院されます。さらには、四国中央市や西条市など、勤務先が新居浜という理由で遠方から通われている方々もいらっしゃいます。患者の層は幅広いですが、大学病院に比べると日常的な症状、例えば中耳炎のような感染症やアレルギーなどが多く、手術を必要としないケースが中心です。年齢でいうと、お子さんでは、中耳炎や副鼻腔炎、風邪などでの受診が多いですね。大人の方では、アレルギー性鼻炎や中耳炎といった慢性的な症状で受診される方が中心です。新型コロナウイルス感染症にかかった後に、喉の不調が長引いているため相談したい、といったケースもあります。手術が必要な場合は、設備の都合上、十全総合病院や住友別子病院、県立新居浜病院など近隣の医療機関へご紹介し、連携を図っています。
ご家族は、新居浜での暮らしは初めてだそうですね。
はい。妻は岡山出身で、私とも岡山で知り合いました。今回、私が地元に戻るタイミングで、家族そろって新居浜に移ってきました。買い物や生活の利便性が高いですし、雰囲気のある町並みも妻は気に入ってくれているようです。3歳と1歳の男の子がいるのですが、2人ともちょうどエネルギーがあり余っている時期で、毎日元気いっぱいです。休みの日には、家族で大型公園に出かけて、思いっきり体を動かしています。自然も豊かで、子育てする上でもとても良い環境だと感じています。
お子さんにも、4代目として継いでほしいというお気持ちはありますか?

長く続いているクリニックなので思い入れはありますが、今のところは子どもたちに対して「継いでほしい」と強く願っているわけではありません。医療の世界は日々進化していて、10年後には今とはまったく違う形になっているかもしれませんし、何よりも子どもたちが自分のやりたいことを見つけて、その道に進んでくれることが一番だと思っています。今はまだない新しい職業が登場している可能性もありますしね。ただ、私自身はこれからも地域の皆さんに信頼される医師であり続けられるよう、誠実に、一人ひとりの患者さんと向き合っていきたいと思っています。
「目で見てわかる説明」を心がけ、安心感のある診療を
大学病院の時と比べて、診療の違いはどんな点にありますか?

大学病院では、外来の担当医が曜日ごとに変わることが多く、継続的に一人の患者さんを診続けることが難しいケースもあります。一方こちらのクリニックでは、私が一貫して診察を担当するため、患者さんの経過や背景を踏まえた上で治療方針を立てることができます。そうした積み重ねが信頼関係を築くことにもつながりますし、日常のちょっとした不調やお悩みに寄り添えるのは、地域のクリニックならではの魅力だと思いますね。
診療において、心がけていることはありますか。
診療では、患者さんの不安や疑問にしっかりと向き合いたいと思っています。そのためにも、「目で見てわかる説明」を心がけています。例えば、鼻から内視鏡を入れて、喉や声帯の様子を一緒にモニターで確認しながら説明することで、患者さんもご自身の状態をより具体的に理解しやすくなります。「見える化」することで、納得感や安心感が生まれるんです。鼻に麻酔をかけて行うので、負担も少ないんですよ。
最後に、今後の展望を教えてください。
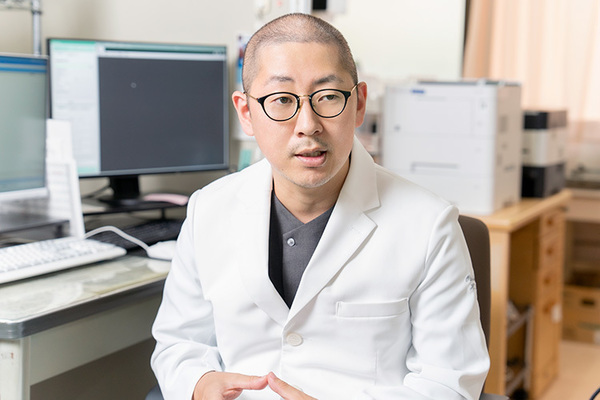
大学病院時代に診ていた、いびきや睡眠時無呼吸症候群、声のかすれのような音声障害の分野などには、地域でも一定のニーズがあると感じています。特に、睡眠中の無呼吸は命に関わることもありますし、放置してしまいがちな問題でもあります。さらに、最近は難聴と認知症との関連性も注目されています。とあるデータでは、日本の補聴器装用率は非常に低いといわれているんです。「もう高齢だから聞こえづらいのはしょうがない」と思ってしまいがちなんでしょうね。そのような方への補聴器の提案なども含め、耳の健康を守ることが地域の高齢者ケアにも直結すると考えています。「風邪は治ったのになかなか咳が止まらない」「市販薬で様子を見ていたが、良くならない」という方や、「これって耳鼻咽喉科で良いのかな?」と迷っている方たちが、いつでも気軽に相談できるような存在でありたいですね。






