福岡 圭介 院長の独自取材記事
福岡小児科・アレルギー科
(松山市/三津駅)
最終更新日:2021/10/12

伊予鉄道高浜線三津駅から徒歩9分。「三津の渡し」にほど近い場所に位置するのが「福岡小児科・アレルギー科」だ。院長の福岡圭介先生は、内科の医師である祖父と父から影響を受け医師を志し、「子どもの将来を支えたい」という思いから小児科の道へ。1987年に現在のクリニックを開院し、地域の小児科・アレルギー科として30年以上、子どもたちの成長を見守ってきた。開院当初は喘息の治療に力を入れていたという福岡院長だが、現在は食物アレルギーの治療に尽力。「子どもの食への興味や気持ちを、大切にしたいのです」と話す福岡院長に、食物負荷試験の大切さや、診療に対する心がけなどを聞いた。
(取材日2020年12月23日)
食物アレルギー治療に尽力し子どもの未来を支える
先生はなぜ、医師をめざされたのでしょうか。

祖父と父の影響が大きいですね。祖父は現在のクリニックから少し離れた場所で、内科の医師として開院していました。しかし時代背景から、内科だけではなく、地域のかかりつけ医として幅広い診療を行っていました。けがをした人の処置なども含め、お産以外はすべて相談を受けつけていたようですね。父も内科の医師であり、私が医学部に進んだタイミングで、この場所にクリニックを構えたのです。
小児科の道を選んだきっかけを教えていただけますか。
将来のある子どもたちの役に立ちたい、と思ったからです。私は大学を卒業し昭和大学医学部小児科学教室に入局した後、東京都立成東児童保健院で勤務していました。その後は神奈川県立こども医療センターアレルギー科で勤務し、1987年に松山に戻って来たのです。当時、喘息は東京や神奈川の病院ではコントロールできていましたが、松山ではまだ吸入ステロイドが浸透しておらず、たびたび発作を起こす子どもが多くいました。ですから松山に戻って最初の10年ほどは、喘息の治療に力を入れていましたね。やがて全国的に治療方針やガイドラインが広まり、喘息の一般的な症状であれば、ほとんどの病院でコントロールが可能となりました。現在は食物アレルギーの治療に力を入れることで、子どもたちの未来を支えることができればと思っています。
食物アレルギーを持つ患者さんは時代とともに増加しているのでしょうか。

そうですね。2005年から松山市内の保育園、幼稚園を対象に調査を行っていますが、やはり1歳未満の食物アレルギーの増加が見受けられます。食物アレルギーの診断は血液検査も参考になりますが、実際に食物負荷試験を行って少しずつ食べていくと、普通に食べられるようになることがめざせる子どもが多いのです。そのため、当院では血液検査のみではなく、食物負荷試験を受けていただくことを推奨しています。
子どもの「食べたい」という思いを大切にしたい
食物負荷試験とは、どのようなものなのでしょうか。

当院では基本食材である卵、牛乳、大豆、小麦の食物負荷試験を積極的に行っています。具体的には、アレルギー反応がみられる食材をごく少量から実際に食べ、2時間ほどかけて反応を見るというものです。血液検査の結果で食物アレルギーがあると、その食材は徹底的に避けなければならない、という認識をされている方もいらっしゃるようです。しかしこうして食物負荷試験を行い、将来的な改善につなげて行く方法もあるのです。基本食材は使われているメニューが多く、アレルギー反応がある場合、外食が制限されてしまったり、親やきょうだい、友達と同じものが食べられず、子どもが不便な思いをしてしまうこともあります。そして何より、子どもの「食べたい」という気持ちを大切にしたいのです。
必ずしも、徹底的に避けなければならいわけではないのですね。
例えば以前、血液検査の結果で卵も牛乳もアレルギーと診断され、その子は2歳4ヵ月まで卵と牛乳を避けており、食物負荷試験も牛乳1ccからスタートしましたが、やはりアレルギー反応が出てしまったのです。しかしその後4年半、食物負荷試験を繰り返しながら行い、少しずつ量を増やしていくことができました。当院ではピーナッツやそばなど、基本食材ではなく、アレルギー反応が特に激しい食材の食物負荷試験は行いません。あくまで基本食材のみ、安全範囲に細心の注意を払いながら、負荷試験を行います。
患者層は、やはり食物アレルギーの方が多いのでしょうか?

はい、松山市全域からいらっしゃっていますね。食物負荷試験は時間がかかってしまうので、近隣の小児科では行っていないという患者さんが、市外からいらっしゃることもあります。当院は土曜日も午前、午後と診療を行っていますので、お仕事や学校の関係でその日に合わせていらっしゃる方も多いですね。またこれは当院ならではだと思うのですが、この土地で長く開業しているので、過去に小児科にかかっていたお子さんが、今度は自分の子どもを連れてやってくることもあるんです。さらに、父の代に内科に通っていた患者さんのお孫さんがいらしたりすることもあります。そんな光景を見ると本当にうれしく、大きなやりがいを感じますね。
食物アレルギーは自己判断せず、適切な検査と対応を
先生が診療の際に心がけていることはなんですか。

全身をくまなく診察することです。親御さんが「風邪をひいてしまったってようです」とおっしゃり、お子さんを連れて来られることも多いのですが、そんな時も、必ず体格や栄養状態を確認し、おなかを触診します。小児科にかかるお子さんは、大人と違って具体的に症状を訴えることが難しい場合も多々あります。どこかに隠れた症状があるかもしれませんから、全身をよく診ることは常に心がけていますね。
ところで、先生はどのようにリフレッシュされているのですか?
実は私は音楽と、スポーツ観戦が好きなんです。松山東高校出身なので、彼らが春の選抜に出た時は応援しに行きましたよ。中学の時は陸上部に所属していて、短距離の選手だったんです。高校の時はコーラス部に所属していたので、大人になってもカラオケに行って歌うことでリフレッシュしています。最近は新型コロナウィルス感染症の流行でカラオケにはなかなか行くことができていませんが、それでも音楽は大好きですね。
最後に、読者の方にメッセージをお願いします。
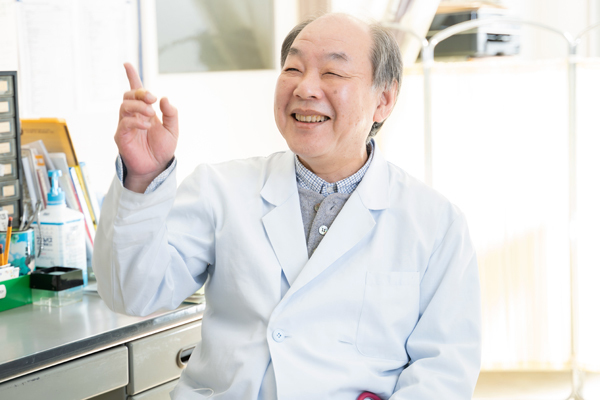
小児科の医師は、専門的な診療はもちろんそうですが、いちばん大切なことは、保護者の方と一緒に子どもの成長を見守ることだと考えています。現在は核家族化が進み、子育ての相談をしづらい環境もあると思います。ですから何か悩みごとがある時は、「こんなこと聞いて良いのかな?」と思うようなことでも、気軽に相談していただけたらうれしいですね。また昔と違って、今は食物アレルギーの認知度が高まっています。少し食べてみて、何か反応があるとアレルギーだと思い、自己判断でその食べ物を一切摂取しなくなってしまうこともあるようです。アレルギーに関することで困りごとがあれば、きちんと血液検査や食物負荷試験を受けることが大切です。その結果をふまえ、適切な対応をしていくことで、将来的なお子さんの食の楽しみや安全を一緒に守っていきましょう。






