谷口 裕 院長の独自取材記事
たにぐち小児クリニック
(広島市東区/矢賀駅)
最終更新日:2023/09/04

1997年の開業以来、小児科が少ない広島市東区エリアにて、地域の子どもたちに寄り添う診療を実践してきた「たにぐち小児クリニック」。「お母さん方の不安を取り除くのはもちろん、小さな子どもたちにもしっかり目を見て話すように心がけています」と語るのは、院長の谷口裕(たにぐち・ひろし)先生。長年、大学病院や基幹病院の小児科で研鑽を積んできたドクターで、日本小児科学会認定小児科専門医でもある。待合室には子どもたちが好きな熱帯魚の水槽があったり、本や玩具がたくさんそろっていたりと、遊び心いっぱいの院内になっている。スタッフ手作りの掲示物やイラストも好評だとか。今回、小児科の医師をめざしたきっかけや開業までの経緯、診療方針、今後の展望やプライベートのことなど、豊富な話題で語ってもらった。
(取材日2023年3月16日)
かかりつけ医として、ありふれた病気に真っ当な治療を
まずは、この地で開業したきっかけからお聞かせください。

開業して25年以上が経過しますが、大学病院で研究に携わっていた頃、この近くの産婦人科で非常勤医師として乳児健診を担当していたんです。その時によく、この近辺には小児科が少ないという話を聞いていました。子どもの風邪は内科や耳鼻咽喉科の先生に診てもらうしかなく、保護者の方々が困っていることを知りました。そこで、開業を決めた際に、少しでも地域医療に貢献したくてこの土地を選びました。
そもそも医師を志した理由は何でしょう?
小さな頃から「人間って何だろう?」みたいなことを感覚的に考えているような子どもでした。進路を選ぶ際にも「人間がどんなものか」を勉強したいと思い、医学部を選択したんですね。勉強を始めた頃はどちらかというと精神医学に興味を持っていましたが、後々に出会った先輩が小児科の医師でして。ロジカルに物事を考える先輩の姿に憧れを持ち、私自身も小児科へ進むことにしました。そして大学卒業後は、関西医科大学小児科・新生児集中治療部に所属し、新生児呼吸窮迫症候群(IRDS)などの新生児の呼吸障害の治療に携わり、命の大切さを学ぶことができました。当時は医師になりたてでしたし、赤ちゃんの生命力の強さを感じながら、無我夢中で取り組んでいましたね。
その後は、どのような経歴を歩まれたのですか?

地元である広島に戻り、広島大学医学部小児科で免疫学の研究を行い、医学博士を取得しました。当時の論文は、イギリスの免疫学の雑誌にも掲載されましたよ。その後は地域の基幹病院などで経験を重ね、小児科部長も務めた後、当院を開業しました。地域のクリニックですので専門性の高い治療はできませんが、ありふれた病気に対して、真っ当な治療をしていきたいと考えています。病気の早期発見・早期治療に努め、必要に応じて専門の医療機関につないでいくことが、地域のかかりつけ医の役目だと思っています。
一人ひとりに寄り添う治療で、子どもの目線も大切に
診療で心がけていることをお聞かせください。

小児科の場合、お母さんなど保護者の方が不安感を抱いて受診されるケースがほとんどです。そのため、診療ではその不安を取り除くことができるような説明や検査を心がけています。例えば、基本的に無駄な検査はしたくありませんが、それが保護者の方の安心につながるならば、検査を行い、数値化して説明することも大切だと思っています。さらに、病気の見通しをしっかり説明することも大切にしています。風邪などで高熱が出ていて、「2、3日すれば熱が下がります」と説明する場合でも、「今は高熱だけど、病気の重さと熱の高さは比例しません。初感染だから熱が高く出ているだけですよ」など、丁寧に説明するようにしています。
子どもに対する接し方の工夫などはありますか?
お子さんに対しても、しっかりと目を見て説明するように努めています。たとえ幼くて内容を理解することができないとしても、その子の自尊心を傷つけるようなことはしたくありません。そして注射をするときは「ごめんね」と謝ったりせず、「こういう理由があるから、今から注射をするね」と話すようにしています。当院には、保育園での勤務経験があるベテランの看護師もいますし、安心してお任せいただきたいです。保護者の方も医師には言いづらい子育てに関する相談など、気軽にしていただけるとうれしいですね。
今、力を入れている分野について教えてください。
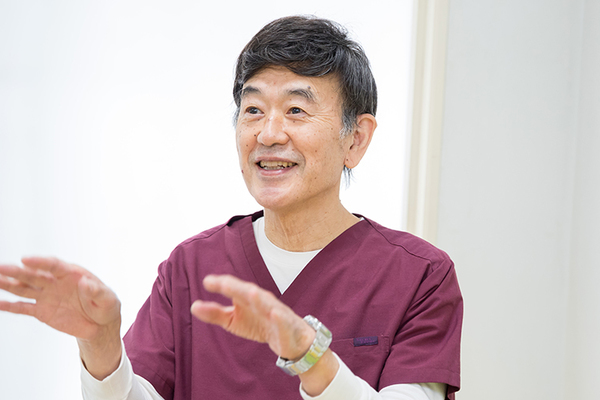
アレルギーと喘息の治療です。子どもは大人のように慢性疾患は多くありませんが、アレルギーや喘息に悩む患者さんは少なくありません。特に喘息は苦しいときに対症療法を行えば良いと思われがちですが、実際は違います。私はよく火事に例えていますが、大火事でゼーゼー苦しいときに対処しても、種火まで消えた状態にしなければ、再発を繰り返してしまうのが喘息です。また息を吹きかけたり、いろんなことがあったりすると燃え始めるため、しっかり消火するまで治療に取り組まなければいけません。当院では、気道の炎症をモニターする検査として、呼気の一酸化窒素の数値をチェックしています。喘息の症状が落ち着いて、その数値が正常になることを目安に、治療を続けていく流れです。そうすることで保護者の方の安心にもつなげられたらと感じています。
弱視の検査にも対応していると伺いました。
そうですね。乳幼児健診と併せて、弱視の検査を受けていただくことを推奨しています。というのも、当院をかかりつけ医にしてくれていた女の子が、小学校に入学してから眼鏡をかけるようになったんですね。小児科ですので、これまで目を診ることはありませんでしたが、どうして考えてあげられなかったんだろうと頭に残り、乳幼児でも視力のスクリーニング検査を行うことができる機械を導入しました。この検査を受けて弱視が見つかった場合は、子どもの目の病気に対応している専門病院を紹介させていただきます。
受動喫煙の危険性を伝える啓発活動にも注力
お忙しい毎日だと思いますが、診療以外ではどのような活動をされていますか?

現在、近隣の小学校4校の校医を務めています。学校の先生方に対して、食物アレルギーのアナフィラキシーショックで使われるアドレナリン注射薬に関する講習会を開き、使用方法の説明などをすることもありますよ。また、プライベートでは以前はサッカーが趣味でした。音楽も好きで、サックスでクリスマスソングを練習したこともあります。また時間があれば、再開したいですね。最近の休日は、映画鑑賞などを楽しんでいます。
読者へのメッセージをお願いします。
開業してから気がついたのは、子どもの受動喫煙による喘息やアレルギーへの影響です。受動喫煙は喘息の発症リスクを上げるなど、子どもたちの体に悪影響を及ぼします。あまり知られていませんが、お父さんが家でタバコを10本吸うと、子どもは3本分吸ったことと同じ状態になるともいわれています。体の細胞が傷つきますし、将来的にがんになるリスクも高まります。たとえ外で吸っていても、家のなかで吐く息にタバコの害が付着しています。タバコは依存症ですので、子どものためにもしっかり病院で治療を受けて、止めるようにしていただきたいですね。当院でも、乳幼児健診ではタバコを吸っているご家族がいないかを確認するようにしています。
最後に、今後の展望をお聞かせください。

当院は、長年地域に根差した診療を続けてきました。これからもファミリークリニックとして、近隣の駆け込み寺のような役割を担っていきたいと思います。敷居を低くして、ご家族の皆さんがなんでも相談しやすい雰囲気づくりに取り組んでいきたいです。気になる症状やお悩みがある方は、気軽にご相談ください。スタッフ一同、真摯に対応させていただきます。






