砂田 尚孝 副院長の独自取材記事
砂田医院
(箕面市/北千里駅)
最終更新日:2025/08/18

阪急北千里線北千里駅から車で15分、マンションや戸建てが並ぶ住宅街に「砂田医院」はある。39年の歴史を持つ同院に、2024年から本格的に診療に加わったのが砂田尚孝副院長だ。「患者さんが来てくれたおかげで自分は育った」と、医師への道を支えてくれた地域への恩返しの思いを胸に、日本精神神経学会精神科専門医として認知症の早期発見・治療に取り組む。「一緒に希望を見出す」「患者さんの人生の晩年を伴走する」という言葉には、単に病気を診るだけでなく、その人の人生に寄り添う覚悟がにじむ。新薬による早期治療の重要性や、薬以外の予防アプローチ、支援者支援への思いなど、認知症医療にかける情熱を聞いた。
(取材日2025年7月14日)
患者への恩返しから始まった認知症医療への道
こちらで診療を始められた経緯を教えてください。

もともとは2021年頃から新型コロナウイルスワクチン接種で関わり始めました。当初は「なぜ精神科医の自分がワクチンを」という思いもありましたが、お世話になった患者さんたちへの恩返しという気持ちで納得できたんです。実は医学部受験で浪人させてもらった時期があったのですが、この医院があったから私も医師への志を持ち続けることができました。その感謝の気持ちがずっとあって。2024年1月に診察室ができ、6月から精神科を標榜して本格的に外来を始めました。週1回は関西医科大学の外来も続けていて、そこで得た知識のブラッシュアップも大切にしています。
精神科を専門に選ばれた理由は?
学生時代は内科志望でしたが、関西医大での初期研修で精神科の奥深さに気づきました。当時の教室では精神医学をサイエンスとして捉え、数値化や有意差を重視していて、その知的探求心に惹かれたんです。「なぜ同じ薬なのに適応病名が違うのか」といった疑問を追求できる。また、遺伝子研究など個別化医療への取り組みも魅力でした。勤務医時代は広島の離島から大阪の総合病院までさまざまな地域で診療し、それぞれの特性に合わせた医療の在り方を学びました。地域によって制度も症状の現れ方も違う。その経験が今の診療にも生きています。
認知症医療に注力されるようになったきっかけは?

身近な人の病気がきっかけです。小学生の頃だったので介護保険もない時代で、子育てが終わったら介護かと子ども心に思ったものです。医局では最初に認知症関係の事務局を任されて、そこから自然と専門性が深まっていきました。印象的だったのは、患者さんが亡くなった後もご家族が来てくださること。「ありがとうございました」と言われることが多くて。精神科全般を診ながらも、物忘れに特化していったのはそんな経験からです。認知症の研究では、統合失調症やうつと比べてはっきりとした結果が出やすいという学術的な興味深さもありました。
新薬がもたらす希望と丁寧な診療の重要性
新しい認知症治療薬について教えてください。

MCIという軽度認知障害の段階から使える薬が出たことで、かなり早期から介入できるようになりました。2つ原因物質あるうちの1つに対してアプローチできる点滴治療で、当院でも2週間に1回の投与を行っています。最初の6ヵ月は大きな病院でしか導入できませんが、その後は当院のようなクリニックでも継続治療が可能です。まだ高額で1年半続ける必要があるなど課題もありますが、認知機能の進行をかなり遅らせることにつながる可能性を持った薬です。今までは認知機能の「維持」か「低下」しか言えなかったのが、「進行の抑制」もめざせると言えるようになったのは画期的です。
治療の際、気をつけられていることはありますか?
実は治療できる認知機能の低下もたくさんあるんです。例えば使用している薬によって、認知機能に影響がでるものもあります。その場合は、服用を控えることで改善が図れることも。そのため私は必ずお薬手帳をチェックし、市販薬も含めて把握します。薬は極力シンプルにして、飲み薬を減らすために貼付剤も活用しています。
診療で特に大切にされていることは?

患者さんの背景を丁寧に聞き取ることです。どこで生まれて、何人兄弟で、どんな環境で育ったか。出生地から始まって家族構成、既往歴まで詳しく伺います。昔のことをよく覚えている認知症の方にとって、生まれ故郷の話は大切なんですよ。また「限界を認識しているのが専門家」という考えを持っています。一人でできることには限界があるので、ケアマネジャーや薬剤師、民生委員など多職種と連携し、関係者会議も積極的に開いています。ご本人と家族の価値観を聴くこと。それが大切だと思っています。
地域とともに歩む認知症ケアの未来
早期受診の目安や相談方法について教えてください。

大事なのは「自覚症状としての物忘れに不安が付随している」ということ。「あれ、大丈夫かしら」という不安があれば、気軽に相談に来てください。「脳の定期健診」のような感覚で構いません。今の状態を記録しておくことが大切です。1年後に来ていただければ変化もわかります。ご本人が受診を嫌がる場合は、まず家族だけでの相談も受けつけています。箕面市立病院とネットワークでつながっているので、検査データも共有でき、継続的な経過観察が可能です。
先生は診療以外でも、認知症に対する取り組みを積極的にされているそうですね。
はい。私は箕面市の認知症施策推進会議の委員でもあります。今は、9月21日の世界アルツハイマーデーに向けた取り組みを進めています。ただ、当事者の方が参加しやすい形をもっと考える必要があると感じているところです。9月の日本はまだ暑いので、日本独自のアルツハイマーデーをつくってもいいかもしれないなと考えたりしています。私の理想は、診察後に患者さん同士がお茶をするような自然な交流。実際、当院でも認知症の方同士が来院後にお茶している姿を見かけます。将来的には、皆が集まれる場所、囲碁や将棋を置いて「先生に呼ばれたから診察行ってくる」というような、ざっくばらんな雰囲気の場所にしたいですね。
読者へのメッセージをお願いします。
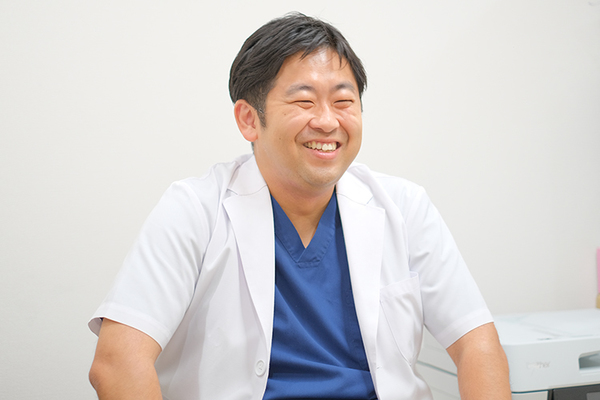
新薬が出て、認知症は「診断して終わり」から「治療」の時代になりました。大きな病院で導入後、当院のような地域のクリニックでフォローアップできる体制も整いつつあります。また、支援者の方への支援も重視しています。介護で煮詰まっている時、白衣の者が入るだけでも流れが変わります。私たちは通院での精神療法で介護者の方の心のケアもしています。何より「一緒に希望を見出す」ことを大切にしています。新型コロナウイルス感染症の時も希望があれば乗り越えられました。認知症と向き合うのは不安かもしれませんが、希望を持って一緒に歩んでいきましょう。気軽にご相談ください。






