藤尾 智紀 院長の独自取材記事
藤尾医院
(枚方市/御殿山駅)
最終更新日:2025/07/31

枚方市の静かな住宅地で、京阪本線の御殿山駅から徒歩で15分ほどの場所に、糖尿病内科を専門とする「藤尾医院」がある。同院は、長年この地で糖尿病の診療を続けてきた藤井医院を前身とし、日本糖尿病学会糖尿病専門医・日本内科学会総合内科専門医を有する、現院長の藤尾智紀先生が2021年に継承、開業した。糖尿病は生涯付き合う病気で、クリニックには定期的に通うことになる。そのため「クリニックに来られる楽しみを一つでも増やしたい」と、待合室などは、季節ごとの花等で華やかで明るい空間を心がけているという。こまやかな気遣いで患者を迎える藤尾院長に、同院の診療内容や糖尿病治療にかける想いを聞いた。
(取材日2025年5月29日)
人に感謝される職業をめざして
医療を志したきっかけは何ですか?

子どもの頃、病気で足や視力に不自由がある家族がいたことが、私が病というものと向き合うきっかけになりました。具体的に医師になろうと思ったのは、高校の頃です。理系科目が得意で医療には興味もあり、将来どうしようかと両親に相談したところ、医師がいいんじゃないかと。特に会社員だった父が「仕事をしながら感謝をしてもらえて喜んでもらえるなんてすごいことだ」と、背中を押してくれたんです。周囲に医療関係者もいないし、高校でも周りに医学部をめざしている同級生が多くいるという環境ではなかったのですが、私自身、人の役に立つ仕事に就きたいと思っていたので、とにかく医学部に行こうと思って勉強していました。
大学ではどのような学生生活を送りましたか?
北九州にある産業医科大学へ進学しました。この大学は働く労働者の健康を守る医療を提供する医師を育成する大学です。労働者が健康に生活を送るために、生活習慣病や予防医療についても学ぶので、糖尿病に関心のあった私にとっては素晴らしい環境でした。先生方も素晴らしい先生ばかりで学ぶことは多かったのですが、今振り返ると部活で培った人間関係にも随分助けられました。ゴルフ部と映画研究会に入っていたのですが、先輩や先生から、医療関係の情報をいただいて、自分の将来像を想像していました。
医師になって開業に至るまで、どのような経験を積まれましたか?

大学卒業後は地元の大阪に戻ってきて、松下電器健康保険組合の松下産業衛生科学センター(現・パナソニック健康保険組合産業衛生科学センター)を経て、関西医科大学の勤務医になりました。ここは糖尿病患者の教育入院を受け入れている病院で、私は主に糖尿病診療を担当しました。同時期にご縁をいただき、こちらのクリニックの前身である藤井医院に勤務するようになりました。藤井医院の院長は地域医療の中で長年にわたって生活習慣病、特に糖尿病に注力されていた先生でしたので、私も現場で多くを学ばせていただきました。2018年にはクリニックの院長に就任、2021年に継承というかたちで、藤尾医院を開業し、現在に至ります。
糖尿病は誰もがなり得る病気
このクリニックの治療で重視していることは何でしょうか?

糖尿病の中でも多くを占める2型糖尿病は自己免疫によって起こる1型糖尿病と違い、世の中には「乱れた生活習慣でかかる病気」という偏った見方があります。そして、患者さん自身もそういった思い込みや偏見に苦しんでおられる方が少なくありません。しかし糖尿病の要因は、遺伝的な要因、生活習慣などいろいろなんです。ですので、まずは患者さんご自身の偏見を取り除くお話をするところから始めます。プロスポーツ選手も年齢を重ねれば心肺機能が落ちて引退するように、長生きすれば誰でもインスリンを出す膵臓の能力が落ちます。つまり長生きすれば誰もがなり得る病気なんです。極論ですが、糖尿病にならない人は糖尿病になる前に寿命が尽きただけ。誰だって心不全にも透析にも認知症にもなり得るわけです。ですから「悪いことをしたわけではない」と丁寧にお話をし、インスリン治療の説明をする際も老眼鏡や杖と同じ「補うもの」としてお話ししています。
具体的な治療法はどのようなものでしょうか?
今から約100年前にインスリンが発見され、血糖値がなぜ上がるか下がるかが、わかってきました。2型糖尿病の場合、こういった科学的見地から、まずは自前のインスリンで、うまくマネジメントしていただけるように、生活習慣の指導と必要に応じて内服薬の処方となります。ただ、必要なインスリンが自前の量で足りないと判断した場合は、インスリンは残念ながら「飲めない」ので、皮下注射のインスリン治療を行う場合もあります。この100年間でインスリンも注射機器も進化しています。昔は動物のインスリンを使うのでアレルギーの副作用もありましたが、遺伝子工学の進歩で、アレルギーがほとんど出ない人間由来のインスリンを打てるようになりました。注射器も煮沸消毒のような面倒のない、使い捨てのペン型の注射器で簡単です。
治療技術も日々進歩しているのですね。
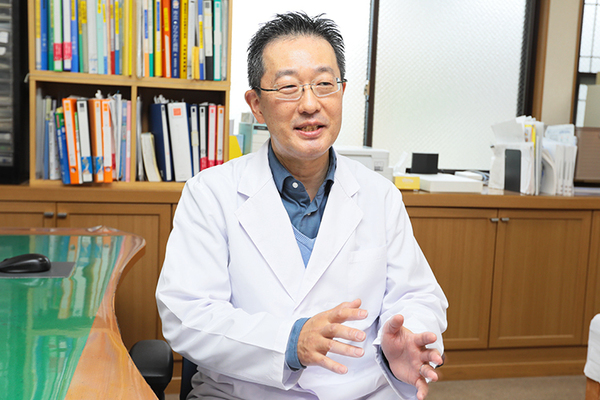
今では、糖尿病は治療さえ受ければ、一般の人と何も変わらない生活を送ることが望めます。ただ、治療は生涯続くので、尿検査や体重測定といった、手軽で痛みが伴わない検査による指標を重視しています。採血も必要に応じて行い、指標は「糖尿病連携手帳」で管理します。前の状況と比べながら、生活状況についても確認して、どの薬をどの程度どう使うのか、患者さんと相談の上で提案しています。
生活習慣の指導などはどうされているのですか?
この地域には私が勤務していた関西医科大学をはじめ、大きな病院が多いので、糖尿病になられたばかりの方には教育入院をお勧めしています。教育入院というのは、実際には治療も行っているので、教育治療入院というべきかと思います。私もかつて教育入院に関わった経験があるため、患者さんには「教育入院はきっとあなたの一生の宝物になりますから」と勧めています。もちろん、さまざまな事情で教育入院が簡単にできない方もいらっしゃいます。そのような患者さんには、パンフレットなどを使って、何度かに分割して教育的な対話を行っています。パンフレットをただ渡すだけでは、理解するのは難しいですから、患者さんが正確に理解できるようにお話をすることを心がけています。
患者とのコミュニケーションを重視
地域医療への貢献として学校の校医もされているそうですね?

小学校の子どもたちを診ています。人間というのは12歳までに食べていたものを一生食べ続けるといわれています。50年以上前の話ですが、アメリカのハンバーガーチェーンが日本に出店し始めた時、子どもたちをターゲットにした販売戦略を立てたといわれています。その戦略が成功し、今やハンバーガーは国民食といってもいいでしょう。それだけ子どもの時の生活習慣は根強く残るんですね。小学校の時の習慣というのは、その後の人生に大きな影響を与えます。業務内容は健康診断がメインですが、そのような思いを持って子どもたちを診察しています。
長い歴史のある医院を継承したわけですが、今後の展望は?
もっともっと患者さんを増やして収益を上げていこうとか、人を雇って分院をつくろうとか、そのようなことは考えていません。それよりも、私は事務処理などの効率化を進めて、患者さんとのコミュニケーションにもっと時間を割けるようにしたいですね。効率を良くして、その分、安全に確実に、患者さんのためになる医療を提供したいんです。
最後に、読者にメッセージをお願いします。
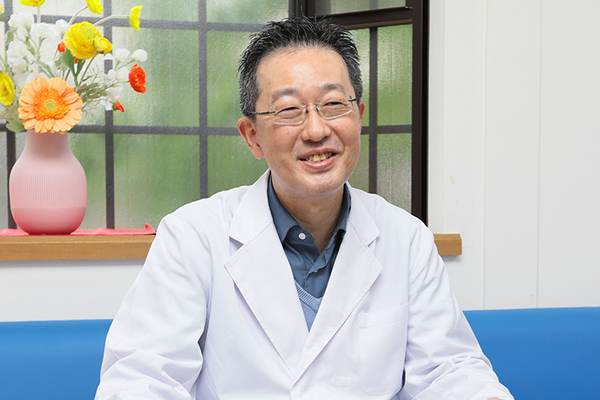
糖尿病自体は、誰でもなり得るものなので、躊躇なくご相談いただきたいです。患者さんお一人お一人と時間を取ってしっかりお話しするため、どうしても待ち時間が生じてしまい、ご迷惑をおかけするとは思うのですが、ちゃんとお話を聞き、ご納得いただけるまでお話をします。患者さんのご負担にならないよう、採血や尿検査は必要な検査のみ行い、無駄な検査はしない方針ですし、また、薬も院内処方で、ほぼ100パーセントジェネリック医薬品(後発医薬品)となるよう努力しています。その一方で、インスリン治療中の方に限りますが、スマートフォンで連続的に血糖値が表示できる機器など、新しい技術の導入にも力をいれています。生活習慣病や糖尿病について、少しでも不安のある方は、まず一度、気軽にご相談ください。






