澤村 昭彦 院長の独自取材記事
沢村内科
(豊中市/千里中央駅)
最終更新日:2025/06/12

高度経済成長期に開発された千里ニュータウンにある「沢村内科」。近隣の医療機関と共通の無料駐車場を16台分有しているほか、スロープも設置されているため車いすでの受診も可能。前身のクリニックから建物を引き継ぎ同院を開院した澤村昭彦院長は、内科・循環器内科を専門として地域住民を30年以上診療し続けてきた。高血圧症・脂質異常症・糖尿病といった生活習慣病の治療・管理をはじめ、地域のかかりつけ医として、認知症の診療や在宅医療にも対応する。そんな澤村院長に、開院に至るまでの詳しい経緯や、診療におけるこだわり、朝早くから診療を開始する理由、これからの地域医療に対する思いなど、たっぷり話を聞いた。
(取材日2024年12月11日)
内科・循環器内科のプロとして地域住民を見守り続けて
この地域に開院したきっかけは何だったのでしょうか?

出身は淀川区・十三なのですが、結婚後は豊中市に住んでいました。開院を考えるにあたり、自宅に近いほうがいいと思ったので、豊中市内で良い場所を探していました。そんな時、知り合いから、医院運営のバトンタッチを考えている先生がいることを聞き、紹介してもらいました。紹介された後にわかったのですが、その先生は偶然にも同じ大学の医局の先輩だったのです。お互いにご縁を感じ、その先生がリタイアされた後、内装だけリフォームして、同じ建物に沢村内科を新規開院しました。
開院までのご経歴を教えてください。

私は奈良県立医科大学を卒業した後、大阪大学の医局に入り、そこでおよそ12年間、主に研究に携わってきました。医学博士を取得するために、途中1年半ほどアメリカの大学に留学していた時期もあります。アメリカでは研究室でひたすら実験に没頭する日々でした。ただ、時がたつにつれて次第に研究のテーマが複雑化していって、自分には研究と臨床のどちらが向いているのか、改めて考えるようになりました。その後、大学の人事で国立療養所近畿中央病院(現・近畿中央胸部センター)に勤務医として勤めるようになり、この先進んでいく道について考えた結果、「自分は臨床を専門とする」と決意し、40歳の節目に開院するに至りました。
診療内容について教えてください。
標榜しているのは循環器内科と内科です。後期高齢者の患者さんが多いので、特に生活習慣病の診療には力を入れています。生活習慣病が悪化すると、脳血管疾患や心臓病、腎臓病などを引き起こす可能性があります。最近は、加齢による動脈硬化の影響で硬くなった弁の動きが悪くなり、そこから弁膜症を引き起こす患者さんもかなり増えました。高齢の方が多いため、当院では認知症も診ています。高齢化自体は社会全体で進んでいるので、今はどこの病院も認知症の外来は混んでいます。そこで当院では認知症診断のための簡単なテストを率先して行い、しかるべき病院に紹介するようにしています。
患者一人ひとりへ寄り添うことを最優先に
勤務医と開業医、やりがいに変化はありましたか?

病院の場合、基本的にガイドラインに従って治療・薬の処方を行うので、診療が比較的システマチックに思えました。また、患者さんの懐具合は二の次で何よりもガイドラインが最優先されるので、経済的に苦しい患者さんに高額な薬を処方することに対して、胸が痛んだこともありました。一方で現在は、一人ひとりの患者さんとじっくり対話し、それぞれの方に合った治療を進めていくことができます。医療者からの治療提案を拒否して、「コレステロールなんて高くてもいい」「食事療法がいい」とご希望を主張したいと思う患者さんもいらっしゃるかもしれません。そういった場合には具体的な治療の選択肢や見通しなどを丁寧に説明した上で、できるだけ患者さんの意向に沿いたいと思っています。
診療にあたって大切にしていることはありますか?
最近はCTやMRIなどの検査で詳細な状態がわかるので減っているようですが、若い女性の患者さんを除き、必ず聴診器で心臓の音を聴くようにしています。「聴診器でわかるんですか?」と疑問に思われる人もいらっしゃいますが、「手当て」はその名のとおり「手を当てること」。これも一つの医療行為として、私は大切にしています。エックス線検査で見つかる病気のほうがはるかに多いですが、心臓弁膜症や喘息など、聴診器を当てることで早期発見につながる病気もあるのです。
こちらならではの特徴はどんなところでしょうか?
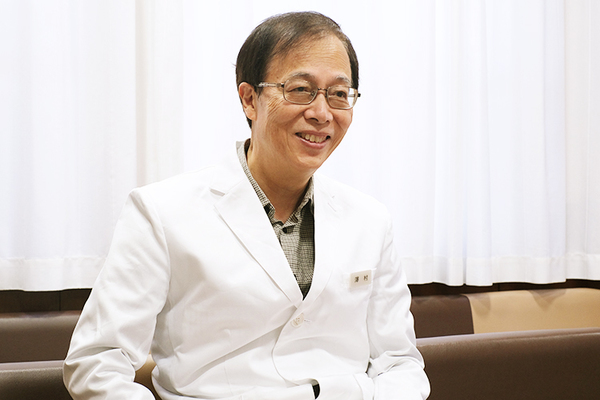
まず、朝開院するのがとても早いことです。私は医院の奥に自宅を構えているので、7時には鍵を開けて、8時にはもう診察が始まります。一番乗りの患者さんはだいたい7時半頃に来院されます。この早朝診療は、前身の医院の先生から受け継いでいるこだわりです。例えば、診察した結果、別の病院に紹介状を出すことになったとしても、朝早い時間に診察が終わっていれば、紹介先の病院にその日のうちに行くことがかないやすいでしょう。さらに当院の一般診療は予約制ではないので、例えば朝急に具合が悪くなった患者さんも比較的すぐに受け入れられます。また、担当の先生の都合もあってのことですが、日曜日に胃の内視鏡検査を行っているのも珍しいと思います。さらにはワクチン接種も時々日曜日に行ったりと、患者さんの幅広いニーズに応えやすい体制を取っています。
苦痛をできるだけ減らし、個々の実情に応じた診療を
予約制を設けていないという話が出てきましが、こちらの理由をぜひ詳しくお聞かせください。

先ほどの話と通ずる部分がありますが、予約制の場合、緊急の患者さんをなかなかすぐに診ることができません。患者さん一人ひとりを平等に診るということを考えたら、予約制は選べないと思いました。インフルエンザなどの感染症が流行している時は、どうしても1〜2時間くらい診察待ちの時間が発生してしまう場合もありますが、平時は30分くらいで順番が回ってきます。患者さんをお待たせしすぎることなく診療できているので、これからも先着順の診察を続けていくつもりです。
これからの展望をお聞かせください。
これからも引き続き、ガイドラインにとらわれすぎない、個々の実情に応じた診療に尽力したいと考えています。当院では在宅療養中の患者さんも診ていますが、在宅療養を選ばれる方の中には、入院がどうしても嫌だからという理由を挙げられる方もいらっしゃるそうです。近くで見守られているご家族、ご親族の皆さんとしては最期の時が近づいてくると、「どうしてこんなに状態が悪いのに、在宅医療を担う医師は入院させないのだろう」と疑問に思われるかもしれません。しかし私は、高齢者の場合は「どう治療するか」よりも「いかに快く見送るか」を重視しなければいけないと考えています。患者さんにとって苦痛のより少ない寄り添いに、今後も努めていきたいです。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。

当院は、診察時に適切な判断を行うため、先進の機器を一通り取りそろえています。ただ、必要な時や患者さんがご希望される時には、大きな病院や専門の医療機関を速やかに紹介する体制も取り、患者さんの状態やご意向を第一優先にしています。私が大事にしているのは、幼少期に母から諭された「本人の努力で治らないことを口にしたり、批判してはいけない」という言葉。当院での診療を通して、障害者や認知症の高齢者、その他、地域の方々が安心して生活できる「地域包括ケアシステム」の構築に尽力していきます。






