加藤 徳介 院長の独自取材記事
加藤医院
(世田谷区/豪徳寺駅)
最終更新日:2025/08/01

世田谷区の閑静な住宅街で、80年を超える歴史を持つ「加藤医院」。3代目として2025年に院長を継承した加藤徳介(のりゆき)先生は、専門である腎臓内科の視点から、全身の健康を診ることを意識している。地域のかかりつけ医として発熱や頭痛といった一般内科から生活習慣病、骨粗しょう症、無呼吸症候群など幅広い症状を診ているが、特に慢性腎臓病(CKD)の早期発見・早期治療に力を入れているという。その裏にあるのは、「透析になる患者を地域からなくしたい」という強い思いだ。また、外来で診ている患者を最後まで診たいとの思いで訪問診療も開始したという。「気軽に立ち寄って何でも相談してもらえたら」と親しみやすい笑顔を見せる加藤院長に、地域医療にかける思いを聞いた。
(取材日2025年7月4日)
「全身の健康を診たい」との思いから腎臓内科の道へ
3代目として院長を継承された経緯を教えてください。

子どもの頃から、祖父や父の診療する姿を見て育ち、いつかは自分もこの医院を継ぐのだろうと漠然と思っていました。ただ、大学卒業後に腎臓内科で研鑽を積むうちに、勤務医としての仕事もいいなと思うようになったんです。大学病院や総合病院の腎臓内科は、外来診療に加えて、シャント手術や血管拡張手術といった外科的治療を行う場面も多く、やりがいを感じているうちに気づいたら25年がたっていたという感じですね。今でも毎週金曜は埼友クリニックでの診療を続けています。その一方で、医療のデジタル化が進む中で当院の診療体制を変えていく必要があり、このタイミングで継承するのがいいのかなと考え、後を継ぐことを決意しました。現在は父と2人で診療にあたっています。
なぜ腎臓内科を専門に選ばれたのですか?
もともと、全身の健康を診る視点を養いたいという気持ちがありました。勉強をしていく中で腎臓が全身と関わっていると感じ、それで腎臓内科を専門にしようと思ったのです。腎臓はいわば血管の塊のような臓器ですから、全身の血管の病変が反映されやすい特徴があります。経験を積んでいくうちに、糖尿病をはじめとする生活習慣病から、脳疾患や心血管疾患、さらには骨の病気まで、腎臓を通じて全身の状態が見えてくることを実感しました。最近では、腎臓が老化とも密接に関わっていることがわかってきています。血管の老化を防ぎ、健康寿命を延ばすためにも腎臓を守ることが大切です。「全身を診る」ために腎臓内科を専門にした当時の決断は間違っていなかったなと思っています。
開業して感じる地域の医療ニーズはいかがですか?
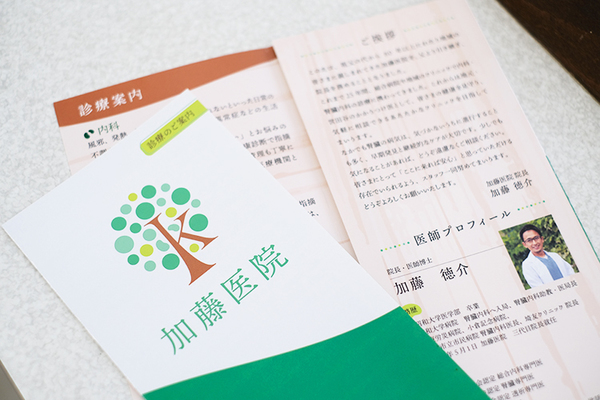
継承後、ウェブによる初診予約を始めたことで、大学生や会社員など若い世代の患者さんも少しずつ増えてきました。一方で、この地域の高齢化は想像以上に進んでおり、90代の患者さんも多くいらっしゃいます。慢性腎臓病の方が透析に進まないよう取り組むと同時に、超高齢の方が多いこの地域では、「透析を行うかどうか」「腎移植は可能か」といった「腎代替療法」に加え、透析をあえて導入せず、苦痛の少ない形で病状の進行を見守る「保存的腎臓療法」という選択肢も含めて説明する必要があります。勤務医時代には、そうした意思決定のための外来も担当していました。当院でも、患者さん一人ひとりの希望に寄り添った情報提供と治療方針の提案を大切にしていきたいと考えています。
腎臓病は早期治療が鍵。健診で指摘されたら受診を
慢性腎臓病に対する取り組みについて教えてください。

慢性腎臓病こそ私が最も力を入れたい分野です。腎臓は「沈黙の臓器」ですから、症状に気づかず、健診で引っかかっても放置してしまう方がいらっしゃいます。でも「その時点で診ておけば透析にならずに済んだのに」と思う若い方が年に4~5人はいると感じていて……。そういう方の治療の機会を絶対に逃したくないので、もし健診でタンパク尿が出たらすぐに来ていただきたいです。それが今、地域で一番伝えたいことですね。受診してもらえれば、進行度合いにもよりますが、生活習慣や栄養の指導から始め、必要に応じて薬を使っていきます。ここ数年、SGLT2阻害薬という薬が慢性腎臓病に対して使えるようになり、治療の状況が変わりました。投与の判断に悩む先生にもぜひご相談いただきたいです。とはいえ、私の治療方針は、過剰医療はせず必要な人に必要な治療を提供すること。早期発見・早期治療で、透析に進む患者さんをなくすために努めていきたいです。
糖尿病についてはいかがでしょうか?
糖尿病も腎臓病の原因の一つですから、注力する分野です。例えば血糖の管理については、24時間、血糖を測定できる小型機器も出ていて、こうしたものを使うと、どんな食事でどのように血糖が上がるかがとてもわかりやすいのです。野菜から食べたほうが血糖の上昇が緩やかになりやすいといったことも、実際に数値を見れば実感しやすいですよね。患者さん自身の意識が大きく変わるきっかけになると思っています。また、血糖コントロールだけでは難しくなった方にはインスリン導入も行います。今年から週1回投与のインスリン製剤が出て、治療の選択肢が広がりました。高齢患者さんでもきちんと対応できそうな方であれば、看護師と一緒に使い方を丁寧に指導して、通院時に練習してもらうといった工夫をしながら、積極的に治療に取り入れています。
先ほど、腎臓は骨の病気とも関係があるというお話がありましたね。

そうなんです。実は、腎臓は骨とも密接に関わっています。骨に必要なビタミンDは腎臓で活性化されるので、腎臓の機能が低下すると骨がもろくなりやすく、骨粗しょう症になってしまうケースがあります。つまり、骨粗しょう症の原因は加齢によるものだけでなく、腎臓病をはじめ、加齢以外の原因によるものもあるので、それぞれの原因に応じた適切な治療を行っていくことが大切なのです。その点、私は腎臓と関わりの深い骨についてもずっと勉強してきましたし、骨密度を測る機器も導入していますので、骨粗しょう症についてもこまやかに対応できるのが強みです。また、全身の血管と関わりがある疾患を診るという観点から、当院では、睡眠時無呼吸症候群の治療も行っています。慢性腎臓病や心臓、血管の病気とも関連がある病気ですから、気になっている方はご相談いただけたらと思います。
不調を気軽に相談できる地域のかかりつけ医に
診療の際はどんなことを心がけていらっしゃいますか?

患者さんの話をよく聞くこと、これに尽きますね。その上で、寄り添いながら治療していくということをずっと意識してやってきました。先ほどふれたとおり、健診などで何かあれば、とにかく来ていただくことが大切ですから、そのためにも話しやすい雰囲気を大切にしています。時には、治療の合間にプライベートについて会話することもあります。ライブやゴルフに、家族の話、競馬も守備範囲ですよ(笑)。まずは受診のハードルを下げることを大切にしています。そうして、関わった患者さんはずっと診ていきたいと思っています。その思いを実践するために、訪問診療も始めたところです。
訪問診療について教えていただけますか?
高齢で通えなくなった患者さんを最後まで診たいという気持ちがありますし、患者さんから「何とか先生に診てほしい」と声をいただくこともあったので、まずは今まで通院してくださっていた方を対象にスタートしました。腎臓の状態が悪くなっていて、ご本人やご家族に腹膜透析のご要望があれば、必要に応じて連携する総合病院への紹介を行える体制を整えています。血液透析と違ってご自宅で処置できる方法な上に、最近は腹膜透析用の液もいいものが出てきているんです。訪問診療であってもそうした治療の選択ができますし、外来でも対応しますので、気になる方はお声がけください。
地域の方々へのメッセージをお願いします。

繰り返しになりますが、透析に進む人をなるべく減らしたいという強い思いがありますので、腎臓で何か問題があればぜひ頼っていただけたらと思います。また、これまで、体全体を総合的に診るということを意識して、「プライマリケア」と呼ばれる初期診療にもずっと関わってきました。「何だか調子が悪い」といった違和感があれば、気軽に受診していただけたらと思います。昭和大学病院に勤務していた時代に、総合診療部門の立ち上げに関わった経験もありますので、これまで培った知識を地域に還元していきたいですね。かかりつけクリニックとして地域の皆さまの健康を守っていきたいと思いますので、何でもご相談ください。






