大田 桂一 院長、大田 一路 副院長の独自取材記事
大田医院
(さいたま市西区/西大宮駅)
最終更新日:2025/09/22

西大宮駅から歩くこと約10分。閑静な住宅街の中にある「大田医院」は、泌尿器科と皮膚科を担当する大田桂一院長と、一般内科と脳神経内科を受け持つ大田一路(かずみち)副院長が親子で診療を行う地域のクリニックだ。院内は空間にゆとりのあるバリアフリー仕様となっており、靴を脱ぐ必要がない造り。小さな子どもから高齢者まで、あらゆる年齢層の患者が通いやすい設計となっている。院長と副院長はともに患者との対話を重視し、患者に寄り添う診療姿勢で真摯に日々の診療と向き合っている。そんな2人にこれまでの歩みやクリニックの特徴、診療で大切にしていることなどを聞いた。
(取材日2025年8月6日)
皮膚科・泌尿器科に加え、脳神経内科・一般内科を診療
開業までの経緯と、医院のリニューアルについてお伺いします。

【桂一院長】私は昭和医科大学を卒業後、大学病院に勤務し、その後開業を見据えてさいたま市内の皮膚科で約5年勤務して、1998年にこちらで開業しました。当時は今のように周囲は住宅街ではなく、雑木林ばかり。泌尿器科と皮膚科での開業はチャレンジングと言われたものですが、患者さん方に恵まれて、順調にここまでやってくることができました。
【一路副院長】私が当院での診療を開始する前の2025年4月に、医院を大リニューアルしました。私は脳神経内科と一般内科を担当しますが、難病の患者さんも来られますので、利便性を考えて靴を脱がないスタイルのバリアフリー仕様とし、玄関も車を直接つけられるよう広くして屋根をつけました。おかげさまで来院しやすいと好評です。
近隣エリアで脳神経内科を診療するクリニックは珍しいと伺いました。
【一路副院長】脳神経内科を診療しているクリニックは数が少ないと思いますので、より地域のお役に立てると思っています。私がこちらでの診療を開始する前に、お知らせのチラシをポスティングさせていただいたのですが、私の同級生のおばあさまの目に留まり「大田くんが診てくれるなら」と来院してくださいました。チラシを握りしめて来院されて、見覚えのあるお名前から同級生のおばあさまだと私も気がつきました。お医者さんになかなかかかってくださらなかった方が、私が診るならと来院されたのですから、とてもうれしかったですね。信頼にお応えできるよう真摯に努めようと思います。
一路副院長の脳神経内科ではどのような症状を診ていただけますか?
【一路副院長】脳神経内科専門の医師として片頭痛、脳卒中、認知症やパーキンソン病、重症筋無力症などの難病の疾患を取り扱っています。さらに専門的な診療が必要な場合は、近隣の基幹病院や大学病院など病診連携を行っている病院にご紹介します。脳神経内科は脳や脊髄、末梢神経、自律神経、筋肉の病気を診る内科です。体を動かす、温度や痛みを感じる、考えたり覚えたりすることがうまくできなくなった場合に、こうした病気が疑われます。診察では話をよく聞いて、診察して診断する、それを確認するために検査を併用していきます。診断後の治療に関しても、ただお薬を出すのではなく、年齢や持病、もともとの記憶力や家族との関係性など社会背景までケアしなくてはなりません。例えば、介護保険制度を用いてデイサービスやリハビリテーション、訪問看護などうまく活用していけるように社会制度についてもご案内しています。
院内の連携についても教えてください。
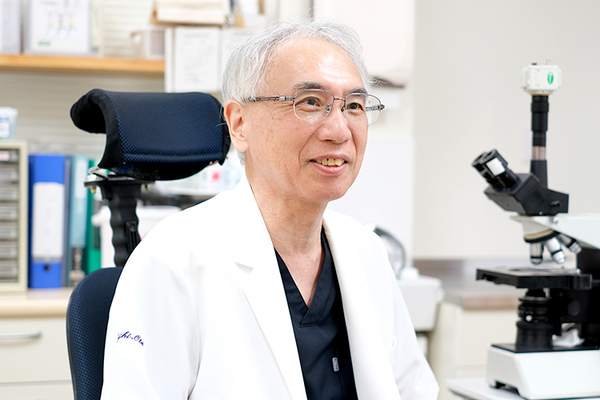
【桂一院長】血圧の高い人や血液検査の際に内科的な疾患の可能性がある場合にはスムーズに内科医の一路副院長に診ていただくことができます。以前は他の内科にご案内しておりましたが、現在は当院の内科で原因を探れるように尽力しております。また、皮膚科で診ている帯状疱疹は強い痛みを伴う場合もあるのですが、そんな痛みの管理も副院長はうまく対処してくれます。まったく性格の違う診療科なので、連携を密に取ることで、今後も患者さんのお役に立てると思います。加えて日頃から気軽に何でも話し合えるので、その点でも助かっていますね。
患者の様子のすべてが診断のもとになる
診察の際には患者の一挙手一投足まで診るそうですね。

【一路副院長】診察室に入る前から患者さんの診察は始まります。入室されるご様子、歩き方、椅子への座り方、立った時の重心の位置、話し方、礼節などなど。すべてが診断に必要なことです。当院の診察室が一般的なクリニックの診察室に比べて広く取ってあるのも、患者さんに歩いてもらったり、ご様子を観察するのに必要だからです。血液検査や画像診断がすべてではありません。ときにはご自分の症状を明確に言葉にできないこともあるでしょう。そんなときは病状だけでなく、患者さんのお人柄や精神状態なども慎重に拝見しつつ、こちらから積極的に話しかけて見極めます。病状を説明する時も個々の患者さんに合わせて、わかりやすく伝わるように説明の仕方も工夫しています。そういった丁寧にやりとりをする基本姿勢を今後も大切にしていきます。
診察の際に大切にしていることはありますか?
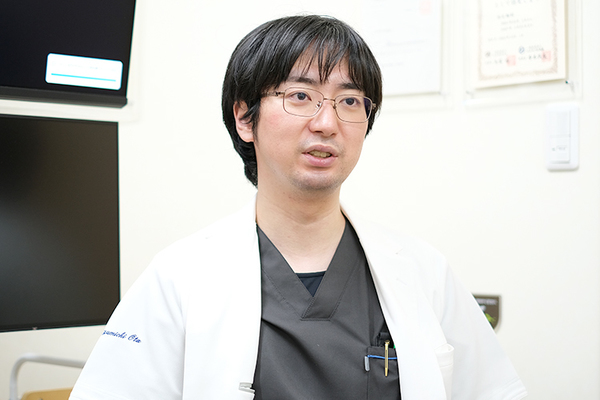
【一路副院長】きちんと丁寧にお話を伺い、適切な診断をし、患者さんの生活など社会的な背景も考慮した治療へと導くことです。例えば頭痛。緊急性のある頭痛から日々付き合う必要のある慢性的な頭痛まで多種多様です。どのような痛みなのか、これまでの経過はどうなのか、丁寧に話を伺って、治療の際も妊娠のご希望などライフスタイルまで考慮しなければなりません。また、今困っている痛みに対処した後は、予防的な療法も大切です。私のところにはセカンドオピニオンを求めてお越しになる方もいらっしゃいます。原因が多岐にわたるなら、患者さんも同じ方はいらっしゃいません。適した治療法もそれぞれ違うのです。それは当然頭痛だけでなく、認知症や脳神経系の難病から生活習慣病など、何にでも言えることです。時にはご家族にご協力を仰ぐこともあります。そうして、原因と患者さんに適した治療を行い、症状の改善をめざしています。
日々、知識のアップデートも続けていく
一路副院長は埼玉医科大学で研究員としての活動も続けておられます。

【一路副院長】大学病院の常勤医師は辞しましたが、研究員として在籍しており、現在も継続して取り組んでいるのが脳に関する研究です。近年はアメリカの臨床医向けニュースサイトで私の研究が紹介される機会もあり、非常に励みになっています。難病の研究チームにも所属しており患者さんにより良い医療を提供するためにも、インプットとアウトプットの両面を大切にしながら、日々の診療と真摯に向き合っています。また、よく知る先生方が多数おられるため、患者さんを入院加療のために紹介する際も、単に紹介状を書くだけでなく、現状を直接伝えることでスムーズに高度治療に移行が可能です。特に脳神経系の病気は命に関わったり、難病で患者さんがつらい思いをされることもあるため、少しでも早くご紹介しています。
常に知識などのアップデートも心がけておられます。
【桂一院長】開業すると、病院勤務の時のどんどん情報が降ってくる状況とは違い、自分で積極的に情報を得る姿勢が大切になります。特にお薬の進歩は著しいものがありますから、ウェブの講演会や勉強会に参加するなど、情報収集にも努力を惜しみません。
【一路副院長】私は免疫疾患を診ることも多いですから、製薬会社の方と新しい薬や学会、ガイドラインの改定など情報交換を積極的に行っています。免疫抑制剤の進歩は目覚ましいですからね。生物学的製剤など新しい知識を貪欲に吸収しています。
最後に読者へのメッセージをお願いいたします。
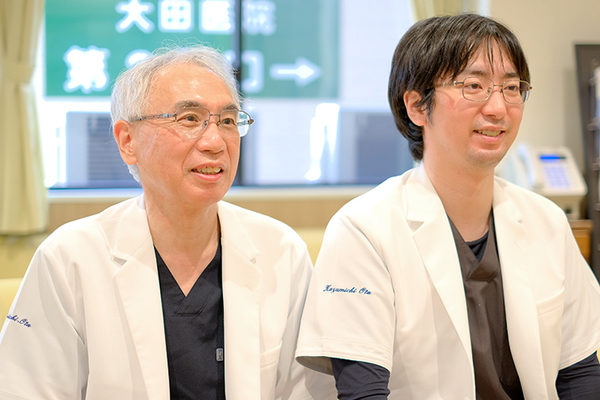
【桂一院長】当院の法人名は「一実会(いちじつかい)」と言います。これには、医療スタッフの心と努力が「小さくても一つの実になるように」との意味が込められています。患者さんが安心して相談できる存在であり続け、患者さんだけでなく、患者さんを支えるご家族も支えられる「かかりつけ医」としてこれからも地域の皆さまの暮らしに寄り添っていきたいと思っていますので、何かあればお気軽にご相談ください。






