野口 寿行 院長の独自取材記事
のぐち内科呼吸器内科クリニック
(幸手市/幸手駅)
最終更新日:2025/09/25

東武日光線幸手駅から徒歩約10分。内科・呼吸器内科を診療する「のぐち内科呼吸器内科クリニック」は、長年幸手市で地域住民の健康を支えてきた。住宅街の一角にあるクリニックで、整備された駐車場と広々とした清潔な待合室を備え、患者の通院の負担に配慮している。「気になる症状があったらまずはご相談いただきたいです」と穏やかな口調で語る野口寿行院長。野口院長の専門は呼吸器内科で、クリニックではさまざまな呼吸機能検査も可能だ。呼吸器疾患にとどまらず生活習慣病や発熱まで幅広く診療する野口院長に、患者や地域への思いや、診療ポリシーを聞いた。
(取材日2025年7月23日)
当日、予約なしでも受診できる地域のかかりつけ医
クリニックの成り立ちや、医師になったきっかけを教えてください。

当院は70年ほど前に曽祖父が幸手市で開業したクリニックです。父が3代目院長としてクリニックを引き継ぎ、母も小児科の医師として診療していました。私は祖父や両親が働いている姿を直接見ていたわけではありませんが、職業として医師がイメージしやすい環境で過ごしていたためか、医師になる以外の選択肢はあまり考えたことがありませんでしたね。その後、自分が勤務医になって帰ってきた時、父が夜中にかかってきた電話に対応したり、患者さんのご希望で往診に向かったりしている姿を目にしました。根底にはきっと「患者さんにとって良いことをしたい」という気持ちがあるのでしょう。私も患者さんが受診できない状況をつくりたくないと考えていますので、その点は父と共通しているのかもしれません。
予約制を導入していないのも、何か理由があるのでしょうか?
かかりつけ先が完全予約制の場合、急に具合が悪くなったときにすぐに診てもらえません。するとどこに行ったら良いかわからなくなり、患者さんが困ってしまうと思うんですよね。特に学生は、日頃から受診しているクリニックがない人も多いでしょう。「つらいときに診てもらえない」というのはかわいそうですし、診療所としての役割を果たせていないとも思いますので、急患も含めて柔軟に対応できる場所でありたいと考えています。また、一人あたりの診療時間を厳密に決めてしまうと、検査や診療が十分に行えないリスクもあります。それなら多少待っていただいてでも、一人ひとりにきちんと時間を割いて診療したいんです。現在、午前は父との2診制を取っており、症状によって患者さんを分担して診療しています。
勤務医時代のご経験や、クリニックを継承した経緯について伺います。

初期研修を受けた愛媛大学医学部附属病院の血液内科は当時、血液疾患の他に感染症・膠原病などの病気や原因が不明確な病気を診ており、現在の「総合診療科」に近い内容でした。血液内科での研修を選んだのは、実家を継ぐためにも内科系の診療科でさまざまな病気を診られるようになりたいと考えたからです。兵庫県立淡路病院では、救急科外来と病棟で消化器内科・呼吸器科・循環器科・血液内科の診療経験を幅広く積みました。その後、呼吸器内科から外来診療の依頼を受けて呼吸器にも携わるように。東京に戻った後は、東京都健康長寿医療センターの呼吸器内科で勤務しました。そして日本呼吸器学会呼吸器専門医となり、2012年から新久喜総合病院での外来と並行して当院での診療を始めました。2022年には、私が院長に就任したタイミングでクリニック名を現在のものに変更しました。
生活習慣病から呼吸器疾患まで幅広く診療
患者さんの病状や治療内容には、どのような特徴がありますか?

内科では高血圧症・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病を多く診療しています。治療の進め方は基本的に、ご本人と相談しながら決めていきます。薬を使うことへの考え方も、食事・運動といった生活習慣をどれだけ自己管理できるかも人それぞれ異なるためです。呼吸器領域においては気管支喘息、間質性肺炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の他、感染症罹患後に咳が長く続いている患者さんも多くいらっしゃいます。そのような方をしっかり検査すると気管支喘息が判明する可能性もあり、総合的に見ると咳で通院する方が増えている印象がありますね。最近では睡眠時無呼吸症候群の検査に対するニーズが増えており、「睡眠時に呼吸していない」と家族に指摘されて来院する方もいます。また、患者さんが発熱していれば、通常とは別の動線で院内に入っていただき、隔離部屋で診療を行います。熱がある方はできれば事前にお電話でご連絡ください。
こちらでは、さまざまな呼吸機能検査が可能と伺いました。
スパイロメトリー(肺機能検査)FeNO(呼気一酸化窒素濃度)測定、モストグラフ(呼吸抵抗検査)などの呼吸機能を調べるための検査が可能です。咳が続いている時は、FeNO測定をよく実施します。FeNO測定は、気管支喘息の患者さんに多い「好酸球性気道炎症」と呼ばれるアレルギー反応の一種が肺の中でどの程度起こっているかを調べるための検査です。気管支喘息の診断基準にFeNO測定結果は含まれていませんが、参考所見として役立ちます。FeNO測定器のマウスピースをくわえていただき、10秒程度息を吐くだけで測定でき、息苦しさがある方でも比較的負担が少なく測定できる検査です。また息を吸ったり吐いたりする時に、気道へかかる抵抗の値を調べるための検査がモストグラフで、気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患の方に行う検査です。モストグラフの結果はグラフで見られるので、患者さんは検査結果が理解しやすいと思います。
検査方法の選択で、意識されていることはありますか?

患者さんの病状に応じて、なるべく負担がかからない検査を選ぶようにしています。本来なら、気管支喘息は肺の機能を検査するためのスパイロメトリーで診断基準を満たすかどうかを調べるのが基本です。しかし、発作や息苦しさがある方にとってスパイロメトリーはつらい検査でもあります。スパイロメトリーは、機械を使って患者さんに息を吸ったり吐き出したりしてもらう検査で、1度実施した後に吸入薬を使用し、再度実施する必要があるからです。そのため、まずは簡便なFeNO測定をしていただき数値や症状をもとに気管支喘息の可能性があるかを説明することもあります。その上で、スパイロメトリーを希望される方は実施することもできます。
何か困り事があれば遠慮せず話してほしい
患者さんと接する際や、診療で大切にされていることはありますか?

診察中はなるべく専門用語を使わず、患者さんにとってわかりやすい説明を心がけています。例えばFeNO測定の結果説明だと、「息の一酸化窒素の量を測って、好酸球性気道炎症というアレルギー反応が起きているかを調べました。数値が低くても気管支喘息の方はいらっしゃいますが、これぐらいの数値から上だと気管支喘息の割合が多くなります」といった要領で説明をしています。「FeNOの値が高いから気管支喘息でしょうね」と言うだけでは患者さんには伝わりませんよね。
理想とする医師像、クリニック像はありますか?
この地域は高齢化が進んでいるため、祖父、父の代から長く通院されているご高齢の患者さんも多くいらっしゃいます。そうした患者さんたちを、最期までしっかり診ていきたいです。一方で、咳で受診されるような若い年代の方も増えています。新たに来院される方にも「ちゃんと診てもらえた」と安心していただけるように診療して、次も来ていただけるような環境をつくりたいですね。検査設備の更新もその一つだと考えており、最近は胸部エックス線撮影の際にAI技術を補助的・試験的に取り入れ始めました。こちらは主に、私が検査を行った後、見落としがなかったかを確認するために使用しています。
地域の皆さんにメッセージをお願いします。
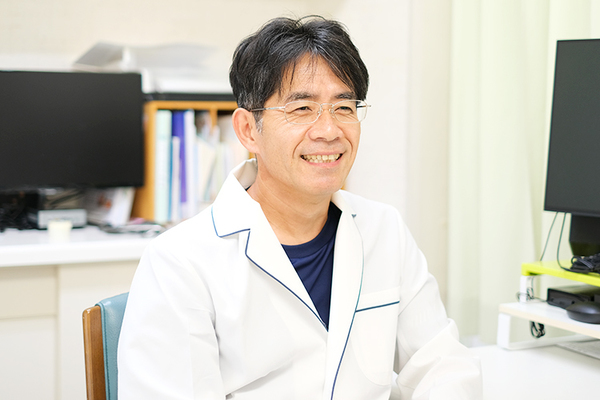
地域にお住まいの方には、気になる症状があったら一度ご相談いただければと思います。例えば、甲状腺ホルモンの数値の異常から、気管支喘息が発見されることもあり得ます。よく「主治医に遠慮してあまり話せない」とおっしゃる方がいますが、自分で感じている症状は自分にしかわかりませんので、些細なことでもぜひお話しください。スタッフも患者さんに温かく接するスタッフばかりで、同じ地域の一員として話しやすい部分があると思います。ご相談いただいた結果、当院で治療が難しい病気に関しては適切な医療機関をご紹介いたしますので、まずは受診をお勧めします。






