大川 修 院長の独自取材記事
大川医院
(春日部市/武里駅)
最終更新日:2025/09/12
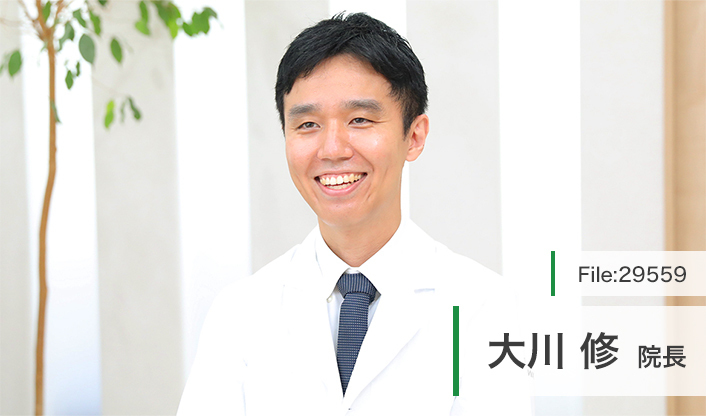
親子2代で30年以上にわたり、地域住民のホームドクターとして親しまれている「大川医院」。2代目院長の大川修先生は、同院の役割を「一定レベルの診療を提供する場」だと話す。救命救急を含むさまざまな医療の経験を積み、日本内科学会総合内科専門医をはじめ複数の専門医資格を取得した上で、地元である春日部で総合診療を手がける大川院長。さまざまな症状でも同じ水準の診療が受けられるような環境を整え、広い知識と視野で状態を見極めている。等身大の診療で患者の気持ちに寄り添い、一人ひとりに丁寧に向き合う大川院長に、同院の診療内容や診療の際に心がけなど話を聞いた。
(取材日2025年6月13日)
地域のホームドクターとして一定レベルの診療を
親子2代で30年以上、この場所で診療されていると伺いました。

当院は私の父が開いたクリニックで、2020年に私が2代目院長として継承しました。地元でもある春日部の地で、親子2代にわたって「地域のホームドクター」としての役目を果たせることをうれしく思います。開業当初から通われていた方はご高齢になり、健康上の新たな悩みが出てきたり、サポートを受けて来られたりする患者さんも少しずつ増えてきました。そのご家族である働き世代の方、日々の生活の中で健康にちょっとした不安を感じている方、また社会に出て健康診断を受けるようになった方にも、気軽にご利用いただいています。この辺りは住宅街ですし、いずれの場合も患者さんは近隣にお住まいの方が多いです。皆さんに気持ち良く受診していただけるよう、スタッフの接遇にも気を配りながら診療を続けています。
どのような症状を診てもらえるのでしょうか?
発熱や喉の痛みなどの風邪症状、突然の腹痛、嘔吐・吐き気、動悸や息苦しさなど、日常でよく起きる急性症状を中心に広く診療を行っています。「どこの診療科に行けば良いかわからない」とお困りの際もご相談ください。高血圧や糖尿病、花粉症など、長い治療期間を要するとされる慢性疾患にも対応しています。詳細な検査が必要と判断した場合には適切な診療科におつなぎしますし、入院や高度な医療機器による検査や治療が必要という場合は、当院と連携している総合病院や専門の医療機関を紹介いたします。地域のホームドクターである当院が提供するのは「一定レベルの診療」です。とても専門性の高い検査や治療を行うわけではありませんが、さまざまな症状で同じ水準の診療が受けられるような環境を整え、広い知識と視野で状態を見極める。それが地域医療における当院の役割だと思っています。
院内設備や予約方法についても教えてください。
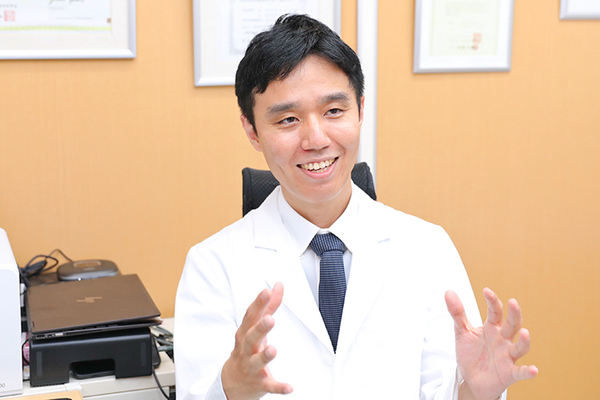
エックス線や心電計の他、エコー、CT、内視鏡、呼吸機能の検査機器など、これらはすべて父の代から備えています。この場所である程度の検査が受けられれば患者さんの負担も減らすことができます。エコー検査は臨床検査技師が行い、CT検査は読影専門のセンターと当院とのダブルチェックで精度向上に努めています。また、代替わりのタイミングで院内を改装して診療室を増やし、待ち時間の軽減のために予約制を導入しました。電話・インターネットのどちらからもご予約いただけます。
専門的な知識を生かしつつ広く診る
先生は初めから総合診療を専門にされていたのですか?

総合診療に興味はあったものの、医師として何かしらの専門性を持つことがまだ一般的でした。それでもやはり「幅広く診たい」という思いがあり、研修期間はあえて母校とは異なる横浜市立大学附属病院を選び、それから大学病院ではなく3次救急医療機関の横須賀共済病院で、救命救急を含むさまざまな医療の経験を積みました。その後、専門として選んだのは消化器内科。胃・肝臓・膵臓・大腸と、幅広く診られることに魅力を感じたんですね。こうして内科領域について広く学び、日本内科学会総合内科専門医、日本消化器病学会消化器病専門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医と、複数の専門医資格も取得して今後について考え始めた頃に、父から継承の話が出たのです。総合診療への思いは持ち続けていましたから、これが良いきっかけになりました。
大学病院から町のクリニックへと診療の場が移って、何か思うことはありましたか?
診察の重要性を実感しました。町のクリニックに来る患者さんの中には「原因はわからないけれど、なんとなく不調」という方も多く、必然的に細かく診ることになります。胸の音を聞くことで不整脈を疑ったり、足のむくみから心臓の病気や血栓がないか考えたりすることが大切なのです。その後により詳しい検査が必要になることも考えられますが、きちんと診ることが発見の第一歩になるのだと改めて感じています。逆の例として、実際とは異なる病気を疑って「そうに違いない」と思い込んでいる方も多いです。そのような場合の説明に難しさを感じることもあります。
地域のホームドクターとして、患者とのコミュニケーションも重要なのですね。
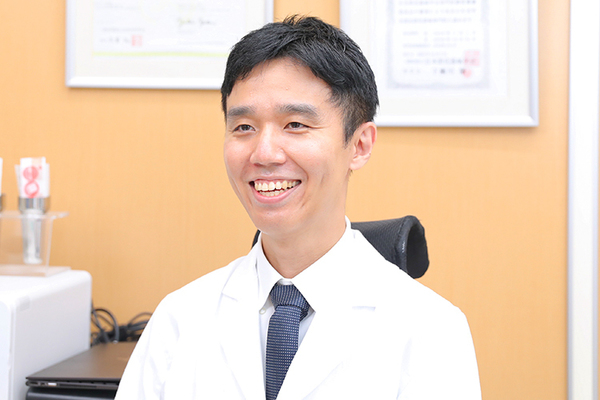
もちろん患者さんとの会話も大切にしています。ただその中でも特に、私は患者さんが“何を求めているのか”を理解できるよう努めています。他の病気ではないかと疑ったり、治療内容に不安を感じていたりするのならば、検査結果やガイドラインをもとに説明を行います。その他にも、「とりあえず痛みを取ってほしい」「まずは原因をはっきりさせてほしい」など、患者さんは医師に何かを期待して来院されているはずです。同じ対応でも患者さんの捉え方はそれぞれですが、限られた時間内で患者さんのご希望を読み取り、できるだけ満足してお帰りいただけるような対応を心がけています。
さまざまな角度から働き世代とその親世代をサポート
働き世代の方からはどのような相談が多いですか?

30代~40代頃から、糖尿病や高血圧といった生活習慣病のご相談がとても増えてきます。健康診断で異常を指摘されて相談に来られる方も多いです。自覚症状はほぼ感じず、他に痛い場所も何もないのですから「まだまだ自分は病気とは無縁」と思っている方も多いでしょう。私も同世代ですから気持ちはわかりますし、仕事で忙しくて検査の時間が割けないということも理解しているつもりです。ですが現実問題として、一度検査に引っかかった方は翌年もまた引っかかることが多く、治療もせず意識も変わらなければ何年も同じことの繰り返しです。放置すると薬が手放せない事態にもなりかねず、もっと悪いことに動脈硬化や脳梗塞などの病気が待ち構えていることをご理解いただきたいですね。当院では患者さんからの希望があれば定期的に管理栄養士による栄養指導を取り入れて、生活習慣や意識の改善をサポートしています。
その世代になると、親のサポートという問題も出てきますね。
そうですね。開業当初から通われている患者さんの中にも、一人で通うのが困難になってきた方や、認知機能の衰えから日々の薬を忘れてしまう方が増えてきました。そのようなケースでは患者さんだけでなくご家族とのコミュニケーションも必要になりますが、ご自身の生活も忙しい中で、ご高齢の親御さんのサポートに時間を取れないこともあるでしょう。程度によってはご家族や当院で対応できる範囲を超えているかもしれません。介護や自治体の制度、また認知症専門のクリニックの存在をご存じない方も多いです。これからこのようなケースはますます増えるでしょう。当院では情報提供という形で、認知症や介護という問題を支えていきたいですね。
最後に、読者へメッセージをお願いします。

働き世代からご高齢の方まで、当院にはさまざまな症状の方が通われています。ガイドラインに基づいた治療を行うことはもちろん、一人ひとりに合わせた治療の提供が当院のモットーです。生活背景や体質にも配慮しながら、他院との連携も視野に入れて、その方に必要な医療におつなぎいたします。気になることがあればお気軽にご相談ください。






