末次 麻里子 院長の独自取材記事
岩槻西原クリニック
(さいたま市岩槻区/岩槻駅)
最終更新日:2025/08/12

「岩槻西原クリニック」の院長を務めるのは、幼い頃、親族が糖尿病に悩まされる様子を身近で見た経験から、予防医療の重要性を痛感してきたという末次麻里子先生。末次院長は、2024年に同院を継承。従来の一般内科診療中心の体制から専門性を強化した体制へと進化させた。日本糖尿病学会糖尿病専門医である末次院長は、腎臓内科を専門とする妹、呼吸器内科と訪問診療を専門とする弟とともに家族でクリニックを運営。糖尿病性腎症の院内連携治療などおのおのが専門性を持つチームならではの診療を展開している。「流れ作業」ではなく、患者一人ひとりの背景を考慮したオーダーメイド治療を大切にする末次院長に、クリニックの進化と糖尿病予防への思いを聞いた。
(取材日2025年7月17日)
専門性を追求したチーム医療が特徴の地域のクリニック
2024年にクリニックを継承されたそうですが、クリニックは変化ではなく進化されたようですね。

前院長が一人で内科全般を診ていた体制から、より専門性を強化したクリニックへと変わりました。私は糖尿病・内分泌が専門ですが、腎臓内科、呼吸器内科、訪問診療をそれぞれ専門とする医師も加わり、4人体制になりました。今は専門性をより強く出しているクリニックが多いと思うので、各医師の専門分野を明確に打ち出すようにしています。ただ、患者層は変わらず地域の方々が中心です。この近くに住んでいる人たちが何世代にもわたって通ってくださる、地域密着型のクリニックという基本は変わりません。診療時間も患者層に合わせて1時間前倒しにし、高齢の方が早い時間に受診できるよう配慮しました。専門性は高めつつも、地域の皆さんが気軽に相談できる雰囲気は大切にしています。
糖尿病を専門に選ばれたきっかけを教えてください。
子どもの頃、祖母と一緒に糖尿病だった親族の病院に付き添いで行っていました。その時「糖尿病ってすごく大変な病気なんだな」と強く感じました。祖母も、親族に糖尿病の人がいたので発症を非常に恐れていて、結局かかることはなかったのですが、その姿も印象的でした。生まれて初めて「この病気は大変だ」と思ったのが糖尿病だったので、医師をめざした時から糖尿病を専門にしようと決めていました。獨協医科大学埼玉医療センターの糖尿病内分泌・血液内科で学んだ後、国立病院機構埼玉病院や済生会川口総合病院で研鑽を積み、いろんなところで知識を習得してきました。今は世界中で糖尿病患者が増えているので、治療だけでなく予防にも力を入れていきたいと思っています。
家族でクリニック運営をするからこその強みもありますか?
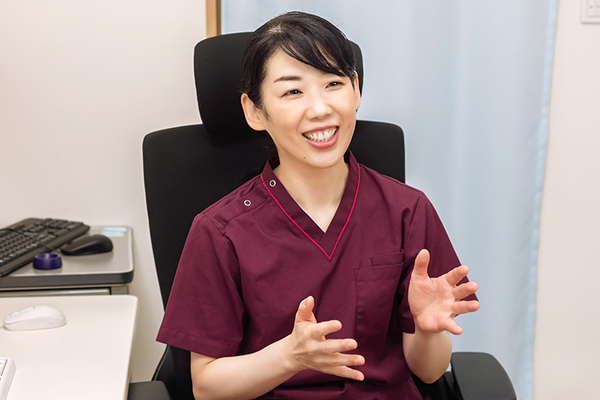
はい、腎臓内科は私の妹が、訪問診療と呼吸器内科は弟が担当しています。元院長である父も理事長として週に何日か診療しています。患者さんも「みんなきょうだいなんだね」と笑ってくださいます。家族だからこそ連携もスムーズですし、患者さんにも安心感を提供できているのかなと思います。家族で医療への同じ思いを共有しているので、予防から治療、通院困難になったら訪問診療まで、患者さんの人生を最後まで支えるという理念も自然と実現できる体制になっています。
一人ひとりに寄り添う診療を
糖尿病の予防にはどのような取り組みをされていますか?

まず健康診断を強く勧めています。そして健診で異常が見つかったら、必ず医療機関を受診してほしいです。ブドウ糖負荷試験という検査をして、予備軍の早期発見につなげ、栄養指導や療養指導を強化することで、糖尿病の発症予防につなげたいと考えています。祖母が糖尿病を恐れていて、結局発症しなかった経験から、予防の大切さを実感しています。当院には管理栄養士が2人いて、1人は運動療法の専門的な知識を持っているため、食事と運動の両面からサポートできます。また、看護師と臨床検査技師が定期的な糖尿病合併症評価も行っており、それぞれの職種が連携して、一人ひとりの理解度や合併症の進行具合に合わせたアプローチを心がけています。
糖尿病治療における連携体制について教えてください。
当院の強みは、院内で専門家同士が連携できることです。特に、糖尿病性腎症という合併症は、ガイドラインでは「ここまで悪くなったら腎臓内科を専門とする医師に紹介しましょう」となっています。でも、当院は腎臓内科の専門家が院内にいるので、外に紹介しなくても院内紹介で済みます。慣れ親しんだクリニックで継続して治療を受けられますから、これは患者さんにとって大きなメリットになるでしょう。また、訪問診療も行っているので、高齢になって通院が困難になった患者さんも継続してフォローできます。もともと通院されていた患者さんが、通えなくなったからと訪問への切り替えを希望されるケースが多く、これこそが私たちのめざす「予防から人生の最期まで患者さんを診る」医療の実現です。なるべく入院せず、普段と同じ環境で過ごしていただきたいと思っています。
診療で心がけていることを教えてください。

流れ作業ではなく、患者さん一人ひとりの背景を考慮したオーダーメイドの診療を大切にしています。例えば、この数値だからこの薬、というだけでなく、一人暮らしの方なら服薬管理のしやすさも考慮します。患者さんの年齢層もさまざまなので、話すスピードや声のトーンにも配慮しながら診療を進めるようにしています。お伝えする内容が難しい場合や、より重要なことについては、クリニックみんなでサポートすることに努めています。その他、診察室だけで終わらせず、その後看護師からもう1回話してもらうといった工夫も取り入れるなど、一人ひとりに合わせた対応を心がけています。一人ひとりに寄り添った診療を行うには、そういう姿勢が大切だと考えています。
働き盛り世代は特に、生活習慣病の予防を大切に
医師以外のスタッフや院内環境について教えてください。

医師を除いて15人のスタッフがいます。管理栄養士2人、臨床検査技師、看護師などが連携して患者さんのケアにあたっています。スタッフ全員で毎朝掃除を行い、清潔な環境維持に努めているのも当院の特徴です。院内のこだわりについては、待合室を広く取ることで、ゆったり待っていただけるようにしています。また、糖尿病の方は感染症に弱いことから、院内の感染症対策にも力を入れていて、発熱患者さんの動線はしっかり分けています。院内で発熱のある患者さんを診ているクリニックも多いかと思いますが、当院では外で診察するようにしています。その他、部署ごとのミーティングや全体ミーティングを行い、スタッフ間で意見の違いが出ないようコミュニケーションを大切にしているのもこだわりです。さまざまな面から、患者さんに「また来たい」と思っていただけるような環境づくりを心がけています。
今後の展望について聞かせてください。
糖尿病の療養指導をもっと充実させたいと考えています。そこで、以前開催していた糖尿病教室を再開して集団指導を行ったり、新型コロナウイルス感染症流行前に実施していた運動教室も、今後は運動療法の専門的な知識を持っている当院のスタッフの力を借りながら、院内で運動教室を再開予定です。すべてが一律の療養指導にならないように、一人ひとりの理解度や合併症の程度に合わせた指導スケジュールを作ったりしたいですね。それと、糖尿病じゃない患者さんが居心地悪くならないよう、バランス良く診療を展開していきたいという気持ちもあります。例えば風邪で受診した人も満足のいく診療を提供し、疎外感を感じないようにしたいと思っています。
最後に読者へのメッセージをお願いします。

特に30代から50代くらいは働き盛りで、結構体をないがしろにしがちな世代だと思うんです。でも生活習慣病の予防は本当に大事です。健診を受けたままにしている人も多いので、ちょっとでも異常があれば必ず受診してほしいです。早期に発見できれば、そこから重篤化させないための対策も図れるんです。当院がそのお手伝いをできれば良いなと思います。






