原 健一郎 院長の独自取材記事
原内科医院
(伊勢崎市/新伊勢崎駅)
最終更新日:2025/03/28

伊勢崎駅より徒歩20分、伊勢崎市宮前町に位置する「原内科医院」は、開業より30年以上、地域医療の一員として地元住民の健康をサポートしてきた。2024年に同院を父から継承した原健一郎院長は、「地域のかかりつけ医としてどんな症状も診ます。また、患者さんの体だけではなく心理的な面や社会的な面にも配慮し、個々の患者さんの状態とニーズに合わせた『全人的医療』をめざしています」と語る。一方、日本内科学会総合内科専門医としての総合内科的な診療と同時に、日本呼吸器学会呼吸器専門医や日本アレルギー学会アレルギー専門医としての豊富な経験を生かし、より専門的な治療をめざしていきたいと語る。そんな健一郎院長に、患者や診療への思い、先端的な呼吸器疾患の治療法などについて聞いた。
(取材日2025年1月28日)
長引く咳は「呼気NO濃度測定」で喘息検査を
こちらのクリニックは30年以上の歴史があるんですね。

当院は私の父が1988年に開業しまして、以来この地で地域医療に携わってきました。2024年に息子である私が継承し、現在は父と2人体制で診療を務めています。地域のかかりつけ医としてどんな症状も診るのですが、特に父は中性脂肪やコレステロールといった脂質系分野が専門のため、脂質異常症や糖尿病といった生活習慣病を得意としています。また、私は大学病院や米国留学での研究を通じ、呼吸器内科の専門家として経験を積んできました。呼吸器内科系分野である咳や痰、胸の痛み、息苦しさといった症状や、喘息、アレルギー疾患などの治療を得意としています。
どのような患者さんが多いのでしょうか?
主訴については、風邪や腹痛など一般内科的な症状も多いですし、専門である生活習慣病や呼吸器疾患も多いです。当院の診療は高校生以上となっていますが、年代的には幅広く、高齢者の方も多いですし、喘息などは高校生の方もけっこういらっしゃいます。私の専門の呼吸疾患でいえば、最近は特に咳が増えてきていますね。「咳が止まらない」「咳が長引いている」などです。原因は風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症後の長引く症状、喘息、肺炎、マイコプラズマ肺炎、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などさまざまです。あと人数は少ないですが、専門的な治療を必要とする、非結核性抗酸菌症という慢性的な呼吸器感染症の患者さんもいます。
咳が長引いていると、喘息などの病気ではないかと心配になります。

そうですよね。当院では喘息かどうかを調べるため、「呼気NO濃度測定検査」を行っています。これは一酸化窒素ガス分析装置によって、吐いた息に含まれる一酸化窒素(NO)の濃度を測定する検査です。気道に炎症があると一酸化窒素の濃度が高くなりますので、症状の様子や喘息治療の必要性などを短時間で確認するのに役立ちます。この分析装置を導入しているという点は、呼吸器疾患の専門的な診療を行っている当院の強みともいうべき点です。その他、肺機能検査、心臓・頸動脈・腹部の超音波検査、睡眠時無呼吸症候群のための簡易ポリソムノグラフィなど各種検査を実施しています。CTは当院にはないのですが、車で5分ほどの所にある伊勢崎佐波医師会病院で受け、当院で画像を見ながら診断と患者さんへのご説明を行います。
クリニックを転々とせず専門医師に一度相談してほしい
咳の症状からどうやって病気を見分けるのですか?

咳の場合は特に問診が大事です。例えば、咳の出るタイミングは必ずお伺いします。夜や明け方に咳が出て日中は意外とそうでもない場合は、喘息という可能性を考えます。また、会話や電話をしている最中に咳が出る場合は、一つの予想として、アトピー咳嗽の可能性を考えます。声を出す刺激や花粉、気温の変化などその場所の環境が原因で咳が出るアレルギー疾患です。ご家族にアレルギーを持っている方がいるのかも判断材料です。あとは、よく逆流性食道炎などでも咳が出る人がいます。その疑いがある場合は胸焼けがあるか、ゲップが出るかなどお伺いします。その他、痰の様子やタバコを吸っているかどうかなども重要です。もちろん問診だけでなく、専門的な検査なども丁寧に行って総合的に診断します。
専門的に調べていただくと安心ですね。
咳がひどくてクリニックを転々としてる患者さんもいらっしゃいますので、一度、当院のような呼吸器内科の専門クリニックに来て、専門的な診察を受けていただくのがお勧めです。正しい診断がつけば、その疾患に合った治療を提案することができます。いかに的確に疾患を特定して、的確な治療に結びつけるかが当院のめざすところです。当院で可能な治療はもちろん当院で行いますが、例えば、内視鏡などを用いる精密検査が必要だったり、入院が必要だったりする場合は、必要に応じて適切な医療機関につなげるということも、地域のかかりつけ医の重要な仕事です。実は私自身、当院の診療の合間に、群馬大学医学部附属病院と伊勢崎佐波医師会病院で、呼吸器内科の外来を担当しているため、両院と深い関わりを持ち、密接な連携を行っています。
こちらの診療方針を教えていただけますか。

「全人的医療」の実践をめざしています。患者さんのお話を丁寧にお伺いし、患者さんの体だけではなく、心理的な面や、家庭・仕事などの社会的背景も考慮します。その患者さんにとってどのような治療がベストなのか、総合的に判断して治療するように心がけています。また、疾患も呼吸器にこだわらず、ちょっとした風邪や腹痛、頭痛などでも気軽に来院していただいています。もともと、呼吸器内科は他の診療科と比べても非常に扱う疾患が幅広い領域で、内科全般に通じるものがあります。肺、気管、喉もそうですし、肺循環・心臓循環など循環器もかなり関わりがありますし、皮膚科や耳鼻科につながるアレルギーの種類も多く、感染症や免疫関連の膠原病も呼吸器内科の範疇に入ります。そのため、全身の幅広い症状や総合的な診療に自信を持っています。
総合的な内科、呼吸器・アレルギーの専門的診療の両立
アメリカのメイヨー・クリニックで学ばれているんですね。

メイヨー・クリニックへは基礎研究者として留学しました。でも、私は最終的には臨床医になる道を考えていたため、研究の合間に病院での臨床のカンファレンスやレクチャーに積極的に参加し、先端的な治療法についても勉強させていただきました。ただ、今思うと、基礎研究者時代の知識も、現在の患者さんの治療で役に立っているんですよね。例えば、近年、生物学的製剤という特定の細胞の分子を標的としたお薬が重症喘息患者向けに保険適用されました。けっこう高額なお薬ということもあり、どんな患者さんに用いるべきかを見極めなければなりません。その判断のため、そのお薬の基礎研究的な要素である、薬のメカニズムや細胞レベルの解析への理解が必要になってくるんです。
研究がクリニックでの診療にも生きているんですね。
喘息は白血球の一種である好酸球やリンパ球が必要以上に増えて集まることで炎症が起こるのが原因なのですが、その時、サイトカインと呼ばれるホルモンのような物質が炎症に関わってきます。近年、そのサイトカインを抑制して症状を改善するために生物学的製剤を用いるようになりました。私は研究者時代にそのサイトカインの研究をしていました。当時はそのようなお薬は存在していなくて、まだまだ研究段階だったんですよ。お薬として実用化されたのは感慨深いですね。生物学的製剤の治療は一般的には大きな病院で行うもので、クリニックレベルで行われているところは少ないと思います。当院では私の呼吸器専門医や基礎研究者としての豊富な経験がありますので、安心してお任せいただければと思います。
今後の抱負を聞かせていただけますか?
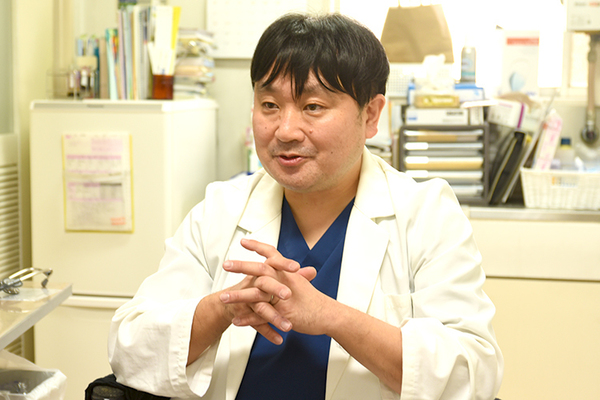
父の代からの古い建物なので、診療を続けながら少しずつ医院内のリフォームを計画しています。また、院内薬局から院外薬局に変更し、患者さんをお待たせすることがなくなったり、吸入薬指導なども薬剤師から丁寧にレクチャーを受けていただけるようなクリニックをめざします。今後も、どんな症状も診ることができるかかりつけ医として住民の皆さんに寄り添った医療を続けていきたいです。加えて、呼吸器内科・アレルギー科の専門性を生かした専門的な治療の提供も行うことで、呼吸器・アレルギー疾患の患者さんのお役に立てたらうれしいです。






