渡邉 秀樹 院長、渡邉 京子 副院長、近藤 千治 さんの独自取材記事
長門クリニック
(足立区/亀有駅)
最終更新日:2025/06/23

亀有駅から歩いて10分ほどで、住宅街の中に立派なれんが造りの建物が見えてくる。産婦人科の「長門クリニック」は、2025年には開業から76年目を迎えた。亀有の地とともに長い時間を過ごしてきた歴史あるクリニックだが、これまで続けてきた出産の取り扱いを、2025年2月末で終了。今後は、外来診療と産前・産後のケアをさらに手厚くしていく方針。渡邉秀樹院長は「時代の変化によって、妊婦さんの望まれる出産の形も変わってきています。私たちは、妊婦さんやご家族が安心して出産・産後に向き合えるよう、そのサポートに全力を尽くしていきたいと思います」とほほ笑む。変化の背景や今後の診療体制、力を入れている産後ケアの内容について、秀樹院長とその妻で副院長の渡邉京子先生、そして助産師長の近藤千治さんの3人に話を聞いた。
(取材日2025年3月6日/情報更新日2025年5月20日)
親子3代にわたって地域医療に尽力、女性の健康を守る
クリニックのこれまでの歩みや、先生方のご経歴についてお聞かせください。

【秀樹院長】当院は、私の祖父が1949年に開業しました。初めは外科をメインとしながら、診療科にとらわれずオールラウンドに診療していました。そして先代からは産婦人科、小児科、内科に注力し、私が院長に就任するタイミングで大幅にリニューアルし、現在に至ります。ここに戻って来る以前は、私も妻も筑波大学附属病院の産婦人科で治療や出産に携わっていました。産婦人科を選んだのは、もちろん父の影響もありますが、新しく生まれてくる命に貢献したいという思いがあったからです。
【京子副院長】もともとはがん治療に興味がありましたが、出産も含めて女性の力になりたいと考えるようになり、産婦人科の道へ。他の診療科と違い、診断から治療、手術、抗がん剤治療まで、一貫して同じ医師が担当でき、患者さんが主治医の手から離れないという点が魅力でした。
長年続けてこられた出産の取り扱いを、2025年2月末で終了されました。
【秀樹院長】はい。出産は前院長の父親が亡くなったタイミングで一時的に中断していましたが、2008年に再開。それから17年間、このクリニックでたくさんの命が誕生しました。しかし、出産を受け入れるための人員の確保が難しくなったことや、近年は無痛分娩を希望される妊婦さんが増えたことなどさまざまな要因が重なり、出産の取り扱いを終了するという結論に至りました。ですが私たちは、あくまでもこの変化を前向きに捉えています。出産の取り扱いがなくなった今、産前・産後ケアと外来診療に、より力を入れていきたいと考えています。
先生方のご経験や多くの出産の実績は、今後も診療に生かされていくのですね。
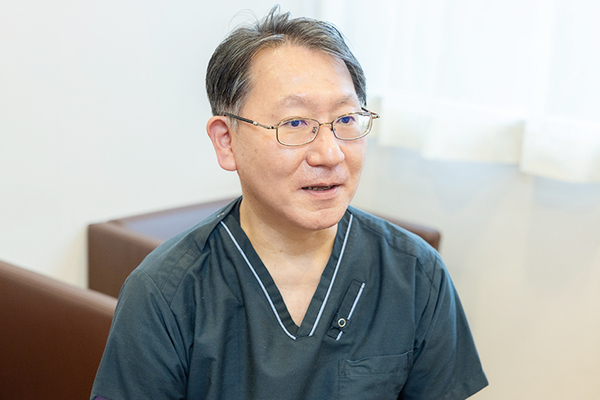
【秀樹院長】妊婦健診に関しては、たくさんの妊婦さんを診てきた私たちだからこそできるアドバイスや、見つけられる異常もあると思っています。これは妊婦健診に限らずすべての診療でもそうですが、もしも異常が見つかった場合には、適切なタイミングで地域の連携する総合病院にご紹介しています。近年は高齢出産をはじめハイリスクの妊婦さんも増えていますので、出産までは当院で見守り、出産は大きな病院で、そして出産後のケアをまた当院で担当するという良い流れをつくっていけたら、妊婦さんや出産後のお母さんたちの負担も減らせるのではないでしょうか。
子育てを多方面からサポート、母親が一息つける場所に
こちらで行われている産後ケアについて、詳しく教えてください。

【京子副院長】一昔前は出産後も、一緒に住む家族や近くに住む両親が子育てに協力してくれました。しかし今は、両親が高齢のために頼れないお母さんや、知り合いのいない土地で子育てしなくてはならない若いご夫婦も増えています。家族の助けが難しくなった分、その代わりとなる助けが必要なのです。当院では、去年の8月から宿泊型の産後ケアをスタートしました。4月からはデイケア型の産後ケアも開始しています。授乳やおむつ替え、沐浴、スキンケアなど育児練習のサポートに加えて、一時的に赤ちゃんをお預かりして、お母さんに休息を取ってもらうことを目的としています。当院の2階には、出産などで使われていた宿泊できる個室が10部屋ありますので、そこを産後ケアのための部屋として用意しています。疲れた時や「ちょっと休みたい」と感じた時、また、パートナーの方と一緒に育児について学びたいという時に、ぜひご利用ください。
助産師の皆さんによる外来も準備しているそうですね。
【近藤さん】出産がなくなるのは寂しいですが、積み重ねてきた経験や知識を生かして、妊婦さんやお母さんたちをサポートしていきたいと思います。助産師が担当する外来では、妊娠や育児に関する不安をご相談いただけます。また、産前・産後ママへのアロママッサージ、妊婦さんのための整体などを行います。女性の中には「子育て中の不安や悲しみを人に話してはいけない」と考えている方もいるようですが、決してそんなことはありません。むしろ「何もなくとも、いつでもクリニックに来て良いんだよ」というメッセージを、多くの女性に伝えていきたいですね。妊娠や子育てについて悩んだり、誰かに話を聞いてほしいと感じたら、1人で抱え込まず相談に来てくださいね。
外来診療で相談の多い症状はありますか?

【秀樹院長】年齢によって異なりますが、10代や20代を中心とした若い世代では、生理痛や無月経、月経前症候群など、生理に関する相談が増えています。一方、40代以降の女性で多いのは更年期障害に伴う症状です。生理痛も更年期障害も、以前は病気ではないという認識から、受診されずに我慢していた方も多くいました。しかしどちらも、治療のためにお薬を、体質改善のために漢方薬を用いるなどによって、症状の軽減がめざせます。産婦人科の医師としては、できるだけ早いタイミングでご相談いただき、生理痛や更年期障害などの症状のコントロールを通して、少しでも快適な生活を送っていただきたいと考えています。
相談しやすい雰囲気を大切に、悩みに真摯に向き合う
患者さんと接する際、どのようなことを心がけていますか?

【秀樹院長】産婦人科に関する症状は、早めの受診がとても重要です。病気の早期発見やQOL(生活の質)向上のためにも、日頃から産婦人科に対する受診のハードルを下げられるよう努めています。患者さんにまた来たいと思っていただけるように、お話やお悩みにじっくりと耳を傾けること、専門用語を使わずに、わかりやすくかみ砕いた言葉でお伝えすることなどを心がけています。
【京子副院長】地域のクリニックは、患者さんが何かあったときに最初に訪れる場所ですので、何でも相談しやすい雰囲気を大切にしています。ちょっとしたことでも、気になっているのであれば気兼ねなくお話ししてもらいたいです。そして来ていただいたからには、患者さんの疑問や不安を一つでも多く解決したいと思っています。「また相談してみようかな」と思ってもらえたらうれしいですね。
妊婦さんや出産後の女性と接する時間の長い、助産師の皆さんはいかがですか?
【近藤さん】時代の変化とともに、女性やお母さんたちの考え方も変わってきているのを感じています。例えば赤ちゃんにあげる母乳ですが、今は、母乳にこだわらずミルクでも良いという方が増えています。昔はできるだけ母乳で頑張ってもらいたい気持ちがあったのですが、実際に子育てするのはお母さんたちですから、こちらの意見を押しつけるのではなく、ご本人やご家族の意志を尊重するよう心がけています。同じ方向を向いて、その方が頑張っていけるようアドバイスしたりサポートしたりするのが、私たちに求められる役割だと思っています。
最後に、地域の皆さんにメッセージをお願いします。

【秀樹院長】当院は駐車場も広く、自転車置き場も用意しているのでアクセスも非常に便利です。また、医師をはじめ経験豊かなスタッフが多い点も、患者さんに安心していただける要素の一つではないかと思います。現在、症状が落ち着いている方に関しては、オンライン診療の拡充も検討しているところです。引き続き思春期から更年期まで、この地域で暮らす女性の一生をサポートできるクリニックとして診療に取り組んでまいります。妊娠や出産後の子育て、生理痛、更年期障害など、何かありましたらいつでも気軽にご相談ください。






