伊能 智明 院長の独自取材記事
あすなろデンタルクリニック
(江戸川区/新小岩駅)
最終更新日:2025/11/20

JR総武本線の新小岩駅からバスで約15分。幹線通り沿いに位置する「あすなろデンタルクリニック」の院長、伊能智明先生は、江戸時代の測量学者として知られる伊能忠敬ともゆかりのある家系の出身だという。2010年5月に開業した同院は、白を基調とした明るく清潔感のある空間で、院内には落ち着きと温かみが調和した穏やかな空気が流れている。歯学部を卒業後、東京医科大学病院の口腔外科に入局した伊能院長の強みの一つは、「全身管理を前提とした有病者の歯科医療」にある。日々の診療に加え、日本有病者歯科医療学会理事や江戸川区歯科医師会理事を務め、地域と専門領域の両面で重要な役職を担う。「声をかけていただけるうちは、できる限り力を尽くしたい」と語る伊能院長に、診療方針や開業の背景、地域医療への思いについて聞いた。
(取材日2025年10月22日)
有病者の歯科治療と口腔外科を柱に据える診療
最初に、診療方針についてお伺いします。

当院の診療方針は、実は開業当初からまったく変わっていないんです。私は大学病院に20年間勤務し、その経験の中で「地域で有病者の方々の歯科治療を支えたい」と強く思うようになりました。その思いを形にするために開業し、今でも有病者の方々が多くいらっしゃいます。歯科医院の専門性は、標榜科を見るとよくわかります。例えば「歯科、歯科口腔外科」と掲げている歯科医院であれば、それはその分野を得意としている、あるいは歯科口腔外科を専門とする歯科医師がいるなど、しっかりした背景があるということだと考えます。当院も「歯科、歯科口腔外科」を掲げています。有病者の歯科治療と口腔外科を軸に、地域の皆さんに安心して通っていただける診療を続けたいと考えています。
クリニックの特徴を教えてください。
当院の特徴の一つは、有病患者さんの歯科診療にしっかり対応できる体制です。治療中の安全を守るため、脈拍・血圧・酸素飽和度・心電図まで確認できる大型モニターを設備。一般的な歯科医院でもモニターを導入するところはありますが、心電図までチェックできる設備は限られます。リアルタイムでデータを確認しながら、安全性を重視した治療を行っています。もう一つのこだわりは、かぶせ物や入れ歯など補綴物の品質です。信頼する技工所に製作を依頼し、細かな要望にも丁寧に応えてもらっています。痛みがなく、すぐに噛めて違和感のない補綴物を提供するために、写真で仕上がりを指示することもあります。
患者さんの傾向として、どのようなことが挙げられますか。

当院は、平日は休診日以外夜8時まで、日曜日も診療しています。平日にお忙しい方や、「日曜でないと通えない」という方にも対応できるよう、柔軟にスケジュールを調整しています。おかげさまで「通いやすくて助かる」というお言葉を多くいただいています。また、当院の患者さんは高齢の方が多い一方で、子育て世代のファミリーも意外と多いんです。お子さんの受診をきっかけにご両親や祖父母の方が来院され、3世代で通ってくださるケースもあります。最近では、メンテナンスや予防歯科を目的に通われる方も増え、開業当初に比べて患者さんの意識が大きく変わってきたと感じます。開業当初から通い続けている患者さんもいらっしゃり、うれしく思っています。今後は、疾患を抱えながらも長く健康で過ごされる方がますます増えていくでしょう。そうした方々にとって「安心して通える歯科医院」であり続けることが、地域医療の一員として私が果たしたい役割です。
地域に根差した、寄り添う診療を
大学卒業後は、どのような研鑽を積まれたのでしょうか。

私は1991年に鶴見大学歯学部を卒業し、同年に東京医科大学病院の口腔外科に入局しました。歯科大学ではなく、医科大学を選んだのは、より幅広い医療の現場で経験を積みたいと思ったからです。医科大学の口腔外科では、心疾患や糖尿病、がん治療中の方など、有病者の患者さんが多く、全身管理を前提とした歯科治療が求められます。主治医との連携や、全身状態を考慮した治療計画など、医科的な思考力が自然と鍛えられました。がんなどの医科的要素の強い外科にも関わることができ、歯科医師としての視野を大きく広げてくれたと感じています。大学病院では約20年間勤務し、現在も非常勤医員として関わっています。この経験が、私の診療の礎であり、「全身を見ながらお口の健康を支える」という今のスタイルにつながっています。
この地で開業に至った背景をお伺いします。
開業するなら、長年暮らした両国のように、土地の雰囲気がよくわかる地域が良いと思っていました。中央区、江東区、江戸川区を中心に物件を探す中で、高齢者の割合が高い江戸川区に注目。大学病院時代に「有病者の歯科治療」に自分の強みを見いだしていた私は、高齢化が進み、持病を抱えた方が多いこの地域でこそ専門性を生かせると考え、2010年5月に開業しました。歯学部に進学した頃から自分のクリニックを持つことは決めており、大学病院で20年経験を積んだ上で、「今、自分が地域で何を提供できるか」を考えたとき、やはり医療を通じて地域に貢献することが一番だと思ったのです。
先生が診療を行う際、大切にしているのはどのようなことでしょうか。
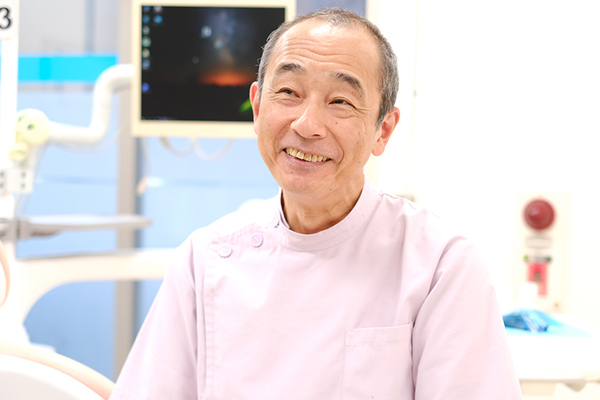
診療で最も大切にしているのは、まず「しっかり話を聞くこと」です。歯の痛みや違和感だけでなく、体調や服薬のことなど、全身の状態も丁寧にお聞きします。有病者の方にとって、歯の治療は全身の健康とも深くつながっていますから、訴えの背景まで理解する姿勢が欠かせません。また、主治医の先生とのコミュニケーションも非常に重要です。医科大学にいた経験から、歯科医師・医師同士の連絡では「文書で伝えること」が基本だと身にしみています。口頭で済ませず、必要な情報は必ず書面でやりとりする、それが、正確で信頼できる医療連携の土台になると考えます。手間はかかりますが、文書で丁寧に伝えることこそが、患者さんに安全で質の高い医療を提供することにつながると考えています。これからも、患者さんに寄り添い、他科と連携しながら、一人ひとりに合った治療を提供していきたいと思います。
医療連携を広げ、地域医療に貢献
先生が取り組む地域貢献について教えてください。

私は現在、江戸川区歯科医師会の理事として2期目を務め、学校歯科医も担当しています。また、日本有病者歯科医療学会の理事も務めています。忙しい日々ですが、地域に貢献できることが何よりのやりがいです。理事の立場を通じて出会った先生方を招き、江戸川区で講演してもらう機会もあります。こうした横のつながりが、病院との連携をより円滑にしています。例えば、墨東病院の部長とは旧知の仲で、患者さんの紹介などを通じて密に協力しています。江戸川区では、港区と並んで都内でも数少ない「口腔がん個別検診」に力を入れて取り組んでいて、医療連携の充実が進んでいます。大きな治療後も当院で丁寧にフォローアップを行う。それも私にとっての地域貢献の一つです。
地域住民の生活習慣改善にも向き合っていらっしゃるとお聞きしました。
患者さんのお口の中を見ていると、生活習慣や地域性がよく表れます。江戸川区は、口腔環境があまり良くないケースも多いんです。お子さんも同様で、虫歯の罹患率はおそらく23区でも最下位クラスではないかと推測しています。この状況をどうにかしようと、江戸川区では2023年から小・中学校で「フッ素洗口」を始めました。清掃だけでは虫歯の発生を防ぎきれない現実がありますので、最終的には「どう過ごすか」という生活習慣の指導が重要なんです。教育委員会とも話し合いながら、学校での「フッ素洗口」を軸にした予防プログラムを始めました。これは2028年まで続く予定で、区として本気で取り組んでいます。
最後に、今後の展望についてお聞かせください。

当院では、医科と歯科が連携し、手術前後の口腔ケアを行う「周術期口腔管理」にも取り組んでいます。目的は、術後の肺炎や感染症の予防、そして回復の促進です。江戸川区では、私が理事を務めた昨年から本格的に始まりました。例えば歯科部門のない東京臨海病院では、当院が手術前後のケアを担当しています。胃がんや肺がん手術後に口腔ケアを行うことで、肺炎の発症率を下げることが期待できるだけでなく、入院期間の短縮にもつながります。今後も医科との連携を広げ、地域で完結できる医療体制を整えていきたいと考えています。周術期だけでなく、有病者の方々が「自分の地域で安心して手術を受けられる環境」を築くことが目標です。






