田上 尚道 院長の独自取材記事
たがみ小児科
(杉並区/久我山駅)
最終更新日:2025/08/08
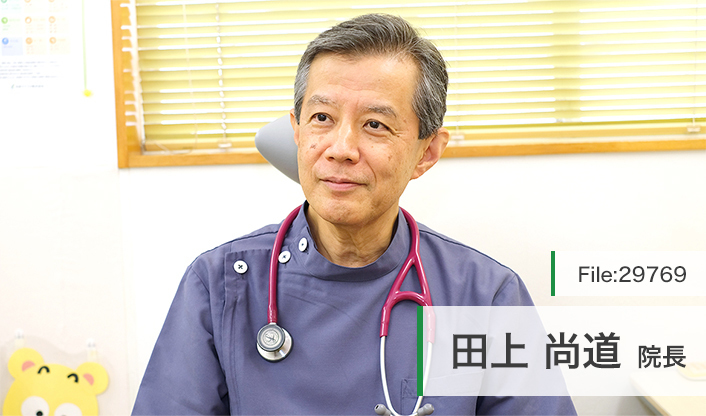
「小児科を専門に選んだのは、子どもたちのあらゆる症状を診ることができるから。循環器内科や消化器内科といった臓器別に細分化して診るのではなく、体をトータルで診たかったんです」。久我山駅から徒歩2分の場所にある「たがみ小児科」の田上尚道(ひさみち)院長はこう語る。開業から21年、地域に根差した診療を続ける田上院長は、つい長話をしてしまうほど患者と家族とのコミュニケーションを大切にする小児科医だ。小児科を選んだのは、子ども全体を診る包括的な医療への信念があったから。診療では患者や家族の潜在的な悩みを引き出すことを心がけている。そんな田上院長に、診療への思いや地域医療にかける情熱について聞いた。
(取材日2025年7月9日)
臓器別ではなく、年齢で区切った小児医療への信念
開業から21年を迎えた久我山での診療について教えてください。

実は久我山に特別な縁があったわけではないんです。杉並区内の総合病院に7年ほど勤務していた時の同僚の医師が先に開業することになり、「小児科専門の医院が久我山駅付近にない」と声をかけてもらったのがきっかけでした。当時この辺りには小児がかかれるクリニックが少なかったことが後押しとなり、2004年にここで開業することになりました。患者さんのご家族は、吉祥寺と渋谷を結ぶ井の頭線沿線ということもあって、IT系企業などで働いている方が多い印象ですね。
小児科を専門に選んだ理由は何だったのでしょうか?
診療する対象を臓器別ではなく年齢で区切っているからです。小児科では子ども全体を診るじゃないですか。臓器別の内科のように神経とか呼吸器とか循環器とか、臓器ごと分けて診る医療には違和感があったんです。神経だけ見ても体はどうするの? 体を見ても心はどうするの?と思っていました。小児科なら、生後すぐから中学・高校生まで、小児科の年齢に該当する人は全部診ます。とにかく子どもだったらなんでも取りあえず診てみる。全身を総合的に診られることにやりがいを感じています。
クリニックの特徴的な点について教えてください。

まず内装ですが、開業当初は白木だった板張りの壁が、7、8年たってあめ色に変化しましたね。建築士さんが「あめ色になるから大丈夫」と言っていたとおりになりました。待合室は天井が低いと閉塞感が出るので、吹き抜けにして開放感を大切にしました。それから疾患や治療法によっては特に年齢制限は設けていません。花粉症の舌下免疫療法などは、大人の方にも行うことが可能です。あと、順番予約システムは開業時からのこだわりで、これがなかったら開業していなかったくらいです。テーマパークで長い行列に並んでいても比較的人が待てるのは、おそらく順番が守られているからですよね。時間予約だと個別の診療時間がマチマチでお待たせしてしまうことが多くなりがちですが、順番予約なら比較的長めの待ち時間でも待てるかもしれない。午前と午後の診療予約が午前7時から取れて、スマホで順番が近づいたら来院すればいいので、院内での待ち時間は最小限です。
コミュニケーションを重視した診療と独自の医療観
診療で特に大切にしていることは何ですか?

例えば、発熱症状で来られた患者さんがいたとします。受診のきっかけは発熱だけれども、実は日常の中で体や健康に関して気がかりなこと、悩んでいることっていっぱいあると思うんです。「そういえばこれが前から気になっていた」、そんなことが言いやすくなるような雰囲気づくりを心がけています。大事なのは、患者さんにリラックスしてもらい、「この先生とはもうちょっと話したいな」と思わせること。私はつい10分でも20分でも喋ってしまうから、お母さんたちも、帰り際に「もう一つ聞いていいですか?」となったりします。ただ、待っている患者さんもいるので、話をじっくり聞くことと、診療の効率を上げることのジレンマにいつも悩んでいますが、いろんな工夫を重ねてこれからも少しずつ効率化していきたいです。
予防医療やスキンケア指導で独自の取り組みはありますか?
予防接種やワクチンも積極的に推奨しています。接種に積極的でない親御さんもいますが、周りがみんな接種することで子どもの健康が守られるという側面があるわけで、予防接種の必要性を説明しています。スキンケアについては、みんな「保湿が大事」と思っていますが、赤ちゃんはもとからみずみずしいので保湿はあまり気にしなくて大丈夫。大事なのは皮膚の保護なんです。赤ちゃんの湿疹は擦り傷のようなもので、治りかけの時にかさぶたができてカサカサするんですが、それを乾燥と勘違いして保湿剤を塗るとジュクジュクになって悪化します。私はワセリンなどの保護剤を勧めています。
どのような症状の患者さんが多く来院されますか?

やはり熱、咳、鼻水、嘔吐、下痢といった一般的なものが多いですね。立ちくらみがすごいとか、元気がないという相談もあります。起立性調節障害といって朝礼でパタッと倒れちゃうような症状です。貧血みたいに見えますが、実は血液は足りていても脳への血流が足りていない脳貧血なんです。あとは花粉症の相談も多く、指先からの微量な採血で検査可能なアレルギー検査を採用しています。注射針を使用する検査ではなく、指先にスタンプを押すようなほぼ痛くない採血で41種類のアレルギーの原因物質を調べることが可能です。スギやダニのアレルギーに対しては舌下免疫療法を提供しています。お子さんだけでなく、大人の方にも行っています。
地域に根差した長期的な信頼関係の構築
スタッフとの連携や地域での活動について教えてください。

当院のスタッフはみんな平均年齢が私と同じくらいで、ベテランぞろいです。事務スタッフも患者さんのことをしっかり見てくれていて、待合室で「ちょっと様子が変」と気づいて看護師に伝えてくれたりします。看護師は診察室にいて気づかないこともあるので、本当に助けられていますね。それから私は8つの保育園の園医をしていて、今日も80人の健診をしてきたところです。週1回の休診日は主にこうした園の健診にあてています。保育園で働いていたスタッフもいて、院内の装飾を作ってくれています。時には園児たちから足型で作ったウサギの作品をもらうこともあって、うれしいですね。地域とのつながりを大切にした診療をこれからも続けていきたいです。
長年の診療で印象的なエピソードはありますか?
開業して21年もたつと、10歳くらいで来ていた子がもう30歳を超えています。花粉症とかのどが痛いとか、何かあると今も通ってくれる人がいます。喘息でずっと薬を飲んでいる人などは、今さら新規で内科に行って「前はこの薬使っていました」と説明するのも大変だから、慣れているところがいいんでしょうね。最近では「先生、生まれました」と言って自分のお子さんを連れてきてくれる患者さんも出てきて、そのお子さんのワクチンの予定を立てたりするのは、結構うれしい瞬間ですね。あと、引っ越しても通い続けてくれる方もいて、調布や大泉など少し離れたところから車で来てくれます。今まで診てきて、その子の性質をわかっている医師のほうが診察も手際良くスムーズにできるというのはあると思います。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。

病気のことが心配で来院されるでしょうけど、日頃のちょっとわからないことや不安に思っていることがあれば、私だけじゃなくスタッフにでもいいので相談してください。子育てに悩んでいるとか、この子の成長は大丈夫なのかとか、そういう漠然とした不安もあるでしょう。メモにびっしりと書いて、完璧に準備してからじゃないと来ちゃいけないと思っている人もいますが、そんなことはありません。来てから「えーっと……」となってもいいんです。子どもの症状の何が、どこが心配かがわからなくてもいいですから、まずは来ていただくことが大事で、あとはこちらで判断しますので、気になっていることがあれば、気兼ねせず、ぜひ話をしにいらしください。






