山田 堅一 院長の独自取材記事
香流もの忘れと心の診療所
(名古屋市名東区/上社駅)
最終更新日:2025/10/02

名古屋市名東区の住宅街、大型ホームセンターのすぐ近くにある「香流もの忘れと心の診療所」。山田堅一院長は、国立病院機構で40年以上のキャリアを積み、長良医療センター院長を経て、70歳を越えて初めて街角の診療所での診療を実現した。学生時代から恩師・笠原先生の影響で「いつかは街角の精神科医に」という夢を抱き続け、管理職から臨床現場に戻れたことを心から喜んでいる。治療への強い信念を持ち、診療では一人ひとりにじっくり時間をかけ、精神療法を中心としたアプローチで患者と向き合う山田院長に、診療スタイルや物忘れ相談での独自の取り組みについて話を聞いた。
(取材日2025年9月2日)
70歳を越えてようやくかなえた精神科医としての夢
40年以上の国立病院勤務を経て、現在に至った経緯を教えてください。

名古屋大学卒業後すぐに国立名古屋病院(現・名古屋医療センター)の精神科に入り、そのまま40年以上勤めてきました。精神科病棟があり、救急から緩和医療まで幅広い経験を積むことができたのは貴重でした。その後、長良医療センターで院長を6年務め、2020年に退官しました。実は学生時代、恩師から「将来の精神科医療は街角の診療所から始まる」と言われて以来、いつかは町の診療所で診療したいとずっと思っていたんです。70歳を過ぎてやっと実現できました。理事長が声をかけてくれたおかげで、管理職で終わらず臨床に戻ってくることができ、久しぶりに精神科医として患者さんと向き合える喜びを感じています。
なぜ精神科医を志し、長年その道を歩んでこられたのですか?
医師を志すきっかけになったのは、1歳の時に負った左手の大やけどです。当時の医療では命に関わるほどの深刻なものでしたが、幸い一命を取り留めることができました。しばらくたった小学生の頃、同じくやけどが原因で左手に障害があった野口英世の伝記を読んで感銘を受け、「自分も医師になる」と作文に書いたんです。その決意を貫いて医学部へ進みました。精神科を志したのは高校時代。図書館で精神科関連の本を読み、医学と文学の間のような診療科目であることに魅力を感じたのです。国立名古屋病院では病理解剖についても研鑽しながら精神科診療を続け、総合病院だからこそできる全身管理を含めた精神科医療を実践してきました。今思えば、特殊で恵まれた環境だったと思います。
こちらのクリニックのコンセプトについて教えてください。
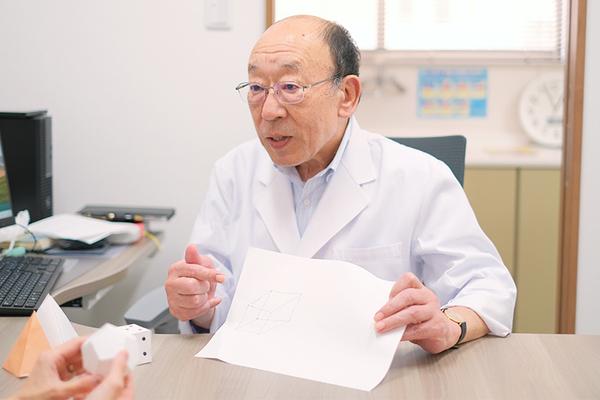
「心に寄り添う、街角の診療所」として、気軽に立ち寄れる場所をめざしています。主に診ているのは、いわゆる神経症レベルの方々です。精神病ほど重くない、ちょっと心が痛んだとか傷ついたという方。頑張り屋さんで努力家の人が多いですね。環境が変わって今までの頑張り方が通用しなくなったり、職場の人間関係で悩んだり、そういったことが引き金となる。つまり、「みんながなり得る、誰もがなり得る」ものだと考えています。心療内科の疾患以外には、物忘れの相談もお受けしています。患者さんの傾向としては「物忘れが認知症につながるのではないか」と心配されて来られる方、あとは「他院で治療を受けていたけれども改善が見込めなくて受診した」という方も多いです。そういう方々にとって身近な相談場所になれればと思っています。
じっくり向き合う精神療法へのこだわり
先生の診療スタイルの特徴を教えてください。

基本的な精神療法の技法に従って診療しています。まず患者さんの気持ちや考えを表現できるようにする。次に支持的精神療法で共感を示す。でも、そこで終わらせません。洞察的精神療法で「なぜそんなに頑張るのか」を気づいてもらい、最後に今後の対処法を一緒に考えていきます。私は患者さんを治したいという思いが強く「治すことは、その人を変えること」だと思っているので、慰めの先を行うんです。もちろん、そうだよねって共感も大事です。しかし、結局自分を変えないといつまでも患者さんはつらい経験をしてしまいます。患者さんを想うがゆえに、時には一言多くなったり、苦言を呈したりすることもあります。そのせいで嫌われることもあるかもしれません。それでも患者さんと「自分を大事にしてね。応援しているから一緒にこの問題を乗り越えよう」という約束をして、真剣に向き合っています。
診察にはどのくらい時間をかけていらっしゃいますか?
初診では最低でも30分、場合によっては60分以上かけることもあり、じっくり時間をかけて診ることができます。当院には不登校の10代のお子さんから、認知症の90代の方まで幅広く来院されていますが、それぞれの患者さんに合わせて診療しています。時には「10分も話を聞かずに薬だけ出す医師が多い」などと、ご立腹の患者さんが当院にいらっしゃることもあります。恐らくいろいろなクリニックを転々としてこられたのかなと思いながら、長年この仕事をさせてもらっている身としては「僕が最後まで付き合いますよ」という気持ちで、じっくりとお話をお聞きしています。
深刻な状態の患者さんへの対応はどうされていますか?

精神病と神経症では治療アプローチがまったく違います。精神病の場合は妄想など特別な症状があり、薬物療法が主体になります。当院には入院設備がないので、精神病レベルの方や入院が必要な方は、きちんと病診連携で精神科病院にお願いしています。例えば「1ヵ月ほど安静にしましょう」とお伝えしても、自宅ではゆっくり休めないという方もいらっしゃいますから、その場合は入院が必要だと判断します。当院で診るのは、あくまでも外来で対応できる神経症レベルの方や、薬で安定している方です。時に患者さんの状態や症状に合わせて、適切な病院を紹介する。それも町の診療所の大切な役割だと考えています。
物忘れ相談に特化した外来では「脳トレ」も推奨
物忘れの相談に対応する外来について詳しくお聞かせください。

この外来には、「物忘れが度々あるけど、これが認知症にならないか心配」という方が多く来られます。外来の特徴は、脳トレーニングを取り入れていることでしょうか。例えば、サイコロの展開図を作ってもらったり、ナンプレ(ナンバープレース)に取り組んでもらったりしています。これらは、言葉を介さずに動作で空間を理解する訓練となり、頭頂葉から側頭葉、前頭葉の機能を刺激するんです。そこでスタッフにもナンプレがうまく誘導できるよう練習してもらい、一緒に「この列を考えてみようよ」と取り組んでいます。物忘れは、単に面談を繰り返しても症状改善が期待しにくいので、こうした脳の刺激になることも組み込んでいます。とはいえ、脳トレで改善が見込めるのは70代前半まで私は思っています。80代半ばになると正直難しい面もありますが、それでも一人ひとりに合わせた対応を心がけています。
クリニック名に「もの忘れ」を入れた理由は?
理事長の野口先生が老年精神医学や認知症の専門家ですので、物忘れに取り組んでいることをわかりやすく伝えたいという思いがありました。実際、物忘れで困っている方は多くそういった方はCTやMRIの検査、血流診断などを求めて大きな病院を受診されるのですが、当院には「ちょっと心配」「大丈夫だろうか」という相談レベルの方が来られます。気軽に相談できる場所として、認知症の進行を防ぐために、物忘れに特化した外来を設けていますが「外来を開設するなら、当院らしいサービスを提案したい」という理事長の考えで、先ほどお話しした脳トレーニングを導入しました。独自の取り組みを行いながら、これからも地域の方々の不安に寄り添える診療所でありたいと思っています。
今後、この診療所でどのような医療を提供していきたいですか?
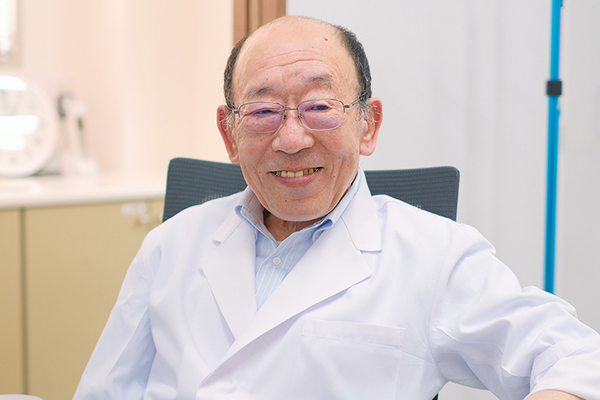
当院を受診してくださった方に関しては、どんなお悩みであってもできる限り診たいと思っています。ただ、診療の際に「あなたにはこういうところがありますね」と分析すると、「あなたのここが悪い」と非難されているように受け取ってしまう方も時々おられます。しかし、症状の改善をめざすためには、自身で意識していない感情や考え方の傾向に気づいてもらわないといけないんです。精神科のクリニックは、今や一駅のエリア内にいくつもあるくらい多いので、患者さんには選択の自由があります。合わなければ他院に行くということも時には大切なことです。それでも当院を選んでくれた方には、私の70年以上の人生経験と40年を超える臨床経験を生かして、その人に合う方法を見つけていきたい。街角の診療所として、一人ひとりの患者さんと向き合い続けることが私の使命だと思っています。






