田村 浩 院長の独自取材記事
メディケアクリニック上石神井
(練馬区/上井草駅)
最終更新日:2025/09/01
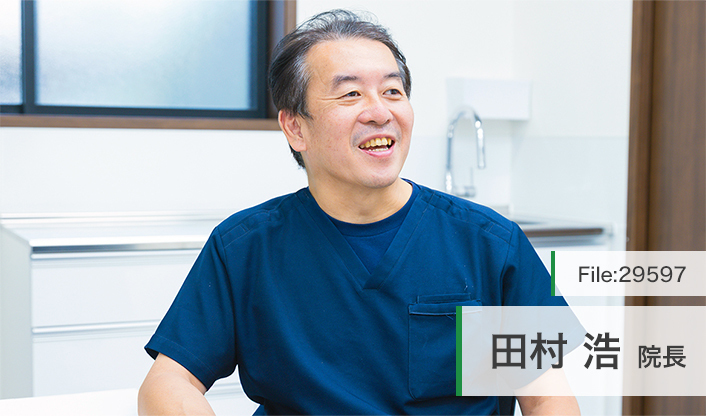
上井草駅から徒歩4分の上石神井メディカルビレッジ内に、2025年9月「メディケアクリニック上石神井」が開業した。同院の本院「メディケアクリニック石神井公園」にて訪問診療を担当している循環器内科医、田村浩院長が診療にあたる。予防から看取りまでをシームレスに支援し、「健康は足から」という考えのもと、フットケアと多角的な視点で診療することで、患者の生活をトータルでサポート。患者の生き方に寄り添った治療の選択を心がけ、人生の終末期を迎える人に、本人の希望や家族の意向を尊重したケアを提供する。穏やかな人柄と優しい笑顔が印象的な田村院長に、診療の特徴や分院を開業するに至った経緯などについて話を聞いた。
(取材日2025年6月16日/情報更新日2025年9月1日)
循環器内科医としての歩みと地域医療への貢献
院長のこれまでのご経歴を伺います。

1997年に順天堂大学に入局し、循環器内科の医師の道を進みました。その後救命救急に強い順天堂大学静岡病院を経て、急性期の患者さんに行う心臓カテーテル治療の様子を見て、大きな可能性を感じました。しかし、臨床経験を積む中で足の血管が詰まる閉塞性動脈硬化症などの患者さんと多く向き合うことになり、足の血管病治療の重要性を痛切に感じたんです。一方、足が壊死してしまう重症患者さんを診る中で一つの科だけでは救済が難しい現実にも直面。複数の科をたらい回しにされてしまうケースも少なくありませんでした。そこで、順天堂大学附属静岡病院で形成外科医とともにフットケアに特化した外来を立ち上げ、その後、順天堂大学附属練馬病院に移ってからは地域に本格的なフットケアチームがなかったため、足の救済を目的とした外来を始めました。これまでの知識と経験を統合し、他科と連携して足の悪い患者さんを支える体制を築いていきました。
なぜ訪問診療に携わるようになったのでしょうか?
重症患者さんが病院で最期を迎えるケースが多い中で、住み慣れた家で穏やかに過ごす重要性を感じたことがきっかけです。そこで、訪問看護ステーションや訪問診療の医師と連携し、大学病院での治療後も自宅で療養できる体制を整え始めました。しかし、大学病院勤務中に連絡が入るとどうしてもタイムラグが生じるという課題があったんです。そこで「メディケアクリニック石神井公園」の長濱久美院長から「一緒に訪問診療をやってみないか」と勧められ、訪問診療に携わることになりました。実際に訪問診療を行う中で、患者さんの家庭環境の中に足の病気を悪化させるヒントがあることに気づき、訪問診療の重要性を感じました。
分院開業に至った経緯を教えてください。

分院開業は石神井地域に深く根差し、防災や教育も含めた地域全体の活性化をめざすという考えからです。訪問診療を行うクリニックは診療圏を考慮し距離を置くことが多いのですが、夜間急変時などの迅速な対応を重視し、患者さんの視点に立った医療を提供したいと思いました。呼吸器の専門家である本院の長濱院長と循環器の専門家である私が、この地域で2つの車輪となり、より一層密度濃く地域医療に貢献したいという思いがあります。
多角的な視点で、患者の健康寿命を延ばしたい
こちらのクリニックの特徴を教えてください。

外来診療と訪問診療の両方を兼ね備えている点が大きな特徴です。働き盛りの世代から高齢者まで、幅広いニーズに対応できる点にあります。外来診療で予防段階からしっかりと診察し、病状の進行とともに訪問診療へと移行しても、途切れることなく最期まで見届けられる、シームレスな医療を提供することが可能です。もう一つの大きな特徴は、健康は足から、という考え方に基づいたアプローチです。フットケアに力を入れ、体全体の健康をしっかりサポートしていきます。ほかにも、当院は歯科や整形外科、婦人科、小児科そして管理栄養士も擁する医療複合施設内にあります。足のケア、歯科、栄養管理といった多角的な視点から、患者さんの健康寿命を最大限に延ばせるよう努めていきたいです。
循環器内科の先生が訪問診療されるメリットを教えてください。
診察はもちろんですが、ご自宅で心臓の超音波検査や足の血管エコー検査も可能です。患者さんが心不全で状態が悪くなっているのか、それとも単に足がむくんでいるだけなのか、あるいは栄養状態が悪いのかといった原因は、適切に判断できると思っています。例えば、高齢になると足がむくむのはよくあることですが、安易に利尿剤を使ってしまうと、夏場などに脱水症状を起こしてしまうリスクもあります。ご家庭で直接診療できることで、むくみや息苦しさに対してより適切な対応ができるのは、大きなメリットです。本来ならクリニックでしかできないような検査や評価の一部が在宅で可能になります。
訪問診療で定期的に診ることで、予防にもつながると伺いました。

外来診療だけでは、次回の診察までの1ヵ月や2ヵ月の間、患者さんの状態を把握しきれない空白期間ができてしまいます。その間に病状が悪化することもあります。訪問診療では月に2回はご自宅に伺うことで、患者さんとの距離感が非常に近くなり、例えば少し体重が増えたといった少しの変化もすぐに察知できます。その場で対応を取ることで、心不全による入院を減らせるのではないかと考えています。
患者の生き方や意思を尊重した医療を
診療時はどのようなことを大切にされていますか?

外来診療においては、もちろんエビデンスに基づいた治療を提供することは大前提ですが、しゃくし定規に進めるのではなく、患者さんがどうしたいのか、という点を大切にしています。大学病院では時間が限られることもあります。ですが、当院では患者さんの背景や事情にも向き合い対話を重視することで、できるだけ内容の濃い外来診療をめざします。訪問診療では、ご家族も含めた関係性を大切にしながら、患者さんの生き方そのものに寄り添い治療を選択していきたいと考えています。中には、タバコをやめられない方や、特定の治療を望まない方もいらっしゃいます。人生の終末期に向かっている方々にとっては、ご本人の気持ちや生き方に重きを置きます。ですから、ご本人の希望やご家族のお考えも含めて総合的に判断し、治療なのか、緩和ケアなのか、状況に合わせて柔軟に対応していきます。
どのような方に来院してほしいですか?
外来診療では、まだまだ働き盛りで動脈硬化のリスクがある方々、具体的には糖尿病、高コレステロール、そのほかの生活習慣病をお持ちの患者さんです。そして、外来から訪問診療へと移行していくような、介護保険サービスへの移行を検討している患者さんも、お越しいただきたいです。この段階の方は、まだまだ元気になる可能性を秘めているんです。当院では足に特化した外来やフットケアにも力を入れ、疾患の予防、介護に進まないための予防、日常生活を維持するためのケアにも注力していきます。最終的には、たとえ病状が進行してもなるべく寝たきりにならないよう支えたいと考えています。そして、看取りの段階になった方々に対しては、治療だけでなく、ご家族を含めた心のケアも含めて診ていきたいと思っています。健康寿命を延ばすこと、そして心不全が増加する中で、緩和ケアにも力を入れていきたいです。
最後に、今後の展望と読者へのメッセージをお願いします。

今後の展望としては医療を提供するだけでなく、地域における災害対応のための事業継続計画「BCP対策」にも貢献していきたいと考えています。また、私が石神井に拠点を移したのは、横浜で暮らす両親の介護がきっかけでした。私自身も介護に直面した経験から、介護は決して他人事ではないと感じています。介護世代であり、医師として要介護者を診ている立場なので、ともに話し合いながら、地域に根差した医療と介護の在り方を考え、築き上げたいと思っています。






