早期発見が難しい肝臓疾患
健康診断で異常を指摘されたら相談を
大久保メディカルクリニック
(印西市/千葉ニュータウン中央駅)
最終更新日:2025/08/13


- 保険診療
代謝や胆汁の生成、解毒などさまざまな役割を担う肝臓。重要な臓器でありながら、問題が起きても自覚症状が出にくいことから「沈黙の臓器」と呼ばれる。「大久保メディカルクリニック」院長の大久保知美先生は、長年にわたって大学病院で肝臓疾患に関する研究を続けてきた。勤務医時代に携わった肝臓疾患の患者の中には、若くして亡くなる人や、「早期に発見し、適切なフォローができていれば」と悔やまれる事例も多かったという。その経験から、同院では脂肪肝などが疑われる患者に対して、詳しい検査や生活習慣の改善を中心にアプローチ。肝硬変や肝臓がんといった肝臓疾患への進行抑制に注力している。日本肝臓学会肝臓専門医である大久保先生に、若い世代にも増えているという肝臓疾患や適切な受診のタイミングについて教えてもらった。
(取材日2025年7月17日)
目次
世界中で増えている非アルコール性の脂肪肝。将来的に肝硬変や肝臓がんを引き起こす原因に
- Q肝臓の疾患にはどのようなものがありますか?
-
A
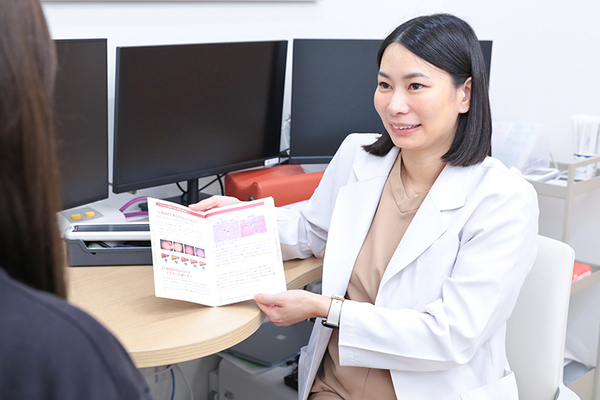
▲アルコールを飲まなくても脂肪肝になる可能性も
主なものにウイルス性の肝炎や脂肪肝、原発性胆汁性胆管炎、肝硬変、肝臓がんなどが挙げられます。中でも皆さんにとって身近なものが、脂肪肝です。肝臓に過剰に脂肪が蓄積された状態を脂肪肝といい、よく知られているのは長期間にわたる過剰なアルコールの摂取が原因のものです。しかし、最近ではアルコールの摂取量が多くないにもかかわらず、食生活の偏りや運動不足による肥満や高血圧症、糖尿病、脂質異常症などが原因の非アルコール性の脂肪肝「MASLD(代謝機能障害関連脂肪性肝疾患)」が世界中で増えています。30代などの若い世代でも注意が必要です。
- Q脂肪肝を放置するとどのようなリスクがありますか?
-
A

▲日本肝臓学会肝臓専門医の資格を持つ大久保院長
脂肪肝が進行すると、肝臓の組織が硬く線維化し肝硬変や肝臓がんを引き起こします。「MASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎)」のうちの5~20%の方が将来的に肝硬変や肝臓がんになるリスクが高いといわれています。さらに、非アルコール性の脂肪肝の場合には肥満や高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を合併しているケースが多いので、心筋梗塞や心不全、脳卒中など肝臓以外の疾患やがんのリスクも高まります。非アルコール性の脂肪肝のほとんどは肥満などが原因ですが、日本では肥満ではない方にも代謝機能障害関連脂肪性肝疾患が見つかっていて、実は「太っていないから大丈夫」というわけではないんです。
- Q健康診断などで異常があった際には、受診が必要なのですね。
-
A

▲肝臓の不調は見逃されがち。若い世代も油断せず、早めの受診を
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、問題があっても初期段階では症状が出にくいという特徴があります。自覚症状が出始めた時には、病状がかなり進行している可能性が高いです。早期発見するためにも、健康診断で脂肪肝などが疑われる場合には、できるだけ早いタイミングで精密検査を受けるようにしてください。脂肪肝は、早期に適切な治療を行えば肝硬変や肝臓がんへの進行を抑制することが望めます。過去に脂肪肝と診断された経験がある方も、できれば一度検査を受けて、自分が今どのような状態なのかを知っていただきたいと思います。脂肪肝がアルコール性のものか、それとも非アルコール性のものなのか、原因を知ることも大切です。
- Q詳しい検査内容や治療の流れについて教えてください。
-
A

▲血液検査と超音波検査で肝臓を総合的に評価する
肝臓疾患が疑われる方が来院されたら、まずは問診で普段の生活や既往歴についてお話を伺います。その上で、血液検査や超音波検査によって肝機能の再評価を行います。健康診断の種類によっては血液検査のみでエコーを行わないケースもあるので、受診の際にしっかりと再評価し、適切な診断を行うようにしています。検査によって脂肪肝が見つかった場合には、食生活や運動など生活習慣の改善によって数値の改善をめざしていきます。進行度や合併症の有無によって通院の頻度は異なりますが、軽症であれば3~4ヵ月に1回のペースで来院していただき、血液検査を行います。
- Q治療における特徴やこだわりがあれば教えてください。
-
A

▲整形外科・循環器内科も併設し、肝疾患を含む多角的な診療が可能
当院は、消化器内科だけでなく循環器内科や整形外科なども対応しているため、総合的な診療が可能です。持病のある方や高齢で体に痛みを抱えている方は、複数診療科も併せて受診できますので、通院の手間やストレスを減らせます。また、脂肪肝の治療は生活習慣の改善がメインとなり、それには患者さんのモチベーションがとても重要です。通院の負担を減らすことで、患者さんの治療に対する気持ちが前向きになればと思っています。そして、無理のない治療計画で徐々に目標とする数値に近づけていき、少しでも数値が改善したら一緒に喜びながら、患者さんと二人三脚で治療を進めていくことを大切にしています。






