桜井 研三 院長の独自取材記事
医ケアこどもクリニック
(伊勢崎市/伊勢崎駅)
最終更新日:2025/06/20

伊勢崎市長沼町で小児在宅医療を中心とした診療を手がける「医ケアこどもクリニック」。院長の桜井研三先生は、大規模病院で小児科医として研鑽を重ねる中、医療的ケア児に対する在宅医療や訪問看護など地域支援サービスの不足を痛感。自身の経験を生かすことで、少しでも力になれないかと開業を決めた。桜井先生のほか、小児外科の医師や小児を専門とする看護師、訪問看護師が小児在宅医療チームとして在籍。医療的ケア児および18歳以上の移行期の患者のケアを行う。「ご家族の思いやニーズにできる限り寄り添い、最善の医療を届けたい」と語る桜井先生に、診療内容から今後の展望、小児在宅医療に対する思いなど幅広く聞いた。
(取材日2025年5月28日)
医療的ケア児と家族に必要な医療サービスを届ける
こちらのクリニックの特徴を教えてください。

小児、または成人移行した患者さまの在宅医療を提供しています。ご自宅で酸素を使っている方、胃ろうをされている方、気管切開をされて場合によっては人工呼吸器をつけている方などが多いですね。医師は、小児科医の私と友人である小児外科の医師の2人体制です。他に、以前一緒に働いていた小児を専門とする看護師や訪問看護師が在籍しています。小児の医療的ニーズに特化した体制で支援できるのが特長です。
なぜ、小児専門の在宅診療クリニックを開業されたのでしょうか?
私は、これまで大学病院や小児医療を中心に扱う病院のNICU(新生児集中治療室)およびPICU(小児集中治療室)で早産児、新生児仮死、先天性疾患、重症疾患の診療に従事してきました。外来では医療的ケア児・者の診療を行っていたので、ご家庭でのケアの大変さと地域支援の重要性を痛感してきました。 新生児医療や手術成績の向上により、医療的ケア児は年々増加しているにもかかわらず、小児に対応する在宅医療や訪問看護、通所支援事業所などの体制は依然として不十分です。遠方の病院に複数の医療機器を持参して通うご家族も少なくありません。そうした現状に向き合い、自らの経験を生かして支援したいという思いから、小児在宅医療を中心とするクリニックの開設を決意しました。
どういった診療をされているのですか?

定期的な診療や一部予防接種のほか、患者さまの容態に沿った医療処置を行っています。先ほど少しお話をしましたが、在宅医療を必要とされている患者さまは、大学病院や小児専門病院といったハイボリュームセンターにかかっていることが多く、通院される際はご家族がお子さまを介助しながら酸素ボンベや人工呼吸器などの医療機材も運搬しなければいけません。1〜2時間かけて通院される方も珍しくなく、酸素は通院時間分あるか、人工呼吸器のバッテリーは大丈夫かなど、いろいろ考えないといけないことがあるんですね。そこで医師が直接患者さまのお宅に訪問し、気管切開カニューレの交換や胃ろうの交換などを行うことで、ご家族の負担を軽減させることができます。
在宅医療を受けることのメリットは大きそうですね。
何よりも患者さま自身の負担、そしてなんといってもご家族の負担を大きく減らすことが見込めます。また、感染症の罹患リスクを減らすことができるのも大きなメリットです。医療機関に行くということは、どうしても感染症をもらうリスクがあります。医療的ケア児の場合は、感染症が重症化しやすい側面があります。通常のお薬をもらいに行くだけなのに感染症をもらってしまい、具合が悪くなって入院する、というリスクも考えられます。毎月受けていた医療機関の受診を3ヵ月に1回に減らせるだけでも、そうしたリスクを軽減できます。あとはお薬の処方箋を発行し、薬局からご自宅にお薬が届くようにすることもできることなど、アウトリーチな医療を提供できることは在宅医療の一番の目的、使命だと思っています。
最善の医療提供をめざし、知識を常にブラッシュアップ
最初から小児科医をめざされていたのですか?

幼少期に祖母と暮らしていたこともあり、当初は地域に根差した高齢者医療に関心がありました。しかし、初期研修で小児科を経験した際、入院中の子どもたちやご家族と関わる中で強くやりがいを感じ、小児科医の道を志すようになりました。以前勤務していた沖縄県立南部医療センター・こども医療センターを退職する時にご家族から頂いた寄せ書き集は、今でも私の一番の宝物です。
伊勢崎市で開業された理由を教えてください。
私が伊勢崎市在住ということもあるのですが、群馬県南部と埼玉県北部の領域を網羅できる場所ということで選びました。特にこの領域は小児の在宅医療の供給が追いついていない状態で、開院前から医療機関や訪問看護ステーション、通所支援事業所などから多くのお問い合わせをいただき、地域の関心の高さを感じています。今は、NICUを退院予定のお子さんや、成人期に移行する方からのご依頼が増えています。出生数は減少傾向にある一方で、医療的ケア児は確実に増えており、今後さらに在宅医療の重要性は増していくと考えています。
小児ならではの診療の難しさはありますか?
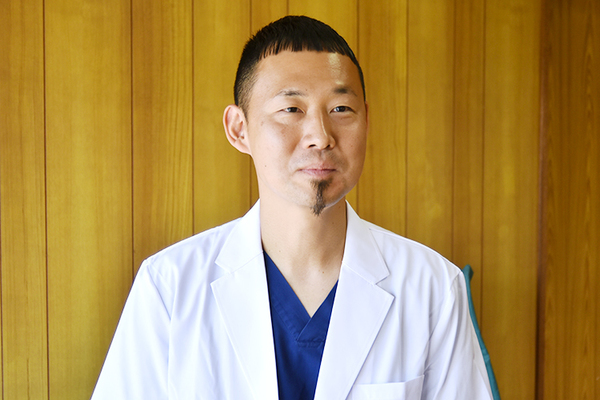
ときに診察や検査に協力的でないということもあるので、そのあたりの難しさはありますね。ただ、それもある程度長く臨床をやっている医師・看護師であれば、こういう声かけをすれば協力的になってくれるといった工夫をすることができます。以前勤務していた病院では、CT検査室に1人で入るのが怖いお子さんのためにDVDを流してあげたり、ご家族に付き添いで入ってもらったりしていました。在宅医療だと慣れ親しんだ自宅でご家族と一緒に医療を受けられるので、病院よりも安心感はあるのかなと思います。
診療で大切にされていることは何ですか?
すべてのご希望にお応えできるとは限りませんが、ご家族の思いやニーズにできる限り寄り添い、提供可能な範囲で最善の医療を届けることを心がけています。 また、医療は日進月歩なので、知識のブラッシュアップに努めています。疾患ごとにもガイドラインがあり、定期的に更新されるため、以前と今では治療の常識が異なることもあります。例を上げると、風邪に対する処方において抗生剤や咳止めの有用性が近年否定されてきており、特に小児領域では処方するケースが減っています。また、赤ちゃんの湿疹も、今は積極的にステロイドを使って良い状態のコントロールを図ります。日本ではステロイドへの抵抗意識が強いといわれており、処方しても過小投与になっている場合が多いため、「このくらいの量を出して、こんな感じで塗ってください」とか、具体的に説明をしています。
自分たちだけで抱え込まず、気軽に相談をしてほしい
お忙しいと思いますが、お休みの日はどのように過ごされていますか?

自然豊かな伊勢崎市に住んでいるので、キャンプや登山、ハイキング、スノーボードなどを楽しんでいます。あとは、音楽も好きでフェスにも行くのですが、自分でも音楽イベントを開催するようになりました。地域の方たちに協力してもらって、年に2回くらい定期開催しています。伊勢崎には2年ほど前に移住してきましたが、今では伊勢崎に限らず群馬が大好きな地になりましたね。
今後の展望をお聞かせください。
開院したばかりなので、まずはこの地域に小児の在宅医療をしっかりと提供して、皆さまから必要とされるクリニックをめざすというのが大前提です。次のフェーズとして、日本のどの地域でも在宅医療がもっと身近で当たり前になる社会を望んでいます。行政との積極的な関わりも重要です。伊勢崎市自立支援協議会のこども支援部会の医療的ケア児のワーキンググループの委員も拝命しましたので、今後も密に連携をとっていきたいですね。 そして、小児科医の中にも在宅医療に関心を持ち、実践する人が増えることを願っています。 生まれつきの疾患というのは、複雑なものや珍しいもの、また小児特有の発育・発達という特性もあるので、小児科医の仲間が増えればいいなと思います。
最後に読者へメッセージをお願いします。

お子さんのケアを抱え込んでしまっているような、責任感の強いご家族が多いことが気になっています。もちろん、供給側が追いついていないという実情があると思うのですが、もう少し在宅医療や訪問看護、地域の福祉サービスなど、周りに頼っていいと思っています。そうすれば休息や就業といった自分の時間を確保できます。ですので、どんな些細なことでもいいので相談してほしいですね。当クリニックのホームページには、お問い合わせフォームを用意していますので気軽に活用してください。






