川畑 隆之 院長の独自取材記事
かわばた頭頸部クリニック
(宮崎市/宮崎駅)
最終更新日:2025/07/07

宮崎駅の北側、車で10分ほどの錦本町に新しくできたひなたメドレータウン。ここに2025年5月に開院した「のど・くびの専門 かわばた頭頸部クリニック」の川畑隆之院長は長年、大学病院や地域拠点病院で多くの患者と誠実に向き合ってきた。耳鼻咽喉科の医師としてキャリアをスタートさせ、頭頸部や甲状腺の疾患を中心に県内外で研鑽を積んできたという。同院では、地域の耳鼻咽喉科クリニックと連携しながら、頭頸部がんの早期発見に力を注ぐ。「いかに早く診断し、治療に結びつけるかが大事」という川畑院長に、開業の経緯や専門分野について尋ねた。
(取材日2025年6月16日)
診断の難しい頭頸部がん、早期発見で地域貢献をめざす
喉や首の専門クリニックは県内では珍しいですね。

口の中や喉にできる腫瘍や首のしこり、甲状腺の腫瘍など、脳より下で鎖骨より上の領域、いわゆる「頭頸部」の疾患を得意としています。もともとの専門は耳鼻咽喉科なんです。幼い頃から蓄膿症を患っていて、高校生くらいまで自宅の都城市から宮崎県立病院に通院していました。そんな経験をした私なら患者さんの立場に立って診療ができるかと思ったことが耳鼻咽喉科医を志したきっかけですね。宮崎医科大学医学部(現・宮崎大学医学部)を卒業後、同大学の耳鼻咽喉科教室に入局しました。久留米大学形成外科や宮崎県立日南病院耳鼻咽喉科での研修医期間を経て、鹿児島市立病院や宮崎県立延岡病院などに勤務しました。
九州各地で研鑽を積まれた後、頭頸部をご専門にされたきっかけは?
耳鼻咽喉科では、舌がんや咽頭がん、喉頭がん、甲状腺がんなども扱いますが、それらの治療は非常に難しく、研修医時代から何とかして患者さんを助けられないだろうかと考えた時に、やはり手術を学ぶのが一番良いだろうと考え、38歳の時に東京都のがん研究会有明病院の頭頸科に国内留学を志望しました。そこで3年半ほど、さまざまな症例を学び、手術の経験を積ませてもらいました。当時は、10時間~12時間かかる拡大手術を1週間に2回、行っていましたね。その時の頭頸科部長が「宮崎に帰るときに失礼のないように」と技術面や精神面を鍛え上げてくれました。特に「倒れるなら前のめり」という言葉が印象に残っています。一番大事なのは手術や治療に対する熱意で、そこに技術がついて来るということを身をもって学びました。その国内留学の経験がなければ、今の私はないと思います。
開業のきっかけを教えてください。

国内留学を終えて帰郷し、宮崎大学医学部助教を経て宮崎県立宮崎病院に勤めていたのですが、50歳を過ぎたこともあり、体力が求められる手術よりも、診断と予防に重点を置くほうが地域医療により貢献できるのではないかと考えるようになりました。宮崎県立宮崎病院では甲状腺の病気も診ていたので、そちらも併せてお役に立てるのではないかと思い、開業を決意しました。一般的な耳鼻咽喉科のクリニックでは、そもそも頭頸部がんの症例を扱う機会が少ないので、診断自体が難しいことも少なくありません。そういう分野を当院がカバーし、地域の耳鼻咽喉科クリニックの先生方と連携しながら、地域医療の質の向上に貢献できればと考えています。若い頃に九州各地の病院で勤務し、地域ごとの社会的背景や価値観、病気に対する認識の違いにもふれてきました。そうした経験も、今後の診療に生かせるかなと思っています。
精密な診断で大きな病気の「小さな芽」を見逃さない
頭頸部がんではどのような症状が現れるのでしょうか?

口内炎や鼻血、鼻詰まり、喉の痛み、声のかすれ、むせ込みなどがなかなか治まらない場合は、がんの可能性があります。でも、がんは診断が早ければ早いほど治療につなげやすくなる。ここが一番大事です。ですから当院では、先進の機器を導入し、エコー検査や内視鏡検査、細胞診、病理検査などを組み合わせて、精密な診断をめざしています。特に細胞診と病理検査に注力しており、1回で診断がつかない場合は再検査を行って診断をつけることを重視しています。CTやMRIなどの画像検査に関しては、近隣のクリニックと連携しているため迅速に対応できるのも強みですね。だいたい2週間くらいで検査を終えて、3週間目に総合病院に紹介し、1ヵ月以内に治療を開始するというのが目安です。症状があってもなくても、がんの小さな芽を拾い上げていくのが当院の役割だと考えています。「がんの診断なら負けない」という気持ちでやっていますね。
診断から治療まで迅速に対応してもらえるのは、患者さんにとっても心強いですね。
いかに早く診断して、適切な治療に結びつけるかですね。一方で、もう一つ大事なのは、受診を途切れさせないことです。精密な診断をつけるためには、数ヵ月根気良く受診を続けてください。定期的に受診を続けていれば、たとえがんだったとしても、適切なタイミングで治療を始めることができます。途中で受診をやめてしまうと、大きな病気を見逃してしまうリスクが高まります。過度に不安がらず、受診を続けることが大事です。
院内オペ室ではどのような症例に対応していますか。

局所麻酔でできるような小さい手術は当院で対応しています。例えば、口の中のできものや首のリンパ節を切除する手術などを行っています。また、甲状腺嚢胞などに対しては、局所注入療法も行っています。細胞を壊死させるためエタノールを注入する方法です。嚢胞を繰り返していて腫れが目立つという場合は、局所注入療法が有用です。手術をせずに治療できるケースもあるので、お気軽にご相談ください。
患者の思いをくみ取り、より満足できる治療をめざす
診療で心がけていることを教えてください。
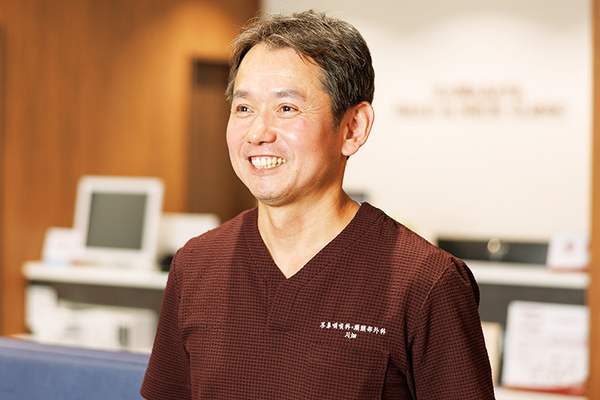
患者さんの気持ちに寄り添って、より満足してもらえる治療をすることです。私自身、蓄膿症を長年患っていた経験があるので、患者さんの「ここがわからない」「こうしてほしい」という気持ちを理解できると自負しています。これは得意分野です(笑)。頭頸部の構造は非常に複雑で、言葉だけで理解するのは難しいので、診療室のホワイトボードに図を描いて、わかりやすく説明するように心がけています。また、多様な現場で経験を積んできたことで、がん治療についての考え方も変わってきましたね。以前は「がんは戦う病気」という思いが強く、手術による完治をめざしていました。でも、場合によっては手術による身体的負担が大きいこともあります。そのため、患者さんの性格や社会的背景、死生観などを尊重し、がんと共存していくという選択肢もあるでしょう。その辺りのさじ加減が重要だと感じています。
スタッフの方との連携についてはいかがでしょう?
当院には、耳鼻咽喉科領域で豊富な経験を持つスタッフが在籍しています。勤務医時代に一緒に働いていたスタッフで、開業するにあたってついて来てくれました。がんが疑われるような初期症状の拾い上げもできますし、治療後のケアや生活指導などの説明も上手です。気心の知れた信頼できるスタッフがいることは、医師はもちろん、患者さんにとっても心強いことだと思います。
オフタイムのリフレッシュ方法を教えてください。

「よく飲んで、よく走る」ことでしょうか(笑)。若い頃からお酒が好きで、今でも高校時代の仲間と集まっては飲んでいますね。そして飲んだ分は走って消費します。今は週に1、2回ジョギングをしていて、1ヵ月で50~100キロほど走っています。青島のマラソン大会にも毎年参加しているんですよ。トレイルランも好きで、特に御池から高千穂峰を登るコースが気に入っています。
最後に読者へのメッセージをお願いします。
気になる症状があれば、放っておかずにぜひ受診してください。意外に思われるかもしれませんが、口の中の腫れや喉の痛み、リンパの腫れから、梅毒が見つかるケースもあります。鎖骨から上で、耳と脳以外のことであれば、どんなに些細なことでも構いません。喉の痛みや鼻水などの風邪症状はもちろん、アレルギー性鼻炎や甲状腺の病気、子どもの診療も行っています。また、気管切開を行っている方のカニューレの交換や気管内の観察などにも対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。






