医師・理学療法士と三人四脚で進める
運動器リハビリテーション
小竹向原おおほり整形外科
(練馬区/小竹向原駅)
最終更新日:2025/08/04


- 保険診療
誰にも理解してもらえない体の痛み。「かつて治療したけれど、いつまでも治らないから」「もう高齢だから仕方ない」と諦めてしまっている人もいるのではないだろうか。「小竹向原おおほり整形外科」ではそんな悩みを持つ人に対し、医師・理学療法士・患者の三人四脚で進める運動器リハビリテーションを提供。情報を共有しつつ、時にはブロック注射も併用して痛みの抑制を図りながら、患者本人が体を動かして改善をめざすリハビリに力を入れている。同院のリハビリの特徴や、在籍する理学療法士のこと、リハビリ中に意識したいことなどを、大堀靖夫院長に聞いた。
(取材日2025年7月15日)
目次
医師・理学療法士とともに取り組んでいく、運動器リハビリ。継続が成果の鍵
- Qこちらのクリニックのリハビリの特徴を教えてください。
-
A

▲さまざまなリハビリに対応できるように整えている
当院では腰痛や肩凝り、スポーツ外傷、術後の機能低下など、幅広い症状やけがに対応した運動器リハビリを提供しています。リハビリの対象となる具体例は、筋・筋膜性腰痛、腰部脊柱管狭窄症による腰痛、ストレートネックや頸椎症による首回りの痛み、五十肩と呼ばれる肩関節周囲炎、靱帯損傷や捻挫などのスポーツ障害、病院で脊椎や人工関節などの手術を受けた後の機能低下など。足底腱膜炎に対する体外衝撃波治療など機械を用いたり、ブロック注射などを併用したりすることもありますが、可能な限り理学療法士とともに体を動かしていただきながらリハビリを進め、最終的には患者さんご自身で管理できる状態をめざします。
- Q具体的にはどのようなリハビリを行うのですか?
-
A
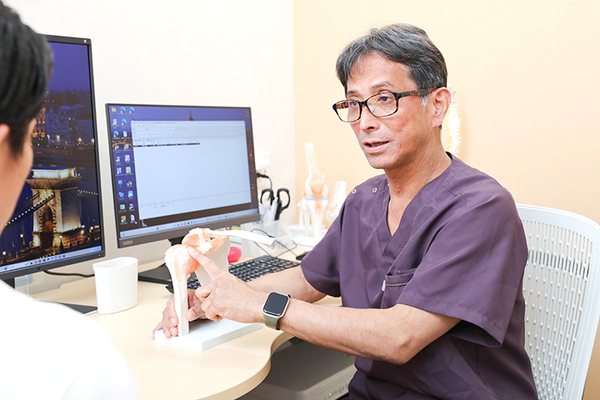
▲診察では、体の状態を丁寧にヒアリングしていく
医師が診察・検査を行い、共有情報をもとに理学療法士が自らの視点でリハビリ実施計画書を立案します。リハビリ機器だけに頼ることなく体を動かしながら、関節の可動域の改善、筋肉の緊張を取る、姿勢の矯正、筋力強化といったことを目標に取り組みます。歩行練習であればタブレットで動画を撮影し、実際にご自身の歩行シーンを確認してもらいながら説明するなど工夫も。1回あたり1単位20分または2単位40分で、理学療法士が個別対応しています。定期的に状態を確認し、必要に応じて理学療法士によるエコーでの確認やリハビリ内容の見直し、ブロック注射の併用なども検討しつつ、医師と理学療法士が連携して進めています。
- Q理学療法士さんについても教えてください。
-
A

▲患者の様子を確認しながら、理学療法士がリハビリを実施
当院の理学療法士は、常勤4人・非常勤3人の体制で、それぞれが異なる専門性を持ち、幅広いニーズに対応しています。例えば、スポーツ経験を生かした指導ができるスタッフや腰痛や首・肩の慢性症状に特化したスタッフも在籍し、患者さんの症状に合った適切なアプローチができるよう担当を割り振っているのが当院のリハビリの強みです。また筋肉や関節の動きをイメージしながらリハビリに取り組んでいただくために、理学療法士がエコーを実施して患者さんに確認してもらうことも。医師との情報共有やディスカッションも密に行い、症状の変化に応じて柔軟に対応しています。定期的な院内勉強会で、知識と技術の向上に努めているのも特徴です。
- Qこちらでのリハビリはどのような患者さんに適していますか?
-
A

▲痛みが出る部位やどの体制がつらいかなどを細かく確認
当院のリハビリは単に治療を「受ける」だけでなく、自分の体と向き合いながら意識を変え、積極的に改善をめざしたい方に特に適していると思います。これまで物理療法を中心とした受け身のリハビリで効果を感じられなかった方、長年の痛みやしびれに悩まされ「もう治らない」と思っている方、年齢や体力を理由に改善を諦めてしまっている方にも、新たな可能性を見出していただけるはずです。加齢に伴う筋力の低下や神経の衰え、関節の硬さといった複合的な問題に対しても無理なく取り組めるプログラムを提供するほか、手術を回避したい方、術後の機能回復をめざしたい方に対しても、適切な評価と運動指導を行っています。
- Qリハビリ中はどのようなことに気をつけるとよいでしょうか?
-
A

▲院長自慢の理学療法士たち
自分の体の状態をよく理解し、無理をしすぎないことが大切です。また、リハビリは継続が重要で、決められた運動や指導を根気よく続けることが大事なので、「宿題」としてご自宅でも取り組んでいただき、次回来院時に答え合わせをしつつ、変化を感じてもらいたいと考えています。さらに日常生活での姿勢や動作にもしっかり注意を払っていただきたいですね。加えて、体調の変化や疲労を感じた時は無理せず休息を取り、体を回復させる時間を持つことも重要です。また痛みや違和感が強くなる場合は担当の理学療法士に調整してもらうなど、コミュニケーションを取りながらご自身の疑問や不安を遠慮せずに伝えることも成果につながります。






