元家 亮太 院長の独自取材記事
もといえ脳神経クリニック
(豊中市/庄内駅)
最終更新日:2025/07/16

阪急宝塚本線・庄内駅の西口前、ビルの1階に「もといえ脳神経クリニック」がある。2025年5月開業の新しいクリニックで、バリアフリー設計の院内はゆとりのある広さが確保され、快適に受診できる。院長の元家亮太先生は、大阪、京都の病院で脳神経外科医として経験を積み、地域で疾患の予防に力を入れたいと同院を開業した。院内にMRIをはじめ先進的な検査機器を備え、スムーズな対応が求められる脳疾患などに対して、迅速な診断を行えるのが強みだ。「地域のクリニック・病院との連携にも力を入れ、 患者をサポートしたい」と語る元家院長に、会社員経験もあるというユニークな経歴や同院の診療ポリシー、地域医療にかける思いなどを語ってもらった。
(取材日2025年4月18日)
患者により近いところで疾患に備える
医師になった経緯を聞かせてください。
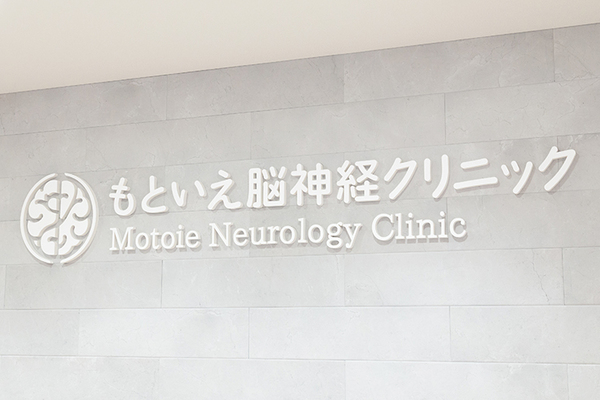
私の場合、ストレートに医師になったのではなく、医学部に途中編入して医師をめざしました。最初は大阪府立大学(現・大阪公立大学)で自然環境について学んでいました。卒業研究は脳外科の先生の下で学び、パーキンソン病などの神経疾患について知る機会を得ました。その後、京都大学の大学院に進学し、医師との共同研究を通じて、医療へどんどん興味が深まり医師になることを意識するようになりました。とはいえ、すぐに医学部に進めたわけではなく、ベンチャーキャピタルに入社して、働きながら学費を貯めた後に愛媛大学の医学部に編入しました。
開業までの診療経験を教えてください。
私は京都や大阪の病院で脳神経外科医としての経験を積みました。初期研修先の馬場記念病院の脳神経外科には"何でも診る"先生がいて、「脳外科医である前に医師であれ」という専門分野に限定しない姿勢を教わりました。「専門外だから」と断らず、まず診断して適切な診療科へつなぐという考えは、現在の私の医療理念の基盤です。実は初期研修前は精神科医を希望していました。しかし馬場記念病院の先生方との出会いが転機となり、脳神経外科医の道を選びました。
当初から独立開業は意識していたのですか?

開業については、医学部在学中から漠然と視野には入れていたものの、当時はまだ強く意識していたわけではありません。転機となったのは、学生時代に家族が脳の病気を患ったことでした。その経験を通じて、「脳は一度ダメージを受けると、完全な回復が難しい」という現実を実感し、病気になる前に備える“予防”の大切さを強く意識するようになりました。その後、脳神経外科医として診療を重ねる中で、脳のどの部位に損傷があるかによって症状がどう現れるか、という関係性を読み解く力が自然と養われていきました。患者さんの症状や訴えから、脳のどこに問題があるのかをおおよそ推測できるようになり、こうした力が早期発見につながると感じています。脳神経外科医として培ったこの“見立ての力”を地域での医療に生かし、病気の予防や早期発見に貢献できれば──。そんな思いから、地域に根差したクリニックの開業を決意しました。
庄内で開業されたのは何か理由があるのですか?
親しみやすい街だと感じたからです。さまざまな場所を検討しましたが、この地域は幅広い年齢層が暮らし、昔ながらの大阪の雰囲気が今も残る街だと思います。健康意識や自己管理の観点では必ずしも先進的とは言えない面もありますが、そういった方々だからこそ、地域のクリニックとして健康増進に貢献できると考えました。クリニックの設計では患者さんの移動経路を重視しています。入り口からMRI室まで直線的に進める配置で、診療の進行に伴って奥へと移動する流れになっています。緊急時の搬送に備えて廊下を広く設計し、中待合に患者さんがいても、ストレッチャーや車いすがスムーズに通れるようにしました。
何げない動作から患者の状態を見極める
診療の際の心がけを教えてください。

できるだけ自然な状態の患者さんを観察するように心がけています。まひやしびれ、歩行困難など緊張状態でははっきりと現れにくいこともあるため、なるべく患者さんが自然体になれるように話し方や話題を工夫しています。日常では立ち上がる際に手を使う方でも、診察室では意識して頑張ってしまうのか、すっと立ち上がることも珍しくありません。私は診療室に入る前から診察は始まっていると考えており、患者さんが椅子から立ち上がり診療室まで歩いて来る様子を見るように心がけています。こうした何気ない患者さんの動作から病気の可能性を察知し、MRI検査で脳の疾患が発見されるというケースも少なくありません。
どのような症状に対応していますか?
頭痛、めまい、物忘れ、手足のしびれ、体に力が入らない、視野が欠けているという方、あとは耳鳴りや味覚や嗅覚の異常といった訴えにも対応しています。頭痛の場合、若い方も多いのですが放置はお勧めしません。MRI検査で病気が見つかることもあります。当院では検査へのアクセスのしやすさを重視しています。検査を受けて脳に異常がないと確認できれば、患者さんの不安軽減にもつながると考えています。
専門性の高い検査が重要なのですね。
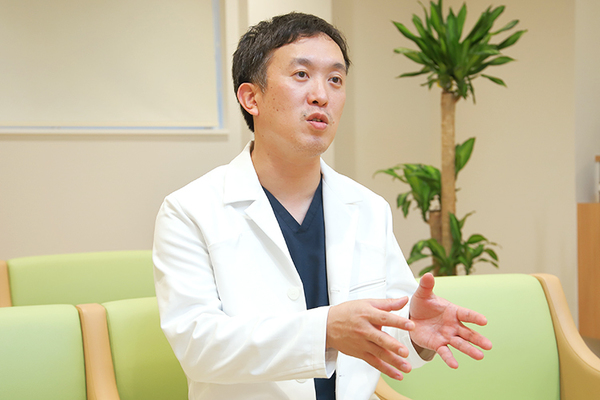
確かにおっしゃるとおりで、症状発現から時間が経過しないと画像に現れない脳梗塞もあります。「様子を見ましょう」という判断だけでは、生命に関わったり後遺症が残ったりするリスクがあるため、たとえMRI検査で異常が見つからなくても、症状に変化があればすぐに受診するか救急車を要請するなど、注意点を必ず患者さんに説明しています。高齢化が進む中、介護が必要な高齢者を減らし、自立した生活を送れる方を増やすことが社会的にも重要だと考えています。
開業の理由でもある疾患への備えについて聞かせてください。
現在のところ、これをすれば脳疾患を予防できるといったエビデンスは残念ながらありません。認知症についても、確実な予防法は確立されていません。しかし、多くの患者さんと接し、さまざまな診療科の先生方とお話をさせていただき、好ましい心がけなどは患者さんにお伝えできます。また、すでに治療を開始している患者さんの場合、お薬をきちんと飲んでいただくことが必要なので、飲み合わせなども考えて、他に飲んでおられる薬がないか、きちんと服用しているかなどを確認します。生活習慣についても確認し、特に喫煙者には禁煙を推奨しています。最近は健康診断で頸動脈エコー検査を実施する機関も増えているため、異常を指摘された方には早めの受診をお勧めしています。
地域全体を一つの病院と考える
地域の医療機関との連携を大切にしていますね。

患者さんの症状や疾患に適した診療科に、積極的に紹介するのが当院の基本姿勢です。どの診療科を受診すべきか迷って来院される方も多く、診察・検査で脳に問題がないことを確認した上で、適切な診療科や医療機関をご案内しています。例えば高血圧以外は特に問題がないといった場合は、内科の先生に紹介します。医療は常に進化し、新薬や新治療法が次々と登場していますが、私自身があらゆる診療科の最新情報を把握できているわけではありません。「餅は餅屋」の考えで、専門家による治療が患者さんにとって最善だと考えています。庄内地域にはさまざまな専門クリニックがあり、私はこの地域全体を一つの総合病院のように捉えています。大規模病院への受診に抵抗がある方でも、地域のクリニックなら比較的気軽に足を運びやすいのではないでしょうか。
先生のリフレッシュ法や健康法を教えてください。
今の私にとって、子どもと遊ぶことが一番のリフレッシュ法であり健康法ですね。
クリニックの目標を聞かせてください。
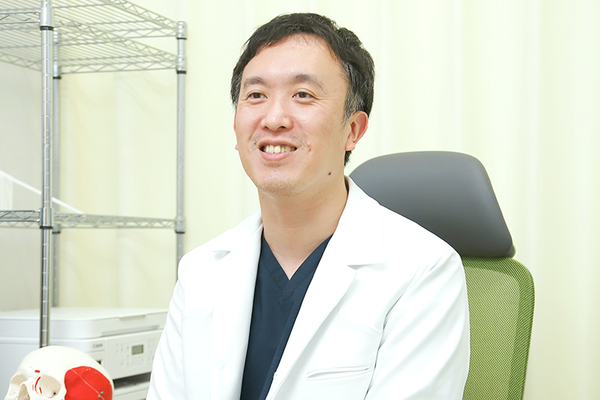
「どこで診てもらえばいいかわからない」という患者さんにも気軽に来ていただけるクリニックをめざしています。駅前という便利な立地で、ウェブ予約と通常の順番受診の両方に対応し、受診のハードルを下げる工夫をしています。一方、スタッフの視点からは「家族に受診を勧められるクリニック」が私たちの目標です。内情をよく知った上で大切な人に紹介できるクリニックであり続けたいと考えています。私自身、一般的なルートで医師になったわけではありません。会社員の経験もあるため診療費に対する感覚も近いものがあるのではないかなあと考えています。地域にお住まいの皆さんと共感しながら対話できると思いますので、気になること、心配なことがあるときは、気軽に受診していただければと思います。
自由診療費用の目安
自由診療とは脳ドック/2万5000円~






