難治性の皮膚疾患にも良好な予後が期待
生物学的製剤の治療
つだ皮膚科クリニック
(四日市市/保々駅)
最終更新日:2025/07/08


- 保険診療
乾癬やアトピー性皮膚炎など、慢性的な皮膚疾患に悩む人は多い。これらの疾患は完治が難しく、長期的なコントロールが求められる。そうした中で注目されているのが、生物学的製剤という新しいタイプの薬である。免疫の働きの調整を図ることで、症状の改善を目的とする。皮膚の炎症の背景には、免疫細胞が出す情報伝達物質であり、炎症や免疫反応を調整するサイトカインと呼ばれる物質の過剰な働きが関与している。生物学的製剤はサイトカインの働きを抑えるのに役立つため、難治性の皮膚疾患にも良好な予後が期待でき、その有用性が評価されている。この生物学的製剤に精通し、豊富な治療経験を持つのが「つだ皮膚科クリニック」の津田憲志郎院長。日本専門医機構認定皮膚科専門医の資格も有する津田院長に、生物学的製剤の治療について話を聞いた。
(取材日2025年6月4日)
目次
検診・治療前の素朴な疑問を聞きました!
- Q生物学的製剤で治療できる疾患を教えてください。
-
A
私が医師になった20年ほど前、乾癬やアトピー性皮膚炎などの皮膚疾患は、強いかゆみや炎症が続き、なかなか良くならない患者さんが多くいました。しかし、生物学的製剤の登場によって状況が大きく変わりました。この薬は、乾癬、アトピー性皮膚炎、じんましんのほか、結節性痒疹(けっせつせいようしん)や壊疽性膿皮症(えそせいのうひしょう)、化膿性汗腺炎(かのうせいかんせんえん)、掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)といった、これまで対処が難しかった病気にも処方されています。激しいかゆみや膿を伴う症状も、目立たない程度までの改善が期待でき、治らないと諦めていた方にも、新たな選択肢となる治療です。
- Q生物学的製剤のメリットについて教えてください。
-
A
最大のメリットは、従来の治療と比べてかなり良好な予後が見込める点です。これまで治療が難しかった乾癬やアトピー性皮膚炎などの皮膚疾患も、日常生活に支障が出ないレベルまで症状の改善が期待できるようになりました。例えば、毎日2回、時間をかけて塗り薬を続けても治せなかった乾癬やアトピー性皮膚炎に対して、新たな選択肢として生物学的製剤が用いられています。毎日の苦痛やストレス、塗り薬に取られていた時間の軽減につながり、生活の質(QOL)が大きく向上することも期待できます。これが患者さんにとって大きなメリットだと感じています。
- Q注射は患者自身が打つのでしょうか?
-
A
生物学的製剤は、ご自宅で患者さん自身に注射してもらいます。通常の治療では月1回、重症例では2週に1回、あるいは週に1回の通院が必要になることもありますが、自宅で注射できれば3ヵ月に1回程度の通院で済みます。仕事や家事で忙しい方にとって、通院の手間を減らせますし、例えば仕事から帰って夜に打つことも可能です。さらに、生物学的製剤は、同居するご家族が代わりに注射することも認められており、高齢の方や子どもさん、体の不自由な方も安心して治療が続けられます。患者さんのライフスタイルに合わせて、無理なく取り入れやすい点もメリットといえます。
検診・治療START!ステップで紹介します
- 1問診と診断を受ける
-

生物学的製剤の治療を始める際は、病気の診断が正確かどうかを慎重に確認。薬によって患者・医療機関双方が一定の基準を満たさなければ使用できないものもあるからだ。例えばアトピー性皮膚炎の場合、かゆみが続いている期間、きちんと薬を使った治療をしているかなど細かい診断基準がある。治療は長期間にわたるので、定期的に通院できない人には向いていない。薬は保険診療だが高額なため経済的負担も考慮しておく必要がある。
- 2検査や採血の実施
-

生物学的製剤は免疫の働きを調整するための薬のため、少なからず体の抵抗力が下がり、がんや感染症、肺炎のリスクが高まる可能性がある。そのため、治療を始める前に胸部エックス線やCTによる検査で体の状態を確認し、血液検査でB型・C型肝炎、HIV、梅毒、リンパ腫ウイルスなどの有無を調べる。特に結核は見落としてはならない。また、治療を始めた後も、これらの疾患が生じていないか定期的に検査で確認する必要がある。
- 3自己注射の指導を受ける
-

自宅での自己注射を始める前に、1回目と2回目の注射はクリニックで行う。まず注射の保管方法や使用期限などについて説明を受ける。その後、具体的な打ち方の指導に進む。へその周りは避ける、毎回違う側に打つなど、細かなルールがある。1回目は医師が説明しながら注射し、2回目は復習も兼ねて患者自身が医師の前で注射する。3回目以降は自宅での自己注射となり、薬を処方してもらい治療を続けていく流れとなる。
- 4自宅で自己注射
-

製剤は冷蔵庫で保管する。凍結すると使用できなくなるので扉側など凍りにくい場所が推奨される。注射は肌に押し当てると薬が注入される仕組みだが、途中で離すと薬が漏れてしまうため、終了するまで押し当てたままにする。落下などでの破損や不衛生にすると使えなくなり、再処方は全額自己負担に。取り扱いには十分注意しよう。使用後の注射器は医療廃棄物となるため、一般ごみとして捨てずに保管し、次回の通院時に持参する。
- 5定期的に通院
-
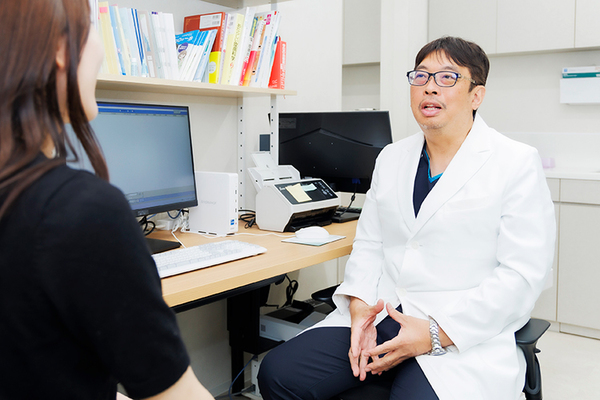
定期的に医師が体調の変化やきちんと注射ができているかを確認。必要に応じてエックス線検査などで悪性腫瘍や感染症の有無を調べる。また、注射後の症状の状態もチェック。長期使用で薬に対する抗体ができ、治療がスムーズに進まないことがあるためだ。症状が安定していれば、一時的に休薬して様子を見ることも可能で、再び悪化した際に再開するというケースもある。大きな問題がなければそのまま薬が処方される。







