園木 一男 院長の独自取材記事
その木内科クリニック
(福岡市博多区/吉塚駅)
最終更新日:2025/07/29
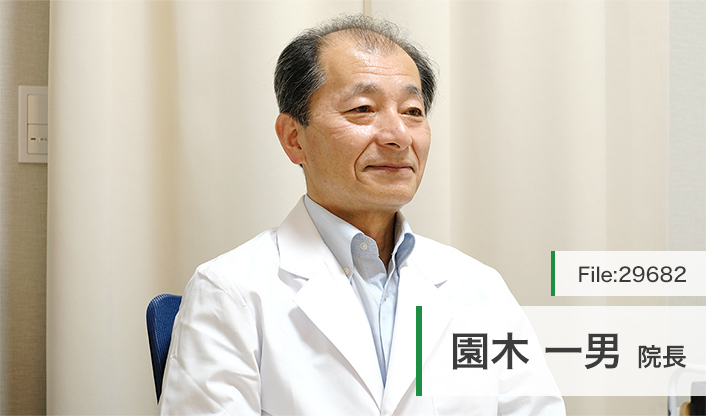
吉塚駅から徒歩4分、吉塚二丁目バス停留所から徒歩2分の住宅街にある「その木内科クリニック」。院長の園木一男(そのき・かずお)先生は、九州歯科大学で25年間、糖尿病をはじめとした生活習慣病や甲状腺疾患などの診察や研究に従事してきた。定年を迎え大学教授を退職した後、これまでの経験と知識を地域に還元するため、2025年1月、開業に踏み切ったという。同院では、一般内科を中心に、糖尿病、甲状腺、内分泌、代謝内科など幅広い疾患に対応。穏やかで親しみやすい園木院長に、これまでの経歴や診療で大切にしていること、今後の展望などについて尋ねた。
(取材日2025年6月19日)
「社会の役に立ちたい」と29歳で医学部へ
先生が医師を志したきっかけを教えてください。

私は九州大学出身ですが、実は最初に入ったのは工学部で、電子工学を学んでいました。大学院を修了後、通信システムの会社に入社。移動体通信事業部に所属し、船舶電話や自動車電話の技術開発に携わっていたんです。その技術は後に携帯電話につながるものですから、当時の先端技術にふれていたといえます。しかし、次第に「学ぶ内容が普遍的でない」と感じるようになりました。もっと自分の知識や技術がダイレクトに社会で役立ち、感謝される仕事がしたいと思い、29歳で医学部に再入学しました。純粋に、工学の知識よりも医学の知識に魅力を感じたのもありますし、10歳上のいとこが整形外科医で、その影響も少なからずあったのかもしれません。
糖尿病内科を専門とされた経緯もお聞かせください。
社会に直接貢献できる仕事がしたいと思っていたので、医学部での学びや実習は非常にやりがいを感じました。さまざまな診療科の中で内科を選んだ理由は、現役の同級生とは10歳以上年齢が離れていたこともあり、徒弟性が強い外科ではなく内科系のほうが自分に合っていると考えたからです。卒業後、内科の中で幅広い診療ができる第二内科を選びました。第二内科は脳循環研究室、高血圧・血管研究室、腎臓研究室、消化器研究室、肝臓研究室、糖尿病研究室、甲状腺研究室、そして疫学研究で知られている久山町研究室の8つの研究室の集合体です。臨床研修終了前に、当時の第二内科教授に「どこの研究室に入りたいか?」と聞かれ、研究室希望を3つ挙げた中で、私に合っているだろうと配属されたのが糖尿病研究室でした。もしかしたら他の希望者との兼ね合いもあったのかもしれませんが(笑)、結果的に25年続けているので、自分に合っていたのだと思います。
教授職を定年退職した後、開業されたと伺いました。

医師になって3年目、学位を取得するために九州大学医学部健康科学センターや九州大学医学部附属病院(現・九州大学病院)第二内科などで研究生をしていたのですが、研究を続けるために九州歯科大学内科学講座で助手をすることになりました。そこで無事に学位を取得し、九州歯科大学を去る時期が近づいた頃、九州歯科大学の教授から「ここに残らないか」と誘われたのです。九州大学の糖尿病研究室には大変ご迷惑をおかけしましたが、助教として残り、その後新設された口腔保健学科に移り、定年までトータルで25年勤務しました。退職後は、再就職や非常勤勤務医の選択肢も考えましたが、これまで学んできた知識や経験を生かして自分の裁量で患者さんに貢献したいという思いが強くなり、開業の道を選びました。
その不調、「甲状腺」に原因があることも
クリニックのこだわりなどはありますか?

コンパクトで利用しやすい施設になるようこだわりました。来院された患者さんにとって、わかりやすく、無駄なく、必要な検査や診療をスムーズに行えることを大切にしています。院内動線もシンプルにして、患者さんが不必要に移動したり長時間待たされたりすることなく、スムーズに診療を受けられるよう環境を整えました。ちょっと受診しただけで、あちこち移動したり待たされたりで半日以上を費やしてぐったり……といった状況にならないよう、基本的な治療はしっかり押さえながらも、無駄を省き、ややこしくない対応を心がけています。スタンダードな治療を真摯に行い、それ以上の精密検査や専門治療が必要な場合は、適切な近隣の医療機関に紹介する仕組みにして、気軽に受診できるクリニックをめざしています。
主な診療内容を教えてください。
一般内科では、発熱や腹痛など体の不調全般に対応。糖尿病診療では、主に血糖コントロールと合併症の予防をめざしています。また、歯科大学での経験から、糖尿病と歯周病の関連についてもお伝えしています。歯周病が進行すると噛むことが難しくなり、やわらかい物や飲み物で空腹を満たすことが増えますが、これらは血糖値を上げやすく悪循環を引き起こします。そのため、糖尿病の患者さんには、網膜症や腎機能のチェックに加えて歯科でのケアも定期的に受けることを勧めています。あとは甲状腺の外来ですね。糖尿病と甲状腺疾患は、両者ともホルモンの分泌異常による疾患ですが、糖尿病は合併症の予防のために治療するのに対し、甲状腺疾患は現在の症状を取るために治療するという違いがあります。こういった両疾患の特徴を理解してもらいながら、診療を進めています。
甲状腺の外来は、どんなときにかかったら良いのでしょうか?

甲状腺疾患の症状はあまり知られていないため、甲状腺の外来を直接受診する人は少なく、他の診療科からの紹介や健康診断で甲状腺が腫れていることで受診される患者さんが多いです。しかし、倦怠感や動悸、むくみ、体重減少など、一見関係なさそうな症状が、実は甲状腺の異常が原因ということがよくあります。さらに、物忘れや意欲低下も甲状腺疾患の症状の一つです。これらの症状のある人は「年齢のせい」や「疲れているだけ」と自己判断せず、一度甲状腺の外来に相談していただければと思います。「何年も原因がわからなかったが、ようやく甲状腺が原因だと判明した」ということもありますので、医師の方々も、これらの症状に対して診察を行う際、甲状腺疾患を疑って当院をご紹介いただけるとありがたいです。
地域にとって信頼できるかかりつけ医でありたい
診療において心がけていることを教えてください。

患者さんに対して丁寧でわかりやすい説明をすることです。診察や診断、お薬の成分や使用する目的などをしっかりと伝えるようにしています。特に糖尿病治療では、インスリンや薬の他、食事・運動を指導し、患者さんご自身に実践していただくことが大前提なので、その重要性を理解してもらうことが大切です。時にはうまく伝わらないこともありますし、伝わったと思っていても実際には伝わっていないことも。私も丁寧な説明を心がけますが、患者さんも、わからないことや疑問に思ったことは気軽に質問してもらえるとありがたいですね。糖尿病は一生付き合っていく疾患ですから、できるだけストレスなく治療を続けていけるよう、信頼関係を築きながら最適な選択をしていくことをめざしています。
クリニックの今後の展望を教えてください。
今は開業して間もないこともあり、まだ余裕がありますが、今後は地域の皆さんにもっと認知され、多くの患者さんに来ていただきたいと考えています。医師やスタッフを増員し、将来的には在宅医療にも対応できるようにしたいですね。在宅医療は私自身もまだ勉強中ですが、実際に訪問診療をしている先生から学び、看取りまでできるような体制を整え、「住み慣れた自宅で最期を迎える」という選択肢をご提供したいです。もう一つ、自由診療にはなりますが、肥満症治療にも力を入れていきたいと考えています。現在、日本で提供されている肥満症治療薬は役に立つのですが、副作用もありますので、医師の指導のもとで治療を進めていけたらと思っています。
最後に、地域の方へメッセージをお願いします。
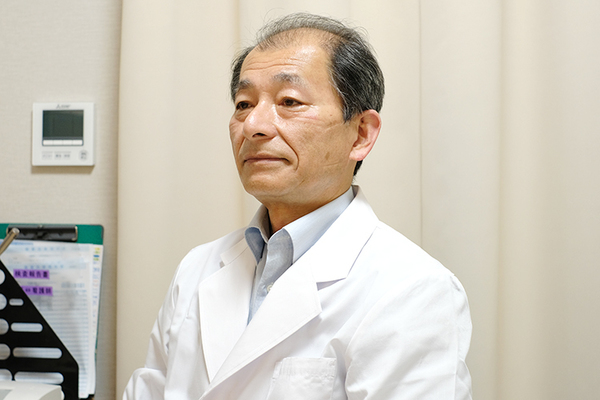
このたび吉塚駅近くに内科クリニックをオープンいたしました、園木と申します。これまで九州歯科大学で診療や学生教育、研究に従事してきました。当院では、糖尿病や甲状腺疾患をはじめとする生活習慣病や内分泌の病気に力を入れて診療しています。また、歯科との連携にも積極的に取り組み、患者さんに総合的な医療を提供していきたいと考えています。患者さんには自分の病気についてしっかり理解し、納得した上で治療を受けていただくことが大切だと考えていますので、わかりやすい説明を心がけ、常に患者さんの立場に立った医療を提供します。風邪や頭痛、腹痛、倦怠感など、少しでもお体の不調がある方はお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いします。
自由診療費用の目安
自由診療とは肥満治療・セマグルチド0.25mg1本/5000円






