安倍 次郎 院長の独自取材記事
あんべハート・クリニック
(ふじみ野市/ふじみ野駅)
最終更新日:2025/10/08

ふじみ野駅から循環バスで訪れやすい住宅街にある「あんべハート・クリニック」。安倍次郎(あんべ・じろう)院長は防衛医科大学卒業後、心臓外科の医師として大動脈瘤破裂の救命など数多くの手術を手がけ、2000年に同院を開業した。「医療機関が患者さんの障壁にならないように」という信念のもと、自分が診るべき患者と他の専門機関に紹介すべき患者を見極め、地域と基幹病院をつなぐ架け橋としての役割も果たしている。また、独自開発の電子カルテにより効率的な診療を実現し、心の悩みから来る動悸・不整脈などの症状にも丁寧に対応。穏やかな人柄の安倍院長に、診療への思いについて話を聞いた。
(取材日2025年9月16日)
心臓外科での経験を循環器診療に生かす
先生が心臓外科医になったきっかけを教えてください。

初期研修医としてさまざまな診療科を経験する中で、心臓外科の指導医との出会いが、私の進路を決定づける大きな転機となりました。手術の技術はもちろん、患者さんへの真摯な姿勢に深く感銘を受けたのです。特に印象に残っているのは、大動脈瘤破裂で救急搬送された患者さんの症例です。その場で開腹し、破裂部を手で押さえながら手術室へ搬送。並行して体外循環の準備を進め、人工血管による置換術を行い、無事に手術を終えました。命に直結する心臓という臓器を扱う責任の重さを実感すると同時に、大きなやりがいを感じ、この道を志す決意が固まりました。大学病院では、ペースメーカー植込み術、下肢の血管外科手術、冠動脈バイパス術、弁置換術など、幅広い心臓外科手術に携わってきました。今後も技術を磨きながら、患者さん一人ひとりに向き合う医療を実践していきたいと考えています。
開業を決意されたきっかけは何だったのでしょうか?
いつかは自分のクリニックを持ちたいという願望はずっとありましたが、転機となったのは自分の視力の衰えを感じたことです。心臓外科手術では、ちょっとした手元の狂いが患者さんの命を左右します。患者さんの安全を最優先に考え、手術から身を引く決断をしました。開業にあたっては、埼玉県内だけでなく関東一円の地域を検討しました。最終的にこの場所を選んだのは、出身校の防衛医科大学がある所沢で長く過ごし、埼玉県が身近な地域だったからです。ここなら地域医療に貢献できると考えました。2000年に開業して以来、心臓外科の手術で学んだ循環器疾患の知識と経験を生かし、心臓外科術後の患者さんも含めて診療にあたっています。
現在はどのような患者さんが多く来院されていますか?

当院には高齢の方を中心に、40代から60代の現役世代の患者さんも多く来院されます。主な訴えとしては、胸痛や動悸、不整脈などの循環器系の症状が多く見られます。「胸や背中に違和感がある」といった漠然とした症状を訴える方も少なくありません。不整脈が出たことで初めて心臓を意識し、「なんとなく心もとない感じがする」と表現される方もいらっしゃいます。特に背中の痛みは注意が必要です。狭心症や心筋梗塞の可能性があるほか、大動脈瘤切迫破裂を起こしているケースもあります。解離性大動脈瘤や胸部大動脈瘤でも背中の痛みが現れることがあり、その場合は迅速な対応が求められます。整形外科を受診し、湿布やリハビリを受けても改善せず、最終的に循環器内科を受診されるケースもあります。こうした症状の背景には、命に関わる疾患が潜んでいる可能性があるため、慎重な診察と的確な判断が重要です。
増加する心不全の症状に向き合う専門診療
心不全の患者さんが増えていると聞きました。

そうですね。近年、高齢化により心不全が爆発的に増える、心不全パンデミックが起こっています。高齢による動脈硬化で弁が石灰化したり、心臓自体が経年劣化することで起こる心不全です。当院でも患者さんの2割ぐらいは心不全傾向があります。心不全は心機能不全とも言うべきもので、心臓というポンプの機能が低下して血液を回しにくくなっている状態です。「疲れやすく、顔や手足がむくむ」「軽い動作でも動悸や息切れを感じる」といった症状が特徴です。治療は、以前は強心剤や利尿剤しかありませんでしたが、今は使用する薬剤も変化しており、「ファンタスティック・フォー」とも呼ばれる心不全の四大治療薬を導入するケースもあります。それでもコントロールを図るのが難しい場合は、外来で点滴療法を行います。利尿剤の点滴で余分な水分を尿として出すことにより、改善を図ります。
クリニックではどのような検査が可能ですか?
循環器の基本的な検査として、まず心電図、胸部レントゲン、血液検査を行います。運動負荷心電図は主に狭心症の診断に使用し、ホルター心電図は24時間の長時間記録で不整脈の頻度や種類を調べます。患者さんが家で普通に生活している時の心臓の状態を確認することができる検査です。そして超音波エコーは特に重要です。25年前の開業時はアナログエコーでしたが、2010年頃からデジタルエコーの設備を導入し、画質が劇的に向上しました。大動脈瘤なども心電図ではわかりにくいですが、エコーなら診断が可能です。これらの検査を組み合わせることで、精密な診断ができます。心臓に不安がある時は、専門の医師を受診することが大切だと思います。
最近は、心の悩みから心臓の症状を訴える方も多いそうですね。
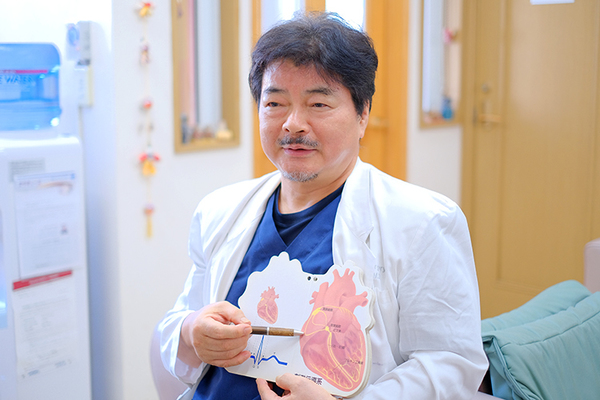
はい。うつ症状や不安神経症で循環器を受診される方は本当に多いんです。気分不快、不安感、パニック発作などがあると心臓はドキドキするので、心臓が悪いと思って来られます。このような場合は一通りの検査をして、「心臓そのものは悪くなくて、不安障害やうつの状態があって、それが原因で心臓がドキドキするんですよ」と説明します。心臓には問題ないとわかるだけでも、一安心して落ち着かれると思います。ただ、明らかに精神疾患が潜んでいるという場合は、速やかにメンタルクリニックや基幹病院の精神科へと紹介します。心臓の専門家として体の面から大丈夫だと確認することも、患者さんの安心につながる大切な役割だと考えています。
独自の電子カルテで地域医療をつなぐ
独自開発の電子カルテについて教えてください。

大学にいた頃から電子カルテの必要性を感じていました。病棟、医局、研究室を移動する際、論文執筆等のためにカルテを持ち運ぶのが大変だったんです。そこで電話回線でネットワークを組み、市販のソフトウエアを使って患者さんのデータベースを作りました。従来の電子カルテが紙をコンピューターに入れただけでエックス線、心電図、エコーなどが連動していないことに課題を感じ、すべてのデータを一画面で一元管理できるものを独学のプログラミングで開発しました。クリニック内で検査した結果がすぐに診察室で確認できるようになったので患者さんの待ち時間も軽減できます。患者さんを他院に紹介する際の書面紹介状も迅速に作成できるようになりましたし、データが一つの媒体に整理されていれば院内のスタッフも自由に扱えます。看護師、臨床検査技師、SEを含む約10人のスタッフ全員がこのシステムを使って情報を共有し、シームレスな体制を整えています。
先生の診療方針について聞かせてください。
開業当時から変わらないのは、「自分が診るべき患者と診るべきでない患者をちゃんと線引きする」ことです。例えば、軽い膀胱炎の場合は対応できますが、前立腺がんや膀胱がんの可能性があれば遅滞なく泌尿器科に紹介します。医療機関が患者さんが医療を受ける上での障壁にならないよう、地域の患者さんと専門の医療機関とのシームレスな架け橋になりたいと考えています。近隣の大学病院などとも連携し、適切な医療を受けられる体制を整えています。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。

患者さんにとって当院が入り口としての役割を担っていきたいと思っています。循環器の症状として、動悸、胸痛、息苦しさがメインですが、それ以外にも「なんとなく心臓の周りが不快な感じがする」という症状でもいらしてください。背中の痛みも心臓や大動脈の病気の可能性があります。当院では内科一般の風邪や感染症も診療していますが、循環器の専門性を生かして、心臓病・高血圧を中心とした診療を行っています。専門性を持ちながらも間口を広げて「まず行ってみよう」と思われるような医療機関でありたいと思っています。少しでも心配なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。






