四宮 祥平 院長の独自取材記事
しのみや内科クリニック
(吹田市/豊津駅)
最終更新日:2025/07/07

阪急千里線・豊津駅から市民プール方面へ徒歩約6分、落ち着いた住宅地の一角にある「しのみや内科クリニック」。院内は白と淡いベージュを基調にした優しい雰囲気の内装で、リラックスして過ごすことができる。院長の四宮祥平先生は、大学病院や地域の総合病院で呼吸器の疾患を中心に診療経験を積んだ後、同院を開業した。生活習慣病をはじめとした内科疾患に幅広く対応するとともに、充実した検査機器をそろえ、とりわけ呼吸器疾患に対する専門的な診療を提供できるのが強みだ。「気軽に受診してもらえる街のお医者さんでありたい」と語る四宮院長に、同院の診療姿勢や注力している診療、地域医療にかける思いなどについて聞いた。
(取材日2025年2月25日)
適した治療法を患者に提案して治療方針を決める
医師をめざしたのはご家族の影響ですか?

祖父と父が耳鼻科の医師で、小さい頃から父が診療する様子を間近で見ていました。家族から「医師になってほしい」と言われていたわけではありませんが、医師の仕事がどういったものかある程度はわかっていましたし、自分も父のようになりたいなという思いがあり、医学部に進みました。呼吸器疾患に専門的に取り組もうと考えたのは、もともと感染症に興味があったからです。臨床の現場で感染症に関われる診療科は、研修先の病院では呼吸器内科と血液膠原病内科のみであり、結果として耳鼻科とも若干重なる部分がある呼吸器内科を選びました。
開業までのご経歴を教えてください。
金沢医科大学医学部を卒業後、金沢医科大学病院では研修医として過ごした後に呼吸器内科に入局しました。地域の総合病院でも診療を担当する一方で、肺高血圧症という疾患の研究のためにドイツのユストゥス・リービッヒ・ギーセン大学への留学も経験しています。ドイツの医師免許を持っていないので患者さんの診療は行えず、動物のCT撮影をしたり、超音波検査を行ったりする日々でした。その後は金沢医科大学病院に戻り、患者さんの診療、医学部の学生や研修医の指導にあたってきました。開業したのは、医師になって16年ほどがたち、年齢的にも40歳になって、そろそろ適した時期だと考えたからです。
吹田で開業されたのは何か理由があるのですか?

現在も父が吹田市内で診療所をやっており、僕が12歳まで育った土地でもあったからです。もっとも、その後は石川県には24年間住んでいたこともあって、言葉のイントネーションが北陸に近いらしく、この近辺に住んでおられる福井や石川出身の患者さんから「北陸の出身ですか?」と聞かれることもあるんですよ。新型コロナウイルス感染症の流行を経験してからの開業だったので、発熱している方専用の出入り口を設けて、一般の患者さんとの動線を区別しました。ただし、インフルエンザの患者さんが急増した時期には、患者さんに院外で待っていただいたこともあり、発熱している方専用の待合室も作ればよかったと痛感しました。院内は車いすやベビーカーでも受診しやすいようバリアフリー設計を採用しており、トイレも広いスペースを確保しています。
どのような患者さんが来られますか?
現在は、20~60代の患者さんが中心です。咳を訴えて受診される方が多いですね。予想外だったのは、お子さんの受診が結構あるということ。小児科を受診しつつ当院にも来られるというケースも少なくありません。スタッフの中には、以前の勤務先で小児科を担当していた人もいて、お子さんの診療の際にはとても心強い存在です。患者さんと接する際には、どちらかというと昔気質の医師である父を見て育ったこともあり、優しく接するように心がけています。治療方針についても医師が一方的に決めるのではなく、症状をしっかり説明して「この治療法が良いと思います」と患者さんに提案した上で決めるスタイルです。最近は自らお薬の種類を指定して処方を希望される方もおられますが、必要ないと判断した場合にはしっかりと説明した上でお断りします。
困った時や診てほしい時に診療を提供する
あえて予約制ではなく順番制にされたと聞きました。

予約制と順番制のどちらにもメリット・デメリットがあるため、ずいぶんと悩みましたが、今すぐ診てほしい、今日なら受診できるという際に、診療を提供できる「街のお医者さん」でありたいという思いで、順番制を採用しました。健康診断やあらかじめ準備の必要がないワクチン接種なども、予約なしで受けつけています。休み明けの午前中は小児科が混み合って予約が取れないからと順番制の当院を受診したり、体調の良い日に当日受診でワクチン接種を受けたり、ということも可能です。
注力されている診療について教えてください。
呼吸器内科の症状を訴える患者さんが多く、呼吸器疾患は当院の強みを発揮できる領域だと思います。かかりつけの医療機関で診てもらっているけれど、咳が長引くと受診される方も増えていますね。長く咳が続く患者さんに対して、他の診療科でも喘息の治療は提供可能です。しかし、呼吸器内科ではその患者さんが喘息であるという診断に基づいて治療方針を決定するのが特徴です。このため、提供した治療で期待した結果が得られない場合は、次の手を考えることができます。
診断のための検査機器も充実していますね。
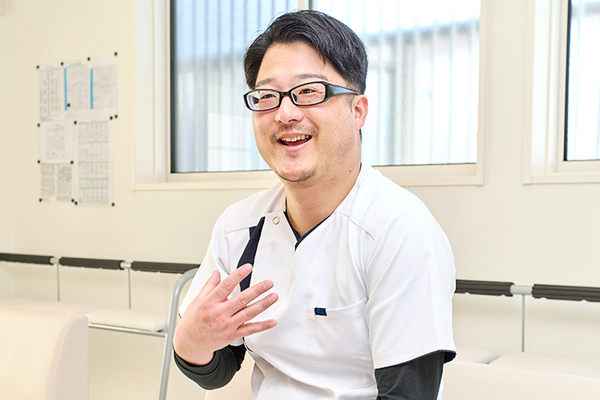
肺活量を調べる肺機能検査は慢性閉塞性肺疾患(COPD)の診断基準となるため、喫煙者で長く咳が続く場合は必須の検査です。呼気一酸化窒素濃度(FeNO)測定も呼吸器内科では一般的な検査で、アレルギーによる気管の炎症の程度も確認でき、喘息の診断に役立ちます。とはいえ喘息には、一酸化窒素濃度が低いタイプもあり、さまざまな要因を踏まえた上で判断することが大切です。また、エックス線検査装置にAIを搭載しており、肺がんなど異常が疑われる部分を細かく抽出できるのがメリットです。
喘息の治療についても教えてください。
成人の患者さんの場合は、ステロイドの吸入治療により症状の改善を図るものが基本です。自己判断でお薬をやめてしまう方がおられるのですが、症状が悪化したり、喘息発作を起こしたりするリスクがあるので控えていただきたいですね。一方、お子さんの場合はステロイドの副作用のリスクも考えられるので、気管支を広げて呼吸を楽にしたりするためのお薬や炎症の緩和を図るお薬を使います。
患者のことを理解して適した治療を提供する
内科疾患の検査機器も充実していますね。

大学病院時代から内科疾患の診療も担当してきた経験があり、生活習慣病などの診療にもしっかり取り組んでいきたいと考えています。コレステロール値などをその場で測定できる血液検査の装置や、糖尿病の患者さんの1ヵ月間の血糖値の変動を確認できるヘモグロビンA1cの測定機器も備えており、素早く検査結果を確認できるのがメリットです。外部の検査機関に依頼すると、結果を確認できるのが次回の診療時になってしまい治療開始が遅れてしまうケースもありますが、こうした機器を活用すれば素早い対応が可能です。
幅広い症状に対応していただけるのですね。
風邪症状はもちろん花粉症の治療などにも対応しています。また、睡眠時無呼吸症候群の患者さんに多いため、ご自宅に持ち帰って簡易的な検査ができるキットをご用意しています。ひとまずこのキットを用いて自宅で、検査していただき、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いと判断した場合は、脳波を測定しながら行う精密な検査を受けていただけるよう近隣の病院をご紹介します。
病院ともしっかり連携しておられますね。

必要と判断した場合は、症状や患者さんのご都合、さらに以前の受診歴があり診療情報が残っているかどうかといったことなども考え合わせながら、より専門的な診療を受けていただける医療機関にご紹介します。「なぜ診てくれないの?」と思われる場合もあると思いますが、早めに専門的な診療を受けたほうが良いと判断した上での対応なので、ご理解いただければありがたいと思います。
クリニックの目標を教えてください。
予約制を採用していないこともあり、つらい時にはすぐに受診してもらい、診療を提供できる医師、クリニックでありたいと考えています。僕が考える「街のお医者さん」は、キャラクターも含めて患者さんを理解し、その方に合った診療を提供できる医師です。必要がある場合は他の医療機関へとつなぐ一方で、複数の医療機関の受診が負担になる場合、症状が落ち着いていれば当院での継続診療にも対応します。気になることや心配な症状がある、咳が1週間以上続くよう場合は、早めにご相談ください。






