松澤 美愛 院長の独自取材記事
神谷町カリスメンタルクリニック
(港区/神谷町駅)
最終更新日:2025/07/09

神谷町駅から徒歩3分という利便性の良い場所にある「神谷町カリスメンタルクリニック」。うつ状態、うつ病、不眠症、神経症、不安障害、パニック障害、強迫性障害、総合失調症などの精神疾患に幅広く対応している。優しく穏やかな口調が印象的な松澤美愛院長は、大学病院、精神科専門病院、国立病院、クリニック、企業などで、精神科医として幅広い臨床経験を積み、2024年4月に同クリニックを開院。「必要な人に必要なことを、必要なところに必要なものを」をモットーとし、薬の副作用を心配する人には薬以外の対処法のアドバイスや、漢方薬などを用いた治療を提供している。「こころのかかりつけ医として、都会で孤独を感じている方々をサポートしたい」と語る松澤院長に、開院までの経緯、治療の方針、患者に対する思いなどについて話を聞いた。
(取材日2025年6月3日)
孤独感を抱えている人々の「こころのかかりつけ医」に
都会のオアシスのようなリラックスできる待合室ですね。

ありがとうございます。最初に来院される方の中には、緊張されている方もいらっしゃるので、木のイメージを取り入れて、心が落ち着く空間をつくりたいと思いました。また、色については人それぞれ好き嫌いがあると思うので、なるべく色を使わないようにしています。自然で優しい色合いにすることで、誰もがリラックスして、くつろげるような空間づくりを意識しました。
クリニックのロゴも優しい色合いですね。ロゴとクリニック名の由来を教えていただけますか?
ロゴのハートは心を表すモチーフなんですが、中に丸があるのは心に芯があることをイメージしています。あえてグラデーションをかけたのは、濃淡をつけることで「皆がそれぞれ自分らしくあっていいのではないか」という思いを込めました。クリニック名の「カリス」には「恵み」という意味があります。誰もが「恵み」を持っていますが、気持ちが落ち込んでいるときやつらいときには気づかないこともあります。一緒にお話をする中で、ご自身が持っている「恵み」に気づいて、一歩踏み出すきっかけにしてもらえるといいなという思いを込めています。
ご経歴と開院までの経緯を教えてください。
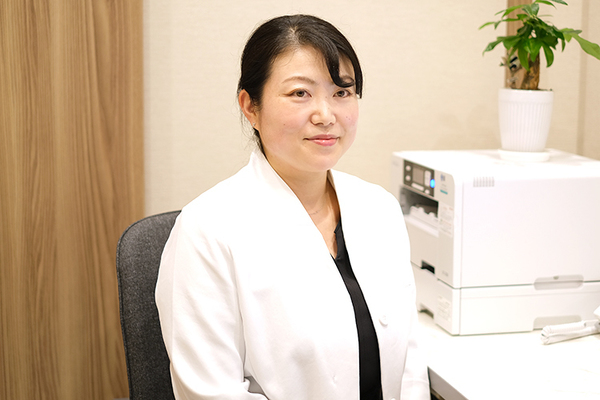
慶應義塾大学病院の精神・神経科に入局後、精神科専門病院、救急や総合病院でのリエゾン、国立病院、クリニック、企業など、幅広く臨床経験を積んできました。さまざまな患者さんと向き合う中で、都会で働く人々の多くが孤独感を抱えていることを痛感し、孤独感を抱えながら働く人々の「こころのかかりつけ医」になりたいという思いで、神谷町で開院することを決意しました。神谷町は、都心の利便性の良い場所でありながら、緑が多く、自然を感じられる場所なんです。来院される方にも自然を感じていただけるといいなと思っています。
精神科のかかりつけ医というのは珍しいですよね。
そうですね。「かかりつけ医」というと内科が一般的ですが、心の不調を感じたときに気軽に相談できる場所も必要なのではないかと感じていました。「胃が痛いから内科」「頭痛が続くから頭痛の外来」など、いろいろな診療科を受診し、飲む薬が増えるばかりで、症状が改善しないというケースも多いです。心と体はつながっていて、体の不調の根本的な要因がメンタルの不調である場合も多いので、根本的な要因を見抜くことが、「こころのかかりつけ医」の重要な役割だと思っています。当クリニックには、内科の先生もおりますし、慶應義塾大学病院や杏林大学医学部付属病院などとも連携しているので、専門的な治療が必要な場合は適切な医療につなげることも可能です。
必要なところに必要な医療を届けたい
治療の方針について教えてください。

「必要なところに必要な医療を届けたい」という思いから、薬一辺倒の治療ではなく、患者さんの心に寄り添い、患者さんが求めている医療を提供しています。例えば不眠でお悩みの場合には、患者さんにお聞きする中で症状の背景に病気がないかを診察しながら、日常生活の中で症状の改善につながることがある場合は、アドバイスをしています。入浴法を変えることが不眠の改善につながることもあるんですよ。それでも改善しない場合には薬を検討しますが、薬の副作用を心配される方も多いので、漢方の処方も行うなど、患者さんのニーズに合わせた治療に幅広く対応しています。
どのような患者さんが多いですか?
神谷町という場所柄、20~40代の働き盛りの方が多いですね。都心で仕事をしている方の中には、一人暮らしで孤独を抱えていて、気分の落ち込みや不眠などの症状を訴える方も多くいらっしゃいます。また、仕事の責任感からストレスを感じて、心の不調を来す方も多いですね。職場で昇進することは喜ばしい出来事ですが、昇進をきっかけに負担が増えて、メンタルの不調を感じるようになる方もいらっしゃいます。
仕事が要因で心の不調を来して休職された方へのアプローチを教えてください。

休職された場合は、復職に向けたアプローチが大切になります。本人は、復職後すぐにフルタイムで働けると思っていても、週3回の勤務で疲れ切ってしまうという方もいらっしゃいます。会社で復職までのプログラムが用意されている場合は、基本的にはその流れに沿うことになりますが、用意されていない場合は、段階的に無理なく復職できるようなスケジュールを提案しています。例えば、休職期間を利用し、週1回から通勤して徐々に慣らしていくなどです。ご自身が納得しながら進んでいくことが大切なので、復職に向けたプランを一緒に考えるようにしています。
他にどのような方がいらっしゃいますか?
更年期のお悩みの方もいらっしゃいます。40代以降の方は更年期と重なっていて、ホットフラッシュなどの更年期特有の症状だけではなく、漠然とした不安、イライラ、落ち込みなどの心の不調を訴えられる方も多いですね。ご家庭をお持ちの方は、子どもの独立、親の介護などが重なる時期でもあるので、一人ひとりの状況や抱えている問題などもしっかりと話を聞くようにしています。更年期特有の症状には漢方を用いることも多いです。また、夫婦関係、友人関係などの人間関係の悩みによって、メンタルの不調を感じている方もいらっしゃいますね。お話をお伺いする中で、本人が問題だと認識していることだけではなく、今まで生きてきた背景や考え方なども踏まえながら、一緒に考えることで、本人が気づかなかった解決策を見つけることを意識しています。
話をゆっくり聞いて、本当に求めている医療を提供
初回の診療の流れや通院のペースを教えてください。

最初に来院していただいたときは、まずお話をゆっくり聞かせていただいています。その後、今の状況や治療の必要性などについて詳しく説明して、今後の治療の目安についてお話させていただきます。通院が必要となった場合、通院のペースは患者さんに選んでいただいています。頻繁に通院した方が安心だという方は週1回、仕事が忙しくて通院する時間が取れないという方は月1回など、ご希望やご都合に合わせて通院していただけます。必ず定期的に通わなければならないということはありませんので、ご安心ください。
そもそも先生はなぜ精神科医をめざされたのでしょうか。
私は、医者の家系に生まれたわけでなく、右も左もわからない状態でこの世界に飛び込みました。どのような道に進むかどうか考えた際に、スペシャリストはたくさんいらっしゃる中で、一般家庭出身というのを生かし、幅広い悩みに応えるジェネラリストをめざしたいと思ったんです。精神科というのは、年齢や性別が関係なく、どなたも病気になり得る科目ですので、めざしたい医療の実現に近いと感じ、この道に進むことを決めました。
クリニックの受診を検討している方にメッセージをお願いします。

精神科で診療を受けるのが初めての方は、ハードルが高いと感じる方も多いかと思います。「どんなことを聞かれるのだろうか」「薬を処方されて副作用に悩まされるのではないか」など不安を抱えているかもしれません。そんな方には、かかりつけ医に行くような感覚で気軽に来ていただきたいなと思っています。気持ちの落ち込みや不安な気持ちなどを抱えていて、とりあえず話を聞いてほしいというだけでも構いません。これの症状は何科に行ったらいいのだろうと迷ったときでも、「こころのかかりつけ医」として、一人ひとりのお話をゆっくりお伺いして、本当に求めているものを理解した上で治療の提案をさせていただくので、安心して来ていただければと思います。






