小嶋 和絵 院長の独自取材記事
おじまクリニック
(西宮市/甲子園口駅)
最終更新日:2025/12/17
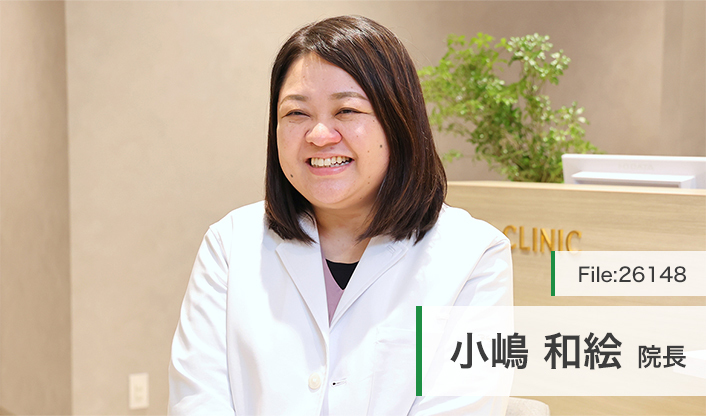
JR神戸線甲子園口駅から徒歩2分、すずらん通り沿いにある「おじまクリニック」は2023年8月に開院したばかりのクリニックだ。リラックスしながら診療を受けてほしいという想いから、クリニック内はウッド調のインテリアなどでやわらかな雰囲気を創出。ウェブ予約や発熱患者専用の待合室・診察室を設けるなど、受診しやすい環境づくりにも取り組んでいる。診療に関しては一般内科や消化器内科に加え、専門的な嚥下診療を提供することで、地域医療への貢献をめざしているという。「今後は往診にも対応して、通院が困難でクリニックを受診できないという方たちにも対応していきたい」と意気込む小嶋和絵院長に、これまでの経歴やクリニックの特徴、専門である嚥下障害治療などについて詳しく話を聞いた。
(取材日2023年10月3日)
「町のお医者さん」として垣根の低い診療を
まずは開業の経緯やめざすクリニック像を教えてください。
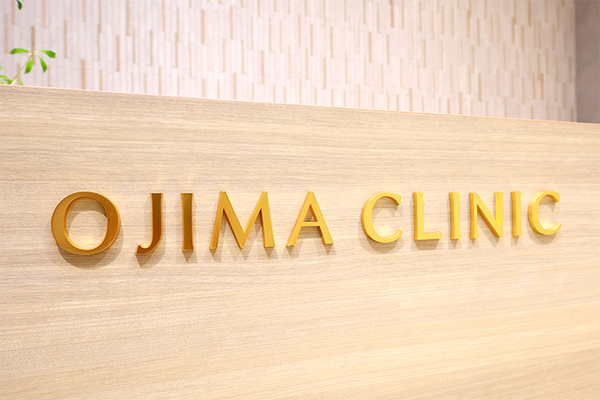
勤務医時代から漠然と開業を考えていて、地域医療に取り組んでいきたいという気持ちも強かったんです。芦屋市の中核病院に勤務していたこともあり、芦屋や西宮に住む方を診ることが多かったので、このエリアで開業することにしました。めざすのは「町のお医者さん」。病気になって受診するだけではなく、悩みやお困り事を気軽に相談できる場所になればと考えています。患者さんにはリラックスして過ごしていただきたいので、内装は優しい雰囲気にこだわりました。また受診しやすいようにウェブ予約を導入しています。ただし嚥下障害は診療に時間や緊急性を要するケースがあるため、電話でのご予約としています。あとは発熱の外来受診予約も電話をお願いしています。感染症対策で一般の外来とは別に発熱患者さん専用の待合室、診察室を設置しました。機器の面では嚥下障害をしっかりと診療できるよう、嚥下内視鏡検査と嚥下造影検査の機器を充実させています。
これまでのご経験についてもお聞かせいただけますか?
大学を卒業してからは、中核病院である市立芦屋病院や住友病院に勤務し内科医としての経験を積み、内視鏡による治療や嚥下障害の治療に専門的に携わりました。学生時代は内科や外科、産婦人科、糖尿病内科など、どれを専門に選ぶか悩んでいたのですが、結果的に消化器内科の道を選びました。血液検査などのデータを見ながら患者さんの健康を管理していくというよりも、内視鏡などを使って実際に悪い部分を見て診断を行いたいと思いました。内科は患者さんが最初に受診する窓口でもありますので、治療に最初から携わることができる診療科として魅力を感じました。
今はどのような患者さんがいらっしゃっていますか?

私自身が消化器を専門としていたこともあって、腹痛や下痢、嘔吐といった腹部症状でいらっしゃる方が多い印象です。もちろん発熱など一般内科で受診される方もたくさんいらっしゃいますよ。また飲み込みが困難な嚥下障害の治療にも取り組んでいるので、食事中にむせる、食事が飲み込みにくいなどの相談もあります。世代的には一般内科は20代、30代の若い方にもご受診いただいていますが、嚥下障害に関してはご高齢の方が多く、70代、80代の患者さんが中心になっています。クリニックの近隣にお住まいの方だけではなく、以前勤務していた時の患者さんも来てくださっていますよ。消化器や嚥下障害が専門ではありますが、最近体が疲れやすい、食欲がないなどの小さな悩みでも気軽に相談いただければと思います。
「飲み込みにくい」を改善へ。嚥下障害の診療に注力
嚥下障害の治療に力を入れていると聞いています。

そうですね、特に力を入れています。嚥下障害とは、老化とともに筋力が衰えるなど「飲み込む機能」に問題が生じ、飲み込む動作がうまくできなくなることです。食道ではなく気管に食べ物が入ってしまう「誤嚥」をし、命に関わる「誤嚥性肺炎」を引き起こすリスクもあるため、早めに医師を頼っていただきたいですね。当院では、開業当初から「誤嚥性肺炎になる前に、外来で早期から嚥下リハビリを開始する」を目標に、嚥下関連筋の筋力改善に努めてきました。嚥下障害は自覚症状がないことも多いですが、例えば「食事中にむせて、人目が気になり外食を楽しめない」などのお悩みがあれば、嚥下障害の可能性があるのでご相談ください。患者さんの健康を守るのはもちろん、食事を楽しむためのサポートができたらうれしいです。
あまり耳なじみのない嚥下障害の治療ですが、取り組むようになったきっかけをお聞かせください。
消化器内科を専門としていた頃、直接栄養や水分を補給するために体外から胃の中に管を通す胃ろうの造設を担当していました。胃ろうの手術を行う前には嚥下機能の評価を行い、本当に胃ろうが必要かどうかを判断します。そこから嚥下という機能に興味を持ち始めました。むせる、飲み込みにくいといった同じ症状であっても、原因や状態によって治療方針は一人ひとり違います。患者さん本人だけではなく、全身状態が悪い場合はご家族と一緒に治療に取り組む必要があり、そういった画一的ではない治療に医師としてのやりがいを感じました。嚥下障害の治療に対応している医療機関も多くはありませんから、クリニックという身近な場所で相談できずに困っている方たちの力になれればと考えています。
嚥下障害はどのように治療していくのでしょうか?

嚥下障害は老化現象の一つ。喉などの筋力の低下が原因となるケースが多いのですが、まずはしっかりと状態を把握して診断することが大切です。当クリニックでは専門家である言語聴覚士と一緒に治療を進めていくのですが、まずは嚥下の状態を把握しながら全身の筋力を測定。それから嚥下内視鏡検査に加え、外来ではあまり実施されない嚥下造影検査を行います。嚥下造影検査では飲み込みの様子をエックス線透視下で確認するので、誤嚥の有無や残留物が残るかどうかなどが把握できます。また全身の栄養状態も調べ、栄養不良が起きていないかなども調べていきます。検査結果を踏まえ、嚥下に関わる器官のマッサージやトレーニング、食べ物を使った訓練などに取り組むリハビリテーションで嚥下の改善をめざします。リハビリテーションで回復が難しい場合は、外科手術を行うケースもあります。
飲み込みの違和感など軽微な症状でも受診を
患者さんと向き合う際に心がけていることはありますか?

病気や治療の説明を行う際、医師はどうしても医学用語で話しがちになってしまいますから、なるべく簡単で平易な表現で説明するように気をつけています。患者さんの中には話を聞いて理解していただいたように見えていても、実は伝わっていなかったということがあるのも事実です。そのため何度も繰り返し説明したり、ゆっくりと説明したりするなど工夫しています。嚥下障害の治療に関してはリハビリテーションが欠かせませんし、長いお付き合いにもなりますから、しっかりとコミュニケーションを図るように気をつけています。コミュニケーションのロスで通院をやめてしまわれたら、一番影響を受けるのは患者さんになりますからね。
元気なスタッフさんが多いので、クリニックも明るい印象ですね。
一般的な内科の外来だけではなく、嚥下障害をはじめ専門的な診療も行いますから、おのずと勉強熱心なスタッフが集まりました。勤務医時代から付き合いのあるスタッフも在籍しているので、働きやすい環境をつくってくれて感謝しています。受付や診療、電話での言葉遣いなど接遇も丁寧で、患者さんとのコミュニケーションも心配ありません。待合室で待っておられる患者さんや、処置前の患者さんなどには積極的に声かけを行うなど、安心して任せられるスタッフに恵まれています。
最後に今後の展望を含め、読者の皆さんにメッセージをお願いします。

嚥下障害では寝たきりなどで通院できず在宅で困っている方もたくさんいらっしゃるはずです。なので今後は往診での嚥下障害治療にも携わっていきたいと思っています。在宅で嚥下機能を評価し、治療だけではなくベッドサイドの環境整備、ご家族のサポートなどに協力していきたいです。おなかが痛い、熱があるなどの症状があればクリニックに行くきっかけになりますが、食事中にむせた程度ではなかなか受診する機会はないと思います。しかしご飯が食べにくい程度の症状であったとしても、放置しておくと誤嚥性肺炎などのリスクを高めますので、むせる、飲み込みに違和感があるなどの症状であっても、風邪や腹痛と同じようにクリニックを受診してください。






