眠れない咳が長引くのは呼吸器疾患の兆候
呼吸器内科で原因を精査
田町三田駅前内科・呼吸器内科・アレルギー科
(港区/田町駅)
最終更新日:2023/08/10


- 保険診療
忙しく過ごす中で「咳くらいなら」と受診を後回しにする人もいるだろう。だが、長引く咳の原因の一つである喘息は、実は働き盛りの世代の発症が多い疾患。「長引く咳の原因には、適切な管理を要する慢性の呼吸器疾患が多いです。問題がある咳かどうかを判断するのは簡単ではないので、気になる咳がある方や他科で治療の成果が得られていないと感じる方は呼吸器内科にご相談を」と話すのは「田町三田駅前内科 呼吸器内科・アレルギー科」の藤原赤人院長。患者に合った薬や吸入デバイスはどれかを見極め、オーダーメイドで治療を組み立てる呼吸器疾患の専門家だ。薬の意味や見通しまで丁寧に説明して治療継続をサポートする藤原院長に、長引く咳で受診するタイミングやその原因、放置するリスク、そして診療の流れまで詳しく聞いた。
(取材日2023年7月13日)
目次
検診・治療前の素朴な疑問を聞きました!
- Q長引く咳が心配なときの受診のタイミングは?
-
A
咳が3週間以上続くのであれば、というのが目安とされます。ですが眠れないほどの咳や季節性の咳がある、小児喘息が大人になってぶり返しているかもしれず心配、呼吸がヒューヒュー・ゼーゼー鳴るなどの自覚症状があれば、早めに受診してください。当院のような呼吸器内科なら胸部エックス線検査の専門的な読影や、呼吸器の状態を精査する肺機能検査や呼吸NO検査などにより、適切な診断につなげられます。
- Q長引く咳の代表的な原因を教えてください。
-
A
咳喘息やアトピー性咳嗽などのアレルギー性の呼吸器疾患、また逆流性食道炎による胃酸の刺激で咳が生じることが多いです。咳喘息と逆流性食道炎が併存するケースをはじめ、複数の原因疾患が重なり合うこともまれではありません。ほかにも、喫煙が喘息と逆流性食道炎を悪化させたり、喫煙から慢性閉塞性肺疾患(COPD)になったりして咳が現れているケースもあります。それに長引く咳をもたらす呼吸器疾患には、慢性のものが多く悪化したり落ち着いたりの波があるのも特徴。そのため当院では、患者さんの疾患や状態に合わせた適切な薬の選択・調整や、吸入デバイスの選択、吸入指導などを細かに行い、症状の改善・コントロールをめざします。
- Q長引く咳を放置するリスクはありますか?
-
A
例えば喘息が原因の場合は、放置して重症化すると発作が起き、入院される方もいますし、重症例では亡くなる方もいます。また喘息を悪化後に治療したのでは、使用する薬の量が増えてしまいます。副作用が出ないよう薬を組み合わせますが、早めに治療を始めて、少ない薬量で症状をコントロールしていくに越したことはありません。喘息に限らず、長引く咳の原因に気管支炎やCOPDがあるなら、自己中断せずに治療を継続して呼吸機能を守りましょう。時に、肺がんや心疾患などが原因で咳が出ていることがありますので、そういった意味でも放置は危険。当院で重篤疾患の兆候を見つけたら連携医療機関に紹介し、より専門的な検査・治療につなげます。
検診・治療START!ステップで紹介します
- 1問診表に記入
-

咳の持続期間や乾いた咳か痰が絡む咳か、痰の色や質感、悪化する時間帯、呼吸音の異常有無、発熱・喉の痛み・鼻水などの随伴症状の有無などの項目に回答。住宅環境についてやペットの有無、呼吸器やアレルギー性の疾患、がんの家族歴に加え、他院にも咳を相談しているなら、その時点で飲んでいる薬についても記入する。同院は、ウェブ問診表も導入している。
- 2問診表の確認を受け、診察へ
-
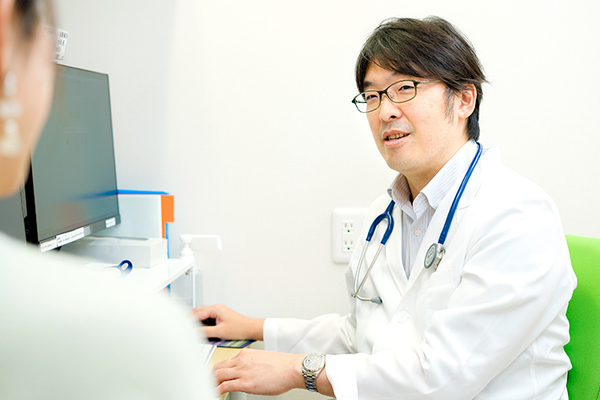
問診票をもとに医師が診察を開始。聴診では、深呼吸をしたり、ハアハアと息を吸ったり吐いたりしながら異音がないかを診てもらう。また喉の状態のほか、気道に異常をもたらす甲状腺疾患や、その兆候であるむくみがないかを含め、全身をくまなく確認。呼吸苦がある場合、酸素飽和度を測定されることも。同院では患者の話を詳しく聞いて、問診表ではつかみきれない不安や要望を把握してから、検査の必要性や組み合わせを判断する。
- 3咳の原因を探る検査を実施
-

胸部エックス線検査や呼吸機能検査、呼気NO検査が主に行われる。いずれも負担が少なく10分ほどで済み、結果は即日出る。肺がんや肺炎、喘息が疑われるなら追加で血液検査を実施。ものによるが追加検査の結果説明は1週間ほど後となる。同院の場合、CT検査が必要なら連携医療機関で受検。
- 4診断後、治療法の決定と説明が行われる
-

検査結果から診断を下し、治療法を選定。喘息の場合は、重症度に合わせてどの程度の強さの薬と吸入を組み合わせるかを選択するのが基本だ。服用頻度が異なる薬が複数選択肢にあるときは、患者と相談してより続けやすいものが選ばれる。同院では各薬の意味合いや、悪化時の対応、今後の見通しなどをこまやかに説明。必要であれば適宜吸入指導も行って、期待する結果が得られるようサポートしている。
- 5定期的な通院
-

喘息やCOPDなどの症状が不安定な時期は1週間に1回ほど、安定してきたら1月に1回ほどの頻度で通院。苦しくなった頻度や発作時に飲む薬の使用量が確認される。ピークフローメーターを持っている喘息患者は、測定数値を日記にして持参。苦しさと測定数値がリンクしていたかといった質問を受ける。同院では、症状が安定している再診患者のみを対象にオンライン診療を実施しており、処方箋をその人の希望する薬局に送っている。







