志賀 洋史 院長の独自取材記事
しが内科・循環器内科クリニック
(世田谷区/経堂駅)
最終更新日:2025/09/08

2023年の開業から丸2年たつ「しが内科・循環器内科クリニック」。同院を開業した志賀洋史院長は、赤痢菌を発見した志賀潔氏を曽祖父に持つ。人のために尽くした曽祖父に多大な影響を受け、臨床医の道を選んだという。そのため、同院はどこまでも「患者ファースト」の精神を貫き、診療室では患者が話しやすい雰囲気づくりを徹底。患者の不安に丁寧に耳を傾けるほか、志賀院長自ら、漢方医学などの知識を含め複数の治療法を提案し、患者のニーズに応える努力を惜しまない。内科と循環器内科の専門家として、生活習慣病の延長線上にある深刻な循環器疾患を未然に防ぐために、患者と真摯に向き合う。そんな志賀院長に、診療のモットーや患者への想いを語ってもらった。
(取材日2025年8月1日)
10年以上心臓疾患に携わった循環器の専門性を強みに
開業して2年がたちましたが、どのような患者さんが多く来院されていますか?

年齢層は10~90代まで幅広いです。東京農業大学が近いので若い世代が多いですが、住宅街の中にあるためファミリー層も目立ちます。多いお悩みは、一般的な内科領域の風邪症状から、専門領域である胸の痛みまでさまざまです。中高年以降になると、高血圧や脂質異常症といった生活習慣病が増えてきます。生活習慣病は、40代から健康診断で指摘されることが少なくありません。それをきっかけに来院されて、きちんと継続して症状をコントロールしていただければと思います。
これまでのご経歴を教えてください。
私は、日本内科学会総合内科専門医と日本循環器学会循環器専門医の資格を取得しています。福島県立医科大学医学部時代に循環器内科を選択いたしました。循環器内科の実習に参加した時、心不全や心筋梗塞の患者さんの治療を目の当たりにし、早い回復をめざせることに驚くと同時にやりがいを感じたからです。卒業後、北里大学北里研究所病院の循環器内科に研修医として入局。その後、日野市立病院循環器内科に10年以上勤務し、至誠会第二病院で1年ほど研鑽を積みました。今までの経験を地域医療に生かしたいと思い、2023年に開業する運びとなりました。
循環器内科について、どのような研鑽を重ねてきたのでしょうか?

日野市立病院循環器内科時代に、心不全、狭心症、心筋梗塞、不整脈、大動脈解離、肺動脈血栓塞栓症などの診療に数多く携わってまいりました。また、手や足の血管から細いカテーテルを挿入し、心臓の状態を調べる心臓カテーテル検査もたくさん経験し、循環器内科医として10年以上急性期医療に従事しています。中高年以降に増えてくる内科領域の生活習慣病、その延長線上に循環器疾患があります。私は内科と循環器の両方を専門としていることを強みとして、生活習慣病の治療、あるいは予防をしっかりとフォローしていくことが大事だと思っています。
患者のニーズに合わせて診療の幅を広げ、漢方治療も
得意な診療について教えてください。

高血圧に対するアプローチとして、血圧をコントロールするための治療を得意としています。高血圧の90%以上は、原因をはっきりとは特定できない「本態性高血圧」ですが、いくつかの要因との関連性は指摘されています。代表的なのは、遺伝や塩分過多、肥満、ストレス、喫煙、老化、極度の寒さですが、睡眠時無呼吸症候群の影響も見逃せません。診療では高血圧の原因を探りつつ、治療の選択肢をいくつか提示いたします。一般的には降圧剤が主流ですが、私は漢方医学も勉強しているので、西洋薬が飲めなかったり抵抗感があったりする方には漢方薬を取り入れることもあります。食事や運動の指導も行いながら、二人三脚で良好な血圧コントロールをめざします。
患者さんと接する時に、配慮していることはありますか?
治療の流れや見通しをきちんとお伝えすることです。例えば薬を処方するときも、「飲み薬で改善が見られなければ、吸入する方法もあります」などと他の選択肢を説明します。今日はこの薬で対応するけれど、吸入に切り替える方法もあることがわかれば、患者さんは治療に前向きになるでしょう。また、「それでも改善しなかったらエックス線検査をして、次の一手を考えましょう」などとお話しすると、患者さんも通院を継続しやすいと思います。そして、最後に必ず「何かほかに不安な点はありますか?」と伺うようにしています。その一言で「相談しようか迷っていたけれど、小さなことでも話してみようかな」と思っていただけたらうれしいです。
既存の薬物療法だけでなく、さまざまな治療の選択肢を提案されているのですね。

はい。そこは診療する上で大切にしていることです。例えば、胸部の違和感を訴える患者さんの検査を行い、検査データには心臓や血管に重篤な所見が認められなかった場合、「異常はありません」と言われても患者さんには不安が残るでしょう。そこで、「違和感を改善したい」という想いに寄り添い、東洋医学の観点から改善を期待できる漢方治療などをご提案することがあります。最近では、更年期障害の患者さんにプラセンタ注射のほか、更年期症状の冷えやほてり、発汗、不眠などに対し漢方治療を試すこともありますね。漢方薬の粉末タイプが苦手な方には錠剤で対応することも可能です。開業医だからこそ、患者さん個人の声を丁寧に拾い上げて、臨機応変にサポートしていきたいと考えています。
地域のかかりつけ医として多くの病院と連携体制を強化
幅広い治療の選択肢に加えて、診療する上で大切にしていることはありますか?

患者さんが話しやすい雰囲気をつくることです。勤務医時代から心がけていることですが、開業後は特に意識しています。とりわけ循環器内科であれば、症状の原因として生活習慣が関係する場合も多いので、患者さんのライフスタイルにまで立ち入ってお尋ねする必要があります。そのため、患者さんとの良好なコミュニケーションは欠かせません。多くの患者さんは受診する時に緊張されるので、いきなり病気の話から入るのではなく、「今日は天気が良いですね」といった世間話をすることも少なくないんですよ。スタッフにも特に指示しているわけではありませんが、自らの判断で患者さんと理想的なコミュニケーションを取ってくれています。明るくてアットホームなスタッフばかりなので、安心して話しかけてください。
複数の病院と連携する体制を整えているそうですね。
重大な病気の疑いがあれば、適切な病院へ速やかに紹介できるように心がけています。連携医療機関は、至誠会第二病院や関東中央病院、東京医療センター、東邦大学医療センター大橋病院、心臓血管研究所付属病院、ニューハート・ワタナベ国際病院です。当院は循環器内科を専門としているので、胸の痛みなどの症状を訴える患者さんが多く、命に関わる病気の可能性や緊急性のある症状を見逃さないことが重要です。そのために、不整脈や狭心症などを診断する心電計や超音波診断装置、胸の疾患の兆候を捉える血液検査装置、太い血管の詰まりを判断するABI検査装置(血圧脈波検査装置)などの設備を整えています。昨年からは動脈硬化の進行を評価する頸動脈エコー検査も開始しました。私は週に1回、至誠会第二病院の循環器内科で外来を担当しています。そのため、CT検査を至誠会第二病院で行い、その後は私の外来日に当院で結果を説明することも可能です。
最後に、読者へメッセージをお願いします。
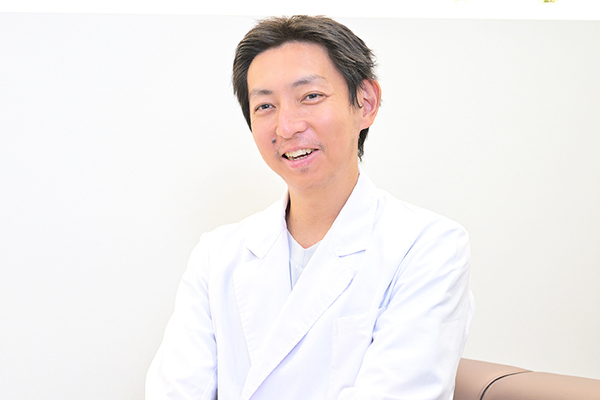
近年、「病気と診断がつかないけれど、症状が出て困っている」という方が増えているように感じます。そういう場合にこそ、当院をご利用ください。適切な検査を行い、症状に合わせた治療の選択肢をご用意いたします。大切にしているのは、患者さんに安心を届けること。そのために、漢方やプラセンタといった治療の選択肢を広げています。また、前職で発熱者専用の外来を担当した経験があり、新型コロナウイルス感染症の流行を経て、当院でも別個に隔離室を準備しております。個室にご案内できる環境が用意されているので、発熱患者さんが一般患者さんに対して気兼ねする必要はなく、一般患者さんも不安なく待合室を利用できるでしょう。今後も、経堂地域の皆さんにとって「何でも気軽に相談できるかかりつけ医」になれるよう、スタッフ一同で力を尽くします。






