楠 裕司 院長の独自取材記事
渋谷睡眠・呼吸メディカルクリニック
(渋谷区/渋谷駅)
最終更新日:2025/08/29

夜も眠らない街・渋谷で、睡眠医療に情熱を注ぐ医師がいる。「渋谷睡眠・呼吸メディカルクリニック」の楠裕司院長だ。15年以上睡眠時無呼吸症候群の診療に携わってきた楠院長は、「働く世代の患者さんが通いきれずに治療を諦めてしまう現状をなんとかしたかった」と2022年の開業を決意。平日夜間診療やオンライン診療で忙しい人でも継続できる体制を整え、治療による症状改善を実感してもらいたいと語る。睡眠時無呼吸症候群への思いと治療へのこだわり、そして患者に寄り添う診療について話を聞いた。
(取材日2025年7月9日)
働き世代のために専門性と利便性を両立
医師をめざした理由と呼吸器内科を選んだ理由を教えてください。

父が開業医をしていて、患者さんから感謝されている姿を見て育ちました。地元の方から声をかけられたり、みんなから知られていたりする父の姿に憧れて、自然と医学の道を志すようになりました。呼吸器内科を選んだのは、父の影響で患者さんと密に関わる外来診療に魅力を感じていたからです。学生時代に呼吸器内科の分野に最も興味を持ち、知識も深めていました。その後、大学病院での研修を経て、睡眠時無呼吸症候群、気管支喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)という専門分野を見つけました。特に睡眠時無呼吸症候群は、若い時から発症し、治療することで症状の改善が期待できる病気だと実感し、この分野に注力するようになりました。
開業の経緯とクリニックのコンセプトについて聞かせてください。
大学病院の外来診療していた時、診療時間が17時までという制約があり、働いている患者さんが通いきれずに治療を諦めてしまうというケースを多く見てきました。睡眠時無呼吸症候群の患者さんは20代から60代の働き世代が中心で、仕事との両立が大きな課題でした。そこで「専門性の高い診療を、もっと便利に手軽に受けられるクリニック」というコンセプトで開業をしようと決意しました。医局の仲間たちと独立してクリニックを立ち上げた経験や、副院長・院長として経営を学んだ経験も生かし、2022年11月に渋谷で開業。スタッフも含めクリニック全体の専門性を高めながら、患者さんの負担を最小限にする診療体制を整えています。
渋谷という立地を選んだ理由と診療の特徴を教えてください。
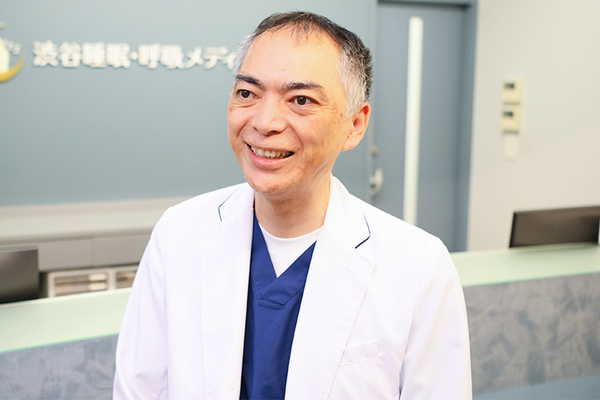
ターミナル駅から近い所なら、皆さん通いやすいと考えて渋谷を選びました。実際、仕事で都内に来ている方が多く、朝一番や仕事帰りの受診、土曜午前の受診が多いですね。診療の特徴としては、オンライン診療を積極的に取り入れ、仕事の合間でも受診できる体制を整えています。また、検査の解析もすべて院内で行うため、診断までの日数が格段に短くなりました。精密検査も9割以上の方が自宅で実施しており、入院費用もかからず患者さんの負担を軽減しています。完全予約制で院内の待ち時間も少なく、平日は19時まで診療しているので、忙しい方でも無理なく通院できます。利便性を上げることで、治療を諦めていた方々にも専門的な診療を届けたいと考えています。
放置するとリスクが高い睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群を放置するリスクと受診のタイミングは?

睡眠時無呼吸症候群を放置すると、十分な睡眠が取れていないことにより、日中の判断力や集中力は飲酒時と同じくらい低下します。交通事故の原因にもなりますし、仕事や趣味のパフォーマンスも落ちてしまいます。さらに深刻なのは、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を合併しやすくなることです。酸素低下により全身の炎症が活発になり、動脈硬化の進行や心臓への負担が増大し、心筋梗塞や脳梗塞の原因になります。認知症、うつ病、緑内障のリスクも上昇し、まさに万病のもとといえる病気です。受診のタイミングとしては、いびきを指摘される、日中の強い眠気、起床時の頭痛や口渇、夜間頻尿などの症状が2つ以上ある場合は要注意です。家族にいびきや無呼吸を指摘されたら、まずは現状評価をすることが大切ですので、お気軽にいらしてください。一人暮らしで心配な方は、いびきを測定するアプリなどで自分の状態をチェックしてみるのも良いでしょう。
睡眠時無呼吸症候群の検査や治療法について教えてください。
検査は簡易検査から始め、必要に応じて精密検査を行います。当院では精密検査も自宅で実施でき、入院の必要がありません。機械の使い方は院内で丁寧に説明し、困ったことがあればスタッフがすぐに対応します。治療は、軽症の場合はマウスピースを使用し、中等症以上の場合はCPAP(持続陽圧呼吸療法)が第一選択となります。CPAPは睡眠時に鼻にマスクを装着し、空気の圧をかけることで、呼吸が止まらないようにするための機械です。最初は抵抗を感じる方もいますが、自転車に乗れるようになるのと同じで、慣れてくると寝ぼけていても使えるようになります。当院では導入時にスタッフが40分から1時間かけて説明し、最初の不安な時期を手厚くサポートしています。
先生がめざす、睡眠時無呼吸症候群の治療のゴールはどこでしょうか?

睡眠時無呼吸症候群の治療でめざすのは、症状の改善により生活の質を向上させることです。無呼吸による集中力や判断力の低下を改善できれば、仕事への取り組み方にも変化が出てきます。また、日中の眠気からの解放ができれば積極的に物事に取り組むようになります。さらに将来の病気のリスクを減らすこともまた、大きなメリットです。20代、30代で治療を始めることで、その後の健康維持にも役立てられます。睡眠時無呼吸症候群の治療で症状の改善を図るだけでなく、患者さんが日常生活を快適に過ごせるようサポートし、より充実した毎日を送れるよう導いていきたいと考えています。
二人三脚でめざす質の高い睡眠と健康
診療で心がけていることとスタッフの役割について教えてください。

二人三脚で治療を進めることを大切にしています。初診では病気についての共通認識を持ってもらうことから始め、医師だけでなくスタッフとも話をしてもらい、不安や疑問を解消できるようにしています。治療を継続する上で重要なのは、患者さんが前向きに治療に取り組めるようサポートすることです。私たちは伴走者やサポーターのような存在として、患者さんに寄り添います。スタッフは全員が睡眠に関する専門知識を持ち、機器の説明から日常的な相談まで、院内ですべて対応できるよう体制を整えています。医師に言いにくいことでもスタッフになら相談できることもあるので、チーム全体で患者さんをサポートしています。
質の良い睡眠を取るためのアドバイスをお願いします。
寝室環境を整えることが重要です。遮光をしっかりして、温度は少し涼しめに設定することをお勧めします。最も大切なのは、寝る前のスマートフォンやパソコンを避けることです。ブルーライトは昼間の光と同じ働きをして、眠りを妨げます。動画やSNSは交感神経を活発にし、眠りを悪くする要因になります。スマートフォンの普及により先進国の睡眠の質が悪化したというデータもあるほどです。どうしても見たい情報があれば、朝に回すことをお勧めします。睡眠の質を上げることは、日中の活動だけでなく、長期的な健康維持にもつながります。
今後の展望と読者へのメッセージをお願いします。

日本には睡眠時無呼吸症候群の治療が必要な方が約940万人いるといわれていますが、実際に治療を受けている方は100万人に満たない状況です。この現状を変えていきたいと強く思っています。当院では専門性の高い診療を便利に受けられる体制を整えていますので、いびきを指摘されたり、日中の眠気に悩んでいる方は、まず現状評価をしてみてください。睡眠時無呼吸症候群は治療することで症状の改善が期待できる病気です。せっかく治療法があるのに、知らないまま、受けないまま過ごすのはもったいない。SNSなどでの情報発信も含め、睡眠に関する啓発活動にも力を入れています。一人でも多くの方が健やかな睡眠を取り戻すお手伝いができればと思っています。気になる症状があれば、ぜひ気軽にご相談ください。






