入江 泰正 院長、入江 未香保 副院長の独自取材記事
延岡こども歯科・おやこ歯科
(延岡市/南延岡駅)
最終更新日:2025/11/17

南延岡駅より徒歩で12分ほど。「延岡こども歯科・おやこ歯科」は、黄色い壁と三角屋根のかわいらしい外観だ。入り口の門には赤い鼻のオリジナルのマスコットが掲げてある。小児歯科を専門とする入江泰正院長と入江未香保副院長。2人とも広島大学歯学部出身で、小児歯科という縁でつながった夫婦だ。予防を普及するために、子どもと保護者に歯磨きの仕方を教えるのはもちろん、さまざまな展示物を利用して食習慣について丁寧に伝えている。日本小児歯科学会小児歯科専門医の資格を持つ泰正院長は「将来はケアが行き届いていない子たちにフォーカスを当てたい」と語り、地域の子どもたち全体をサポートしたいと思い描いている。同院の小児歯科への取り組み方や、子どもの歯の予防について、泰正院長と未香保副院長にじっくり話を聞いた。
(取材日2025年10月8日)
予防の意識を浸透させる
この地に開業した理由を教えてください。

【泰正院長】私の実家は横浜で、妻は長崎なので、どちらも宮崎出身ではないのですが、小児歯科専門医が少ない地域ということで注目しました。人口の多い都市部では小児歯科専門医が多く虫歯予防の情報も浸透し、子どもの虫歯は減っている状況ですが、逆に少ない地域では子どもの虫歯が多く見られます。そういった場所に小児歯科専門医である僕が行くことは意味があるのかなと思いました。
【未香保院長】小児歯科専門医が少ない地域をいくつかピックアップしていたのですが、ちょうどこの延岡に歯科医院の建物の空きがあると紹介され、ご縁があってこちらで開業しました。
どういった患者さんが来られていますか?
【泰正院長】7割ぐらいがお子さんで、残りの3割はそのお子さんの親御さんやご親戚の方が来院されます。主訴としては虫歯が多い印象ですね。最近は、他院で治療した歯が痛み出したと言って来院される方も増えています。保護者の中にはお子さんの乳歯の虫歯に関して、「治療しなくても良い」という認識の方が結構いらっしゃいます。小さい虫歯であれば、その選択肢もありますが、大きい虫歯だと、緊急に治療が必要なケースもあります。お話を聞くと、例えば「チョコレートは駄目だけどグミなら大丈夫かと思っていた」という方もいらっしゃって。グミのほうが歯にくっついている時間が長く、もっと虫歯になりやすいんですよね。まずは食生活を見直し正しい予防の知識をお伝えすることが大事だなと感じています。
こちらのクリニックの特徴を教えてください。

【泰正院長】今の歯科業界では、専門性が細かく分かれています。例えば、日本口腔外科学会口腔外科専門医や日本歯周病学会歯周病専門医など。小児歯科専門医は子どもに関するあらゆる疾患に対応することが求められますが、間口が広い分一つ一つの知識・技術が浅くなってしまう恐れがあります。成人担当の副院長と情報を共有しつつ、最新の書籍・動画を見たり、セミナーに参加したりして勉強を続けています。小児歯科の枠にとどまらず成人の専門的な治療を習得し、それを小児歯科の治療に実践することで、治療の予後を良くしたいと思っています。子ども相手なので安心安全を配慮してスピーディーに治療することは当然ですが、日々進化していく最新の治療を導入し治療の質を上げることを重視しています。
子どもと一人の人間として向き合う
歯科医師を志したきっかけは何だったのでしょう。
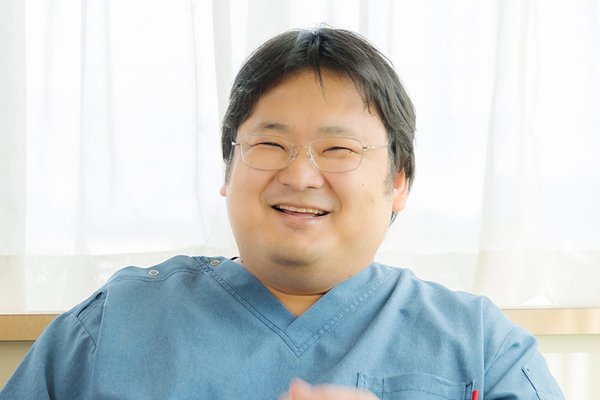
【泰正院長】小学生の頃、サッカーに熱中していて、周りにも認めてもらえてちょっとてんぐになっていたんですね。ところが6年生の時に全治1年という膝の大けがをしてしまい、心がぽきっと折れたんです。絶望していた時期に「人を笑顔にすることが自分の幸せ」という小児科医師が主人公の映画を見て、自分もこうなりたいと思うように。歯科医師になろうと決めてからも、子どもが好きなので小児歯科の道を選びました。子どもは予測不可能なのが面白いですね。ここで泣くかなと思っていたら、頑張って泣かなかったりして、成長していく姿もまた予想をはるかに超えていく。つくづく興味深い存在だと感じています。
【未香保院長】両親が歯科医師だったので、歯科医師以外の人生というのが想像できなかったんですね。入り口はなんとなくぼんやりとしたものでしたが、大学に入ってからの勉強はとにかく楽しくて、この道に進んで良かったと思いました。
お二人は広島大学歯学部を卒業されたのですね。
【未香保院長】学年で言うと、私が院長の1つ下になります。大学卒業後、初期研修で入ったのが院長が所属する医局でした。初期研修を終え、歯科医院で働き始めた時、男性の先生が苦手だという女の子を私が担当することになったんです。まだ経験が浅かった私は不安になり、小児歯科の先生に相談したいと思い、どの先生に相談しようか考えた時に院長が浮かびました。研修医時代に院長が子どもと接するのを見ていて、大人を振りかざさないところがいいなと思っていたので。子どものことを理解して子どもを一人の人間として見ていると感じました。
子どもを診察する際、心がけていることを教えてください。

【泰正院長】子どもの気持ちを尊重するようにしています。特に自我が芽生えてくる4歳を過ぎた子たちに、大人の都合だけで決めるのはどうなんだろうという思いがあります。緊急性が高い場合は少々無理を強いるのは仕方ないところもありますが、やはりお子さんがどうしたいのか、保護者はどうしたいのか、治療法や予後の可能性を提示した上で選択してもらうようにしています。例えば、虫歯がある子は、小さかったらお薬を塗って様子を見ることもありますが、4歳を過ぎたら、「虫歯を放置したらこうなるよ、それをやっつけるためにはこういう道具が必要なんだよ」と絵本を使ったトレーニングから始めて治療に進みます。それでも怖がりの子は、慣れるまで治療をしないでこまめに通ってもらうという選択肢を保護者に検討してもらいます。
小児歯科医療をすべての子どもに普及させる
ご自身の場合の虫歯予防についてお聞かせください。

【泰正院長】僕自身は虫歯を抱えた子ども時代を過ごしました。歯科医師になり勉強してから、虫歯はできにくくなりました。虫歯は歯磨きの善しあしでできるのではなく、日頃の食生活が大きく関わっているとわかり、食習慣を変えたことも改善につながったと思っています。
【未香保院長】私は子どもの頃から今まで虫歯になったことがないんです。お菓子を食べ始めたのが小学校に入ってからだったことが大きいのかもしれません。そのためか、甘すぎるものは食べられない味覚になりました。ジュースは甘すぎて飲めないんですが、そのことが不幸せというわけでもないんですね。味覚に合わず飲みたくないから飲まないというだけなんです。
子どもには、どういったことを注意すればいいのでしょうか。
【泰正院長】まずは、口腔内の細菌の問題があります。お口の中にはすごい数の細菌がいて、その細菌が陣地を取り合っているんですよ。1歳半から2歳半が虫歯菌の定着感染時期といわれているんですけど、その時期にジュースやお菓子など甘いものをほとんど取っていない子たちは、3歳以降にお菓子を食べても虫歯になりにくいんですね。あともう一つは味覚の問題があります。人間の味覚は3歳くらいまでに形成されるといわれているので、その間に甘いものを控えればその後も執着は減ると考えられています。
【未香保院長】口呼吸のお子さんは、風邪をひきやすいなど、全身状態にも影響があります。鼻で呼吸の場合、鼻の粘液が細菌やウイルス、ちりごみのフィルターになってくれます。口呼吸はウイルスなどを含む外気がいきなり喉に入るため、炎症を起こしやすくなるので、改善が必要です。
今後の展望を聞かせてください。

【泰正院長】今のところ、基本的に困った時に来院される患者さんがほとんどなので、大勢の人に正しい情報を伝えたくても機会が得られずもどかしい思いがあります。それならば保育園をつくって、そこに歯科医師が介入したら、少なくとも園児たちは虫歯にならずに済むのではと考えています。僕は子ども時代にけがをして、そのつらさを誰にも理解してもらえず一人で苦しかった経験があります。なので、将来的にはそういう子たちにフォーカスを当て、サポートする活動もしたいですね。今現在は、延岡地域で僕らが小児歯科医療において最後の砦になれるよう全力を尽くすことに集中しています。困ったことがあったら気軽に来ていただきたいですね。
自由診療費用の目安
自由診療とは◎虫歯治療
かぶせ物8万~11万円、詰め物4万4000~5万5000円(いずれも素材により金額が異なります)
◎ホワイトニング
ホームホワイトニング2万2000円、オフィスホワイトニング(1回)1万2000円
◎歯列矯正
小児矯正(ワイヤー等)29万~45万円、成人矯正(ワイヤー等)70万~90万円
◎マウスピース型装置を用いた矯正
部分矯正(マウスピース型装置)40万~45万円、フルマウス矯正(マウスピース型装置)70万~85万円、小児矯正(マウスピース型装置)50万円
◎部分矯正
部分矯正(ワイヤー等)16万5000~33万円
※歯科分野の記事に関しては、歯科技工士法に基づき記事の作成・情報提供をしております。
マウスピース型装置を用いた矯正については、効果・効能に関して個人差があるため、必ず歯科医師の十分な説明を受け同意のもと行うようにお願いいたします。






