茂呂 直紀 院長の独自取材記事
西東京あゆみクリニック
(西東京市/田無駅)
最終更新日:2025/07/07

西東京市、東久留米市、三鷹市、武蔵野市、小金井市、小平市、杉並区を訪問エリアとし、24時間365日体制で在宅訪問診療や緊急往診を行う「西東京あゆみクリニック」。茂呂直紀院長と多職種のスタッフが連携しながら、オーダーメイドの治療に取り組んでいる。茂呂院長は大学病院の脳神経内科で培ったその知識と経験を生かし、可能な限り患者の意思に寄り添った治療を行う。「主体は患者さんの生活であり、医療はその生活を支える選択肢の一つ」と語る茂呂院長に、これまでの経歴や診療モットー、今後の展望を聞いた。
(取材日2025年6月3日)
増える訪問診療のニーズに応え、患者の生活を支える
医師を志されたきっかけや、これまでのご経歴をお聞かせください。
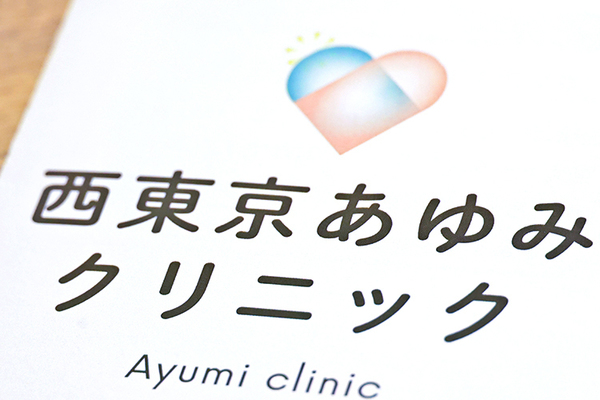
明確なターニングポイントがあったわけではなく、中学・高校と過ごした学校の影響が大きかったですね。全寮制の中高一貫校に通っていたのですが、もともと医学部や歯学部を受験する生徒が多い学校だったんです。そういった環境に身を置く中で、私も自然と医学部を志すようになりました。医学部を卒業後は大学病院の脳神経内科に勤務し、パーキンソン病や認知症といった神経変性疾患や、ギランバレー症候群などの末梢神経の自己免疫疾患の症例を主に診ていました。大学病院は医師の数も多く、さまざまな先生の方針や考え方にふれましたね。学んだ内容を一つ一つトレースして自分なりにまとめ、現在の訪問診療に生かしています。
大学病院の勤務から、訪問医療の世界へ入られた理由は何でしょうか?
いろいろな巡り合わせがあったのですが、やはり訪問医療自体のニーズが年々増えていることが大きかったですね。医師として地域の方々の役に立つために、今何ができるか?と考えた時、その答えが訪問医療でした。私が専門としている神経疾患は、麻痺や筋力低下、震えなどによって、体だけでなく日常生活にさまざまな影響を及ぼすケースが多いです。通院ではなく、こちらがご自宅に伺い、患者さんの日常生活をより身近で見て、理解したほうが、治療に深く介入できると考えました。あくまでも主体は患者さんの生活で、医療はその生活を支える一つのツールですから。当法人には、「医療は患者さんにとっては手段でしかなく、その先の幸せが重要」という共通理念があるのですが、まさにこの考えのとおりだと思います。
こちらのクリニックの診療体制について教えてください。
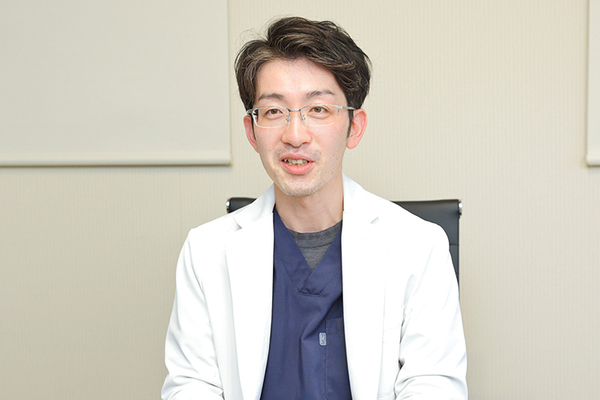
基本は医師と同行クラーク(医師事務作業補助者)の2人体制で訪問していますが、緊急時や土日は、系列グループの三鷹あゆみクリニックや府中あゆみクリニックの先生方とローテーションを組み、24時間365日対応しています。法人には眼科や皮膚科、精神科など他科の医師が在籍しているため、必要に応じて当クリニックの患者さんを診てもらうことも多く、助かっていますね。医師以外にも、内部や外部問わず看護師やケアマネジャー、理学療法士など他職種の方々と連携できる体制が整っている点は強みといえるでしょう。多職種連携チームでそれぞれの専門性を生かし、患者さん一人ひとりに合わせた生活をつくり上げられた時は医師としてやりがいを感じますね。生活支援としてのケアと医療のキュアの両面から患者さんの生活を支えていきたいと考えています。
「自分らしく生きたい」患者の希望に寄り添う診療方針
訪問診療では、主にどういった治療を行うのでしょうか。

患者さんによって必要な治療内容は異なります。パーキンソン病の方や認知症の方もいらっしゃれば、胃ろうや床ずれ(褥瘡)の処置を必要とする方、末期がんなどで緩和ケアを希望される方もいらっしゃいます。また、同じ症状だとしても、一人暮らしなのか、ご家族と同居されているのか、服薬や水分補給をサポートしてもらえるような介護力のある環境に身を置かれているのかなど、生活スタイルによっても必要な対応は変わってくるわけですね。リハビリテーションがどのように進んでいるか、デイサービスにはどのくらいの頻度で通っているかなど、患者さんやご家族の方とお話ししながら生活全体を把握し、柔軟な対応をするよう心がけています。
先生が診療を行う上で大切にしていることは何ですか?
やはり、患者さんの生活が主体ですので、治療によって患者さんの望む生活が妨げられることのないよう意識しています。例えば、患者さんの中には、デイサービスにあまり行きたくない方や、積極的な治療を望んでいない方もいらっしゃるんですね。そういった患者さんに「〇〇したほうが良いよ」とこちらが押しつけてしまうのは、おせっかいになってしまいます。訪問診療を利用される方は高齢の方が多く、自分らしく残りの人生を過ごしたいと考えている方も少なくありません。私としては、極力患者さんのしたいようにさせてあげたいと思っています。もちろん治療の中で守らなければいけない最低ラインはありますし、なんでも自由にさせて良いというわけではないですが、人生の大先輩としてずっと社会の第一線で戦ってきた方々ですから、敬意を持って、可能な限り意思を尊重したいと考えています。
患者さんとコミュニケーションを取る際に心がけていることはありますか?

先ほどの内容につながってくるのですが、患者さんが求める生活と、ご家族の意見が異なる場合も多く見られます。その際に、双方と十分にコミュニケーションを取り、皆さんが納得できる提案をするよう心がけていますね。介護の中心にご家族がいらっしゃる場合も多いですから、ご家族との関わりも大切です。ですが、あくまで主体は患者さんの生活ですので、患者さんの意見を代弁しつつ、ご家族の意見も聞きながら、程良いあんばいを探してうまく調整していくというのが理想ですね。説明の仕方や、話題の持っていき方で印象が変わる場合もありますので、なかなか難しいことも多く、私自身まだまだ勉強中です。
患者の気持ちに気づいてあげられる医師をめざして
忙しい日々だと思いますが、リフレッシュの方法はありますか?

月に1回ほど、社会人サークルでバドミントンをプレーしています。大学時代にバドミントンをやっていたのですが、医師になってからは離れていました。体を動かそうと思って最近再開して、すっかり楽しさに目覚めてしまいましたね。訪問診療は24時間365日体制で稼働しているため、常に電話がかかってくる可能性があります。オンとオフの切り替え方に悩んでいたのですが、バドミントンで体を動かしていると、うまくオフへの切り替えができていると感じますね。
今後の展望を教えてください。
まだ訪問医療の世界に入って日が浅いので、もっと勉強が必要だと感じています。ですので、まずは学びながら、しっかりと訪問診療の経験を重ねていきたいです。特に、大学病院で神経疾患の治療に携わっていましたので、そのノウハウを生かしてパーキンソン病やALS(筋萎縮性側索硬化症)といった神経難病の方を支えていけたらうれしいですね。西東京市は比較的訪問診療を行っているクリニックが潤沢にありますので、その中ですみ分けというか、ある程度注力分野を分けて治療の幅を広げたほうが、地域の方のメリットにつながるのではと考えています。対応できる範囲を増やして、西東京エリアの方々の生活をサポートしたいですね。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。

患者さんには、多少わがままでも構わないので、自由に楽しく、ストレスなく過ごしてくださいとお伝えしたいです。とはいえ、皆さん言えないこともあると思います。言葉にしなくても、患者さんの気持ちを読み取れるような、気づいてあげられるような医師でありたいですし、言いづらいことを言える関係性を築いていきたいですね。患者さんに大きな不利益がない限りは、好きなように過ごしていただきたいと思いますので、ぜひ遠慮なくお話しください。また、要介護状態や、ご家族の付き添いが難しいなど、外来通院が負担な方は、ぜひ訪問診療を選択肢として考えてくださいね。






