岡田 研吉 院長の独自取材記事
岡田医院
(町田市/玉川学園前駅)
最終更新日:2024/09/10
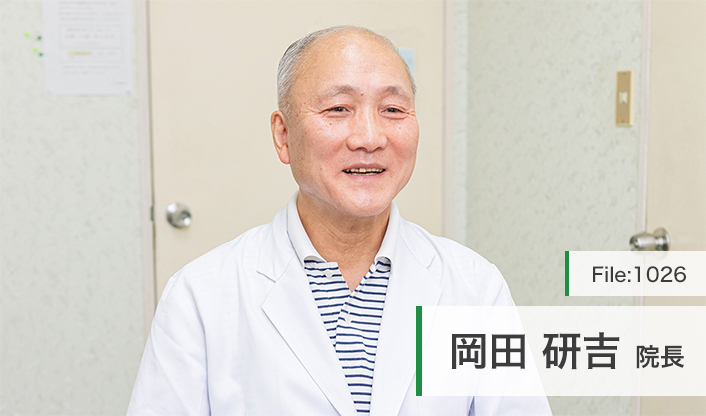
漢方を中心に、一人ひとりの患者に合った最適な治療を追求する「岡田医院」は、小田急線の玉川学園前駅にある。この場所の桜並木が好きで開業場所を決めたという岡田研吉先生は、ユーモアのにじむひょうひょうとした口調と、優しいまなざしが印象的なドクターだ。「品質が良く、信頼できる商品なら活用すべき」だとして、希望があれば健康食品の相談も受けつける。真摯な診療姿勢と効果にこだわった治療、悩める人をそっと包み込むようなアドバイスを求め、遠方から訪れる患者も多いという。「漢方に携わって40年以上。いっこうにマンネリ化しないし、興味も尽きません」と話す岡田院長に、治療方針や薬の飲み方、健康の秘訣など、さまざまな話を聞いた。
(取材日2024年7月11日)
産前産後の症状にも漢方で対応
遠方からも患者さんがいらっしゃるそうですね。

当地の桜並木に魅せられて開業した当初は、それほど多くの患者さんがいらしていたわけではありません。少しずつかかりつけとして頼りにしてくださる方が増えてきて、次第に全国からいらっしゃるようになりました。でも、予約制にはしていないんですよ。医療機関を受診する方というのは、どこか具合が悪くて、必要に迫られているわけですよね。そうした方々に応えるのが医療機関の仕事ですから、そもそも予約があるのがおかしいと僕は思っているんです。混み合うときはお待たせしてしまうこともあるかもしれませんが、これからも開業以来の方針として守り続けていくつもりです。
女性の患者さんが多いのですか。
女性が圧倒的に多いですね。生理や妊娠出産、ホルモンバランスの変化などで体調を崩しやすい女性には、鍼や灸などを提案することもあります。本来なら、女性は生理が始まった段階で何かしらの漢方を飲んだほうが良いと言っても過言ではないと考えています。お産に備えて安産祈願をしたり、腹帯を巻いたりはしても、体を冷やさないようにして体調を整えておくという一番大切なことを忘れてしまう方は多いんですよ。体調を整えることこそ安産の基礎になると考えて、漢方を含めた自己管理の大切さに気づいていただけると良いですね。一方男性は、自律神経の乱れからくる不調を訴える方が目立ちます。ストレス社会で頑張っている方が多いんだなあと思いますね。
女性については、産前産後の諸症状にも漢方で対応されると伺いました。

産前から継続的にケアをしておくと、産後の体調にも良い影響が出ると考えています。誰でも、体には弱いところと強いところがありますから、できるだけ早く弱点に気づき、上手に調整していくことが重要なんですよ。それから、産後はできるだけみんなの助けを借りること。核家族化が進んで、1人で子育てを抱え込んで苦しむお母さんが増えました。部屋で子どもとだけ向かい合っていたら、気が滅入って当然ですよね。子育ては1人ではできないと割り切り、周囲を巻き込むことが健やかでいられるコツだと思います。最近は昔の大家族のような、人とのつながりを求めて都心を離れる人も増えてきているようですね。自然の中では体が素直になるので、良いことだと思います。子どもたちにも、せめて小学校低学年までは自然の中で生き生きと遊びながら暮らしてほしいですね。大人も、滑ったり転んだりしながら成長する子どもを温かく見守る余裕を持ってほしいと思います。
大切なのは「自分にとって最善の治療」を見つけること
早くからのケアが大切なんですね。

僕には90歳を超える母がいますが、とても元気ですよ。早めに弱点に気づいて、母に合った漢方や鍼でケアしてきたのも良かったのでしょう。人はどうしても自分の強いところを頼りにして頑張ってしまいがちですが、それが続けばひずみが広がって弱いところから崩れてしまいます。僕としては、45歳を過ぎたら体全体を見直して、ケアを始めてほしいと思っています。他には、良いものであれば健康食品を取り入れるのも良いと思いますね。健康食品、僕は大好きなんです。江戸時代から戦前くらいまで実践されていたさまざまな健康法を記した本があるのですが、その半分くらいは健康食品について書かれているんですよ。
弱点に対して、自分に合ったケアをすることが大切ということでしょうか。
そうですね。僕は、漢方だけが良いもので他は駄目だと言っているわけではありません。日本は漢方が健康保険で認められていて、東洋医学との併用も一般的に行われていますよね。これは世界的にも珍しいことなんです。ですから、信頼できると思った先生に処方された治療法や薬を試して、具体的に症状が改善されたり、感覚的に今までより良いと思ったり、患者さん自身が何かしら「効いた」と思ったら続けてみることが大切なのではないでしょうか。逆に、「効かない」と思ったら素直にそう伝えることも忘れないでください。ずっと西洋医学の薬を飲んでいるけど漢方を試して比べてみようとか、もしかしたらいつも飲んでいる半量でも効くのかもしれないとか、体の経過を見ながら自分なりの「気づき」を探してほしいですね。
治療ありき、薬ありきではなく、「患者ありき」で治療法を選択するべきなのですね。

そのとおりです。今は薬に限らず、治療法もたくさんありますから、患者さんはその中から最善の組み合わせを探すことが大切です。「この治療が良い」というように治療が主語にあるのではなくて、「私にはこの治療法がいい」というように、患者さんが主語であるべきだと思います。
自分と家族の健康のために、漢方をもっと身近に
先生はいつ漢方と出合われたのですか。
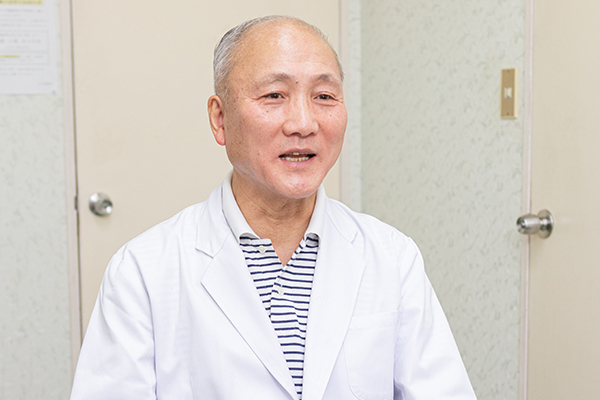
医師になって2年目、大学病院の産婦人科に勤務していた時です。僕の目の前で、患者さんが術後の肺動脈血栓症で亡くなられたんです。どんどん病状が悪化していって、あっという間でした。いろいろと勉強をした結果、そうした事態は一定の確率で起こり得るものだということはわかったのですが、どこか納得できなくてずっと悩んでいたんです。そんなときに出合ったのが漢方でした。西洋医学にはない漢方独特の考え方を学ぶうちに、手術前から血液の流れを良くしたりむくみを取ったりと血栓症に至る条件を取り除いておけば、亡くなる人を減らせるのではないかと思ったんです。当時、医師で漢方を取り入れている人は、まだまだ少なかった時代です。それでも、僕は迷わず漢方を専門にしようと決めました。そして術前の患者さんのコンディションを整え、どんな医師が手術をしても死に至る人がいなくなるようにしたいという目標を立てたんです。
そのような時代、どのように勉強をされたのでしょう。
何もかも手探りでした。とはいえ、ゼロから始められる分野に若い頃から携われたのは幸せなことだったと思いますね。システム、学校、法律、そういうものがみんなそろった状態で何かを始めると、楽ではあるけど探検隊みたいな楽しさがありません。何もないときに始めると、発見と自己満足の連続なんですよ。人生においてそういう経験ができたことは、その後の糧になっていると感じます。当時は、とにかくいろいろな場所でいろいろなものを見ようと考えて、中国に留学もしました。漢方は中国だけでなく台湾や韓国、ベトナム、タイ、ミャンマーなどにもあるんですよ。できるだけ足を運んで、現地の教育システムや市場を実際に見ながらバランス感覚を養い、日本の状況に合うものは取り入れるようにしています。
ちなみに最近、漢方の他に新たに勉強されている分野はありますか?

最近は、同じく医師である娘や息子との会話をきっかけに、再生医療への興味も高まっていますね。自分でいろいろと調べたところ、再生医療と漢方の併用に可能性を感じ、本格的に研究を始めたのです。再生医療はまだエビデンスが確立していない分野。僕も時代に遅れないように臨床の現場で頑張っています。将来的に産婦人科をはじめとする多様な領域で生かせたらと思っています。
最後に、読者へメッセージをお願いいたします。
漢方には長い歴史があり、僕が漢方に関わるようになって40年以上となります。それでも一向にマンネリ化しないし、興味も尽きません。これからも、個人的に興味を持って研究している再生医療や遺伝子治療などとの関係も考えながら、より良い治療を追求していきたいと思っています。大学病院などでも漢方を処方するようになった今は、昔に比べて漢方は身近なものになりました。自分の健康だけでなく、家族の健康を守るためにも、漢方を取り入れていただけたらと思います。






