北畑 亮輔 院長の独自取材記事
新宿・代々木こころのラボクリニック
(渋谷区/新宿駅)
最終更新日:2025/08/13
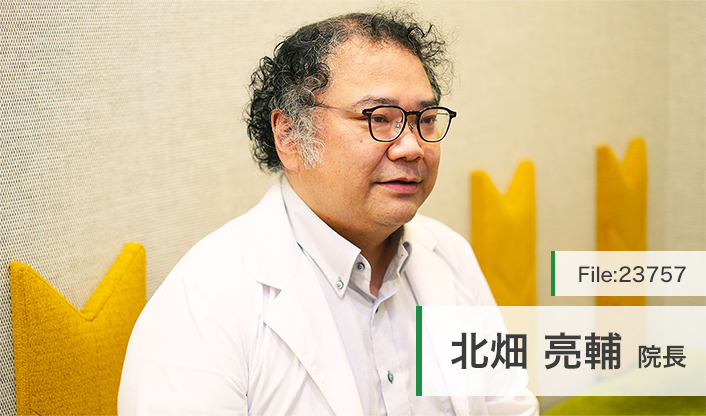
新宿駅直結5分、代々木駅から徒歩4分とアクセスしやすい立地に構える「新宿・代々木こころのラボクリニック」。院長を務める北畑亮輔先生は、近畿大学医学部卒業後、数々の大学病院などで研鑽を積んできた。2020年に開業して以来、「より良い治療をより多くの人に」を診療方針に掲げ、患者に寄り添い続けてきた。精神保健指定医および日本精神神経学会精神科専門医でもある北畑院長に、クリニックについて詳しく話を聞いてみた。
(取材日2025年7月14日)
より多くの人により良い治療を提供したい
来院される患者層と、診療内容について教えてください。

ビジネスパーソンの方がやや多いですが、お子さんや未成年の方、高齢者の方など、幅広い世代の方がいらっしゃいます。診療内容は、精神科や心療内科全般で、患者さんはうつ病や統合失調症、適応障害や発達障害の方などさまざまです。保険診療での薬物療法、カウンセリングや認知行動療法などの精神療法も行っています。あとは、開業当時よりも発達障害がかなり周知されてきているのを感じます。「発達障害じゃないか?」とご自身で考えて受診される方が、年代問わず増えましたね。
注目している治療法を教えてください。
rTMS療法(反復経頭蓋磁気刺激療法)です。rTMS療法とは、うつ症状の改善を目的に行われる治療法です。バタフライ形の刺激装置を頭に当て、微弱な電流により機能の回復をめざす方法です。脳内の定めた位置を刺激し、刺激の仕方を変えるなどして、活動が低下していると思われる神経にアプローチすることができます。当院としても、今後導入したいと思い注目している治療法の一つです。
月曜日から金曜日は21時まで、土日も17時まで診療を行っているのですね。

より良い治療をより多くの方に届けていくことが大事だと思っていますので、受け入れがしやすいように通いやすい立地を選び、平日夜と土日も診療を実施しています。クレジットカードや電子マネー対応なども導入しました。完全予約制ですが、空いていれば当日の予約・受診も可能です。発達障害の検査は保険診療でやっていますし、カウンセリングも患者さんの通院負担が少ないような価格設定にしています。本当に必要な人が、きちんとした精神科医療を受けられる体制が必要だという想いで、診療に臨んでいます。
どのようなスタッフが在籍されているのでしょうか?
それぞれの専門分野を持つ医師や臨床心理士が多数在籍しており、医療従事者全員が意見を交換し合いながら、より良い治療をめざしています。開業当初は、専門分野が比較的ばらついていて、心理寄りの方、薬理寄りの方、神経心理寄りの方など、さまざまでした。今は、どちらかというと薬理やrTMSを専門とする先生が少し多い印象です。いずれにしても、しっかりとした専門を持ち、研究も含めて真摯に取り組んでいこうという姿勢のある方々です。若手・ベテラン問わず、専門性を持って誠実に医療に向き合おうとされている先生が来ていただいていますね。特に大学病院は予約を何ヵ月も待たなければ診てもらえないような場合もあるので、身近なクリニックで専門的な診療を受けられるのはメリットだと思います。
仕事に支障を来したら、早めの受診を
うつ病の治療法としてはどのようなものがありますか?

一般的に、薬物療法、rTMS療法、精神療法です。急性期においては薬物療法とrTMS療法が中心になってくると思います。慢性的な症状には薬物療法、rTMS療法、精神療法、再発防止に関しては精神療法が中心になってきます。特に適応障害などですね。薬物療法とrTMS療法も選択肢としてはありますが、あくまでも補助レベルと考えていただいて、精神療法により考え方の根本から改善を図っていきます。精神療法とは、カウンセリングや認知行動療法を表しており、人は極端な考えになってしまうとストレスを感じやすくなり、調子を崩してしまうこともありますので、認知行動療法では、それを防ぐような考え方の訓練も行います。
薬物療法に関してはどうでしょうか?
薬物療法に関しては、副作用さえひどくなければ、継続的に行える治療方法の一つです。副作用は薬や患者さんの体質によっていろいろで、気持ち悪くなる、便秘になる、喉が渇く、目がしょぼしょぼするなどのほか、眠気が出たり体重が増えたりする場合があります。向精神薬においても手足が震えたり動作が鈍くなったりなどの錐体外路症状が、抗不安薬などですと依存症や眠気などが見られることも。こうして並べるとマイナスの印象を持たれるかもしれませんが、薬物療法も有用な治療方法ですし、当院では薬の飲み方を工夫することで、副作用の低減をめざしています。
発達障害の相談への対応は、どのようなことをされていますか?

まずは検査を行います。内容としては、質問に答えていただいたり、課題に取り組んでいただいたりするような形式の検査です。その結果から、どのような特性があるのか、障害と診断すべきものなのか。例えば、少し工夫すれば日常生活に支障なく対応できる程度なのかどうか、ということをまず丁寧に見極めます。得意なことや苦手なこと、「ここは問題ないけれど、ここは少し注意が必要」といった点を明確にし、それに応じた具体的な対応策を一緒に考えていきます。「ミスを減らすにはこういう工夫をすると良いですよ」「こうすれば片づけがしやすくなります」といったふうに、生活上のヒントをお伝えしています。検査の結果、ADHD(注意欠如・多動症)的な特性が見られる場合には、必要に応じてお薬を処方することもあります。ご自身の行動や気持ちをよりうまくコントロールしやすくするためにも、薬の併用は役立ちます。
無理をせず、自分のペースで病気と向き合ってほしい
診療において大切にされていることを教えてください。

患者さん一人ひとり、抱えている事情はさまざまです。たとえ同じ病名がついていたとしても、困っていることや苦しさは全然違うことが多い。悩みの答えというのは、結局のところご本人の中にしかないんですよね。僕たち医師は、その答えを見つけるためのお手伝いをするだけで、こちらから一方的に与えるものではない。対話を重ねながら、本当に困っていることを一緒に探っていく。そういう関係性が大切だと感じています。あと、僕自身の中にも発達障害的な傾向があると感じている部分があります。だからこそ、患者さんの話を「自分事」として感じられるのかもしれません。精神科医って、実はどこかしら自分の中にもテーマを持っている人が多いんじゃないでしょうか。それが興味につながって、この道に進んでいる人も少なくないと思います。
今後の展望について教えてください。
空いてる時間を活用して、集団精神療法やデイケアなども行えるようにしていきたいなと思っています。集団精神療法とは、休職している方を対象とした復職支援のための認知行動療法です。休職されている方たちが復職するまでにはいくつかの壁があると思います。例えば、まず朝しっかり起きる、通う、仕事のようなことをしてみる、帰ってしっかり寝るなどです。休んでも問題のない所で練習しながら、認知行動療法や精神療法を通してご自身が職場でどのようなことがストレスになっていたのかと振り返っていただくこともあります。復帰する時にはこうしたら良いのでは、といったことも覚えつつ、仕事のようなことをしてどのくらい集中して続けていけるかも見ていきます。
読者へのメッセージをお願いします。

社会や日常生活の中で、何らかの不都合やストレスを感じている方は少なくありません。そうした場合でも、少し視点や考え方を変えるだけで、状況が大きく改善することもあるんですよ。例えば自閉スペクトラム症などの発達障害の特性がある方の場合、根本的な治療薬が存在しないケースもありますが、自分自身の特性を理解し、考え方や行動の工夫を取り入れることで、ぐっと生きやすくなることも。そのためにも、自分の特性を正しく把握するための検査を受けていただくことは、とても重要だと考えています。また、うつ傾向がある方も、現在のやり方ではうまくいっていない部分があるからこそ、不調を感じているわけで、その場合も視点を少し変えるだけで改善のきっかけになることがあります。いずれにしても、無理をせず自分のペースで取り組んでいただくことが大切です。






