森本 浩一 院長の独自取材記事
森本耳鼻咽喉科
(大東市/住道駅)
最終更新日:2025/09/12

JR学研都市線の住道駅の北側出口からすぐ。落ち着いたれんが壁のビル2階にあるのが「森本耳鼻咽喉科」だ。待合室で出迎えてくれたのは、院長を務める森本浩一先生。「落ち着いたら待合室にキッズスペースを作る予定なんですよ」と目を細める、その表情から優しい性格が見て取れる。かつては母である先代が診療を行っていた耳鼻咽喉科クリニック。十数年のブランクをはさみ、同じ場所で地域に貢献しようと開業医としてのスタートを切った。そんな森本院長の思いが詰まった同院の特徴や診療の内容、方向性などをじっくり聞いてみた。
(取材日2019年8月30日)
地域のクリニックこそが早期発見の最前線
まずは開院までの経緯について教えてください。

ここは以前に母が医師として耳鼻咽喉科診療を行っていた場所なんです。その母が病気になり、2006年からずっと休診状態になっていたのですが、私が同じ場所で開院することになりました。耳鼻咽喉科を選んだ時点からここを継ごうという気持ちはありましたが、当時は私もまだ若く、未熟なままでは地域への貢献も満足にできませんから、もう少し研鑽を積もうと考えたわけです。それで出身である神戸大学医学部の附属病院や関連病院などで咽頭・喉頭がんや音声に関する治療と研究をずっと続けてきました。ちなみに母は1年間の闘病を経て60歳の若さで亡くなりました。10年以上かかりましたが、その遺志を継いでここで開院できたのは感慨深いことです。
どのようなクリニックをめざしていますか?
まず一つは、地域の皆さんが気軽に安心して受診できるクリニックです。耳の不調でいらっしゃり、原因が耳垢だとわかった場合など、皆さんすごく申し訳なさそうにされますが、まったく気にする必要はありません。それで安心していただければ何よりですから、気になることがあれば、ためらわずにどんどん来てほしいと思います。もう一つは、これまで私が培った医療経験や知識をフルに生かして地域に貢献していくこと。がんなどの病気の早期発見は特に力を入れているポイントです。また、院内環境に関しては間取りを一新して動線に進路を持たせ、診察を終えたらぐるっと回って出る仕様にし、入る人と交差しないようにしました。診療スペースには聴力検査室やネブライザー室、個室のカウンセリング室などを用意しています。
こちらには耳鼻咽喉科用の内視鏡があるそうですね。
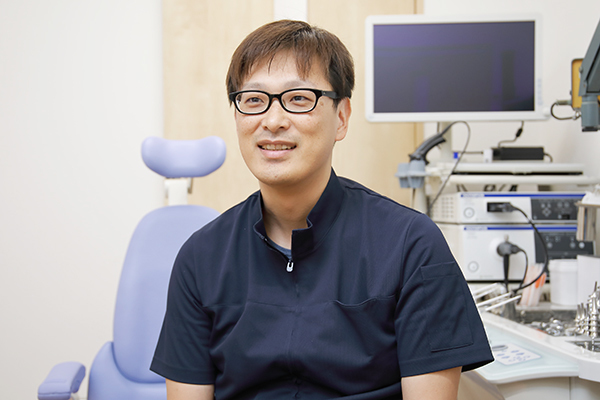
当院が導入しているのはNBIという、早期がんなどの粘膜病変を見つけやすい機能を持った内視鏡です。もともとは胃カメラのシステムなのですが、鼻から喉まで精度にこだわった診断結果が得られ、検査後すぐに診察室のモニターを見ながら説明することができます。もし喉頭がんや下咽頭がんが見つかっても、早期であれば放射線治療をせずに口の中から切除して経過を観察することも可能な場合があります。その早期発見を地域のクリニックでめざせることが当院の大きな特徴と考えています。些細な症状から、顔面神経麻痺や鼻の腫瘍が見つかることもあります。声がかれる、喉に食べ物が引っかかるといった症状があり、何かあるんじゃないかと不安に思われる方は、ぜひ受診をお勧めします。
できる限り体の負担や傷の少ない治療をめざして
どのような症状の患者さんが多いですか?

耳鼻咽喉科というのは幅が広く、鼻が詰まる、聞こえ方がおかしい、味覚がおかしい、舌がしびれるなど、実にさまざまな症状の方が相談に来られます。例えば女性の声に関する悩み。50代後半ぐらいから声が変わってきて、見た目は若々しいのに声が少ししわがれているという方に対しては、言語聴覚士による喉の筋力トレーニングのような訓練も行っています。あと、私は小児診療も結構得意なんです。怖がって泣く子は初回から無理をせず、まずは友達になることから始めます。そうすれば数回目には自分から椅子に座ってくれる子がほとんどです。大人もそうですが、恐怖心や不安感が痛みや苦しみを倍増させることもあるんです。私も痛いのは苦手なほうですから、患者さんの気持ちがよくわかるのかもしれません。
勤務医時代は頭頸部腫瘍を専門にされていたそうですね。
頭頸部腫瘍とは、首から上の脳以外の部分のがんを指します。神戸大学に勤めていた頃は、喉の腫瘍摘出のために、10時間以上に及ぶ手術も何度となく行っていました。体への負担の大きい放射線治療や抗がん剤はなるべく避けるべきと考え、最終的にはできるだけ傷をつくらずに口の中から手術をする方法や、ロボットを使った国内手術の実現準備などに力を注いでいました。こうしてつくづく実感したのは、やはり病気をできるだけ早く見つけて侵襲の少ない治療を施すことの大切さです。大学病院は最終機関ですから、まず最初に患者さんが来る町のクリニックに経験のある医師がいて早期発見につなげられれば、それが一番の貢献になるのではないかと考えました。
患者さんとの印象的なエピソードはありますか?
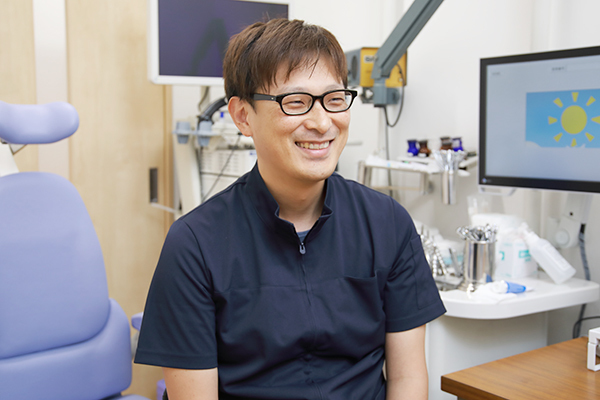
この分野は難しい症例の方も多く、どうしても気の毒なかたちで終わってしまうケースも避けられません。そうした患者さんが終末期の病院へ移られた場合、私はできるだけそこを訪ねるようにしてきました。それは一度担当した患者さんは単に病気だけでなく、生活そのものに寄り添いたい気持ちがあるためです。今年も、四国在住の担当患者さんに会いに行きました。残念なことではありますが、すべての患者さんが助かるわけではありません。力及ばず、といった心残りはありますが、だからこそ避けるのではなく、最期までしっかり見届けさせていただくことが大切ではないかという、そんな思いです。
充実した生活を送ることに健康の意義がある
お母さまとの思い出を聞かせてください。

うちは両親とも医師で、父は脳神経外科、母が耳鼻咽喉科の医師でした。家では普通の母親で、私と妹の2人を働きながら育ててくれました。母がここで開業したのは私が6歳ぐらいの時で、子どもの頃はよくこのクリニックの中を走り回って遊んだものです。診察室にある顕微鏡は母が愛用していた物で、最新の機器に比べるとずいぶんレトロに見えますが今も現役でこれを使っています。診察室の椅子や机、待合室のソファーも母が残した物です。新規開院なのにどこか懐かしいような雰囲気があるのは、たぶんそのせいでしょう。同じ耳鼻咽喉科の医師として、いつかはここで母と一緒に診療したいという思いはありました。残念ながらそれは実現しませんでしたが、今になって私が再開できたことをきっと喜んでくれているのではないかと思います。
現在のご家族や休日の過ごし方などは?
今は妻と3歳の娘の3人家族で、秋には一家でこの大東市に戻ってくる予定です。妻は放射線科の医師ですが、年内に出産を控えているのでそろそろ産休に入ります。開院から引っ越し、出産まで、いろんなことが一度に重なって大変ですよ(笑)。私の趣味はいろいろありますが、運動不足を解消しようと6年前から走り始め、フルマラソンにも3回出場しました。大学時代はバスケットボール部で、医学部のリーグ戦に出るなど、みんなで和気あいあいとやっていました。今も当時の仲間と飲むのが一番楽しいひとときです。
最後に、読者へ向けたメッセージをお願いします。

やはり大切なのは早期発見、早期治療です。早く見つけて早く治療を行えば、元気に長生きすることもめざせます。もう一つ重要なのは生活の質で、そこには聴覚も嗅覚も、味覚も大きく関わります。ただ単に寿命を延ばすのではなく、豊かで充実した生活のために健康がある、そう思ってもらえたらうれしいですね。病気になれば本人はもちろん、家族みんながつらい思いをします。早期に治療につなげ誰もがハッピーに過ごしていける、それをこの地域で実現したいというのが私の偽らざる気持ちです。親しみやすさは心がけていますが、これまでに自分が培ってきた医療を惜しみなく提供していきたいと考えていますので、お近くの方はぜひ一度相談にお越しください。






