藤原 良平 院長の独自取材記事
ふじわら耳鼻咽喉科
(富田林市/金剛駅)
最終更新日:2025/11/06
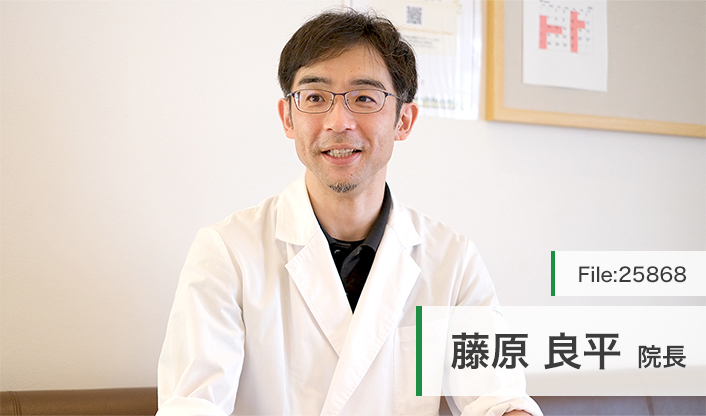
南海高野線金剛駅から南海バス、または近鉄長野線富田林駅から近鉄バスに乗車し中央センター前バス停で下車して徒歩2分。周辺にショッピングモールやしゃれた住宅街が広がる地域に、2019年開業の「ふじわら耳鼻咽喉科」はある。院長を務める藤原良平先生は、大学付属病院の耳鼻咽喉科や関連病院で甲状腺専門の外来に長く勤務していたが、地域医療の一端を担いたいと開業に至った。スタイリッシュな外観のクリニックには、エレベーターで2階に上がると天井の高い開放的な待合室があり、患者がリラックスして過ごせる落ち着いた空間が広がる。院長は「一次診療を担うクリニックとして適切な診療を行いたい」という強い思いを持ち、CTやエコーも導入し、幅広い症例に対してわかりやすく丁寧な診療を行うことに努めている。そんな院長に話を聞いた。
(取材日2023年8月7日)
医師を志したのは「恩返しがしたい」という思いから
2019年に開業されましたが、それまでの経緯を教えてください。

大学を卒業後、その付属病院や関連病院で研鑽を重ねました。甲状腺疾患が専門で、耳鼻咽喉科の中でも主に頭頸部の腫瘍を担当していました。大規模な病院でしたので、重症の患者さんも多く、さまざまな難症例の診療や手術に関わる日々でした。忙しい中でも非常にやりがいを感じていましたが、一人ひとりの患者さんにしっかりと向き合いたいという気持ちが募り、開業を決意しました。実は当院がある富田林市は、個人的にはゆかりのない場所だったんです。しかし、以前この場所に耳鼻咽喉科のクリニックがあったので、地域の方にも親しんでもらいやすいこと、在籍していた大学にも比較的近く連携を取りやすいことなどが後押しとなり、現在の場所での開業を決めました。
耳鼻咽喉科の医師をめざしたきっかけは、どのようなものだったのでしょうか?
研修医の時に各科を回ってみて、純粋に一番興味深かったのが耳鼻咽喉科でした。理由としては、幅広い年齢層の患者さんと向き合うことができ、手術にも携われるので自分に合っているなと感じたことですね。いざ大学の付属病院で勤務し始めると、患者さんとゆっくり向き合う時間が思うほど取れず、手術、手術の目まぐるしい毎日でしたが、それも今となっては良い経験です。また、家族が甲状腺の病気を患っていたことも、耳鼻咽喉科を選んだきっかけの一つでした。担当医師の診療の光景をよく見ていましたし、医師に対しての感謝の気持ちもありました。だから少しでも恩返しがしたくて、今度は自分が患者さんやそのご家族を助ける側になりたいという思いがずっとあったのです。
大学の付属病院では甲状腺専門の外来に在籍されていたようですね。

大学の付属病院でも、その後に勤務した病院でも、甲状腺専門の外来を担当していました。耳鼻咽喉科と聞くと、耳、鼻、喉を診るという印象で、甲状腺は切り離されがちなイメージがあるかもしれません。しかし甲状腺は、耳、鼻、喉に近く、耳鼻咽喉科の領域でもあるのです。耳鼻咽喉科診療においては、鼻から内視鏡カメラを入れて一元で診ることができるので、何か合併症などが起きてしまった場合にも非常に効率的に診療ができます。ちょっと痛みがあったり、腫れがある場合にも気軽に来て相談していただければうれしいです。
一次診療に携わるからこそ早期発見に全力を尽くしたい
診療で一番大切にしていることは、どのようなことでしょうか?

私が最も大切にしているのは、早期発見をすることです。当院のようなクリニックは、患者さんが「ちょっとおかしいな」「体調が悪いな」というときにまず訪れてもらう、一次診療を担う場所です。だからこそ、最初に適切な診断をつけることが大切だと思っています。じっくり診療して、当院で対応ができる症例なら治療を、大規模病院での治療が必要な場合は紹介をという判断を速やかに行う必要があります。処置が遅ければ重症化する可能性があったりするケースも考えられます。そういった小さな異変を見逃さないよう、できる限り丁寧に適切な診療を行うことを心がけています。
適切な診療を行うための設備も充実していますね。
当院でできる限りの診療をするために、エコーやCTを導入しています。エコーは首のしこりや炎症疾患などを早期に発見するために使いますが、耳鼻咽喉科で導入しているのはわりと珍しいかもしれません。最近では若い方でも首のしこりを気にして来院する場合があります。その大半は深刻なものではなく、リンパ節の腫れなどが原因であることが多いのですが、その場合はエコーで悪いものかどうかだいたいの判断がつきますので、当院でも診療が可能です。また1年ほど前にはCTも導入しました。こちらは難治性の副鼻腔炎の患者さんに使います。そうした機器を使うことで患者さんそれぞれの診療方針が明確になりますので、いち早く快復へ向けて治療が進められるのではないかと思っています。
患者さんと接するときに心がけていることは?

「患者さんに向き合って診療する」ということを言葉どおり実践するため、診療時のパソコン入力はクラークと呼ばれるスタッフにしてもらい、私自身は患者さんの目を見て話を聞くようにしています。少しの違和感も見逃さないようにするのが目的ですが、患者さん自身の気持ちを大切にしたい、寄り添いたいという思いもあります。また症状によっては、喉の奥や鼻の中をカメラで撮った写真を見てもらいながら、今このような状態ですよとお話しします。どこに原因があるのか、どの程度炎症を起こしているのかなどを視覚的に確認することで、患者さん自身もご自分の症状を把握しやすくなりますし、こちらからの診療方針も伝えやすくなると思っています。
「ここに来れば安心」と思われるようなクリニックに
小さなお子さんへの対応では特徴的な取り組みをされていますね。

お子さんで多いのが、鼻水がずっと止まらず息苦しいという症状です。その場合、当院では鼻水を吸い取るために生理食塩水を使って鼻うがいができるような機器を用います。注射器で生理食塩水を吸い上げ、鼻水の吸引機を通じて鼻洗いをします。鼻の中を洗浄するので抵抗のあるお子さんもいらっしゃいますが、洗うことによって詰まりを取ってスッキリとさせることが期待できます。洗浄自体は少し気持ち悪いかもしれませんが、お子さんの痛みや息苦しさを取り除くためにできる限りのことをしていきたいと思っています。
院内にはどのような工夫をされていますか?
開業の際に、もともとあった建物を大きくリノベーションしました。まず入り口が2階なので、バリアフリーにするためにエレベーターをつけました。院内も開放的なスペースにしたかったので天井を取り払ったのですが、その際に太く立派な梁が出てきたので、あえて見せるような内装にしました。天井が高く、天然木の風合いを感じられる気持ちの良い空間で、患者さんにゆったりと過ごしてもらえればうれしいですね。またキッズスペースや小さいですが感染症対策のための部屋などもありますので、できるだけ幅広い症状の方々にご利用いただけるのではないかと思っています。
今後の展望を教えてください。

近隣に住む方だけでなく、少し離れたエリアからも通院してくださる患者さんが増えてきました。そのため、どうしても待ち時間が長くなってご迷惑をおかけすることがあり、その点は心苦しく感じています。今後もお一人お一人としっかり向き合い、丁寧な診療は変えることなく、院内のスタッフの配置や作業の効率化を進めることで、患者さんの負担が少ない環境を作っていきたいと思います。また可能な限り幅広い診療ができるように設備も充実させながら「ここに来れば安心」と感じていただけるような体制を整え、患者さんファーストの環境を充実させていきたいと考えています。






