片桐 佳明 院長の独自取材記事
うした耳鼻咽喉科クリニック
(広島市東区/牛田駅)
最終更新日:2021/10/12

「うした耳鼻咽喉科クリニック」は、アストラムラインの牛田駅から徒歩5分ほどの場所に位置する商業施設内にあり、施設の駐車場も利用できる。近くには住宅街があり、同院には新生児から高齢者まで幅広い年代の患者が通う。院長の片桐佳明先生が、耳や鼻、喉に関すること、そして睡眠時無呼吸症候群やめまいの症状に対応している。患者が安心して通えるような清潔で快適な環境を用意したいという思いから、院内の設計や検査機器の充実にもこだわったそう。今回の取材では片桐院長に、医師になったきっかけや、耳鼻咽喉科を専門に選んだ経緯、クリニックを開業してからの診療に対する思いについて詳しく聞いた。
(取材日2020年12月3日)
快適な環境で患者が安心できる医療の提供をめざす
医師をめざしたきっかけを教えてください。

父が整形外科医、祖父が皮膚科医で、医師が身近な環境の中で育ちましたので、私も医師をめざすのが自然な流れでした。幼少期から祖父のクリニックに遊びに行き、仕事をする姿を見て育ちましたので、私は亡くなった祖父に強く影響を受けており、医師としての原点となっています。そして、私が開業したのも、開業医であった二人の影響からです。私自身の出身地でもある広島市内の地域医療に貢献したいと、この地に開業を決めました。この辺は、広島市内でも多くの人が住む住宅街があるので、さまざまな患者さんがいらっしゃいます。まだ首が座っていない新生児から高齢者まで幅広いですよ。クリニックが入っている建物も新しく、地域の住民の方々に必要とされ、とてもやりがいを感じているところです。
なぜ耳鼻咽喉科を選ばれたのでしょうか?

祖父にも父親にも進路は自由に決めていいと言われていました。東京医科大学を卒業し県立広島病院で研修医を開始しましたが、その時点では何を専門にするか決めていませんでした。研修医の2年間でさまざまな科を勉強させていただく中で、耳鼻咽喉科に魅力を感じました。なぜなら耳鼻咽喉科は耳、鼻、喉の範囲であれば診断して薬も出しますし、手術もします。診断から治療まで一貫して対応できるからです。
クリニックの診療方針について教えてください。
「安心できる治療」「快適な環境」「患者さまの尊重」の3つを診療方針として掲げています。当院では診察を大切にし、患者さんに十分に説明をしてご理解と同意をいただき、治療の方針を決めています。患者さんに安心して治療を受けていただけるように、検査や治療の説明や、診断の根拠については、しっかりお伝えしています。説明する際には、易しい言葉を使ったり、図を使ったりして、伝わりやすいよう工夫しています。また、患者さんのニーズに合わせるのも大事だと考え、詳しい説明を聞きたい人にはより丁寧に説明します。快適な環境づくりに関しては、動線を考慮した2つの診察室と待合室の設計にこだわりました。バリアフリーにしたり、キッズスペースを設けたり、幅広い方に来院していただきやすいような工夫をしています。
睡眠時無呼吸症候群やめまいの相談にも対応
まずは、耳の診療における特徴を教えてください。

小さいお子さんに多い病気の一つに、中耳炎があります。これが長引いた場合、カッターナイフのような器具で鼓膜に穴を開け、中にたまった膿や液体を抜く「鼓膜切開法」で治療を行うのが一般的です。しかし、この方法は出血したり、すぐに穴が閉じてしまったりといったトラブルが起きやすい。そのため、当院ではレーザーで穴を開けています。痛みや出血の低減が図れ、患者さんの負担も少ないのです。さらに、膿をきちんと出しきることを考えると、切開した場合よりも穴が閉じにくいという点もメリットだと言えるでしょうね。大人の患者さんですと、花粉症などのアレルギー性鼻炎、ご高齢であれば耳鳴りに悩んで来院される方が多いです。治療効果がなかなか出ず、長期の治療になることもありますが、可能性のある治療を患者さんと根気強く探っていくことを心がけています。
鼻や喉の治療については、どのような特徴がありますか?

当院では、花粉症に対してもレーザーで鼻の粘膜を焼く処置を行うことがあります。また、スギやダニのアレルギーに対しては、舌下免疫療法も行っています。舌下免疫療法の場合は3年間薬を飲む必要があるのですが、患者さんと一緒に完治をめざしています。もちろん、従来どおりの飲み薬や点鼻薬にも対応しています。蓄膿症に対しては、CTを利用してしっかり判断し、適切な治療方法をご提案できるようにしています。当院で治療が難しいと判断した場合は、手術ができる専門の病院をご紹介しています。喉の領域では扁桃腺に関する症状が多く、軽症から重症までさまざまな方がいらっしゃり、手術が必要になることもあるのでその判断をしっかり行うことを大切にしています。
その他の治療では、どのようなことを行っていますか?
睡眠時無呼吸症候群の治療にも対応しています。睡眠時無呼吸症候群は、放っておくと脳梗塞や脳出血、心筋梗塞のリスクが高まる可能性があることがわかってきましたので、治療は早期に行いたいものです。診療の流れとしては、診断をつけるためにまず検査を実施します。検査はご自宅で専用の機械をつけて一晩寝てもらうもの。そこで重症の睡眠時無呼吸症候群と結果が出たら、治療を開始します。当院では、睡眠時に専用の機械を装着するCPAP療法に対応しています。他には、めまいに悩まされて来院する患者さんも多いですね。めまいには原因がわかるものと、原因不明のものがあり、どちらなのかをまず明確にすることが大切です。原因がわかるめまいではそれぞれの原因に合わせた治療をしていきますが、原因不明のめまいは、症状に対するアプローチをしていきます。
極力院内で診療を完結できるよう検査機器の充実を図る
検査機器の充実にもこだわられているそうですね。

自分の理想の医療を行うために、検査機器は充実させたいと思いました。クリニックにCTやエコーがあれば、患者さんに大きな病院に行ってもらわなくても、すぐに診断につなげることができますからね。中には当日に結果を出せるものもあるんですよ。当院で、なるべく多くの検査をできるようにして、何回も検査のために病院に行ったり、検査結果が出るまで長い時間待ったりする患者さんのストレスを軽減させたいと思ったのです。また、大きな病院の先生やスタッフさんの負担を減らすためでもあります。自分が勤務医として働いていたからこその視点かもしれませんね。クリニックの中で対応できることはしっかり行っていきたいと思います。
開業されてからも、新たな勉強をされているのですか?
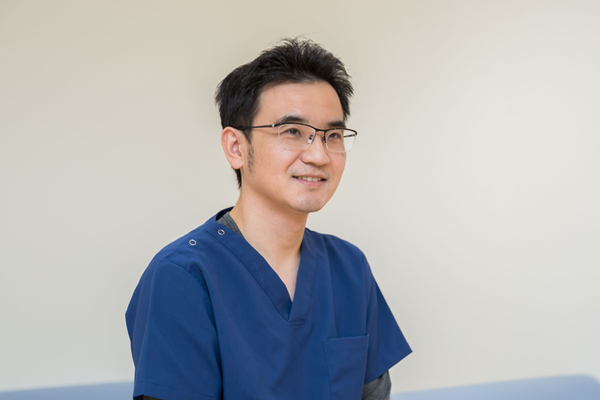
患者さんを診療していると、原因がわからず治療方法もわからないということが出てきます。そこで、「あれは何だったのだろう?」という疑問から、詳しく勉強をし始めたり、患者さんを大きな病院に紹介して専門家の見解を伺って知識とすることもあったりします。医師は、常に勉強が必要ですね。横のつながりや勉強の時間を大切にしています。同じ科目の先生や、違う科目の先生と話す中で気づくこともたくさんありますし、製薬会社の勉強会などにも参加するようにしています。特に漢方薬は、開業してから患者さんに必要だと感じ、勉強するようになりました。診察や投薬のスキルは、開業してから上がったと思います。これからさらに磨いていきたいですね。
最後に読者へメッセージをお願いします。
これからも、患者さんに安心して受診いただけるような工夫や勉強を続けていきたいと思っています。現在は、原因不明のめまいや耳鳴りに対して、症状の軽減をめざした新たなアプローチを考えて、ご提案しています。また、最近導入した取り組みとして、2020年の春からオンライン診療を始めました。ずっとアレルギーの治療で通院してくださっていた患者さんが、新型コロナウイルス感染症の流行で通院するのに躊躇しているのであれば、アプリを通じて診療することが可能です。家にいたままいつもの診療を受けられるようにしました。薬も郵送でご自宅に届けることができます。気になっていることがあれば些細なことでも構わないので、まずは気軽にご相談いただきたいと思っています。






