根本的な原因を見極め症状にアプローチする
関節リウマチ治療
竹内リウマチ整形外科クリニック
(北九州市門司区/門司駅)
最終更新日:2025/05/16


- 保険診療
手足の関節で起こりやすく、痛み、こわばり、腫れなどを伴う関節リウマチ。発熱、だるさ、食欲不振といった症状もあり、放っておくと関節が変形してしまう病気。本来、自分の体を守るべき免疫機能が何らかの原因で骨や関節軟骨を攻撃することで起こる疾患で、高齢者だけでなく、どの年代でも発症の可能性があるという。そこで今回、関節リウマチの症状や特徴、薬物療法やリハビリテーションなどによる治療の流れについて専門の先生に話を聞いた。
(取材日2022年9月13日)
目次
検診・治療前の素朴な疑問を聞きました!
- Q関節リウマチの症状について教えてください。
-
A
代表的な症状は「痛み」「倦怠感」「こわばり」です。痛みについては重い物を持つと手首が痛んだり、ドアノブを回すときやペットボトルのふたを開けるときに手や指の関節が痛んだりします。その他にも体中がずきずきと痛んで眠れないといったケースもあります。そして、体のだるさや微熱、食欲不振、体重減少といった症状に加え、よく知られている朝のこわばり。起きたときに手足の指などの関節が動かしづらいと感じるものの、少しずつ関節を動かしていくと徐々に症状が緩和するという特徴があります。このように症状はさまざまです。
- Q発症しやすい人の特徴などはありますか?
-
A
発症しやすい遺伝子を持つ方が喫煙をしたり肥満になったりすることで、発症の可能性が高まるともいわれていますが、まだ詳しいことは解明されておりません。本来は自分の体を守るべき免疫機能が何らかの原因によって骨や関節軟骨を破壊したり攻撃したりすることで起こる自己免疫疾患で、どちらかというと女性に多く見られます。40代くらいから発症する方が多く、手をよく使う仕事やストレス、歯周病なども関係しているのではともいわれています。遺伝子的要因と環境的要因の組み合わせで発症する疾患だと考えられているため、どの年代でも発症する可能性はあります。
- Qどのように治療を行うのですか?
-
A
エビデンスとして信用度の高い治療を早期から積極的に行うことが推奨されています。具体的には、糖質コルチコイド(ステロイド)は副作用などのリスクから極力使用しないように、という流れに変わってきた一方、これまで慎重に使われていた生物学的製剤や分子標的薬の有用性と安全性の確認が進み、治療の効果が不十分であった場合はこれらを積極的に使用するようになってきています。高齢であることや合併症の多さから治療を躊躇される方がいますが、治療効果が不十分な場合、しっかりモニタリングした上で有害事象を予防しながら、より効果の見込める生物学的製剤や分子標的薬を使用したほうが安全ではという考えが主流となってきています。
検診・治療START!ステップで紹介します
- 1医師による診察
-
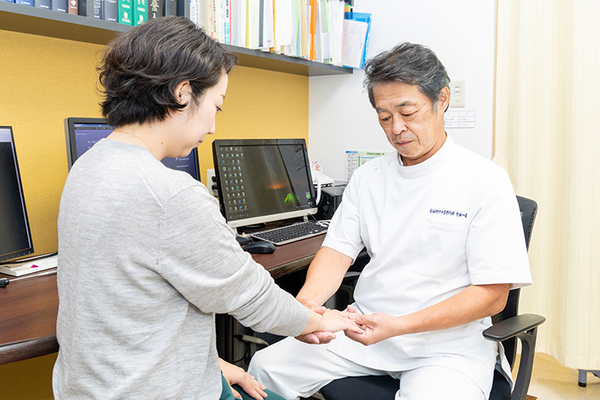
まず、手指、上下肢の代表的な28ヵ所の関節の腫れや圧痛の有無を確認。その後、医師は患者の主観的な痛みを定規(1~100mm)で評価するビジュアルアナログスケールを実施した上で、定量的疼痛評価を行う。痛みの感じ方はそれぞれ異なるため、大げさと思われるかもと心配せずに、自分が感じる痛みの度合いを正直に伝えよう。似た症状の病気も多くあることから、関節リウマチ以外の病気との鑑別や除外診断も実施される。
- 2看護師によるヒアリングや採血
-

看護師から生活習慣などについてヒアリングを受ける。酸素飽和度、血圧、体重も測定。採血では免疫、炎症以外に赤血球、肝機能、腎機能、タンパクや中和脂肪、コレステロール値などを調べる。免疫機能の変化を伴う可能性もあるため糖尿病の検査や肝炎ウイルス、結核、深部真菌症の検査をすることもあるという。検査について疑問点があれば、遠慮せずに何でも聞いておこう。
- 3画像検査・診断
-

エックス線検査で骨や関節の状態を確認し、関節の中で起こっている炎症をチェック。関節超音波(エコー)検査では、関節の中の血液の流れ方や腫れ、痛みの原因となる滑膜の増殖や骨びらんなどもわかるため、関節リウマチの早期診断や病状評価などにも有用だという。トモシンセシスやCTによる肺の断層撮影では結核や悪性腫瘍、リウマチ性や薬剤性間質性肺炎の早期発見が見込める。このような各種検査実施後に診断を受ける。
- 4リハビリの実施
-

炎症が起きている場合は安静を優先しなくてはならないため、リハビリは必ず医師の指示に従って行うことが重要。決して自己流で行わないこと。理学療法士によるリハビリでは関節の動きや筋力の維持などを目的に、手を握ったり開いたりする、足の上げ下げなどの動作を繰り返す「理学療法」、生活動作を改善する「作業療法」、痛みの抑制や変形を予防するために行う「装具療法」のほか、それぞれに適した生活指導も受ける。
- 5定期的な通院で寛解状態を維持
-

一般的な抗リウマチ薬や生物学的製剤、分子標的薬の投与といった化学療法を行い、長期的に治療のゴールをめざすため、定期的に通院し診察を受ける。年齢や状態によって通院の間隔は異なるが、毎回課題を達成できているか、寛解状態を維持できているか、病態の悪化、薬の副作用がないかなどをチェック。完治が難しい病気のため、薬の量や種類をコントロールしながら寛解状態の維持に向けた治療を続けていく。







