山地 康文 院長の独自取材記事
やまじ呼吸器内科クリニック
(観音寺市/豊浜駅)
最終更新日:2025/08/28

国道11号沿いにあり、大野原ICからも1km圏内とほど近い場所に位置する「やまじ呼吸器内科クリニック」。同院では2016年の開業以来、呼吸器内科・内科・アレルギー科を掲げ、西讃地域に根差した診療を続けている。院長の山地康文(やまじ・やすふみ)先生は、三豊総合病院で呼吸器科医長や副院長などを歴任。呼吸器関連疾患の重症患者と約20年間、向き合ってきた人物だ。開業後は専門性を生かした検査設備を整え、増加するCOPD(慢性閉塞性肺疾患)や喘息などの継続的治療にあたるとともに、県内での実施先が限られる呼吸器リハビリテーションにも注力している。今回の取材では、山地院長に現在の医院の体制や呼吸器診療への想いなどを詳しく聞いた。
(取材日2025年7月8日)
高度な専門性を生かし、地域の呼吸器診療を支える
北欧風で、かわいらしい雰囲気のクリニックですね。

患者さんがリラックスした状態で受診できるよう、内装にはこだわっています。妻の意見も取り入れながら、待合室の照明やクッション、各部屋のカラフルな壁紙、トイレの床のモザイクタイルなども遊び心を持って選びました。早いもので、2016年の開業から間もなく10周年を迎えます。継続的に通われる方も増えたことから、現在はカルテの入力や紹介状の作成などを手伝う医療クラークを採用し、スマホやタブレット端末から事前に来院目的などを入力できるAI問診システムも導入しました。まだまだ試行錯誤の日々ですが、スタッフ間の密な連携を欠かさずに、今後も患者さんが安心して過ごせる環境を整備していきたいと思います。
患者さんはどちらから、どのような理由で来られていますか?
香川県西部は、呼吸器内科を専門とする医師が非常に少ない地域です。そのほとんどは高松市に集中しているため、当院には観音寺市や三豊市の他、愛媛県東部や徳島県西部の三好市からも患者さんが訪れます。最も多い受診理由は、長引く咳です。その原因は多岐にわたり、喫煙に起因するCOPD(慢性閉塞性肺疾患)というケースもあれば、喘息というケースもあります。COPD患者さんは高齢者、喘息は小学生を含めた若年層が大半で、年齢層が幅広いという点も当院の特徴です。最高齢でいいますと、過去には100歳近い方も来られていましたね。呼吸器内科以外の領域ではじんましんやアトピー性皮膚炎のご相談が多く、注射薬などで対応しています。
現在、力を入れている治療や特徴的な検査などがあれば教えてください。

圧倒的に多いCOPDと喘息の治療、あとは予備軍も含めて間質性肺炎の患者さんが増えていますので、この疾患の進行抑制を目的とした治療に注力しています。間質性肺炎には複雑なパターンがあり、基本的には病院で治療を進めるのですが、そもそも数が限られる呼吸器内科の医師として、私は原因の特定から治療方針の相談・決定まで引き受けています。治療は薬物療法だけでなく、呼吸器リハビリテーションという選択肢も可能です。特徴的な検査といえるのは呼気NO検査と、モストグラフ(気道抵抗性試験)でしょうか。特に、モストグラフを実施するクリニックはあまり多くないはずです。当院ではこれら複数の検査を組み合わせて、喘息の診断につなげます。なお、COPDを予防する上で重要な禁煙治療は内服薬の供給が困難な時期もありましたが、現在は貼付薬を用いて再開しました。初回の受診は、火・木・土曜の14時から予約可能です。
血液内科からの転身。すべてが今につながる経験に
呼吸器リハビリテーションは、このクリニックの大きな特徴ですね。

呼吸器内科のクリニックを開業する上では、必ず呼吸器リハビリが必要だと考えて専用のリハビリ室を用意しました。香川県において、呼吸器に特化したリハビリを実現するクリニックは、そう多くありません。対象となるのはCOPDや喘息、間質性肺炎などの呼吸器疾患を抱え、呼吸機能の低下を来している方々です。リハビリ室では中央のベッドを囲むように手すりとカラーコーンを設置しており、理学療法士と連携しながら、6分間にわたる歩行試験や筋力トレーニングなどによって、呼吸困難感の軽減と運動能力の改善をめざします。呼吸器リハビリの最終目的は、患者さんの生活の質の向上を継続的に支援することです。まだまだ認知度が低く、呼吸器リハビリを目的に来られる方は多くありませんが、潜在的なニーズは非常に大きいと思いますので、今後も診療の柱として取り組んでいきます。
先生が呼吸器内科を志した経緯をお尋ねしたいです。
高松市に生まれ育ち、いずれは地元へ帰ることを見据えて、香川県内に関連病院を持つ岡山大学医学部へ進学しました。香川医科大学、今の香川大学医学部が開学したのは私が卒業する数年前のことです。香川県出身の学生を中心に採用がスタートし、私は憧れの医師が教授に内定したこともあって応募に至ったのですが、1981年の卒業時点では、大学病院が未開設。病院が誕生するまでの3年間は、県外研修に励む運びとなりました。東京の国立病院で血液内科を志し、2年が経過した頃のことです。上司の鶴の一声で、名古屋市の愛知県がんセンターへ移り、肺がんについて学ぶことが決まりました。それが、私が呼吸器内科に進んだきっかけです(笑)。後から知ったのですが、当時の愛知県がんセンターは化学療法、つまり抗がん剤を用いた肺がん治療の先端施設だったんですね。結果的に国内先進の医療にふれ、今の診療の土台を築くことができました。
研修後は、どのように研鑽を積まれたのですか?
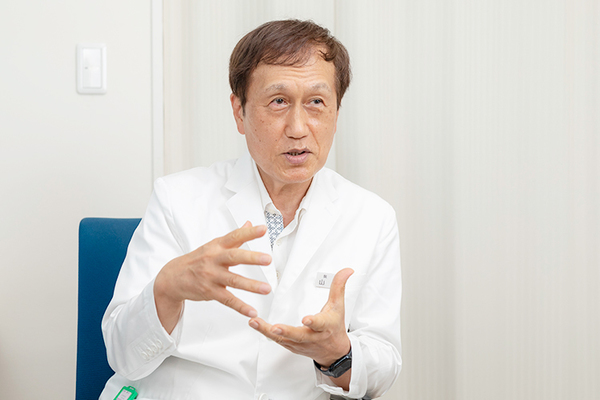
香川へ戻り、香川医科大学の第一内科に入局しました。第一内科は血液内科から内分泌内科まで広く扱っていましたが、新興大学ということで、呼吸器内科の指導者は不在。現場で学びながら、専門性を磨いていきました。1987年にはアメリカのインディアナ大学へ留学し、抗がん剤の基礎研究に従事。帰国後は大学病院と並行して、先輩医師がいた三豊市の橋本病院にも勤務しました。専門の医師が不足していた呼吸器科の医長として、三豊総合病院に入職したのが1996年。以降は内科の主任部長や副院長などを歴任しました。開業が頭に浮かび始めたのは、20年近く勤めた後のことです。病院が拡大する中でも、呼吸器の医師は少ない状況が続き、さらに役職を得たことで多忙を極めるようになりました。循環器内科を退職し開業した先生の存在も後押しとなって、一度リセットがしたいなと。ただ、今でも週に1日は病院で外来や検査、病棟のフォローを続けています。
日常生活に寄り添った、相談役でいたい
病院時代に出会った、印象的な患者さんはいらっしゃいますか?

30年ほど前に、派遣先の病院で発見した肺がんの患者さんは今でも記憶に残っています。肺がんは小細胞がんと非小細胞がんの2種類に大別され、その多くは非小細胞がんに分類されるのですが、この患者さんは非小細胞がんの疑いがあったにもかかわらず、なかなか診断がつきませんでした。当時は、がんの診断もがん治療もまだまだ手探りの時代。診断がつかない限りは、化学療法を始めることもできません。悩みながらも病理検査技師にかけ合い、病変部から細胞を採取する別の方法を提案したところ、無事に診断を確定することができました。治療につなげられた患者さんからは、深く感謝されましたね。目の前の命を救うため、一から考え自ら動いていた、そんな時代の出来事です。
呼吸器疾患は、亡くなる方が多いというイメージがあります。
肺がんは今も日本人の死亡原因の多くを占めており、生活習慣病に位置づけられるCOPDは今後さらに有病率、死亡率の増加が予想されています。私も体力の続く限りは頑張るつもりですが、呼吸器内科という意義のある分野を支える医師が一人でも増えることを願うばかりです。後継者探しも念頭に、患者さんやスタッフを困らせない状況を整えることが、私の現在の課題といえます。
読者へのメッセージをお願いします。
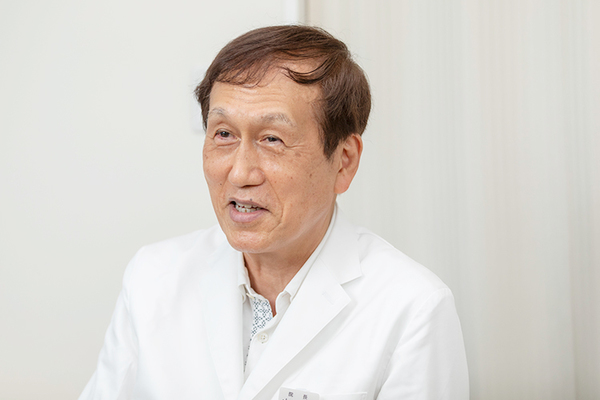
呼吸器のお悩みに限らず、どのようなことでもまずは相談していただきたいです。私は全人的な医療をモットーに、患者さんの心理的・社会的側面も考慮した総合的な診断と治療、そしてお困り事の解決をめざしています。と同時に、地域の医療体制の中で連携を保ちながら診療にあたることも大切にしています。特定健診や予防接種、また小学校では校医としての健康相談や健康診断も請け負っているので、なかなか忙しい日々です(笑)。これからも、地域のかかりつけ医として長く皆さんの生活に寄り添い、皆さんが何でも話せる相談役であり続けたいと思います。






